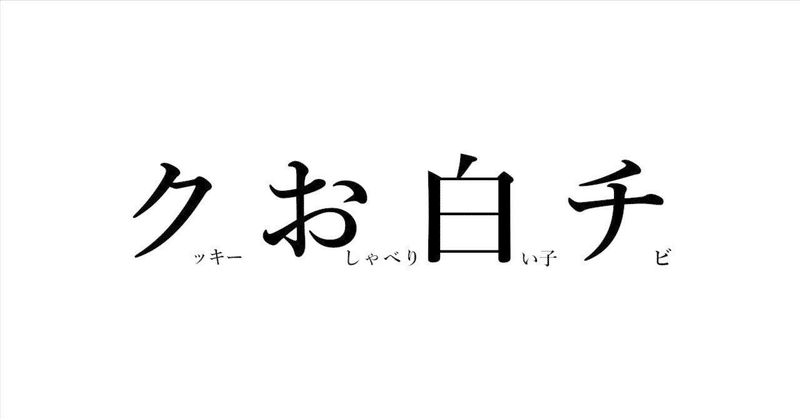
【小説】クお白チ 105【第一期】
「おにいさんごめんなさい。私達じゃ分からない苦しみなんですね」
「いや、いいんだよ。怒鳴ってごめん…」
「でも、私の前で思ってる事を言ってくれてよかったですよ」
「ラブの前だから言えたのかな…」
「少しは悲しくなくなりましたか?」
「ラブに言ったら気持ちが楽になったよ」
「お仕事してても、ご飯をたくさん食べてても、みんなを笑わせたり、いじめたりしてても、おこってても、笑ってても、泣いてても、強がってても、弱くても、みんな、私の大好きなおにいさんですよ」
強がってても、弱くても…チビの前では強がってる。ラブの前では弱いところまで見せてしまった…いや、見せられる…素直になるってのはこういう事なんじゃないのかと思った
「そうやって優しくしてくれるラブが大好きだよ」
「嬉しいです」
「もう一つ聞かせてくれないか?」
「なんですか?」
「俺が誰とエッチしても平気なのか?」
「もう平気ですよ。私の初めてはもらってくれたし大丈夫ですよ」
「たとえば俺とラブが付合う事になって、俺が浮気したらどうするの」
「一番じゃなくてもいいって言ったじゃないですか。おにいさんの事を好きだって思う私の気持ちが大切なんですよ」
「チビや白とエッチするかもしれないぞ?」
「平気ですよ。たまには私もしてくださいね」
「なんでラブは平気なの?」
「私がおにいさんを好きだって事が大切だって言ったじゃないですか」
「じゃ、ラブが俺を好きじゃなくなる事はあるんだね?」
「ないですよ」
「なんでないの?」
「おにいさんは、初めて好きになって、初めてキスして、初めての人になってくれて、秘密を教えたいって思った人だからですよ」
「理由はそれだけなの?」
「初めての人に秘密を教えて、その人をずっと思い続けようとずっと前から決めてたんです」
「いつから?」
「小学校6年生の時です」
「かたい決心なんだね」
「私は秘密を分かってもらえない人とは一緒にいたくないんですよ。だから、おにいさんがどんな事をしても嫌いにならないで好きでいますよ」
「それも誓えるの?」
「一生好きですよ。誓います」
「なんでそこまで献身的になれるの?」
「私が決めた人だからですよ」
「じゃ、俺が誰ともエッチしちゃダメだって言ったらしないの?」
「しません。誓います」
「いや、これは誓ってくれって言ってないだろ」
「やです。私が誓いたいんです。だから誓います」
「独占したいからそういう事言うの?」
「今言ったじゃないですか。おにいさんが誰とエッチしても平気です。独占なんかしませんよ」
「やっぱり分からない…」
「いいんですよ。おにいさんは好きな事をやっててください。それをちょっとでも知る事が出来れば私はそれでいいんですよ」
訳が分からないのだけど、ものすごく好きで、ものすごく大切なものが手に入ったと思った。ラブは無償の愛を通りこしてる…
「じゃ、誓ってください。俺を永遠に愛し続けますか」
「私はおにいさんを永遠に愛し続けます。誓います」
「ラブ。俺の一番の彼女になれ。そして俺を一番の彼氏にしろ」
「一番の彼氏にします。私は二番でも三番でもいいです」
「違う。二番の彼女が出来ちゃうかもしれないから、ラブを一番の彼女にしたいんだよ」
「一番の彼女になりたいです」
「一番の彼女になると誓えますか」
「誓います」
抱きしめた。抱きしめたまま立ち上がった。ラブの両腕を首に回し、左手を腰に当ててから、右手で両膝の下を持って持ち上げた。俺の一番の妖精は羽が生えたように軽かった。足の痛みは感じなくなってた
「え゛ーーー!私を持ち上げちゃうんですかー」
「一回しかできないかも知れない。あははっ」
「初めての人にだっこまでされちゃった♪」
「嬉しい?」
「嬉しいですよー♪」
「キスしよ」
ラブが腕に力を入れて、俺の顔を引きよせてそのままキスをした。二人のほっぺの涙もキスをした。さっきまで空いていた穴が少しずつ小さくなって…消えた。愛されていると言う事が分からない俺が、人に愛されると言う意味が、少し分かった気がした…時間が流れた
ラブを下ろして時計を見る
「ラブ、用務員室に行くよ」
「なにしに行くんですか?」
「戸締まりして、鍵を返さなきゃいけないんだよ」
「分かりました。これも一番最後ですね♪」
「本当に一番が好きだよね…」
「一番ってなんかいいじゃないですか♪」
「だっこはクッキーの方が先だったよ?」
「私の初めての人に私がだっこされたのは一番じゃないですか」
「あぁ、そういう考え方もあるか…」
「手をつないでくださいよ」
「いいよ」
「これも一番ですよ♪」
「変なやつ…」
「え゛ーーーー!」
「大丈夫。嫌いにならないし、大好きだから」
「あははははっ」
鍵をかけてから、用務員室のドアから見えないところにラブを待たせて、用務員に鍵を返してお礼を言った。ラブと一緒に校舎の出入り口に戻り、タオルを敷いてラブをそこに座らせた。ハチマキを取って、ラブが『初めて』と描いたタオルを取り出して、ハチマキにし
「おにいさん。汚いですよ」
「おまえは俺の足をなめたじゃないか。同じ様な事だろ」
「あぁ…そうですね…でもなんか恥ずかしいですよ」
「そだ、デートの時って何時頃に帰れば平気なの?」
「10時位に家に着けば平気ですよ」
「そんなに遅くて大丈夫なの?」
「うち、門限ないんですよ」
「へぇー」
「私だけは放任主義なんですよ」
私だけ?気になったけど聞かなかった
「それにしたって15だろ?」
「もうすぐ16です!もう!」
「それだけはゆずらないね。あはははっ」
鞄から手帳を出してカレンダーを見る。水曜日か…
「誕生日は一緒にいてあげられないかもね」
「無理しなくていいですよ。覚えてもらってるだけで嬉しいですよ」
「初めてのデートの時になにかプレゼントを買ってあげるから考えておいてね」
「いらないですよ。たくさんもらったからもういいですよ」
「じゃ、ラブは嫌いになる…」
「え゛ーーーーー!分かりました。考えます、考えます」
「あはははははっ」
「初めての人になってもドキドキさせられる…」
「これからなん回もドキドキさせてあげるよ」
「それも嬉しいです♪」
「変なやつ…」
「え゛ーーーーー!」
「毎回引っかかるから、楽しくてしょうがないよ。あははっ」
「あんまりいじめないでくださいよー」
「いいじゃん。俺は楽しくて、ラブはドキドキするんだから」
「そうですね♪注目されてるんですもんね♪」
「さて、そろそろ帰ろうか」
ラブが時計を見て
「もうこんな時間なんですね」
「かなり話せたじゃん。また話せるじゃん」
「そうですよね♪」
「立って」
敷いていたタオルを鞄に入れて、ラブの太ももを両手で抱きかかえ、両足にキスしてから立ち上がり、ギュッと抱きしめて、今度は唇にキス。歯が当った。俺も前歯が二本出てる
ラ&俺「あはははははははははははっ」
「もう一回やりなおしー」
「はーい♪」
別れることが寂しいんじゃなく、二人がお互いに大切な物を手に入れた事を確認しあう様に長いキスをした…
手をつないで正門まで行く途中で、ラブと手を離し、立ち止まって振り向いた。毎日、朝迎えてくれ、夜送り出してくれた出入り口にかかった丸い大きな時計に、精一杯の声で
「ありがとうございましたーーーー!」
と叫んだ。俺の声が校舎に跳ね返ってすぐに消えた。時計に深々と頭をさげた。ラブの方を向くと、また泣いてる。ラブの右手を取り振り返らずに、二人で正門を出た
八人の妖精達との奇妙な夏の十数日間はこれで幕を閉じた…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
