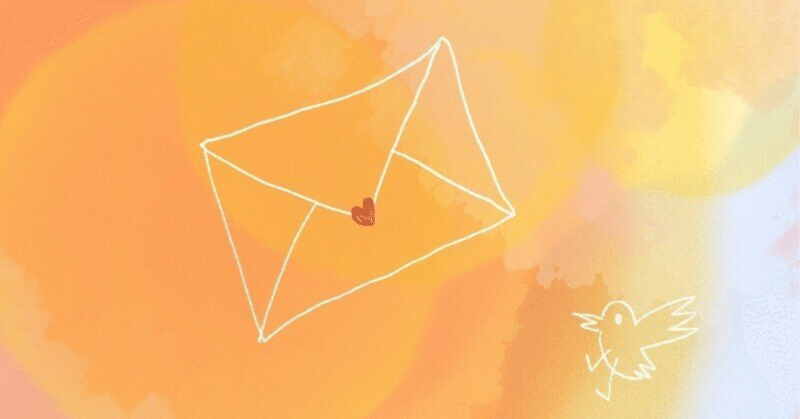
手紙
「僕の瞳は宝石でできているんだ」
「多分君も同じだよ」
1.
「君の瞳は宝石みたいに綺麗だね」
彼女は僕にそう言った。
「そっか」
嘘だって分かっていたけど、僕は笑うことも呆れることも出来なかった。
宝石ってどんなだっけ。たしかキラキラしてて凄く綺麗だったよな。覚えているけど思い出せない。だって僕は目が見えないんだから。
僕の目が見えなくなったのは、高校2年生の春。それまでは何処にでもいるような普通の高校生だった。友達は多い方じゃなかったけど、一人でいる時間が好きだったから不満はなかった。学校から帰るといつも自室に引きこもって本を読む。両親は共働きで父か母が帰ってくるまで3時間くらいはこの家に僕一人しかいない。上着とカバンを掛けてソファに寝転がり僕は本の世界に入り込む。言葉の世界では全てが自分の想像のままで、まるで自分が本の中で生きているような感覚になれる。昔の僕は本当に本が大好きだった。
友達には秘密にしていたけど、中学生の時から物語を書き始めていた。小説家になるっていう夢だってあった。特別才能があった訳じゃないけど、短編小説を書いてはネットに公開して、新人賞に応募して、そんな毎日がとても楽しかった。初めはネットにあげても誰にも見て貰えず、賞に応募してもどれも1次選考落ちだった。このままじゃだめだと思って、高校生になったら文章の基礎を学び直し、物語の作り方を勉強した。そうして5作品目が完成した高校1年生の夏、僕は初めて1次選考を通過した。その勢いのまま2次選考も通過すると、家に出版社からの手紙が来た。残念ながら賞には選ばれなかったとの旨の手紙だったが、確実に夢に近づいている気がして、その頃の自分は小説家になるのだと信じて疑わなかった。
思えばこの頃から少し目がチカチカして文字が読みづらくなった気がする。目も悪くなってメガネをかけ始めたけど、特に気にしてはいなかった。いつもと変わらず学校に行って本を読んで小説を書く。そんな日々を繰り返していた。
冬休みに入り二週間後、僕は会心の出来栄えのSF短編を書き上げた。
「これはいける!」
パソコンの前で小さくガッツポーズをし、すぐに創作SF大賞に応募した。
大賞とまではいかなかったけど、上位10組が受け取れる奨励賞に受かって1万円の賞金を受け取った。「このまま出版社から声をかけられて小説家デビューするぞ」と僕の心は熱く燃えていた。
2.
その日が来たのは突然だった。冬休みが開けて間もない頃、高校二年生になってまだ五日目くらいだったと思う。
休み明けで生活リズムが治っていなかった僕は、深夜まで次の小説を描き続けていた。
「はぁ〜、今何時だぁ」
僕は視線をパソコンのモニターから少し上の壁掛け時計に移す。しかし視界がボヤけて時計の文字盤が見えない。
「あれ、また目が悪くなったかな」
「寝不足だからかぁ」
深夜テンションで自問自答を繰り返し、スマホを取ろうと立ち上がったその時だった。
「バタッ」
大きな音を立てて僕はその場に倒れ込んだ。
深夜三時くらいだったと思う。
気が付いたらそこは病院だった。
目を開けるとぼんやりとした白色が視界に写った。
「大丈夫です。意識に異常はありません。」
「本当ですか!?息子は無事なんですね!?」
知らない女性と両親の声が聞こえた。僕は病院に運ばれて、今見ているのは病院の天井なのだろう。
「ですが、、、」
医者が重たい口調で父と母に病状を伝える。
「息子さんの視力が回復するのはかなり難しいです、、、
「光線力学療法です。要するにレーザーを使った新しい治療法で、、、
「視力が回復する可能性は良くて30パーセントです」
そんな会話だった気がする。だけど意識が朦朧としている僕には理解が追いつかなかった。両親は泣いていた。
「ンッ、、、エッ」
僕は声にならないような音を発した。すぐに3人が僕の意識が戻っていたことに気がつく。それを確認した医者は急いでどこかに報告に行ったようだ。その間、横では母が僕の身体に寄りかかって泣いている。父は力んだ手で僕と母を支えいた。
二分ほどしてすぐ、さっきの医者が男性の医者を引き連れて僕の病室へと帰ってきた。たくさんの検診や説明を受けたが、そこからのことはあまり覚えていない。
唯一覚えているのはこの一言だけ。
「この手術が失敗すると一生目が見えなくなる」
3.
未来のことなんて何も考えられず、真っ白な味気のない病室で僕はボーッとしていた。小説のことなんてもうどうでも良かった。本の世界なんてない。物語なんてもうどこにもない。あるのは行くあてもない恨みと自己嫌悪だけだった。絶望だけが僕の頭を支配している。
そんな時、僕は彼女と出会った。彼女は隣の病室で落ち込んでいる僕にいつも話しかけてくれた。声の感じからして恐らく年齢は僕と同じくらいだろう。初めは何を言われても無視していた。
「もう僕に構わないでくれ!」
そんな酷い言葉を彼女に投げかけてしまった時もあったかもしれない。それでも
「また明日ね」
って少し気を遣ったような声で笑ってくれた。手術は数週間後に控えていたけれど僕の恐怖は次第に和らいでいった。
それから数週間、僕は彼女と色んな話をした。彼女との会話はいつも午後だけで、朝から昼にかけて何らかの検診に行っているらしい。彼女は音楽が好きで僕もよく聞かされた。ロックとかヘビメタとかばかりで始めは聞き馴染みがなかったけれど、聞いて行くうちに僕もだんだんハマっていった。
「いつかライブに行きたいね」なんてことも言ってたっけ。
ある日、小説を書いていた事が彼女にバレた。お見舞いに来てくれた母が大きな声で話すから彼女にも聞こえていたのだろう。彼女は図々しく母との会話に割り込んできて
「えっ君小説とか書いてたの!読ませてよ!」
といつもより少し明るい声で話しかけてきた。断ろうと何か言いかけたが、母が「良いでしょ?良いでしょ?」と嬉しそうにこっちを見てきたのではっきりと断ることができなかった。自分が葛藤しているうちに僕のことなんかほったらかしで彼女と母がどんどん会話を進めていく。自分が否定しようとした時には
「じゃあ明日持ってくるね」
「うぉぉ、ありがとうございます!」
みたいな感じで話が進んでいて、もう取り返しがつかなくなっていた。
彼女は僕の小説をとても褒めてくれた。
「君の新しい作品が読みたい」って言われたけど、もう本なんて嫌いだった。入院中、音声で本を聞いていたが情景が思い浮かばないのだ。全部覚えているはずなのに思い出せない。空の色もリンゴの色だって。思い出せないのだから想像なんてできるはずもない。小説なんてかけるはずもない。
4.
ついに手術当日になり、僕は大きな病院へと運ばれた。様々な器具と医師達に囲まれて手術が始まった。
そして手術は失敗に終わった。
僕の目は完全に見えなくなった。覚悟はしていたはずだけど、とても現実が受け入れられない。もう何も考えたくない。
そのあと前いた病院に戻って検査漬けの日々が始まった。もう何も見えないから前の病院かどうかなんて分からないけど、看護師さんがそう言っていたからそうなのだろう。僕を励ましてくれた彼女はどこにもいなかった。どこにいったのか気にはなっていたけれど、自分のことで精一杯でそんなことを聞く気力すら起きない。幸い僕は1週間ほどで退院できるらしく、その後は視覚障害者のための共同訓練に参加するとの事だった。メンタルはだんだん回復していき、ついに明日病院を出ることになった。
5.
「ついに明日退院か」
ふと彼女のことを思い出した。彼女はよく僕の目を褒めてくれた。
「君の瞳は宝石みたいだね」
なんてお世辞を言われたこともあったよな。小さい時にも母に綺麗な目だって褒められた気がするけど、自分の顔なんてもう忘れてしましった。僕の瞳が宝石で出来ているかどうかなんて確認のしようもないんだ。。。
「あっっ」
我に返った僕は慌てて看護師さんに彼女のことを聞いた。
「あーあの娘ならあなたと入れ違いで別の病院に移ったわ。心臓の病気が悪化したみたいで大きな病院で手術することになったの。」
「えっ、、、」
僕は1度、彼女の病気について聞いたことがある。その時は足の怪我だってはぐらかされて詳しくは話してくれなかったけれど、よく考えたら思い当たる節はたくさんあった。しっかり考えれば、足の怪我で毎日長い検査なんて必要ないことくらい簡単に分かるものだけど、今そんなことはどうでもいい。
「会いに行けますか?」
看護師の声の方を向いて訴えかけた。
「うーん、、残念だけどそれは無理ね。彼女の手術は1週間後だし、あなたは盲導犬のトレーニングに行かなきゃでしょ?」
「そこをどうにかお願いします!1日だけでも!」
「そうねぇ、、でも、あそこの病院はここから20キロは離れているし、、今のあなたの状態で行かせることは出来ないわ。」
「、、、あーでも手紙くらいは送れると思うわよ」
手紙。そうか手紙か、それなら僕も彼女を励ますことが出来る。僕はコンピュータを受け取り、読み上げ機能を使って彼女に手紙を送ることを決心した。そう決めたは良いももの僕の指は全く動かなかった。文章が書けないのだ。話したいことなんていくらでもあるのに何一つ言葉が出ない、何を書けばいいのか全く分からない。
、、、いや書くべきことならあった。あの日に彼女は言っていた。母が僕の小説を持ってきたあの日に
「君の新しい作品が読みたい」と。
6.
「書き方を忘れたんだ。情景が思い浮かばないから書けないんだ。僕はもう海の色も空の色も何も思い出せない。」
いつもよりワントーン低い声で僕は言った。そしたら彼女は笑ってこう答えた。
「なに言ってんの。そんなの君の物語に書いてあるでしょ。ほらこれ。」
そう言って彼女は僕の小説の原稿を僕の目の前に突き出した。するとすぐに僕の小説を音読し始めた。
多分その時僕は初めて彼女に怒った。嫌いになった小説なんかと向き合いたくもなくて、彼女の言葉をよく聞かなかった。もう想像出来ない自分が嫌で仕方なくて。昔の自分が嫌で仕方なくて。
でも今なら思う。初めから想像することは出来たんだ。本の中で景色を見ることはできたんだ。本当は怖かっただけだ。現実の景色を忘れることが受け入れられなかった。最初から視界なんてなかったことにしたかった。本なんて、物語なんて、現実なんて、全部幻想でそんなもの最初からなかったんだって、そう思うことで僕は安心したかったんだ。
もう書き方は分かったよ。いや本当はずっと前から分かっていたんだ。
次の物語のタイトルも登場人物もストーリーも景色も構成も。
この手紙に何を書けばいいかも。
僕はずっと閉じていた瞳を開ける。キーボードに手を添える。モニターを見る。
ノンフィクションの作品を書き上げよう。
彼女の手術まであと1週間か。
よし。
この物語の書き出しはこうだ。
「僕の瞳は宝石でできているんだ。」
「多分君も同じだよ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

