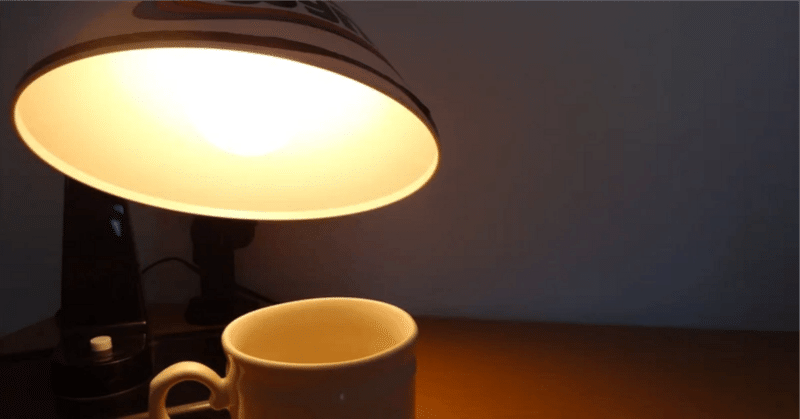
『街のあかり』の数だけ、そこには人間がいるのに
アキ・カウリスマキという名前を初めて聞いたのは、たしかTwitterだったと思う。『枯れ葉』という映画が公開された時に、誰かが「パレスチナを思う感情と、日常を送ることの両立を描いた」と書いていたのを見て、興味を持った。というのも、ちょうどそのころ、イスラエルとハマスの対立が悪化していた。今でも、イスラエルがガザ地区の人を―特に子どもだ―を殺していく、ジェノサイドが続いている。新作であるその『枯れ葉』はまだ見ていないが、実家のテレビに搭載されているアマゾンプライムで「カウリスマキ」と入力し、検索結果の上のほうに表示された映画を見ることにした。
家に誰もいない昼間は、この特別に静かな映画を見るのに適していた。この映画の静けさは、ひとつの逆転現象を起こしていた。普通は映画というものは、静けさを破るために見るはずだ。画面の中で起こる激しいアクションで、日常の静けさを忘れるための体験。僕はそれが映画だと思っていた。だが、『街のあかり』は、まさにその静けさを表現の主題としているような雰囲気を持っていた。人物の構図も、演劇のように分かりやすい構成が多い。だから少しの間、肩透かしを食らった気分になった。口数が少ない主人公のコイスティネンをしばらく見ていると、「これは退屈かもしれない」という第一印象に、「だけど、『退屈』を描いているんだろう」という文言が加わった。
いま「主人公のコイスティネン」と言ったが、この映画でいちばん主人公らしいのは、むしろ、断片となって様々な角度から映し出されるヘルシンキの街だ。コイスティネンは、ただもう不条理に巻き込まれていく。また、悪役や裁判官まで、誰もが「自分がなぜそこにいて、なぜ働いているのか」を分かっていない、あるいは気にしていない顔をしている。これらをじっと見ていると、彼らを突き動かしているひとつの原理として、圧倒的な静けさを持つ「ヘルシンキ」というひとつの都市が浮かび上がってくる。だから、実質的に『街のあかり』は「ヘルシンキ」というただ一人の主人公の、静かなモノローグだったのかもしれない。
ところで、印象的だったシーンがある。コイスティネンがミルヤという女性に「振られた」とき、彼がバーで悲しみに浸る場面だ。彼の周辺には、同じように疲れた顔の男たちが座っており、グラスを持って煙草を咥えている。そこにフィンランドの大衆歌のようなものが流れ、彼らの顔にカメラが近づいていく。
僕が特にこのシーンを覚えているのは、彼らの悲しみが、「大衆歌」というひとつの語彙でのみ表され、片付けられていくことが、言いようもなく悲しかったからだ。彼らはそれぞれに、語ればキリがない辛さや苦しさを持っているはずだ。21歳の僕でも、それぞれの顔を見ればそのくらいは分かる。だが、こちらとしては、彼らの経験を知るための手がかりは「大衆歌」しか存在しない。大衆歌で読み取れる以上の感情が、まさにその人の個別の物語が出てくるところである気がするのに、それは省かれている。本人たちも、それが当然であるような顔をしている。
僕は、これはひとつの「暴力」であるような気がした。語るべき言葉が、それより安易な言葉で代替されている。この責任の所在は分からないし、これが悪いことなのかどうかも分からない。もしかすると、余計な詮索で、僕の態度こそが「暴力」なのかもしれない。ただ、僕が分かるのは、こうやって他人の理解のなかで「省略」が起こることが、個別の人間を「群衆1」「群衆2」として捉えることに繋がっているのだということだ。僕はそこに、「暴力」のひとつの芽を見た。
ともかく、僕はカウリスマキ監督が好きになった。
【部屋のあかり】
・2024. 3. 8から3.11までの記録
・目次
6. おわりに 港町の門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
