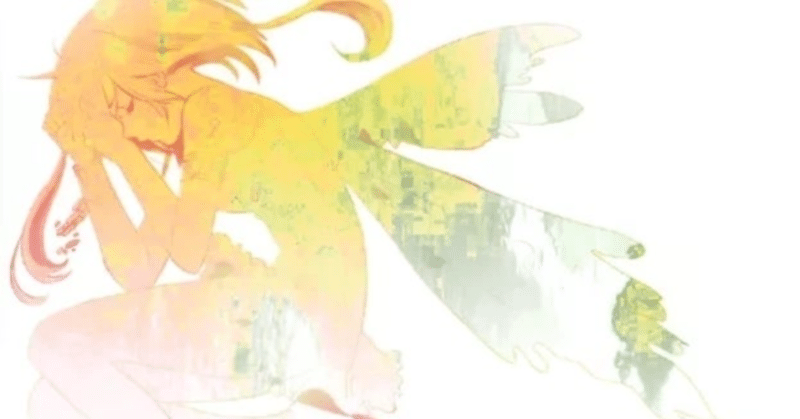
【掌握小説・らしく①】それはきっかけに過ぎない
「ねぇねぇ。〇〇に似てるって言われない?」
隣でペチャクチャ喋ってたMが髪の房をくるくると指に巻きつけながら突然こっちを向いた。
いや、そばに人が来ていたことも、それがMだということも今この瞬間まで気づいてはいなかった。ただ、機関銃のような彼女は誰彼かまわず急に話を振るのがデフォ。
「えっ?」
(何?私に話しかけてる?〇〇って誰?あ、あのTVでよくイジられてる芸人のこと?)
私はハっと顔を上げるも、驚いて発したセリフと頭に浮かんだ言葉の配分量を間違えた。
手には発売日を今か今かと待ちわびていた大好きな作家の最新作。先ほど大学構内の本屋で開店と同時に駆け込んで手に入れたのだ。
先日までの試験勉強や提出課題で寝不足の上、ちょうど佳境を迎えるハラハラドキドキの展開。フィクションの世界に没頭していて現実に戻ってくるのが遅れた。
「すっごい似てると思うんだよね〜」
『あたし素直に思ったこと言っちゃうのぉ』と宣わった、いつかの時と同じくテカテカとルージュのついた唇が動く。向かい側にいるMの友人が申し訳なさそうにコッチに目線を投げる。
「え、あ、そうなんだ。。。」
いまだ半分くらい小説の世界にいる感じで、頭がぼーっとして表情筋は凝り固まったまま。
Mは同じ学部の同級生で似たような講義に出てるから知り合いではある。ではあるが、人もまばらな学内のカフェテリアで、しかも距離も近いのに、そんな通る声で話す話題だろうか。
学生がいる方が珍しいこの時期になぜリア充の塊のようなあなたが大学にいるのだ。暇なの?と聞いてみたいがそんな勇気はない。
私の反応が思ったより薄かったようで別の『楽しいこと』に興味が移ったらしい彼女は「じゃあね〜」と手を振り去っていった。テーブルに残された使い捨ての紙コップからはカプチーノの香ばしさが微かに薫った。
ふーーーっと息を吐くと、私は本の続きに取りかかった。
.
.
.
.
.
.
.
.
「はぁ…」
しばらく文字を目で追っていたが視線が上滑りするだけで内容はまったく入ってこない。脳内には先ほどのMのセリフがぐるぐると際限なくループ再生されている。
私は化粧っ気もなく着ているものも所謂プチプラ・ファッション。自分自身、周りの女子大生みたいに可愛くないし可愛くなろうと努力すらしていないのは百も承知。
とはいえ、仲のいい友達でも気のおけない家族でもない、どちらかと言えば他人のようなクラスメイトから突然、ブスで笑いをとっている女芸人に似ていると言われる所以はあるのか。
ふつふつと怒りのような悲しみのような感情が湧いてくる。
早く読みたくて買ったその足で一番近いカフェテリアに来たのが運の尽きか。席など選びたい放題の店内で、なぜ私の横に座っていたのか。至福の時間を満喫しようと、あえて人気のない場所に来たのに何の因果でその楽しみを奪われねばならぬのか。
人形のような可愛らしさが放つ言葉の刃。その切れ味の鋭いことよ。
.
.
.
「帰るか…」
適当なページに栞を挟んで席を立つ。ポツンと残された紙コップもしょうがないから手に取り、出口付近のゴミ箱に放り入れた。
***
大学近くの下宿に戻り、ベッドの上で本を開くも思考は途切れなかった。親に言おうものなら、少しはオシャレでもしたらと返されるのが関の山。
愚痴を吐き出せるほど心を許せる友人は休みに入った途端、地球の裏側へ旅立ってしまった。メールすら届かない秘境にいるらしいし、こんな負の感情を文字で残すのも癪に触る。
オシャレに興味はないが暗に可愛くないと言われれば傷つく。だからって同じような化粧をして趣味じゃない服を身に着ける気にはならない。なぜ人の言葉に、自分の行動や嗜好を左右されなければいけないのか。
ただ、本の続きを楽しむには、この案件を何とかしないといけないらしい。さっきから開いたり閉じたりするたびに印刷されたばかりの紙の匂いが鼻先を掠める。
.
.
.
.
.
.
「よしっ!」
読むことを諦め、勢いよく立ち上がる。そのまま財布とトートバッグだけ持って外に飛び出した。
春がそこまで来ているよと、ヒンヤリ冷たい風に乗って花の香りが漂ってくる。うっかりコートを忘れて寒いはずなのに、なぜか身体の中心は熱を帯びて暑いくらいだ。
足取り軽く着いたのは、近くの電気店。大音量で流れる音楽に圧倒されないようにハッとお腹に力をれて店内に足を踏み入れた。
***
「お〜!思い切ったねぇ」
春真っ盛り。新しい一年が始まる期待と休み明けの高揚感に溢れるキャンパス。
同一人物かと疑うくらい真っ黒になって帰ってきた友人は、長年の夢を叶えた自信と満足感いっぱいの顔をしていた。そんな彼女ですら久しぶりの挨拶もそこそこ、開口一番、驚きとも称賛とも取れる声を上げた。
『一生に一度はやってみたい』
そんな願望が誰にでもある。人の言葉はきっかけに過ぎない。やってみたいからやっただけ。ただ、それだけ。
ニヤニヤと嬉しそうな友人を横目に、私はスッキリとした気持ちで短くなった髪をつるりと 撫でた。
*つづく*
第2弾はこちらからどうぞ↓
noteというコミュニティの雰囲気がとても心地よく、安心安全の場所だなあって思います。サポートいただいた優しさの種は、noteの街で循環していきますね。
