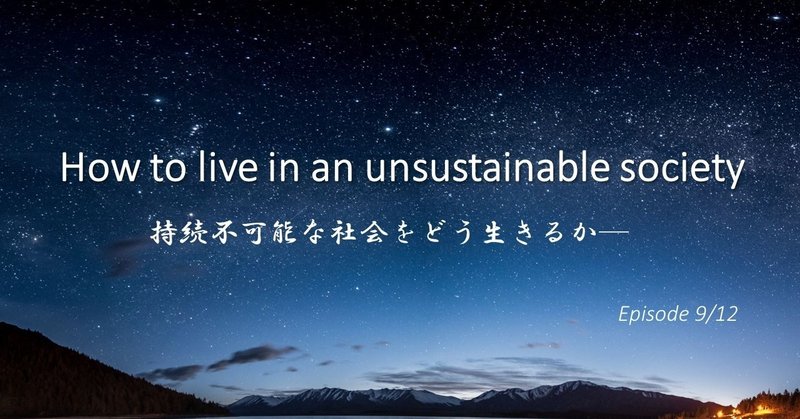
No.9|資本主義という願望機の欠陥 - 前編
資本主義の原則は、他者のニーズに応えることで報酬を得るシステムだ。「より良いものを、より安く、より早く」をモットーに、資本家間・労働者間が互いにしのぎを削り合うことによって技術を高めた結果、今のような物質的に豊かな社会を築くことができた。
この自由な経済は、多くの人の願いを叶えてきた一方で、重大なシステムの欠陥も露呈した。それは、「いつまでも競争が終わらず、しかも競争が過酷になり続ける」という欠陥だ。
資本主義のシステムとその負の効果について、順を追って説明していこう。
生産性の向上による競争の激化
産業革命以降、技術は驚くほどのスピードで発展し続けることができた。技術が発展することで、一人当たりの生産性は向上し、より少ない人数でも同じ量の仕事をこなせるようになる。それが社会全体として人員に余剰を生み、人々に新しいことを挑戦させ、再び技術の発展につながるという"好循環"を生み出すことができた。

生産性の向上が生み出すスパイラル
ただし、このシステムに"アクセル"はあっても、"ブレーキ"はなかった。労働者は競争で勝ち残るために、生産性を上げ続けなければならなかった。生産性を上げるほどに人は余り、競争はより過酷になるにも関わらず...
仕事の意味の変遷

取り掛かられる仕事には優先度がある。おおよその場合、比較的必要性の高いもの、簡単なもの、コストパフォーマンスに優れたもの、リスクが低いもの、やりがいを感じられるものから真っ先に手を付けられる。生産性が向上してくると、このような仕事は順に満たされるようになり、より優先度の低い仕事——必要性に乏しく、難易度が高いもの、利幅の小さいもの、リスクが高いもの、やりがいを感じにくいものへと変わっていく。
以下は、その詳細な変化である。
(教育コストの増加)
仕事に求められる技術は、より高度で専門的なものへと変わっていく。労働者は、過酷な競争の中で雇用を確保しようとし、懸命に技術を磨こうとする。それは高等教育への進学率や期間を増加させ、労働者にコストとして重くのしかかる。
(利幅の低下)
技術の発展は、後続企業が追いつく速度も増加させ、競争優位を保てる期間を短命化し、事業収益を減少させる。労働者個人としても、大学で学んだ知識はすぐに陳腐化し、絶えず学び直しが求められる。学習に関わるコストは増加する反面、それに見合うリターンが減っていく。
(リスクの増加)
苛烈な競争による収益の低下は、よりリスクの高い行動へと追い立てる。他者よりも先手を取るために、情報が不足している段階でも早急に決断が求められる。先にシェアを持った企業が利益を総取りするようになり、ほんの一握りの勝者と、数多の敗者を生み出している。学生は、良い職に就くために高額の奨学金を借りてまで大学に進学するようになり、希望の就職から漏れた卒業生は借金の返済に行き詰まるようになっている。
(抜け出せない低賃金競争の渦)
高条件の就職が叶わなかった労働者は、低賃金の競争に巻き込まれる。時に単調、単純、あるいは3K(きつい、きたない、危険)な仕事であるにも関わらず、求職者数の増加によって労働賃金は低く維持される。総じてこのような仕事は技能の獲得が難しく、それがキャリアアップを妨げ、年数の経過とともにこの競争の渦から抜け出すことをより一層困難にする。
(欲望の喚起)
必要なモノで満たされ、"意味のある"新たな仕事を創り出すことは容易なことではなくなる。"欲しい"と自然に思えるものは開拓し尽くされ、売り手の方が積極的に顧客に"欲しい"と思い込ませなければ売れなくなる。コモディティ化した商品は、広告の良し悪しに大きく影響を受けるようになり、顧客は絶えず欲望を刺激されるようになる。社会はどこを見ても広告で溢れ、「より便利なもの、より快適なもの、より楽しいもの」を訴えかけられる。
(非合法化)
過酷すぎる環境は、非合法な事業へと人々を追い立てる。品質不正問題が後日発覚し、老舗の大手メーカーが苦境に立たされる事件が散見されるようになった。また、ブラック企業の問題、規制の網をかいくぐった租税回避の横行など、本来の事業性とは関係ない部分での競争に追い込まれる。
広がる世代間所得の格差
以上のように、宿命的に割の良い仕事の就職先(ポスト)は徐々に減ってゆき、労働者は過酷な競争にさらされ続ける。だからこそ、そうならないように労働法があって、安易な解雇を抑制することで労働者を守ることができると信じるかもしれない。けれども、安直な労働者の保護は、時に雇用の硬直化を招き、世代間所得の格差を広げる原因になってしまう。

上の図は、割の良い仕事(例えば正社員)と割の悪い仕事(例えば非正規社員)が労働者の年代ごとにどのくらい占められるかを模式的に示したものだ。もし雇用が流動的(case A)であれば、その時々で適材適所に人員が組み替えられ、能力次第で若年層にも就職のチャンスが巡ってくる。一方で、雇用が硬直的なシステム(case B)では安易な解雇は許されず、人員の整理は定年退職に伴う自然減に頼らざるを得ない。その結果、企業は若年層の採用数を絞らざるを得ず、若年層はポストを巡る熾烈な競争にさらされる。本来であれば社会全体で負うべき事業環境に対する変化——人員整理の痛みを、若年層が集中的に負わされることによって解消している。正社員と非正規社員の生涯年収の差は6,000万円であり、能力ではなく、ただ後で生まれたという理由だけで押し付けられるのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前編まとめ
資本主義経済を成り立たせるためには、特に"新しい仕事"が必要だった。そうしなければ仕事は早々に尽きてしまい、世の中は失業者で溢れ、お金が回らなくなってしまう。労働者は失業の恐怖におびえ、新たな仕事を創り、他者の需要を喚起し続けた結果、あちこちが広告で溢れかえることとなった。モノを余計に買うことが求められ、欲望に従順であることが社会的に肯定された。モノをたくさん買ってストレスを発散し、モノをたくさん買うために長く働く。それは生きるために仕事をするのではなく、仕事をするために生きる、という倒錯を生んだ。
資本主義は、様々な問題を引き起こしながらも、それでも人々の願いを叶え続ける。それが本当に必要なサービスかどうかは関係ない。それがシステムを維持するために必要であったからだ。誰もが「代わりがいる」という恐怖から逃れることができなかった。社会が富を、全くの平等にとは言わなくとも、ある程度公平に分配できたとすれば、ブレーキをかけることができたかもしれない。けれど、資本は一部の人に偏在し、常に労働者は仕事に追われている。
資本主義社会は欲望で動いている。他者の欲望を喚起し、半面で自身も踊らされる。そうした滑稽な騙し合いが、大量生産・大量消費の社会を作り、資源を浪費し、格差を広げ、環境を破壊するに至った。資本主義という願望機は、人の願いを効率的に叶え続け、成果を出した人に報酬で報いるという点でそこそこに機能したけれども、多くの欠陥を露わにしている。あくまで叶えるものは持てる者(資本家)の欲望に対してであり、持たざる者(労働者)の願いは相対的にないがしろにされている。
(後編に続く)
▼マガジン(全12話)
twitter:kiki@kiki_project
note:kiki(持続不可能な社会への警鐘者)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
