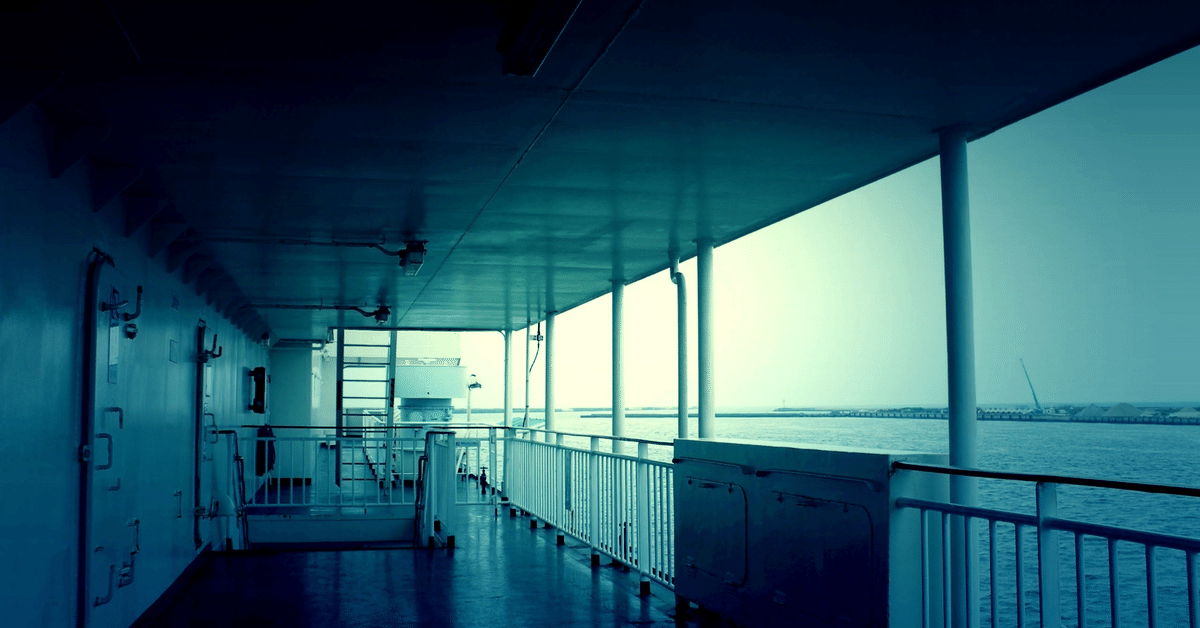
身近な人の死を、人生のターニングポイントに。
はじめに
突然ですが、皆さんは「死生観」という言葉をご存知でしょうか。
生きることと死ぬことについて、判断や行為の基盤になる考え方。生と死に対する見方
就職活動を通じ、未来の人生設計を立てる上で「自分はこうなりたい」「こういった人生を送りたい」あり方、そして理想の死に方やどのようにこの世に別れを告げるかということについて考えるようになりました。
そのようなことを日常でぼんやりと考えた矢先、最近身近な人を突然失くしてしまったケースを残念なことに経験してしまい気落ちしていました。
本文章を通じて伝えたいことは
己の「理想通りの死に方に近づく為に」他人の「死」を受け入れ、今後自らの人生の糧にしていくかです。
以下、順に突然亡くなってしまったケースを振り返りまとめていきます。死は奥深く、儚く、切ない。今後一生涯死生観に関しては付き合っていくのですが今は気持ちを整理して綴っていきたいと思います。
祖父の死
最近のケースとは言いつつ、もう3年3カ月も前のことになります。突然亡くなってしまったことを両親づてから電話で聞いていたのですが鮮明に当時の状況を覚えてます。
まだ当時大学1年次。それまで怠惰な学生生活を行ってた私にとって挽回する唯一のチャンスかもしれないと息巻いて挑んだベトナム・ホイアンでの海外インターンシップ(俗に言う武者修行プログラムというやつ)
Day9、プレゼン発表の準備の為に宿舎に戻り作業をしていた午前1時、意気消沈といった様子の母から電話をうけ衝撃を覚えました。
衝撃を覚え、暫く私自身も意気消沈し必死に理解しようと、かみ砕こうとしていましたがプレゼン内容をどうするかの考えは完全に思考停止というか、死に方も死に方だったので頭の中は真っ白…!という状態。
今でも偶に故人を回帰する際、あの時こうしてれば良かった、こうしなければ良かったといった後悔の言葉が親から出ていてその都度、私は切ない気持ちになっています。
一連の流れで私は祖父の死から2つのことを学びました。
自らの選択に意思を持ち、決断する
死の知らせを聞いた翌日、当時プレゼンで同じメンバーに対してメンターと併せて開示する時間を設けて貰い話した記憶があります。
当時何者でもなく、パワポはおろか人前で何か発表もしたことが無い自分にとってベトナムという地はビジネス観点では恐怖でしかなく日が経つにつれ帰りたいと頭の片隅で想っていました。
自分にとってチームに貢献できる役割はなんだろうと、貢献場所を探し雑務を引き受けつつあった中、死の知らせを聞いた時に心の中で少し「お葬式に出るという名目でインターン中だけど帰国出来るのでは…?」と今考えれば不謹慎極まりないですが思ってしまった節があって。
ダナン国際空港までタクシーを使い搭乗の切符を買おうとしていた矢先、当時のメンターや運営陣が引き留めてくれたこともありインターンを最後までやり遂げました。
まとめると、日本に帰らないといけない理由、ベトナムで頑張らないといけない理由を天秤にかけ子供ながらに迷い続け決断に自信を持てずブレブレなままズルズルと、帰国までいってしまった印象があります。
状況を整理し、決断に自信を持たなければいけないといった学びを得ました
素早く立ち直る努力をする
前者の話に通じますが、決断に自信を持てずクヨクヨしてしまっては後々後悔するというか、時間が勿体なく感じてしまいます。
大前提ですが、素早く立ち直れと述べているのではなく「努力をしようよ」ということです。私もまだ両親の死、或いはこれから授かるかもしれない子供の死を経験したことが無いからこそ死んでしまった対象によっては受け入れがたい。
寧ろ、生涯立ち直れない可能性だってある。生きる目的を見失ってしまうことだってある。ただ幸いにも今生きている社会環境は多少の問題はあれど永遠に孤独になることは無いのだから、立ち直る機会は外に出れば幾らでもあるのだから
故人を思いつつ、立ち直るきっかけをつかみにいく方が故人の為にもなるのでは無いかと個人的な解釈として、考えています。
コーチの死
今回、執筆しようと気持ちを湧かせてくれた存在です。突然の訃報に驚き悲しいという一言では抑えられず、一昨日お別れ会に出席して本当に亡くなってしまったのだと。色紙にメッセージを書きながらひしひしと、実感していました。
若すぎる。あまりにも若すぎる死で私も立ち直るのにまだ時間がかかりそうですが、コーチの分まで生き抜こうと思います。
ただお別れ会には少し愛を感じました。親族に限った話では無く、過去コーチに指導を受けた教え子は勿論、以前のコーチの同僚や奥様、はしゃぎまわる息子さん。体感60~70名は来てたと思うので死に直面することは叶いませんでしたが多くの人が見送りに来てました。
また、在世中の賞状や写真、ユニフォームといった遺品を見ていると胸が締め付けられる思いは勿論ですが出会って良かったなと改めて考え直すきっかけを創出してくれた感謝というか、有難みを感じています。
私は在世中のコーチから以下のことを学びました。
子供達の上達の為に試行錯誤してメニューを作っていた
何か明確に〇年生の代を持っているのではなく、キーパーコーチが主でしたが僕らの代に教える時も常にサッカーが上達できるように、走れるようにハードなメニューを作ってくれていました。
特にランメニューは恐ろしかったですがお蔭様で中学以降も大抵のフィジカルメニューは音を上げること無く、高校まで一貫してサッカーという競技を続けることが出来ました。
子供である事を言い訳にせず厳しさを持って接してくれていた
日頃から何か子供達が失礼なことをしてしまった時にしっかりと怒ってくれていたなということが印象に残っています。
大会に向かう際に、子供達で固まって大きなエナメルバッグを抱えながら電車移動していた時があったのですが、最寄り駅に降りた瞬間かなりの剣幕でコーチが怒っていた時があって。
内容は簡潔に言うと「近隣のお客様に迷惑になるから節度を持って行動して」ということなのですが当時の子供達は私も含めてまだ反省していないというか、理解力に各々差があったなと感じています。
最近、ゲストハウスで子供達に接していたりして分かってきたのですがそもそも活気盛んな、特に精神年齢がまだ低く大人でない男の子達相手にしっかりと世の中の道理を伝え叱ることは中々出来ない。つい遠慮してしまう。
そんな子供達に厳しく接してくれた経験はいつまでも忘れることは無いですし、今私が生き抜く上で必ず糧になっているといえます。
また大学以降でもそれまでサッカー触れたこと無かった…!とかの層に対してもエンタメとしてですがフットサルの企画をしたり、自ら個サルに参加したりといった経験を積めるようになりました。これからも私自身が取り組む生涯スポーツとして楽しんでいこうと思います。

改めて心より、お悔やみ申し上げます。
多田会長の死、Forbesの記事を読んで
さて、最後の事例は私の原体験ではなく、著名人の死について触れようと思っています。
背景として、長期インターンシップ先で働いていてある社員さんがシェアした記事を読んで上記の祖父の死、コーチの死を経験した自らと重ね合わせて読みたいなと思ったからです。

興味があった点としては下記あたり。
・代表が急死した後、どのように会社を立ち直らせていくのか
・社員各々のメンタルケアはどうするか
ビズリーチは、会社を立ち直らすのに早急な意思決定を2つ「継続体制を早急に構築すること」「社内外の動揺を最小限に抑えるコミュニケーションを取ること」行いました。
理由は、社内外の混乱を防ぐのにトップ交代を含めた新体制づくりが急務であり事業を進み続ける必要性があったから。
とりわけ凄いなと思ったのは新体制づくりと、引継ぎの社長が発した挨拶の言葉になります。
新体制づくりに関しては「守破離の守」を徹底的につくるといった、言わば
教えられた、言われた内容をしっかりこなすことが出来るような仕組みがまずビズリーチに出来ている。
今回迅速に代表を決めることが出来た最たる例が「副社長」というポジションを以前から設定していたということ。
そして、副社長が発した、感じていることを等身大で話し、事態を受け入れて進み続けようといった「気丈に振舞う必要性は無い」といった隠れたメッセージを社員一人一人に投げかけたことに凄みを感じました。
メンタルケアに関しては、いくら時間があっても足りないものは足りないので、急死した社長との思い出をみんなで語り合う名目のスラック、追悼用のチャンネルを開設したり、ブログ記事で報告したりしていました。
報告することで、先代の社長が残していったあらゆる格言を改めて思い返すことに繋がる。そして組織としては勿論、個を動かすことにも繋がる。
事態を受け入れ、気丈に振舞うのではなく等身大の自分で話し、次の行動へ繋いでいく。この一連の流れが個人ではなく組織として、企業として出来ていることに感銘を覚えました。
最後に
身近な人の死に直面し、今回死について考えた文章を書きました。祖父の死、コーチの死、多田会長の死。三者とも志半ばで、突然亡くなってしまいました。
幾ら死生観で考えたとしても、いつ亡くなってしまうか想像は出来ない。しかし、死を通じて事態を嚙み砕き受け入れ、○○さんの分まで頑張ろうだとか、故人の想いを背負って次の行動へ進んでいくことは考えられるし、そのような思考が大事かなと。
立ち直るのに幾ら時間が経とうとも時間が経てば解決するような代物では無いので、これからの日々の活動の中で活動の原動力にしていこうと思います
辛い経験を乗り越え、人生のターニングポイントといえるようにしていく。あの時こんなことがあったから今の自分があると言えるような理由づけを自身で作れるようにしていきたいと思います。
とはいえ、リフレッシュの為に友人との遊ぶ時間を楽しんだり、帰省したりしてメンタルを保っていくということも非常に重要。引き続き遊べる時は遊んで人生をFunkyに!頑張っていきたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
