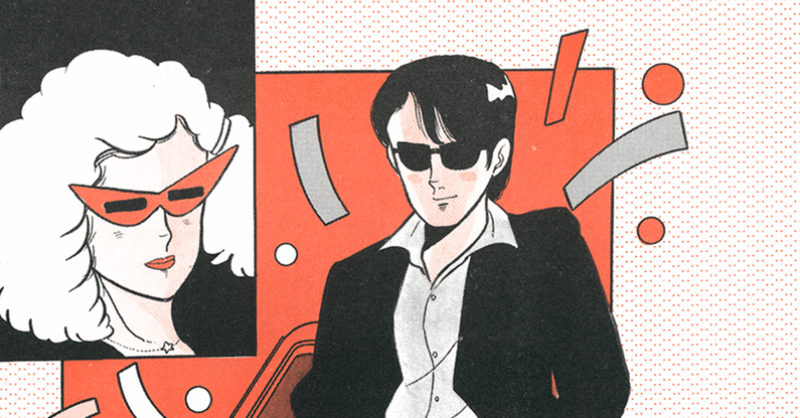
シリーズ考察/シティ・ポップ文脈で考える柳沢きみお世界。
昭和〜平成レトロという価値観により、懐かしき80`s、90`sが注目を集める中でボクが推奨している「柳沢きみお」研究はちっとも注目を集めていない。この切なさ、まるで高木ブー(by筋肉少女帯)いや、「ドカベン」後期〜「大甲子園」あたりの岩鬼ですよ。ちょうど山田太郎が諸々の事情(長屋のオーナー命令による立ち退き問題)によりプロ球団逆指名事件(ロッテでしたな)があったときの岩鬼キャプテンの宣言の虚しさよ。
「山田がロッテ逆指名ならわいも阪神タイガース逆指名や!」
スルーする記者たち。あのやりとりかなり好きなんですよね。まあプロ野球編になり先行する山田とはタイプの違う豪打爆発のスタースラッガーへと変貌していく岩鬼の端境期ならではのエピソードってやつか。
さてシティ・ポップ(笑)の話だ。竹内まりやの「プラスティック・ラブ」が実際に発売された当時、すでに死語だったんだよな、感覚としてシティ・ポップってやつは。実際竹内まりやソロアーティストとして再始動の頃、シティな扱いではなかったもの。なので84年以降の、それっぽいアーティストが「シティ・ポップ」として再評価されていくのは悪い話じゃない。むしろ立ち位置はっきりしてよろしいんじゃないでしょうか。84年以降、とにかく時代的にはアウェイが続いていった音楽ジャンル。たとえばMOONから東芝EMIへと移籍した村田和人、NHK教育のレギュラーとかやってましたけど「電話しても」「一本の音楽」を「湾岸ウイング」は越えられなかったんだよ。メーカーがどうこうってことではなく時代の移り変わりの問題になるんですけど。バンドサウンド、つまりスタジオで気心知れたミュージシャンと練り上げるスタイルから打ち込み問題が主流へとなり、ミュージシャンが作る「音」すら変化を余儀なくされてしまった時代。最初からダンスミュージックとして機能可能な第2期オメガトライブを始めとするトライアングル・サウンドにとってはかっこうの時代ではあったんですけどね。
まつもと泉の「きまぐれオレンジロード」連載が1984年15号、つまり3月ぐらいからスタート、その際の作者巻末コメントが「シティ感覚で描いていきます」である。思うにこのへんがギリギリなタイミングだったんですよね。これが一ヶ月遅かっただけで「きまオレ」は古い作品として受け入れてもらえなかったと思うんだな。
さて柳沢きみおとそのフォロワーたちはその頃どうしていたか。まず柳沢きみおのアシスタント、村生ミオの作品を振り返ってみよう。
82年頃から村生ミオの作品にはカフェ・バーやプールバーが登場、小道具としてピンボールが出てくるなどシティ感覚を先取り感は描いてるほうも自覚的だったのかもしれない。その直前までキャラに「わたし、アイミティー(アイスミルクティー)」「オレ、冷コー(アイスコーヒー)」と喋らせてた村生は常に作中で時代との距離感を絶妙なバランスで図りながら作品を世に送り出していた。唐突にBGMとして大瀧詠一(「結婚ゲーム」少年ビックコミック連載)が登場したりと、まつもと泉が「きまぐれオレンジロード」であからさまに山下達郎や杉真理などナイアガラフォロワーぶりをもっと内包的に作品として昇華させた手法と比べればかなりダイレクトなアピールだったんですけどね。
「(ナレーション的に)いまオレの耳元を大滝詠一の「SUMMER BREEZE」が鳴っていた」とかそんな感じだった。だけど好きだったんでしょうな、村生センセは大瀧詠一とか。
さてボクらのきみおの場合はどうだったか振り返ってみようじゃないか。ボクはまずシティ・ポップ括りであげておきたいのが「瑠璃色ゼネレーション」だ。柴門ふみの「東京ラブストーリー」や「同・級・生」が登場以前、大人のラブストーリーといえば柳沢きみおだった。「瑠璃色〜」のヒットによる土壌がなければビッグコミックスピリッツは柴門ふみを起用しなかっただろうし、もしそうなっていれば「東京ラブストーリー」はなかった。リカとカンチが存在しない90`s。小田和正の「東京ラブストーリー」の大ヒットがない90`s。日本のポップミュージックの歴史が変わっていたと思いますよ。
「瑠璃色ゼネレーション」のなにが新しかったのか。まず主人公カップル、つまり恋人ではなく夫婦の破綻から物語は始まる。それも旦那と妻の両方がほぼ同時に別のパートナーを見つけて別居。そして物語上は仲直りするも最後の最後まで男は惑っているままエンディングなのだ。この夫婦は完全再現いたしました、パチパチパチではなく。読後感は末恐ろしい未来への苦味のみ。恋をして結婚をして子供を作ってというわかりやすい人生設計の裏側をスピリッツというメジャーな大舞台で鬱々と描いた作品であり、まだ新井英樹の「宮本から君へ」登場以前である。花沢健吾の「ボーイズ・オン・ザ・ラン」も生まれる気配すらなかった時代に柳沢は恋愛の裏側に潜むダークネスをメジャーフィールドで描き切った。ここを評価しないっておかしいよ!
「瑠璃色ゼネレーション」はテレビドラマにもなっている。主演は風間杜夫で旦那以外にひたすら愛を求め続ける妻を田中好子とまあトレンディ・ドラマがまだ世の中になかった時代だがプレ・トレンディなドラマとして1984年日本テレビ系でオンエアされていた。主題歌は中森明菜の「少しだけスキャンダル」で作詞作曲は横浜銀蝿の翔が担当していてシングルカットはされていないがドラマオンエアの前年に発売された中森明菜のアルバム「エトランゼ」に収録されているので興味あるひとはサブスクでチェックしてみるのもいいと思います。
さてここまで書いてきて「瑠璃色〜」のどこがシティ〜なんだと思う方が多いと思うのだが、あえていえば「全部」と断言しておく。とにかくシティ・ポップというワード(当時はシティ・ポップスでしたね)が賞味期限ギリギリだった1983年に連載が始まったこの作品には当時の空気を目一杯詰め込まれているのだから「全部」と断言」しても問題ないと思うわけですよ。ある意味幻想としての80`sがもしあるとするならば「瑠璃色ゼネレーション」をまず読んでほしい。誰もがすべてキラキラしていたわけじゃない80年代の現実が切実に描かれているから。誰もがカフェバーやプールバーへ行き、洋楽(AOR)を聴いて刹那的に生きていたわけじゃないだよと。
主人公の同僚はワイフ(笑)に逃げられ実家まで菓子折り持って「戻ってきてくれ」と哀願するも「あなたと暮らすなんて考えたくない」と拒否られる。その同僚、街で家出少女を拾って同棲始めるわ、バーの女の子と付き合うわと放蕩三昧。主人公の深町良のほうがよっぽどストイックだよ!
1983年当時、シティ・ポップが「リアルじゃない」「絵空事」「全部同じ」と散々貶され始めた頃、たしかにアートワークや音楽性的にマンネリ化し始めていたのだと思うが、ほんとに突っ込んだところでいえばボクはシティ・ポップは大人の寓話的音楽とも位置づけられると考えていて。
南佳孝の「冒険王」はまさにソレじゃないですか。幼少期への郷愁をポップ・ミュージックとして懐古主義に陥ることなく松本隆と作り上げたアルバム。寺尾聡の「リクレクションズ」はもはやハードボイルドな短編集だ。リゾート、ドライブ・ミュージックとして当時もてはやされた一面はもちろんあっただろうし、だけどそれだけじゃなくティーンの頃からポップ・ミュージックに慣れ親しんできた層が聴ける音楽としての一面って重要だったと思うのだ。
柳沢が大人向け、青年向けに舵を切ったのも同じ理由だろう。幼き頃から親しんできたマンガという存在、つまり「アトムの子供たち」は大人になってもマンガから離れることはしなかった。ならばそんな大人たちの現実ですり減ってしまった心を癒す寓話が必要じゃないかーそれが柳沢きみおの「瑠璃色ゼネレーション」だと思うのだ。
「瑠璃色〜」の登場人物たちは久しぶりにいったジーンズショップでサイズオーバーに悩んだり、学生時代に買ったセミアコースティックタイプのギターを押入れから引っ張り出すも、すっかり弾けなくなった自分に気づき唖然としてしまう。が、それも一瞬。冷蔵庫から冷えたビールを取り出しすぐに至福のトリップ(「大市民」への萌芽がすでにありますな)へ。女は夫のビール腹を冷めた目で眺めつつダイエットのため始めたジャズダンスに夢中だ。そんな淡々とした日常の中で少しづつ破綻は始まっている。つまり淡々とした日常こそいちばん恐ろしい。
巧妙に作られたトリックが散りばめられたサスペンスや予算を豊潤にかけられたホラー大作をNetflixで簡単に堪能できる時代だが、この時期の柳沢きみおを1日かけてじっくり読む。ボクはこれが今いちばん「シティ」な行為だと思う。曇り硝子の向うで描かれた大人のためのおとぎ話をぜひ読んでみて欲しい。ハマっちゃうと思うんだよなァ、まじで。
よろしければサポートおねがいいたします。いただいたサポートは活動費に使わせていただきます
