
ともに転ぶ、覚悟を持って
あなたは自分が抱えられる責任の重さを量ったことがありますか?
一人で抱えられる責任というのは、実はそんなに大きなものではありません。
しかし、私たちは一人の人間です。
自分で抱えられる最大量が上限だと思い込んでいることもあるのではないでしょうか?
…と、まあ、いきなりヘビーな導入部分にしてみましたが、今回は仕事と責任について書いてみようと思います。
すでにご存知のかたもいるでしょうが、私の現職は障害者福祉施設の現場支援者という側面を持っています。
障害者を障害者として捉えることを差別的な扱いだと感じる方もいるかもしれません。
しかし、障害があることを本人も周りも認めることで、はじめて社会全体として克服できる問題もあるのだと私は考えています。
このあたりは、多様性というよりもノーマライゼーションの概念に近いものかもしれませんが、文中に何らかの格差を表す表現があるかもしれません。
ですが、それは私の主訴を明確にする上で必要であり、言語的に表現したものだとご容赦くださいませ。
それでは、最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
あなたは「てんかん」という病気をご存知でしょうか?
「一人で抱えられる責任」について書くにあたり、少し説明をさせてくださいね。
てんかん発作を繰り返す脳の病気で、年齢、性別、人種の関係なく発病します。世界保健機関(WHO)では、てんかんは「脳の慢性疾患」で、脳の神経細胞(ニューロン)に突然発生する激しい電気的な興奮により繰り返す発作を特徴とし、それに様々な臨床症状や検査での異常が伴う病気と定義されています。(下記参照リンク)
参照リンクには、以下のようなことも書いてあります。
生涯を通じて1回でも発作を経験する人は人口の約10%、2回以上は約4%、そのうち「てんかん」と診断される人は約1%で、日本では約100万人のてんかん患者が存在します。
「100万人」という数字を、多いと捉えるのか少ないと捉えるのかは個人差があるでしょう。
また、てんかんは先天的とは限らず、後天的に脳の一部が傷つくことで起こることもありますから、単純な確率論的に考えれば、誰もが発症リスクを抱えていると考えることが出来るでしょう。
ですから、反対に考えれば、すでにてんかんの発作や症状をお持ちの方も、あなただけが発作や症状に苦しんでいるのではないという解釈で捉えていただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
総人口で統計を取ると「てんかんと診断される人は約1%」となっていますが、水頭症患児のみ抽出すると、約34%が合併症としててんかんに罹患しているというデータが存在するので、言葉の表現上「健常者」と呼ばれる方の発症率は、1%以下だと言える論拠となります。
間違えないでもらいたいのですが、確率論は個人ではなく統計的数値として認識してもらいたいと考えています。
例えば、「○○が出来る人の65%はIQが120を超えている」というデータがあったとします。
このような場合、私たちは自分の能力の上限を知るために試してみようとする好奇心が働きます。
一方で、「○○が出来ない人はIQが50に満たない」というデータの場合、私たちは自分の能力の下限を知るのが恐ろしいので、前者よりも消極的な行動しかしません。
そして、万が一にも当てはまった場合、「自分は特別でIQが50に満たない者ではない」という自己防衛的な思考が働きます。
余談ですが、このような自己防衛が働いている健常な精神を持っている人は、必然的に盲目的ポジティブシンキングの状態にあると言えるでしょう。
生きるために、前向きであろうとするのです。
この本来の働きが機能しなくなる状態が、いわゆる「精神障害」や「精神疾患」の領域ではないかと、私は考えています。

ーーーーーーーーーー
話をてんかんに戻しますが、てんかんに罹患している方の抱えられる責任は、どの程度のモノでしょうか?
発作が始まれば、自らの命の危険も回避できない状況になるのですから、てんかんではない人に比べ、抱えられる責任は少なくなるでしょう。
しかし、社会生活を営む上では、一人の人間として生活しなければなりません。
このような方には、最低限の生活を支援する存在が必要であり、人口減少や少子高齢化が進む日本においては、家族だけでなく福祉従事者、ひいては地域社会が支援していく流れとなっていくでしょう。
もちろん、てんかん以外にも病気や障害をはじめ、合理的配慮が必要な方は数多く存在します。
では、私たちが支援する側となったときに、備えておくべき心構えとして何があるでしょうか?
それは、ともに生きる、ともに歩くという思想だけでなく、ともに転ぶことも厭わない覚悟が求められるようになると、私は感じています。
ここからは、障害者の方と関わっている私個人の話をして、この投稿を終えたいと思います。
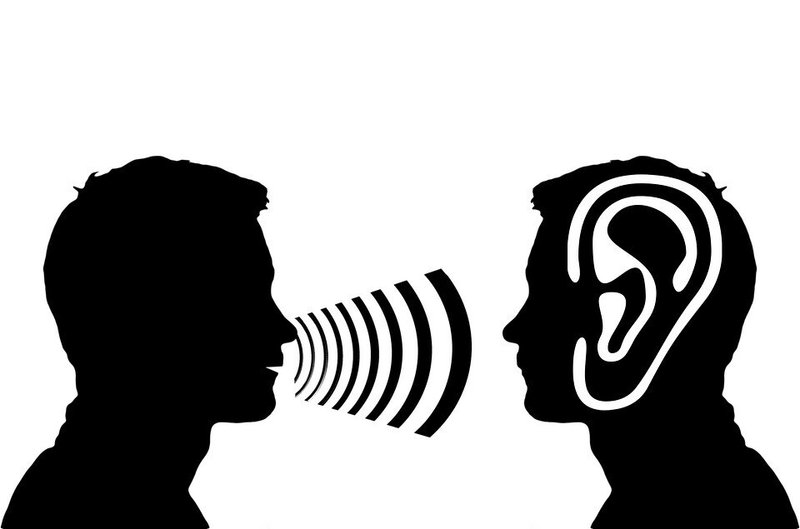
ーーーーーーーーーー
言語コミュニケーションを取ることが出来ず、自律的歩行もままならない、てんかんをお持ちの重度の障害を抱える方の支援を担当したときの話です。
毎日のように複数回の発作が起こるのですが、身体機能を維持するためには歩行訓練などをしなければなりません。
いつ発作で倒れるか分からない方を支援するというのは、よほどの専門的な知識や技術が必要だと感じる方もいるでしょう。
しかし、ともに転ぶ覚悟があれば、最低限でも支援は出来ると感じました。
「倒れないように支えなければ…」と考えてしまうと、倒れてしまうものです。
「倒れても、一緒に転んでケガしないようにしよう」
たったこれだけの考え方の違いでも、支援の手段は大きく変化します。
ーーーーー
また、統合失調感情障害の方の支援をした時の話です。
(下記参照リンク)
記憶力に優れた方で、その場しのぎの言葉が通用しないですし、矛盾があれば高い攻撃性のある言葉で他者を責め立てるようなこともありました。
障害者と接するときだけではありませんが、相手が全力でこちらに向いているときは、同じだけのエネルギーで相手と対峙するスタンスは大切だと思います。
それは、言葉や行動の隅々にまで神経を集中し、相手が口に出せずに困っている本心を引き出すためには、上辺で接してはいけないということです。
何度も何度も同じ話を繰り返していくうちに、少しづつ見えてくる相手の本心。
その方の場合、相手に対して攻撃的だったのは、過剰な自己防衛手段ではないかと思いますし、納得してもらえれば、信頼関係を築くことが出来ますし、次に問題があったとき、本心を見せてくれるまでの時間は少なくなります。
多くの、障害を抱える方の特徴の一つに「いつだって全力」があると感じています。
自分の主張を伝えたい、しかし、伝わらない…。
このジレンマを抱えながらも、それでも訴えかけてくる彼らと向き合うには、やはり覚悟は必要なのです。

ーーーーーーーーーー
現在の精神障害者と呼ばれる方々に手帳が発行されたのは、1995年(平成7年)と、まだ日が浅いです。
さまざまな障害特性が認知されはじめ、今では障害を抱える方との社会的距離が縮まってきていますし、これからもより近い存在になっていくでしょう。
そう遠くない将来、職場や日常生活の中で障害者と接していく中で、彼らへの理解を深めるならば、ともに生きる、ともに歩くという思想だけでは足りない状況に陥ることもあるでしょう。
ともに転ぶ覚悟。
それは、障害のみならず多様性文化を形成するうえで必要となる心構えだと、私は思うのですが、あなたはどう考えるでしょうか?
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
