
訊きたいのは美談じゃない
この記事は、一部偏った表現方法を用いることがあります。
文章のみでお伝えするために、あえて用いていますが、違和感を覚えられる方もいるかもしれませんので、あらかじめお伝えします。
そんな記事の内容ですが、障害者福祉についての体験談を踏まえての話となります。
「障害特性は個性と同義」といった言葉は、福祉の世界では標準語ですが一般的には浸透しきってはいません。
それが顕著に出るのが障害者雇用という、障がい者の社会進出の場面です。
現在の法律では、100名以上の従業員を擁している企業には、全従業員数の2.3%相当の人数の障がい者を雇用させる義務があります。
単純に43.5人に1人が障がい者という計算になります。
障害には「身体」「知的」「精神」という3つのカテゴリーが存在し、それぞれに軽重が存在します。
ちなみに「発達障害」は「知的」と「精神」を跨ぐ概念となりますが、詳細については割愛します。
ということで、今回は不定期に投稿しています「障害者雇用」について書いてみようと思います。
最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
障害者雇用とは、文字通り「障害を持つ者にも社会的責任と社会的幸福を与えよう」というものです。
働くということは、責任と義務が生じる反面、自由と権利を手にします。
実際に「障害はあるが働く能力もある」といった障がい者は、福祉サービスにおいて「就労継続支援B型事業所」と呼ばれる施設の利用をしたりしますが、全国のB型事業所の平均工賃は、2018年現在で月額1万6118円です。
「…生活できないじゃん(゚Д゚;)」と思うかもしれませんが、障害者年金などの制度を複合的に利用することで、どうにか生計を維持している状況にあります。
これは、B型事業所が雇用契約を結ばない就労施設だからこその工賃で、それでも国としては前年度より3.3%(515円)上昇したことを声高に主張しています。
障がい者の生活水準は確実に向上しています…と。
雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型事業所」の平均給与は月額7万6887円で、前年比3.8%(2,802円)上昇です。
具体的な数値については今回触れませんが、法定雇用率の上昇に伴う障害者雇用の推進と就労継続支援事業所の工賃や賃金の上昇といった数値だけを見れば、確かに障がい者の雇用は進んでいるように感じます。
それでは、実際に雇用している企業側は、どのように感じているのでしょうか?

ーーーーーーーーーー
大企業では、従業員数が数万人規模に及ぶところも少なくなく、仮に1万人の従業員がいる企業では230名の障がい者を雇用する義務が発生します。
…障害特性や障害の度合いにもよりますが、これだけの数の障害者を雇用することは、企業にとって大きなリスクでもあります。
日本経済を支える大企業の生産性を下げることは国益を損なうことと同義です。
そこで、日本には「特例子会社制度」という文字通り障害者雇用の特例を設けることで、大企業においても法定雇用率を遵守してもらうシステムが存在します。
ちなみに2020年6月時点での特例子会社の数は全国で542社です。(…特例子会社に関しても説明だけで数千文字になるので割愛します)
一言だけで説明すると「障がい者を一か所に集めて管理体制を構築しつつノウハウを蓄積する子会社」なのですが、今では書籍などで一部の特例子会社の活動については知ることが出来ます。
また、特例子会社のみならず、今は多くの障がい者の就労に関する書籍が存在しています。
私もすべてを読破したわけではありませんが、これらの書籍には共通点があります。
それは、障害者雇用のメリットばかりを謳っているというモノです。
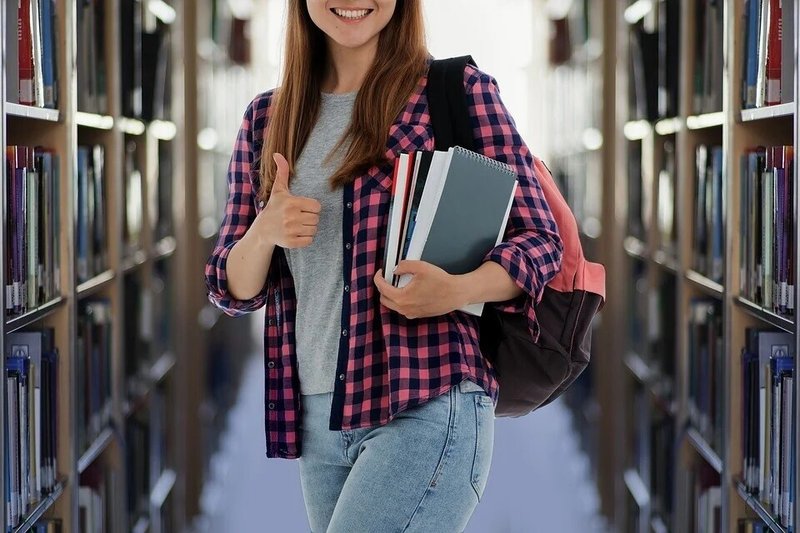
ーーーーーーーーーー
「入社当初は内向的で俯いてばかりのA君ですが、今では誰よりも大きな声であいさつをし、チームリーダーをするまでに成長しました」
「中途採用のBさんは、なかなか作業に慣れず泣いてばかりいましたが、本人の努力の積み重ねにより、見違えるように作業効率が向上しました」
企業で障がい者を指導する立場の人間や、企業へ障がい者を送り出した福祉事業所のスタッフにとって、このようなケースは大いに勇気づけられるものです。
健常者が3日で覚える作業を3カ月かけてでも出来るようになるには、本人の努力も然ることながら、周りの支援がなければならないケースも多々あります。
そんな状況だからこそ、本人の努力が花開く瞬間に立ち会えることは、支援者にとっても最高の瞬間と成り得るのです。
しかし、これは本当に稀なケースで、健常者以上に障害者雇用には美談だけがあるワケではありません。
ときには裁判沙汰になったり、雇用している障がい者が事件を起こすようなケースもあります。
しかし、これらを表沙汰にしてはブランドイメージに傷がつきます。
ですから、障害者雇用についての書籍などには美談が多く掲載されているのです。
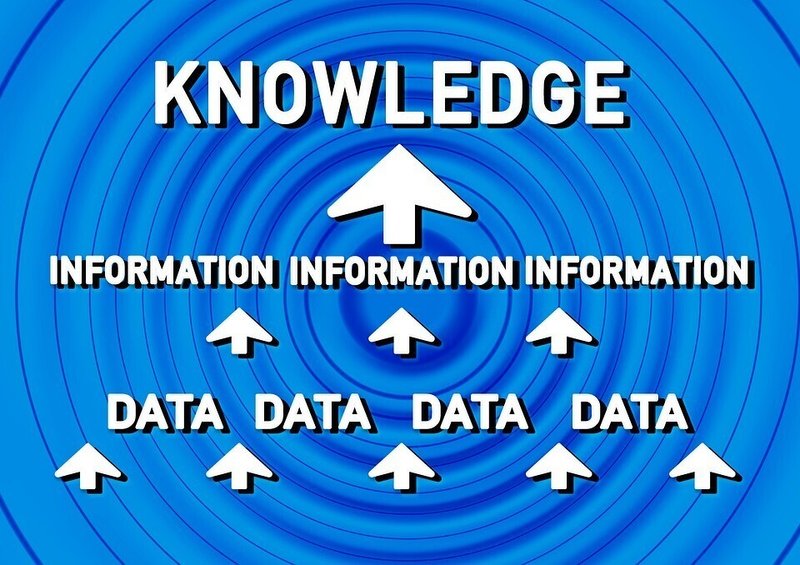
ーーーーーーーーーー
実際の現場で求めているのは、美談ではなくノウハウです。
問題児のレッテルを貼られていた人が、どのような障害特性で、どのようなトラブルを抱えていて、どのような転機があって、どのような支援のもと、どのように変化したのか?
最初と最後だけを掻い摘んで語られても、そんなものは現場にとって役に立たないのです。
どんな支援が効果があったのか?
これが分からなくて苦しんでいる企業は多いように感じます。
企業の障害者支援は、ゼロベースから始まることが多く、言葉は悪いですが福祉サイドから押し付けられた障害者を雇用してしまうケースも未だにあります。
これは、福祉側が障がい者の特性は理解していても、働くことで発生するさまざまな事象を想像できないケースが多いとされています。
企業に働いた経験のない支援者が障がい者の就労支援を行っているのです。
このような現実を聞くと、障害者福祉という世界に入ってわずか半年ですが、胸が痛くなります。
企業と障がい者、どちらもともに成長して定着していく支援というものを目指して、美談で終わらない話を、いずれ記事にしたいと思います。
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
熟語については「障害者」、名詞としては「障がい者」とさせていただきましたが、表記揺れがあったらゴメンなさいm(__)m
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
