
受け止める、受け容れる。
似ているようで、違う言葉。
検索してみると、語彙から違いを探したり、心理学などの視点から差異を見つけたり、さまざまな定義を目にすることが出来ます。
個人的な意見ですが、それらの検索結果は答えであって答えではない、と考えています。
例えば、「悲しみ」と検索すると、さなざまな言語表現で、その感情を言い表すことが試みられています。
一つひとつ、確かにその通りだと感じ、納得はできるのですが、どうにもしっくりこない感情が残ることはないでしょうか?
それは、大衆的な定義と自分の中にある実際の「悲しみ」の間に何らかの違いがあるからだと私は考えています。
テクノロジーの進歩によって、多くの言葉や価値観、ニュアンスまでもが大衆的な定義付けをされ、誰もが理解できる状態に具体化されているとは思います。
しかし、結局のところは、私たち一人ひとりは別の生物であり、似ているようで、違う生命体だと思うのです。
表題の「受け止める」と「受け容れる」についても、「悲しみ」と同じように、誰かによって定義付けはされていますが、どうにも私の心の内を、そっくりそのまま表現した言葉ではありません。
その「違和感」を、私は見逃したくないと考えるようになっています。
…と、話を進めてしまっていますが、今回は「受け止める」と「受け容れる」について書いてみようと思います。
最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
「悲しみ」についても「違和感」についても、それぞれに「受け止める」と「受け容れる」を使い分けることが出来ると思います。
「悲しみを受け止める」とは、悲しいという感情があることを事実として認めることや、自分という存在が悲しみという感情・感覚から何らかの影響を受けていることを感じ取ることだと私は思います。
そして、「悲しみを受け容れる」とは、まさに、自分という器に悲しみがもたらしている何らかの影響を注ぐ行為だと思っています。
ですから、「悲しくて泣く」という事象には、「悲しみを受け止める」ことに抵抗している自身の心の副作用としての涙と、「悲しみを受け容れる」ことによってさまざまな感情や感覚が去来し、浄化される作用としての涙に分けることが出来るのではないかと考えています。
あくまでも個人的な表現ですので、読んでくださる方によっては違いを感じられないかもしれませんが、それはそれで正常な感覚だと思いますし、是非ともご自身の中で納得のいく表現を探してみてほしいと思います。
もし、あなたなら、「違和感を受け止める」と「違和感を受け容れる」に、どのような違いをつけるでしょうか?
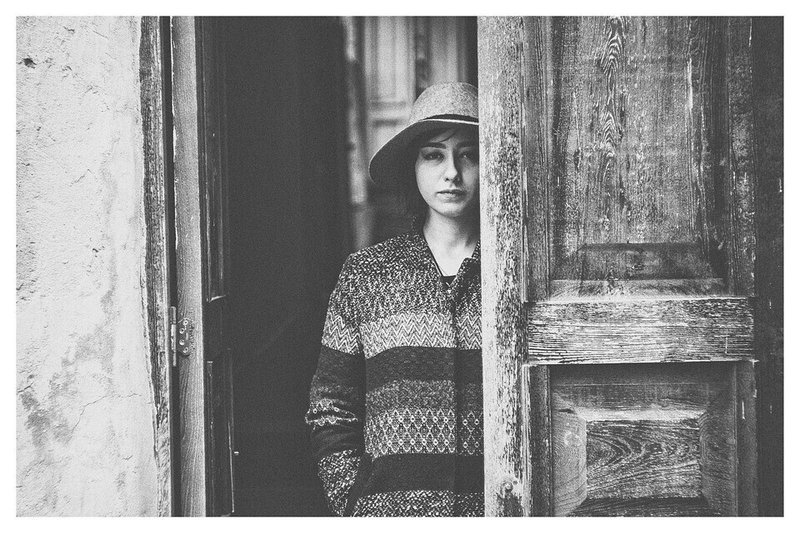
ーーーーーーーーーー
少し別の観点から考察してみますが、「受け止める」と「受け容れる」を他者との関わりで考えてみると、「受け容れる」ことの方がリスクがあると私は感じます。
何のリスクかと言うと、「今の自分を保っていられなくなるリスク」です。
ここから抽象的な表現が増えると思いますが、ご容赦ください。
人間誰しも、自我や自己といったプライベートな領域と、他者との間に隔たりを持っていると思います。
ここでは分かりやすく、「心の壁」と表現します。
「心の壁」は何層にもなっており、他者との信頼度や親密度が変化すると壁に設置された扉を少しずつ開いていきます。
扉には、自身の心への侵入許可を下す門番がいて、侵入を許された他者のみが進むことを許されます。
「受け止める」とは門番による検閲です。
「心の壁」の中心にあるあなたのアイデンティティを守護する門番が、あなたを守るためにさまざまな角度から吟味します。
少しでも害があると判断すれば、中へ招くことはないでしょう。
一方の「受け容れる」とは検閲の緩和です。
「心の壁」の中心から、あなたの意志で侵入を許可する行為です。
場合によっては、受け容れたことで、あなたの心は良くも悪くも影響を受けることでしょう。
影響とは変化の種です。
今の自分が変化すれば、今までの自分を保っていられなくなる、というワケです。

ーーーーーーーーーー
「朱に交われば赤くなる」という言葉があります。
青い絵の具と赤い絵の具は、それぞれに別個の存在ですが、混ぜることで紫色に変化します。
青色に近い紫色もあれば、赤色に近い紫色もありますが、一度混ざってしまえば、元の色に戻すことは出来なくなります。
そういう意味では、「受け止める」と「受け容れる」は、本来は段階的なモノであり、受け止めた結果、受け容れるものを取捨選択するのでしょう。
この段階を経ずに何でも受け容れてしまえば、あなたはあなたでなくなってしまうかもしれない。
だからこそ、その「違和感」を見逃してはいけないと、私は思うのです。
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
