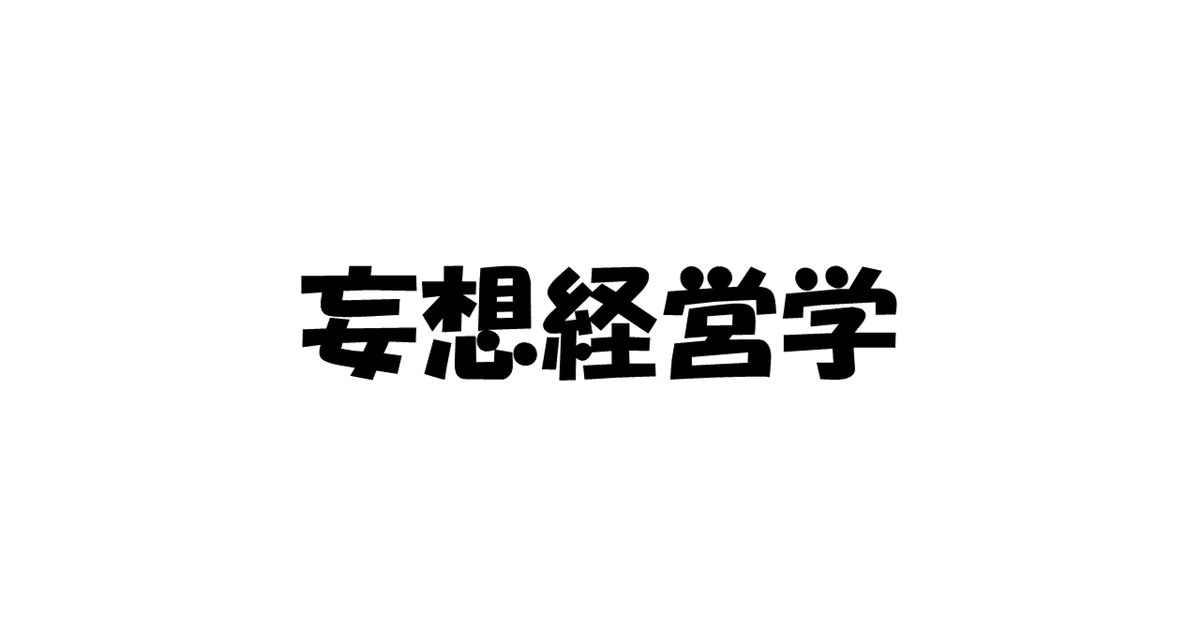
Vol.10 「自浄作用」が働く組織
前回、風土改革は「心理的安全性の確保」で一点突破、という記事を書きました。
私はその先に、「自浄作用」が働く組織をイメージしています。
これがどういう状態なのか、「発言」を事例に、具体的に書いてみます。
ちょっとした会話レベルの小さい話ですが、コンプライアンス上の大きな課題なども結局はその延長線上にあると思います。
「発言」の難しさ
心理的安全性の確保では、何を言っても身の安全が保障された状態と書きましたが、もちろん、本当に何でも好き勝手に言って良いわけではありません。限度があります。
ただ、聞く側が安易に否定や非難をしてはいけないのとは違い、提案や指摘をするケースなどでは、現状否定が前提となることもあります。
その際、どれぐらいまでの言い方ならOKなのか、難しい問題です。
他にも、ハラスメントやダイバーシティなど、OK/NGの境界が曖昧なケースはたくさんあります。
そういうケースでは、どうしても無難な選択をし、発言を控えようとしてしまいます。
ところが心理的安全性の確保が進化すれば、この課題も解決することが期待できます。
自浄作用が働く組織
OK/NGの境界がない発言は、ケースバイケースで結果が変わります。
なので、気を付けるのは当然です。
でも、心理的安全性の確保が本当に浸透していれば、NGだと思ったら、その場で言える関係、指摘できる関係が社員の間で構築できるはずです。
これにより、もし意図せず失言してしまっても、互いに修正し合って高め合える組織になれるのです。これが「自浄作用が働く組織」です。
ケーススタディ
これは私の職場で実際にあった話です。
ある開発プロジェクトで、テストの被験者を部内チャットで募集しました。ところが、その後の進捗(被験者の応募)が悪く見えていました。
すると、ある社員が「あまり人数が増えていないが、みなさん同じ部のメンバーなのに非協力的すぎるのでは?」という少し戒めるような強めのチャットを発信しました。
それに対して、「1日にできる人数が限られているので、これぐらいで妥当なんです」という回答があり、「そうなんですか。わかりました。」と返しました。
これで終われば別に問題はなかったのですが、実は以下のようなことが起こったのです。
「チャットという公共の場で、こういう発信はすべきではない。問題児だ」部門長がそう言ったのです。私はこの耳で聞いたので間違いありません。
そしてその後、その発信はチャットから削除されたのです。指示されたのか、自主的かは分かりませんが、何もなければ削除する理由はありません。
そして発信した社員は、それだけが原因ではないと思いますが、それから数か月後に、自ら異動先を探し出して、職場を出ていきました。
実は私は、最初の発信を見た時こう思いました。
「ちょっとキツイ言い方だけど、他のプロジェクトにも気をかけて、組織のことも考えていてスバラシイ」
同様に感じた人は他にもいたと思います。
後で周りに聞いてみると、「何も思わなかった」という人も多くいました。
そうです。実際にはさまざまな捉え方をされていたのです。
そのぐらいの些細なレベルの話だったのです。
なのにこんなことが起こる、そんな組織はダメだと思いませんか。
ではどうなれば良いのでしょうか。
自浄作用が働く会話
この先に書く例は、元ネタがあります。
私が企業風土世界一と思っているC社の講演で、もしその会社のオープンチャットで不適切な発言があったらどうなるか、という質問がありました。
その時のC社の回答を参考に作った会話(チャット)が以下のやり取りです。これだとどうでしょうか。
-------------------------------------------------------------------------------
社員A:「あまり人数が増えていないが、みなさん同じ部のメンバー
なのに非協力的すぎるのでは?」
依頼者:「1日にできる人数が限られているので、これぐらいで妥当
なんです。」
社員A:「そうなんですか。わかりました。」
部門長:「Aさん、そんなところにまで気を配ってくれてありがとう
ございます。でもちょっと言葉がキツイかも。」
社員A:「あ、そうですね。すみません。気をつけます。」
部門長:「でも、そういう姿勢はありがたいので、これからも
ヨロシクです。」
依頼者:「私も、気にかけていただいてありがたかったです。」
社員B:「ほかのテーマのことも考えるなんて素晴らしいと思います。
見習いたいです。」
-------------------------------------------------------------------------------
大事なのは、指摘しつつ、決して次から発信をやめようと思わないようにフォローすることです。
発信や発言のひとつひとつを評価するのではなく、学びの種にするのです。これが心理的安全性が確保された理想の状態です。
また、これが部門全体が見れるオープンなチャットで行われることも重要です。オープンだと、言う側も言われる側も、少なからず感情的にならないよう抑えます。冷静に会話します。
チャットだと真意が分からない難しさがありますが、だからこそ、チャットの言葉をあまり深刻に捉えず、ちょっと変だと思ったら、それ自体も会話のネタできるような風土を目指したいものです。
そうしないと、記録が残るチャットが気軽な会話の場にはなり得ません。
まとめ
「自浄作用」のイメージを掴んでいただけたでしょうか。
チャットに限らず、会話においてもこういうやり取りができるのが理想です。ハラスメントも、多くの場合、兆しの段階で気づきに変わる期待ができます。
困ったときに通報できる駆け込み寺は必要だし、容認できない事態に対する罰則も不可欠です。でもそれは最終手段であるべきです。
失言が発生することは避けられません。
でも、その芽を小さいうちに摘み取ることができれば、わざわざ通報する必要もないし、罰則を与える必要もありません。
人の体と同じです。病気は避けられないし、大病になれば病院に行くし、入院するし、手術もします。
でも、人体には自然治癒力があります。少し体調が悪いというぐらいであれば、自力で治します。これが組織における自浄作用です。
体が健康であるほど、治癒力も高まります。
会社組織では、健全なコミュニケーションが成立しているほど、自浄作用が強く働きます。
健全な組織は、もしかしてまずいかも、という初期段階で、周りが気づいて修正することができます。相手に直接言うこともできます。
被害者と加害者になる前に修正できるのです。
こう考えると、「建前」の風土改革ではとても実現できない高みだと分かります。風土改革こそ「本気」の経営課題として取り組んで欲しいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
