慶應大学助教 木下衆先生インタビュー(後編・2)
当事者の選択能力がなくなったとき
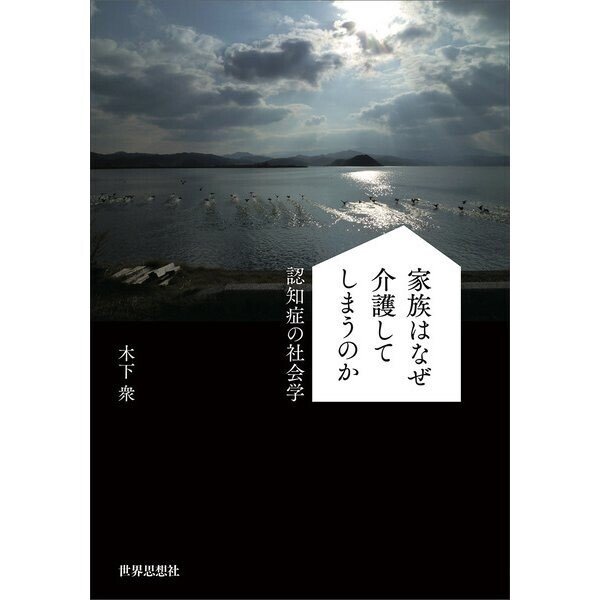
杉本 ところで、一つ先行的に社会学では上野千鶴子さんが根本的で説得力ある話をされてますよね。本人の選択能力がなくなったときどういう形で本人が、たとえば胃ろうをするとか、あるいはそれを選択しないなどの局面もそうですし、施設に入居してもらうかどうか。自分で選択できなくなる、自分の自由選択の意思が機能できなくなったとき、やっぱり家族というものはどうしてもケアに関わらざるを得ないということ。その「残余のケア」の部分が家族にどうしても残ることがあって。先生はこの上野さんの議論をもう一歩、乗り越えたいというお気持ちがあるんじゃないかと捉えたんですが、そこはどういうふうに思いますか。
木下 上野先生はそれこそフェミニズム、ジェンダー・スタディの流れの中で家族とケアの関係を考えたところで外部化して行ってもまだ残るものがあるんだという議論をなさったわけです。で、一方で私が意識していたのは障害の当事者のかたが障害ケアを受ける立場として自分たちの経験やケアというものを分析していく形で「障害学」という分野もあったりする。あるいは知的障害の人とどう向き合うことを考えていくのかということも当然あります。そういう幾つかの文脈を設定した時にやはり僕が考えたのは家族というものもまた、すごく複層的な関係だろうと思うわけです。
例えば本の中でも書きましたけれども、結婚する前を知っている兄弟と、結婚した後を知っている配偶者との関係で当事者がどう見えるのか。あるいはその人が人生に一体どういう意味づけをしてきたのか。それを誰が知っているのかということについては、家族という集団の中でも当然見ているもの、あるいはその人が見せてきたもの、言えることなどが違ってきたりすることがある。
で、本の中でも書いたんですけども、インタビューした事例の中で奥さまに胃ろうをして、最後に在宅でターミナルケアをしたかたがいらっしゃったんですが、その奥さまに胃ろうした夫がですね。満足しているのかというと実は奥さんがなくなったあとも悩んでいるんですね。つまり彼女の思いとは別のところで自分で判断を下しちゃったんじゃないかというふうに思い悩む。彼女には彼女の想いがあるはずである。でも彼女の認知症はすでに進行してしまって胃ろうをしなければならなくなった。彼女の思いをひょっとしたらうまく汲み取れなかったんじゃないのかというふうに考えるのだと。さらに言えるのは、例えば胃ろうみたいな技術って2000年代くらいから日本で普及し始めているので、その奥さんが認知症を発症されたのは90年代なんです。要するに奥さんが認知症になる前、健康だったときは胃ろうという技術は日本になかったわけです。新しい技術が介護現場に入ってきてるわけですね。そうすると新しい技術に関して認知症の人が過去どう思っていたかはたどりようがないわけです。彼は彼女のライフヒストリーからたどりようがない。ライフヒストリーに答えを見出せないし、その人の思いはあるはずなんだけど、それを汲み出すこともできない。すると自分の選択は正しかったのだろうかというふうに悩むということが起こったりする。
上野千鶴子さんの議論をいま話題として振ってくださいましたけども、家族がある種「残余的なもの」というか、さまざまなケア責任を負っていくというよりもむしろ、家族にとってのケア責任は新しい認知症ケア時代の中で新しく生じるものであり、同時に家族はそれを最初から背負っているわけじゃなくて、まさに杉本さんがおっしゃったような「巻き込まれていく」というか、「背負っていく」。しかもその問題というものが何らかどんどん新しいものが生まれてしまったりする。たとえば認知症のかたが発症してから20年生きていたらその間に介護保険の制度も変われば、医療技術も変わるみたいなこともあり得るわけですよね。結局そういう中で家族のケア責任みたいなものが私たちに生じている。だからこそキチンと認知症の人のその人らしさみたいなものを知ってくれる人がたくさんいた方がいいだろうし、やはり最後まで専門職がコミュニケーションを試みてくれること。「この人はもうおしまいだ」みたいなことじゃなくって、要介護度が5になろうと、90歳になろうと100歳になろうと、最後までコミュニケーションできる主体として関わってくれる。それが重要になってくるんじゃないかというふうには思っていますね。
杉本 やはり先生がおっしゃっていた話の中で、一つは例えば私が認知症になったときに家族で看てくれる人がいなくなった時にも社会が私を見てくれる体制が整っているかどうかという側面と、昔であれば死を迎える局面でも医療技術の発展等々でまだまだ生きる方法論があると。例えば私は認知症の薬が発明されてうんぬんみたいなことは二次的なことだと思っていて、あくまでも関係性の問題が大きいだろうと思うので、その関係性の継続、構築が今後想像されるポジティヴな方向にいくことに半分期待しつつ、半分は不安を感じるのも事実ですね。
木下 例えば「可愛いおばあさん」みたいなのが好まれるみたいのはダメだと思うんですよね。何かこちらの扱いやすい人だけを尊重しましょうというのではなくて、ちゃんと包摂していくというか。もちろん利用者さんによるハラスメント的なことは論外ですし、働きかけのまずさによって暴言が出たり、いろんなことが出たりというのは改善していかなければいけないけれども、一方で扱いやすい人だけを見ていくというものではないと思うんですよね。ちゃんと困っている人、弱っている人に関係性を作って、しかも継続していくということ。そこに専門性を認めて制度を作っていくべきじゃないかなと思うんですよね。
杉本 そうですよね。だからケアマネジメントの作業というのは、より一層重要な位置を占めると思うんですよ。後見人みたいな制度もちゃんと専門的に、倫理的にやってくれる人を選任する社会資源がもっと増えてもらえないだろうかとずっと考えているんです。というのは、ぼくも亡くなった父親から始まり、手術とか入院とか、施設入居とかの時、その度ごとに頻繁に呼び出されて病院とか施設とか昼夜関係なく判断し、契約書類など書かなくてはいけなかったりするわけですが、それを代行してくれる社会資源がまだ見えない。家族が代行しているということがやはり今の家族介護が6割みたいな状況を作っていると思うんです。ただ、もうぼくら以降の世代になると家族では難しいと思うんです。子どもがこれだけ減ってくる時代になると。そうするとやはり他者が関わってくれる、信頼できる人が世の中には現れると。そういうのが私が考える理想の社会ですね。ですから両親介護を通して、先生がおっしゃったような自由な民主社会はどういうものか?という切り口が議論になればな、と思います。自分に関しても、親のためのみならず自分のために何が必要かという角度でも考えていきたいと思います。
木下 さっきケアマネージメントの重要性というお話がありましたが、いくら生前に自分で指示を出そうとしても、やはりそれには限界がある。想定しない状況が出てきたりする。やはり限界はどうしても出てくる。そういうときにケアマネージメントというのはやっぱり時間をかけて他者が関係を結びながら要するに手直ししていくということだと思うんですよね。そのときにその人にとって、一体何が必要なのかということを時間をかけて関係を結びながら手直ししていく。私たちは色々環境を手直ししながらより良いものを目指すということにもっと価値を見出すべきだろうなということは思うんですね。
杉本 そう思いますね。ですから、ケアマネージメントをしてくれる人との関係性が、全部はわからないにしてもある程度自分の期待に沿ったものを感受してくれる人がこの世にたくさんいなくちゃいけないわけで(笑)。日本はとにかくこの超高齢社会で、心疾患、脳疾患などの救命率が高くなってきた中で、やはり寿命は延びていく要素が高いと思うんですね。ただその代わりに認知症の患者は増えてくるし、廃用症候群などで寝たきりになったりする人も増えてくる。そう考えると、庶民的にはこれ以上生かされていいものかどうかとか、新しいむずかい課題に直面する要素がたくさん生まれると思っていて、どれだけその人の人間性なりを理解し、意志を感受しながら社会がそういう専門職の人たちがいることに対して価値を置くようになれるか?例えば福祉を考えると北欧とかが理想なのかも?とか思うのですけど、それがどう社会的価値を産めているのだろうか、ということなども考えます。
木下 社会的価値の話のときに、いま北欧がモデルになるかなという話もされたと思うんですけど、私の京都大学時代の指導教官だった*落合恵美子先生という家族社会学の先生がいるんですけども、落合先生はある時期から東アジアから家族を考えていこうということをおっしゃったんですね。つまり既存の国家の分析モデルのものは、英語圏、せいぜいヨーロッパ圏までが中心で、東アジアというのはどこか分析の枠組みから外れてきたと。東アジアもちゃんと加えたモデルを改めて考えていこうということをすごくおっしゃっていて、そういう観点から私は日本の認知症ケアの歴史というのは結構誇れるものじゃないかなと思っているんですよね。つまり70年代にまず家族が声を上げ、呼応するように精神医療の分野、あるいは宅老所などの形で介護の分野も声を上げ、それを受けて国や官僚も動いて介護保険制度が出来上がる。さらに認知症当事者の人たちも声を上げるようになっていく。障害者運動は70年代から自分たちが自立して生活するということをやってきた。じゃあ介護の分野でそれができているのかという批判的な議論を展開したりしている。ある種、鍛えられていくような形で出来上がっているとぼく自身思っているんですよね。もちろん問題はたくさんあるんだけれども、ある種の日本の文脈、日本の認知症ケアの発展として見たときに、成熟したところもすごく見て取れるんじゃないかと考えていて、その良さを活かしていくべきではないかというふうに思います。
杉本 確かに。ぼくの母親の世代だと作家の有吉佐和子さんでしたか。*『恍惚の人』のイメージで生きてきた人ですから、まして自分が痴呆認知症になるなんてことは二重、三重に否定的になる。怖いと思っていた世代なので、そこから考えるとやはり今の時代はかなり様変わりしてますよね。まだまだネット世界などでは心ない偏見が露見されてるとはいえ、一般的にはアルツハイマーと言われる人たちの認識は変わって、今あるのは戸惑いというか、まさに「どう対応したら良いだろうか」ということの悩みであって、そもそも排除しようという意識はもうないですよね。
戸惑いを大事に
木下 やはり80年代以降の家族や当事者の方、それから支援者の運動がいかに分厚かったかというのがあると思います。
で、さっき今日杉本さんのお話の中でキーワードとして出されている「戸惑い」というのはぼくはすごく素敵だし、実態に即した表現だと思うんですよね。本の中でもある種こう、ぼくなんかが「こういう問題があって」みたいなこと、いかに家族が戸惑いを覚えるか葛藤を抱えるか、みたいなことを分析することもあったりするんです。でもぼくは戸惑いがあってもいいんだと思うんです。つまり戸惑いがない社会というのはどういうことかと言ったら典型的なのは80年代的な身体拘束や投薬。これって、戸惑いがないですよね(苦笑)。「これでいいんだ」って。もちろん悩んでいる方はいらっしゃいましたけど。実態はこの人らは何を思ってるんだ?わかんないからしまっとこうよ、そのほうが安全だよ、と。
戸惑いがない社会は結局その人の本人らしさを無視した社会につながりかねない。この人には何かが残っている、この人は何か思っている。でもそれをうまく汲み取れない。だから戸惑うわけですよね。結局、認知症がどれだけ進行しても、その人のことを考え、その人のことを大切にしようと思えば、私たちは戸惑わざるを得ない。だとすれば、そのどうしようもない戸惑いをせめてみんなで支えあっていけるように、せめて独りにさせないようなもの。それは無いかといえば、介護保険が既にある訳です。それをもっとうまく使えるようにしながら、あるいはもっと介護保険の外ともうまく繋がれるようにしながら、例えばそれは家族会なり、自助グループかもしれないし、もっと違うつながり方もできるかもしれない。そうやってソーシャルな中できちんと戸惑いを支えていくということ。戸惑いをなくすのではなくって、戸惑いを支えていく。そして認知症の人が亡くなられたあとで、残された人がまあ、良かったねと言えるような、そういう経験が積み重なっていくことがこの社会、あるいは認知症の人個人、あるいはそのかたを看ている人たちにとってもいいことなんじゃないかなと思っていますね。
杉本 わかりました。大変貴重なお話、身に染みましたし、勇気をいただきました。ありがとうございました。
(2021年9月8日 ズームにて)
*落合恵美子- 1958年1月15日 - )は、日本の社会学者。京都大学大学院文学研究科教授。専門は家族社会学、ジェンダー論、歴史社会学。、現代アジアにおける家族変動の比較社会学的調査研究にも携わる。
*有吉佐和子『恍惚の人』新潮社 1972年
この記事が参加している募集
よろしければサポートお願いします。サポート費はクリエイターの活動費として活用させていただきます!
