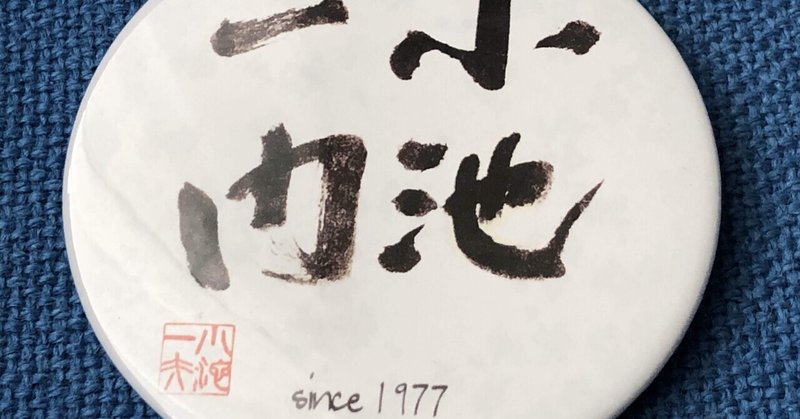
"キャラクターを起てろ!" 劇画村塾第4期生 第3章〈1〉
<小池一夫先生率いるスタジオ・シップの夏合宿〜編集者さん達も参加しての漫画創作セミナー>
今から考えると、
(ホンマにあの頃は俺もまだ初心(うぶ)やったなあ……)
としか思えないのだが、『危(ヤバ)めのヴィーナ』の第一回目が、めでたく『コミック劇画村塾』に掲載されても、相変わらず、不安感と緊張感のほうが先に立っていた。
デビューしたての新人作家にとっては、たとえ一か月に一度の締め切りであっても、ものすごい重圧だったのだ。(その後、経験を重ねて、すっかりスレてしまった自分は、締め切りの当日になってから書き始めるということを平気でやるようになってしまうのだが……自省!)
もちろん、原稿も一度でオーケーが出るわけがなく、K編集長から何度も書き直しを命じられた。
K編集長の漫画原作に対する持論は、
「原作の原稿と言うのは、映画の脚本と同じで、何度も何度も練り直し、描き直しを重ねて、仕上げるものだ」
と、いうものだった。
(申し訳ないのだが、今ではこの論にはちょっと頷けない。梶原一騎先生や小池一夫先生がおっしゃっているように、「たとえ調子が悪くとも、最初に書いたものこそがその作者のその時のベストである」「第一稿=決定稿」という論のほうに、基本的には賛成だ。書き直すことによって、必ずしも良くなるとは限らない。また、他人の意見を聞いたからといって、やはり良くなるとは限らない。個人的な拙い経験から言っても、最初に閃いたことのほうが、後から考えたことよりも、やはり出来がいい)
同時に、
「ちょっとしたアイデアを、色々と自分なりの”こじつけ”をやって、それなりの形でまとめるのがプロだ」
ともよく言われた。
自分なりの”こじつけ”などという技は、当時は到底まだ自分にできるはずもなく、ひたすら書き直しを続けるしか芸がなかった。
(やっぱり、思っていた以上にプロというのは甘くない……)
素直な感想だった。
とはいえ『コミック劇画村塾』でデビューさせてもらったおかげで、スタジオ・シップに出入りしている各社の編集者氏が作品を読んでくれたり、田舎の両親にも「こういう仕事だったのか」と、ほんの少しだけ、自分が何をやっているのか、理解してもらえるようになった。
そして、ちょうど『コミック劇画村塾』の連載が始まってから、しばらく経った頃……。
当時のスタジオ・シップの恒例行事だった、
「夏合宿」
が行われることになった。
本来は、社員旅行も兼ねて、全社員の人たちが参加し、劇画村塾よろしく小池先生の講義を受けたり、ゲストとして招かれている出版社の編集者の方々の話を聞いたりといった、社内セミナー的なものだという話だった。(編集者諸氏は、小池先生の原稿を取りに来るのが本来の目的だった。FAXすら、まだない時代の話である)
その合宿には、劇画村塾生も参加できるということで、自分も末席に加えてもらえることになった。(合宿先を失念してしまったが、確か伊東あたりではなかったかと思う)
神戸や仙台からの劇画村塾生も参加していた。
神戸劇画村塾のエースである西村しのぶさんとは、劇画村塾十周年記念パーティ以来の再会となった。合宿を機に親交を深めることになる浜田芳朗(現・風狸けん)氏との出会いもあった。
また、当時のスタジオ・シップには、やまさき拓味、神江里見、伊賀一洋(現・伊賀和洋)といった漫画家、小堀洋、あきづき笙といった原作者の先生方も所属しておられたし、その先生方のアシスタントの人達も参加しての大所帯で、なんとも賑やかだった。
自分が、何よりも気心が知れていたのは、小池先生のマネージャーの皆さんや、他の部署の社員の方々だった。
連載の打ち合わせなどでスタジオ・シップ本社を訪れる都度、必ず顔を合わせるのはマネージャーさん達や社員の皆さんだったからだ。
その人達には、機会があると、よく飲みに連れて行ってもらったりした。業界の裏話や秘話をいろいろと聞くのが楽しみだった。(現在でも交流の続いている人達もいる)
合宿の陣頭指揮をとられる小池先生は、当然のことながら、何本もの連載原稿を抱えての参加だった。
先述したことではあるが、この当時の小池先生の仕事量は、もう、聞いただけでも目眩がしそうな数だった。
最低でも一日に一本から二本の締め切りがあり、それが土曜日も日曜日も休みなく、ほぼ三六五日、途切れることがなく続いていた。(なぜ断言できるかというと、前述したマネージャーさん達が、小池先生の締め切りのスケジュール表を常に携帯されていたので、それを見せてもらったからだ)
実際、少年誌から青年誌、さらには一般誌や新聞まで、その仕事の幅は多岐に渡っていた。雑誌連載だけでなく、アイススケートショーの脚本や歌の作詞なども手がけられていた。
どうすればそんな分量をこなせるのか、常人には魔神のようなパワーに思えたが、小池先生に言わせると、
「最初にちゃんとキャラクターさえ起てておけば、どうってことはない」
ということになる。
また、
「朝一本、午後一本、夜一本書けば、一日三本書ける」
ともおっしゃっていた。
たかが月一本の原稿でヒーヒー言っている自分が、まさしくアリンコのように小さな存在に思えたものだ。
そして、合宿先でも劇画村塾と同じく、参加者全員に対して、小池先生より課題が出された。
一つテーマが決められ、それに沿った物語を一本書くのである。
絵が描ける人は簡単なネームを、文字でいく人は、やはり簡単な原作を、ということだった。
自分も張り切って書いたが、特にマネージャーさん達の提出した原作原稿が、素人ながら、やけに面白かったのを覚えている。
常に小池先生の側にいて、その仕事ぶりをつぶさに見ている人たちなので、いつの間にかキャラクターの起て方や、アイディアのまとめ方がそれなりに身に付いてしまっていた
らしい。(実際、劇画村塾生ではないが、スタジオ・シップ、後の小池書院の社員から漫画原作者として大活躍することになるのが、『特攻の拓』の佐木飛朗斗氏、『築地魚河岸三代目』の鍋島雅治氏のお二人である)
この合宿先には、某新聞社から記者の人達も取材に訪れて来て、劇画村塾生ということで、自分達もインタビューされ、しっかりと新聞に掲載された。
そんな出来事が続く中で、しかし、自分は、やはり『危(ヤバ)めのヴィーナ』の原稿のことが、終始頭から離れることはなかった。(K編集長をはじめとした『コミック劇画村塾』の編集部の人達も参加しているのだから、当然といえば当然である)
毎月、這々の体で原稿は形にはしていたものの、自分自身でも、
(ぜんぜん、まだまだだ……)
という思いのほうが強かった。
そんな拙なすぎる原作を、それでも丁寧に漫画に起こしてくださっていた愛川哲也先生には、感謝と恐縮しかなかった。
(もっと勉強しなきゃ、それこそヤバい!)
ずっとそう思い続け、ひたすら漫画を読み、映画を観て(ようやく、レンタルビデオ店が出始めたばかりの時代だった)、本を読んでいた。(その頃は意識しなかったが、後に、この時の蓄積が役に立つことになる。やはり、地道な勉強は重ねておくものである)
とはいえ……。
楽しい思い出の多かった夏合宿だったが、自分が参加したものが、諸事情から最後になってしまったようだ。
そういう意味では、実に貴重な体験をさせてもらった夏だったと、今でも感謝している。
そして、なんとかかんとかやっていたところへ、まさに寝耳に水!の事態が勃発する。
『コミック劇画村塾』休刊である。
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
