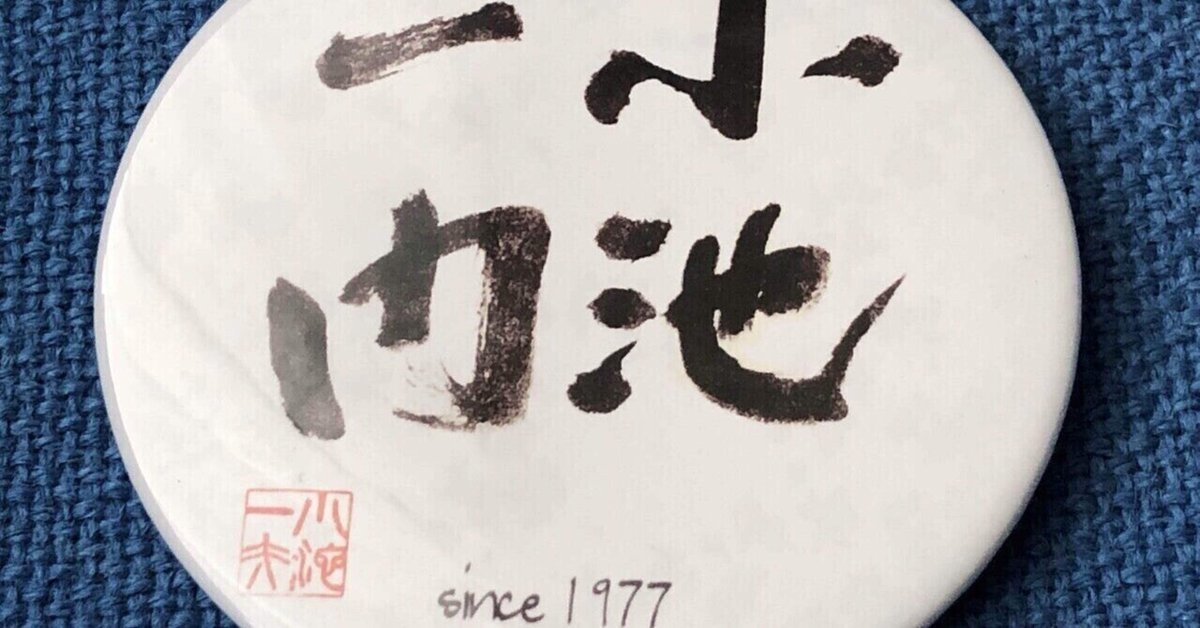
"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第5章〈3〉
<カリスマ性を持った現役の一流作家が率いてこそ〜劇画村塾の存在意義>
ここで、少し閑話休題的に、小池一夫劇画村塾の存在意義について、あくまでも自分なりの意見を記しておきたい。
(劇画村塾に通った皆さん各々で印象も意見も違うはずだからだ)
創作は、本当は、塾やスクールなどでは教えられないという意見もある。
それも一面の真理だとは思う。
が、事実として、劇画村塾からは大勢のプロの作家が育っているし、巷間にある小説教室などからも、やはり今をときめく小説家が多数出ている。
なので、一概に創作の塾やスクールなどを、全面否定することはできないだろう。
要は、教える側がどういう人物であるのか、教えている内容がどれくらい有意義なものであるのかに拠る。
以下、劇画村塾に限定して、いくつかまとめてみる。
(繰り返しになるが、あくまでも個人的な意見である)
(1) 劇画村塾は、小池一夫という、当時第一線で活躍中の、カリスマ的な天才漫画原作者が直接指導するというところに最大の特異性があった。
それは、漫画関係の、他の塾やスクールなどが、決して真似のできない、いい意味で最大のセールスポイントだった。
(小池先生は、小説家の山手樹一郎先生の門下生であった関係で、山手先生の私塾を参考にされていたのかもしれない。似たような形で、池波正太郎先生が出られた長谷川伸先生の私塾なども、きっと同じようなものであったのではないだろうか)
これが、漫画家の場合だと、ある漫画家さんのアシスタントになれば、必然的にそれが実践的な私塾と同じような役割を果たす場合も多々ある。
(漫画家のアシスタントから、プロの漫画家になるのは、今もごく普通のことだ)
だが、全員が全員、漫画家のアシスタントになれるわけではない。
また、漫画の原作者にしても、原作をどのように書けばいいのか、その具体的な方法を、きわめて実践的に教えてくれる人もいなければ、場所もなかった。
漫画家や漫画原作者を目指す人達が沢山いても、なんとか独学するしかなかった。
そういう人達に対して、現役のプロが、漫画と漫画原作の実際を指導していたということは、漫画業界にとっては、ひじょうに意味がある。
そして、先にも書いたことだが、小池一夫という当代一流の売れっ子漫画原作者から、ためになる”雑談”を直接聞けたことも大きい。
作品成立の裏話や秘話をつぶさに聞けたことは、その後、自分自身がプロの作家になってから、どれほど励まされ、役に立ったか、計り知れない。
(これは劇画村塾出身の作家の皆さんが、たいてい口にしていることだ)
ひいては、先輩にプロの作家が多いことも、同じような意味でひじょうに有益だった。
自分自身のことで言うなら、これまで書いてきたように、狩撫先輩やたなか先輩との交流がそうだ。
お二人から学ばせてもらったことは、小池先生からのそれと同じくらいの重みを持っている。
(2)書いた者(描いた者)勝ち、作った者勝ちであることが明確にわかること
劇画村塾は、一つの期に、だいたい六十名が入塾する。
それが一年後には、半数の三十名に減らされ、特別研修生となる。
その間に、課題が何度も出される。
課題とは、すなわち実際に作品を作ることだ。
ひとつの作品を、最初から最後まで、曲がりなりにも”完成”させることは、創作の基本中の基本である。
しかし、それが実際にできる人は、なかなか少なかったりする。
とにもかくにも、作品を何本も完成させることによって、プロへの第一歩を確実に歩み出すことができる。完成させることができない人は、口でいくら何を言おうとも、プロになることは決してできない。
同期生全員が全員サバイバルできないことにより、プロの世界の厳しさの一端を実感することができる。
劇画村塾入塾当初に、自分が小池先生に言われたように、つきるところ、作家は”ローンウルフ”でいくしかないのである。
(3)プロの作家の目を通した、ものの見方や情報収集の方法、それらの作品への活かし方がわかること
小池先生の講義や雑談から、
(プロの作家っていうのは、そういうふうに情報を得たり、そこから閃いたりしているものなのか!)
と、実践的なエピソードを何度も知ることができた。
それまた、自身がプロの作家になってからも、役に立つことの連続だった。
例えば、小池先生の作品には専門的な知識が出てくるものが多いが、資料から取ったものばかりではなく、
「僕はねえ、人間ドックとかに入ると、病院にある医療機器とか、通路に貼られているステッカーとか、いろいろなものが珍しくて、みんな覚えるようにしているんだよ。そして、お医者さんや技師の人に、これはなんですか? とすぐに質問してしまう。そっちのほうに夢中になってしまって、検査が中断してしまうこともしばしばで、怒られちゃったりするんだよ」
というようなことを、よくおっしゃっていた。
あるいは、小池先生原作の時代劇の名作、田村正和さんが主演でドラマや舞台にもなった『乾いて候』の主人公の名前は、腕下主丞(かいなげもんど)というが、
「”腕下”という苗字はね、いろんな人から、よく思いつきましたね、と言われるんだけど、あれは、京都を歩いている時に、たまたまそういう名前の書かれた表札を見かけたんだよ。最初は何と呼ぶか分からなかったんだけど、”かいなげ”と読むと聞いて、これは主人公のキャラクター名に使える! って、すぐにピンときたね」
ということだった。
つまり、実生活において、常にアンテナを張り巡らせていることによって、創作に使える情報を掴むということである。
デビューされて間もない頃は、小池先生は、そういった情報をメモしておくノートを、何冊も所持されていたらしい。
(プロの作家の皆さんは、おそらく皆やっていることだろう)
実際に作家的好奇心から得た知識が、どのように作品に投入されていくのかを知ったことで、
(よし、自分もやってみよう!)
と、自身も動き出すきっかけになった。
(4)最前線で活躍するプロの作家が、いかに自分自身をコントロールしているか、間近で 見れたこと
小池先生が、
「一生を劇画の伴侶として過ごす」
という意味を籠めて、”一雄”から”一夫”に改名されたことは、先でも述べた。
また、”劇画いのち” と書かれた角棒を持って、社内を歩かれていたことも、同じく先述した。
つまり、そこまでして、仕事にのめり込めるよう、仕事に賭けられるよう、”かたち”から律することで、おのれを集中させておられたのだ。
仕事が、他人様のための仕事である限り(作家の仕事には、読者を楽しませるという使命がある)、そこには大きな責任と大変な苦労が伴う。
人間であれば、誰しも、強いプレッシャーからは逃げ出したいと思う時があったとしても、決して不思議ではない。
だが、プロであるからには、逃げ出すわけにはいかない。
そのために、ペンネームを変え、角棒を作り、自分を追い込むような自己管理能力も必要であることを、粛然と学ぶことができた。
(5)不可能だと思える仕事も、やろうと思えばできるという事実を、実地で知ったこと
小池先生は、当時(それ以前も)、まさに殺人的な仕事量をこなされていた。
一年三百六十五日、一日も休まれることなく、執筆を続けられていた。
朝に一本、午後に一本、夜に一本と、一日平均三本の原稿を書き上げられていた。
自分には絶対不可能な技ではあったが、それでも、
(一日一本くらいなら、凡人でも頑張れば仕上げていくことができる……)
それを実地で学ばせてもらうことができた。
プロになれば、状況によって、凄まじい仕事量を的確にこなしていかなければならなくなる。
不可能だと思う分量でも、やってやれなくはないということを、身をもって教えてもらったことは、大きな収穫だった。
その可能性は、他の仕事においても十分に通用するものだった。
自分なりに、劇画村塾の存在意義を書き連ねてみたが、以上のような体験から(他にも細かい学びは沢山あったが)、創作系の塾やスクールには、基本的に賛成の立場である。
そして、教える側の質が、確実にその是非を決めると思う所以である。
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
