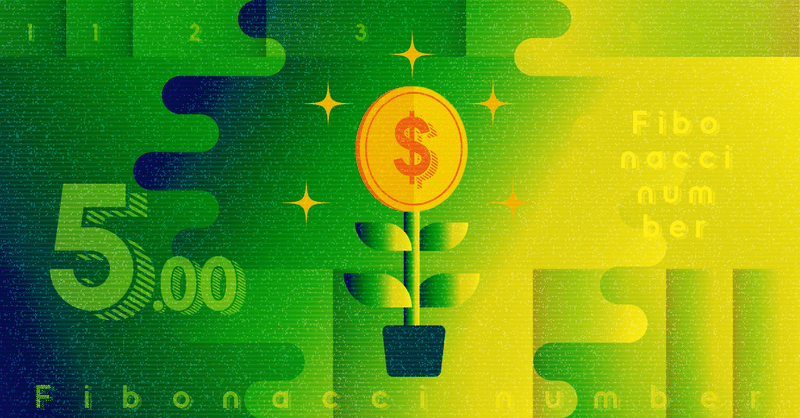
貸株という制度について:2021.08.19
※このnoteは株初心者向けです※
最近、過去に大きく値下がりしたため塩漬けしている株から定期的にお金が振り込まされていたので気になって調べてみたところ、どうやら『貸株』という制度によってお金が振り込まれいるらしい。
『貸株ってなんだ???』
■貸株とは?
下記は、「日本取引所グループ」のページより引用してきたものだ。
証券会社各社が提供するいわゆる貸株サービスとは、投資家が、保有している株券等を証券会社に貸し出すことで、証券会社からこれに見合う貸株金利を受け取ることができるサービスです。証券会社は、投資家から借り入れた株券等を他の投資家等に貸し出すなどの運用を行います。一般に、このような貸株の仕組みは、流動性や決済安定性の向上など、効率的な市場機能の発揮に重要な役割を果たしていると考えられます。
→なるほど。勝手に人の株を証券会社のなんらかの都合で貸しているということか。ただ、『貸株金利』という利息がつくらしい。貸株金利についても同ページに記載があったので引用しておく。
貸株金利は、証券会社が株券を借り入れた投資家に対して支払うレンタル料ともいえ、銘柄や日によって変動しますが、証券会社によっては、年率1%以上が設定される銘柄もあります。
→なるほど、レンタル料か。わかりやすい。
今回振り込まれていた金額はこれのことだ。納得した。
ただ証券会社側は借りてどうするのか?
それについては下図や説明が参考になった。

証券会社は顧客から借りた株を、貸株市場を通じて機関投資家(ヘッジファンドなど)に貸し出し、機関投資家から貸株料を受け取りその貸株料の中から、顧客に金利を払っているというわけです。 ※引用元: マイナビニュース株比較
→あーなるほど。よく理解できた。
■メリット・デメリットは?
まずはメリット。
・保有株式を貸株に出すと、貸株金利が得られる。
・貸株中の銘柄もいつでも売却可能。
というところのようだ。貰えないより貰えはるものは嬉しい。
次にデメリット
・証券会社が倒産した時には株を失う
・配当金相当額を受け取った時には総合課税される
・配当金相当額ではなく配当金を受け取るためには、各企業の権利確定日(決算)にあわせて証券会社に返却指示を出す必要あり
・長期保有に応じた株主優待が受けられなくなるかも
→株主優待については回避方法があるようだが、自分の投資方針とはズレるので一旦ここでは割愛する。
気になるのは、『配当金相当額を受け取った時には総合課税される』という点だ。
■配当金と配当金相当額
貸株の間に配当金の受け取りが発生した場合、配当金に代わって『配当金相当額』が支払われるようだ。
なぜ呼び方が違うのか?
それは呼び方を変えて区別したいからにはからに他ならない。配当金相当額には以下の特徴がある。
・配当金相当額で取得できる金額は、源泉徴収税額を差し引いた配当金の額と同額となります。
・税区分が「雑所得」となり、配当控除の対象外となります。また、株式等の譲渡損と通算はできません。
・外国税額控除の対象外となりますので、銘柄によっては源泉徴収税額を差し引いた配当金の額と同額にならない場合がございます。 ※引用元:GMOクリック証券(配当金と配当金相当額の違い)
→押さえておきたいのは、税区分が変わるということだ。
配当金と配当金相当額の税区分の違いは以下の通り。
配当金(配当所得):源泉徴収後の金額が振り込まれる。確定申告不要制度が選べる。確定申告で総合課税を選ぶと、配当所得控除を受けられる。
配当金相当額(雑所得):源泉徴収後の配当金を同じ額が振り込まれる。確定申告が必要※で、税金が引かれる。総合課税だが配当控除の対象にはならない。 ※年間給料が2000万円以下の会社員で、給与・退職所得以外の合計額が20万円以下の人は確定申告不要。
→なるほど。配当所得または雑所得の違いは押さえておきたい。
あとは気になるのは確定申告のところ。
ただ、給与所得者であれば20万以下の雑所得は確定申告不要となるようだ。
確定申告はめんどくさいけど脱税は絶対したくない。
今後この点(手間も含めて)考えておきたいところ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
