
[無料]2023年の山岳遭難概況雑感
6/14に、警察庁から2023年の山岳遭難概況が発表されました。毎年6月中旬くらいに公開されるものです。
ダウンロードはコチラから↓
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r05_sangakusounan_gaikyou.pdf
来年になると消えてしまうのでダウンロードして取っておきましょう。
去年書いた感想はコチラ。予想もしてますが、結果はどうだったかな?
さて、ざっくりの傾向と感想
発生件数が3126件と過去最多。
死亡・行方不明は335人と微増。なお、最近でこれより多いのは2017年の354人。2017年は那須で高校生達が雪崩に巻き込まれて8名が亡くなった年です。
主な山岳別のページが新設され、富士山、高尾山、穂高などで顕著に件数が増えていると報告されています。
態様別では道迷い遭難の割合が33.7%と減少傾向。件数としても↓のグラフのように2022年で横ばい、2023年でようやく減りました。

道迷いの代わりに増えているのが滑落、病気、疲労。転倒も2022年と2023年では横ばいだけど増加傾向。
落石も例年10件前だが、2023年は20件、雪崩も前年の13件から20件に増えた。もともとの数が少ないので誤差かもしれないが。
年齢層別では相変わらず40代以上が80%、50代以上で67%、60代以上で50%となり、中高年から高齢者の遭難が多い。実際には遭難者の多くが男性という統計があるので、おっさんとおじぃちゃんの遭難が多いと言える。自分の年齢を考えて無理のない登山をしましょう。
死者数が顕著に多いのは70代で35%を占める。団塊の世代の登山者が山で死にすぎです。この傾向はまだ暫く続くでしょう。
訪日外国人による遭難のページも新設されました。こちらも顕著に増えており、コロナ禍が過ぎての円安で今年も来年も増えていくでしょう。遭難対策の外国語対応が急務です。
冒頭のまとめの変化
こんなツイートのやり取りがあったので、ここにまとめておきます。
概況の冒頭では遭難の全体像と対策について書かれているのですが、道迷い遭難対策にGPSアプリが登場するのは、2023年発表の概況からなんですよね。
はい、では2007年からの山岳遭難概況を振り返って、どう変化してきたか見ていきましょう。2007年(2008年発表)は当然言及は無し。飛ばして2013年も言及なし。2018年まで飛んでも無し。通信手段で初めて言及したのが2019年(2020年発表)です。結構早かったと思うかは個人の価値観かも知れませんが。 https://t.co/fIuF3MrxG5 pic.twitter.com/Jvey3rdLjP
— マツモトケイジ@ジオグラフィカ開発者 (@keizi666) June 13, 2024
登山用の地図アプリがこの世に生まれたのが2009年12月、2015年くらいには現在主流の地図アプリは出揃っており、それなりの登山者が使っていたはずですが、長らく遭難対策としては触れられていませんでした…。
僕が持っている2007年以降の遭難概況を遡って見ると、2019年発表の2018年概況でもGPS機器やスマホ、地図アプリには触れていません。
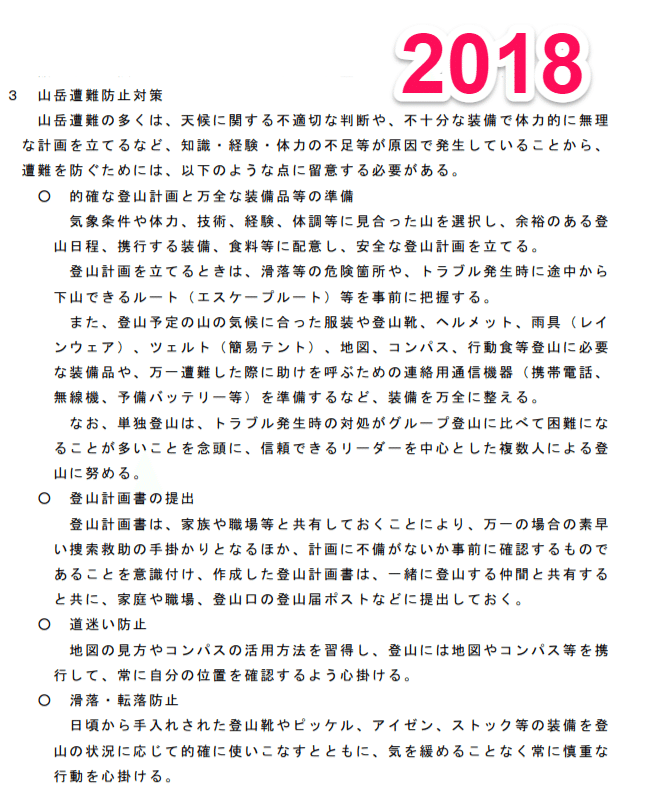
GPSについて初めて触れたのは2020年に発表された2019年の概況で、「GPS機能付きの携帯電話等は、自分の現在地をより速やかに救援機関に伝え
ることができるなど、救助要請手段として有効であるものの、多くの山岳では通話エリアが限られることやバッテリーの残量に注意が必要である」と書いています。

2007年から通報時に通報を受けた側(警察や消防)で位置取得が出来るようになったそうで、「現在地をより速やかに救援機関に伝える」はその機能のことを指しているのでしょう。
初めて登山用地図アプリに言及したのは、2023年6月に発表された2022年版(令和4年)においてです。「なお、登山地図アプリと紙の地図を併用することで、より正確な位置を把握することができるため、道迷いの防止につながる。」と書かれたのが登山地図アプリに触れた初の例となります。

有効と認めるまで時間掛かったな!という感想です。もっと早く言ってれば歴史を多少は変えられたんじゃないかって気もします。もう今更ですけどね。まぁ、警察のように大きな組織の動きが遅いのは仕方ないですね。
登山用の地図アプリは圏外の山奥でも使えます
登山用として開発された地図アプリは事前に地図をダウンロードしておくことで圏外の山奥でも地図を表示して現在地の確認やナビゲーションができます。登山用と名乗っていて圏外で使えないアプリはありません。
拙作のジオグラフィカも同様です。ジオグラフィカの場合は、事前に現地の地図を見ておくことで、画面に表示された地図をキャッシュ(ダウンロードと同義と思ってください)し、山奥でも使えるようになっています。まだ使ったことがない方はスマホにインストールしてみてください。
来年の予想
遭難が減る要素も無いですし、来年もきっと過去最多を更新することでしょう。
3800人が遭難して340人が死ぬくらいの感じですかね。
訪日外国人の遭難も増えるでしょうし、富士山と高尾山の遭難も更に増えてカオスになりそうです。
コロナ禍以降のハイキングブームで増えた、登山を知らないハイカー達がキャンプブームの終焉と同じくして山から去った感じがします。道迷い遭難は更に減るかも知れません。
病気、疲労、転倒、滑落はもっと増えそう。特に病気と疲労が増えそうです。
団塊の世代はまだ登山を引退しそうにないので、あと5,6年は遭難が増えるんじゃないかと思います。その後は団塊ジュニアの僕らが遭難を増やす要因となっていくでしょう。
山岳遭難の未来は暗そうです。
未来を変えていこう!
今年も半分終わります。遭難概況には月別の遭難件数が載ってませんでしたが、神奈川県、北海道、長野県の月別統計で平均を取ってみると6月いっぱいまでに4割の山岳遭難が起きているようです。今年すでに1520人が山で遭難して136人くらい亡くなってるという事になります。
そして、大晦日までに山で2280人が遭難して、204人が死ぬか行方不明になるということでもあります。これは統計的にほぼ間違いありません。これくらいの人数の人達が山で不幸になると確定しています。
しかし、自分や家族、仲間が山で死ぬかも知れない、大怪我をするかも知れないと考えて行動するなら未来を変えることは出来るかも知れません。
今日から先の未来は変えられます。変えましょう。
あなたがやってるのは登山です。散歩やピクニック気分で低山に登る人がかなりいます。観光の延長みたいな格好の方もよく見かけます。水しか入ってないリュック、スニーカーやサンダル、街と変わらない服装…。ガッチリ装備を固めろとまでは言いませんが、もう少し考えませんか?あなたの意識と無関係に、登山は登山です。山に入ることを恐れてください。山は楽しいけれど危険な場所です。東京近郊では高尾山(特に奥高尾)、大岳山、棒ノ折山、サス沢山などで『お散歩登山者』をよく見かけます。かなり危険な行為と自覚しましょう。
ヘッドランプを絶対に持て!これは絶対です。例外はありません。高尾山でもピクニック気分で行く丘陵でも、ハイキングでもトレランでも、山に入るなら必ずヘッドランプを持ってください。山の暗闇を舐めるな。
遭難したらその日には帰れません。なぜ晴れた日にカッパを持つべきなのか?それは遭難して動けなくなったらその日には帰れず、場合によっては数日間山中で生き延びなければいけないからです。そのときに身を守る装備が無ければ簡単に死にます。カッパ、ツエルト、ファーストエイドキット、モバイルバッテリーを必ず装備に入れてください。
欲張ってはいけません。余裕のある計画を立てましょう。基本は15時までの下山です。普通の人は、コースタイム3時間の山からはじめてください。
「登山は死ぬ可能性がある危険な遊び」と自覚して必要な知識を学びましょう。分かった上でリスキーな事をする自由はありますが、知らずに初見の地雷を踏んで死ぬのは不幸です。よく勉強してください。
自分や仲間が、今、どういうリスクを背負っているのか理解して行動しましょう。なんてことない登山道は本当に「なんてことない」のかよく考えましょう。事故はなんてことない場所でよく起こります。
身の丈に合った山に登りましょう。山のグレーディング表などを参考にして、自分のレベルに合った山を選んでください。
登山の難易度は標高では決まりません。メジャーな3000m峰より難しい低山はいくらでもあります。
登山中、危なそうな人がいたら、優しく、カドが立たないよう声を掛けましょう。
調子がいいときは心とカラダがズレてしまう事があるので事故を起こしやすいです。調子良いときこそ注意してください。勝って兜の緒を締めよ。
「良い記録を残したい」とか「いいとこを見せたい」など、邪念があると判断を誤ります。邪念は捨ててください。
年齢を考えて、若いときの感覚で無茶してはいけません。若い頃の感覚でギリギリの登山をすると、条件が悪くなった時に遭難します。余力を残してゴール出来るくらいが趣味としてはちょうどいい。
頻繁に登山できないのなら、ウォーキングやスクワットなどで普段から足腰の運動をしておきましょう。
「まぁいいか」と呟いたら、本当にいいのかよく考えてください。
「~だろう」と都合のいいように考えるクセは危険。「~かもしれない」と考えるようにしてください。天気が悪いかも知れない、道が悪いかも知れない、今日帰れないかも知れない。「かもしれない」を想定して登山をしましょう。
「暑い、寒い、痛い」は我慢しない。出来るだけ早くウェアを調整し、痛い箇所があるなら早めに手当してください。我慢してても改善しません。手持ちの装備で対応出来ないなら撤退を考えてください。
パーティー登山をするのなら、最後まで一緒に行動してください。目が届かないくらい離れたらパーティー登山の意味がありません。
リーダーはメンバーに思いやりを持ちましょう。一人でどんどん先に行ったりしてはいけません。パーティー内の一番弱い人を基準に判断しましょう。それが出来なければパーティー登山の意味がありません。
雑な登山をしていると事故ります。丁寧な登山をして、遭難を防ぎましょう。統計的有意なくらいに遭難を減らして、未来を変えていきましょう!
わぁい、サポート、あかりサポートだい好きー。
