
法人税務データを用いた研究動向と自治体税務データの有用性:行政データと実証経済学⑦
経済セミナー編集部noteでは、『経済セミナー』2022年6・7月号から23年10・11月号まで8回にわたって連載した「行政データと実証経済学:東京大学CREPE自治体税務データ活用プロジェクトの実践」を、第1回から改めて掲載していきます。
第1回から第8回までの各回は、以下の noteマガジン に順次公開していきますので、ぜひご覧ください。
このnoteでは、2023年8・9月号に掲載された連載 第 7 回 をお送りします。
著者紹介
鈴木崇文
愛知淑徳大学ビジネス学部准教授。
プロフィール
2019年、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了、博士(経済学)。愛知淑徳大学ビジネス学部講師等を経て、2023年より現職。 自治体の財政行動や、税制と企業行動に関する研究に取り組む。 論文:"Capitalization of Local Government Grants on Land Values: Evidence from Tokyo Metropolitan Area, Japan," Japan and the World Economy, 60, 101106, 2021 等。
1. はじめに
本連載の7回目となる今回は、法人に関する税務データの紹介を行いたい。東京大学政策評価研究教育センター(CREPE)による自治体税務データ活用プロジェクトでは、2021年度および2022 年度において、都道府県が徴収している法人事業税をはじめとする地方法人税目に関して、過去の申告データを提供いただいている。これまでの連載では、市町村から収集した主に個人住民税等の税務データについて、税収予測やその他研究への利用例を紹介してきた。しかし、経済学研究では、法人に関する税務データを活用した研究も広く行われており、研究結果を政策立案に活用できる可能性は同様に高い。そこで、今回は海外での税務データを活用した研究事例を交えながら、自治体から提供を受けた法人税務データの特徴とその有用性を、実際のデータを用いて紹介することで、法人税務データを利用した今後の研究の方向性を展望したい。
2. 学術研究における法人税務データの利用動向
2010年代前半以降、税務データの学術研究への利用は世界的に急速に浸透している(Currie et al. 2020)。近年では、行政能力の比較的高い北欧、イギリスやフランス、カナダやアメリカ等の欧米先進国だけでなく、ブラジル、チリ、中国、コスタリカ、エクアドル、インド、パキスタン、ルワンダ、チュニジア、ウガンダなど多くの発展途上国でも、こうしたデータが利用できるようになっている(Slemrod 2019)。税務データの利用が浸透する中で、個人だけでなく法人に関する税務データも活用が進められている。たとえば、法人税の課税所得弾力性の推定(Devereux et al. 2014)、企業の脱税行動と税設計との関係(Best et al. 2015)、租税特別措置が企業の設備投資やR&D投資に与える影響(Zwick and Mahon 2017;Chen et al. 2021)、企業が直面する税務コンプライアンスコストの大きさの評価(Almunia and Lopez-Rodriguez 2018;Harju et al. 2019)、付加価値税の価格転嫁(Kosonen 2015)、多国籍企業の移転価格を利用した租税回避・利益移転(Liu et al. 2020)など、枚挙に暇がない。利用分野も以上のような財政・公共経済学分野だけにとどまらず、開発、環境、金融、国際、都市経済学などその他のさまざまな領域で利用が拡大している。また、利用される税目も法人税だけでなく、付加価値税(消費税)や売上税、社会保険料(税)、関税、固定資産税など多岐にわたる。
一方日本では、税務データの学術研究への活用はまだ始まったばかりである。本プロジェクトの他には、国税庁による個人所得税および法人所得税の税務申告データの共同研究利用、また財務省による輸出入申告データの共同研究利用が開始しているが、これらが開始したのは昨年からである [1]。将来的には、こうした研究利用の成果を受けて、利用範囲や利用可能なデータの幅が徐々に拡大していくものと考えられる。
[1] 国税庁と財務省における共同研究について、詳しくは次のホームページ等を参照。国税庁ホームページ「共同研究」、財務省ホームページ「輸出入申告データを活用した共同研究に関する有識者会議」。
本プロジェクトでの法人事業税申告データは、ある都道府県に事業所を持ち、法人事業税を納税している企業の情報しかわからないが、現状、地方法人税の申告情報を捉えることができる唯一のデータであること、地方法人税では多様な課税標準が設定されているために企業によっては豊富な情報を得られること、などが特徴として挙げられる。
3. 自治体法人税務データから何がわかるのか
3.1 都道府県から提供を受けているデータについて
現在、本プロジェクトでは複数の都道府県から法人事業税等の申告データを提供いただいている。今回はその自治体の1つである宮城県から提供を受けたデータを用いて、その特徴やデータから明らかになったことについて紹介したい。なお、データは2014年から2022年までに行われた申告情報を含んでいる。ご存じの通り、宮城県は人口は約 230万人(2020年度 国勢調査)、名目県内総生産は約9.8兆円(2019年度 県民経済計算)で、いずれも47都道府県中14位と、比較的人口・経済規模の大きい自治体であるといえる。また、政令指定都市である仙台市を中心とする仙台大都市圏を含んでいるため、一定程度独立した経済圏における企業の分布が観察できる。
3.2 日本の法人所得税制について
実際のデータを見る前に、日本の法人所得に対する税制について確認しておこう。ここでは、法人所得に対する税制を包括的に説明することは差し控え、国税である法人税と、地方法人二税(法人住民税および法人事業税)に関して概説する。
1つ目の法人税は、法人所得を課税標準とする国税である。法人所得は、益金(売上収入等)から損金(売上原価や販売費等)を引いた金額をもとに、法人税法の規定に基づく税務調整を経て算出する。これに一定税率を適用し、税額控除額を差し引いた額が法人の納税額になる [2]。税率は、現在23.2%であるが、中小法人に関しては軽減税率の特別措置がなされており、所得が年800万円以下の金額については15%となっている [3]。直近ではこれらの税率は比較的安定しているが、長期的には徐々に引き下げられてきた。
[2] 財務省「法人課税に関する基本的な資料」
[3] 中小法人とは、主に資本金の額等が1億円以下の法人で、かつ資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除く(財務省「中小法人に対する課税に関する資料」)。
2つ目の地方法人二税は、先述の通り法人住民税および法人事業税を指し、日本における代表的な地方法人税であるといえる。法人住民税は市町村と都道府県の両方が、法人事業税は都道府県が課税する。これら地方法人税は、国税である法人税と比較すると、課税標準や税率等が法人の業種や規模等により細かく定められており、やや複雑である。以下では、データが得られている宮城県の税制をもとに説明するが、自治体ごとに税率等の点で若干の違いがある点には留意されたい。
法人住民税には、資本金等の額や従業員数に応じた定額税である均等割と、国税の法人税額に応じて比例的に課される法人税割がある。両者について道府県民税および市町村民税が設定されており [4]、法人の事業所等が所在する都道府県および市町村に納税が求められる。
[4] 東京都に関しては道府県民税に相当する都民税がある。
23区内は道府県民税に相当する税と市町村民税相当分を合算した都民税を都に納税する。23区外は都民税を都に、市町村民税を各市町村に納税する制度となっている。
一方で、法人事業税は都道府県のみが課す税である。中小法人については、基本的には、課税所得に一定税率をかけた額を納税する所得割のみが課されるため比較的単純であるが、主に資本金額 1億円超の大企業が該当する外形標準課税適用法人では、課税方法がやや複雑である。外形標準課税適用法人では、上述の所得割に加えて、外形標準課税である付加価値割と資本割が課されることになる [5]。付加価値割は企業の生産した付加価値額に対して、資本割は資本金額に対して一定の税率が課せられる。それに対し、所得割の税率については法人規模や所得によって異なる。第1に、外形標準課税適用法人か否かで異なる。上述のように、大企業は外形標準課税が課せられるため、中小企業と比べて税率が抑えられている。第2に、税率は累進的である。限界税率は、所得が400万円および800万円の閾値でそれぞれ上昇する。外形標準課税適用法人と中小法人それぞれに関して、累進的な税率が設定されている。
[5] 電気供給業(発電事業、小売電気事業又は特定卸供給事業を除く)・ガス供給業(一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業を行う法人)・保険業を行う法人に関しては、収入額に対して一定税率を課す「収入割」が導入されており、基本的に中小法人に関しては所得割と収入割、大法人に関しては収入割、付加価値割、資本割が課される。
その他に、地方自治体における法人課税について注意すべき重要な点を4点述べておきたい。1 点目は、超過税率に関してである。都道府県や市町村は、税目によっては国の定める標準税率を超えて超過税率を定めることができる(ただし国の定める制限税率の範囲内)。そのため、自治体ごとにわずかであるが税率に差が生じている。たとえば法人事業税では、特に三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)を中心に超過課税が行われている。2点目に、法人税の課税所得と法人事業税所得割の課税所得には乖離がある。たとえば、法人税で設けられている繰戻還付制度は法人事業税には存在しない。また、法人税の課税所得を計算する際には、納税申告書を提出した事業年度において法人事業税額の損金算入が可能である。つまり、今年度課税所得を計算する際には、法人事業税の中間申告額や前年度申告額を損金算入できるため、両税の課税所得に乖離が生じることになる。3点目は地方法人二税における分割基準についてである。法人によっては、複数の自治体に事業所を設置するケースがあるが、その場合には納税を行う自治体での従業員数や事業所数等で定められた分割基準に従って課税標準額を按分し、分割後の課税標準に対して各自治体の税率をかけることで税額を算出する。4点目は、法人税と地方法人二税の他に課される税についてである。たとえば、法人事業税所得割額等を課税標準とする特別法人事業税(国税)が存在しており、企業が一定の課税所得に対して直面する税率はさらに高くなる。こうした税目は、自治体間の法人税収に関する格差を縮減する目的で設置されており、政府間財政移転制度を通じて全国の自治体に税収が配分される。
以上のように、法人税と地方法人税を合わせて考える場合、制度が非常に複雑になっている。次項では、提供を受けたデータから明らかになったことについて述べるが、議論を簡単にするために、考慮する税制については法人税および地方法人二税のうち法人事業税の所得に課せられる所得割のみを取り上げる。加えて、他の政府統計等の個票データでは観察が難しい中小法人に特に着目して議論を進めることにしたい。
3.3 既存の統計との比較と税務データから新たにわかること
では、提供されたデータを用いて、法人税法で規定される中小企業を対象として、課税所得の特徴を見ていこう [6]。ここでの中小企業は、大まかにいえば資本金1億円以下の法人である。上述のように、法人税および法人事業税所得割に関して、中小企業は一定以下の課税所得については軽減税率の適用を受けることができる。法人税では、年 800万円以下の所得金額に関して税率が23.2%から15%に軽減される。一方、これを上回る所得に関しては、本則税率である23.2%が適用される。また、今回注目する宮城県の法人事業税所得割に関しては、年400万円以下の課税所得に対しては 3.5%、400万円超800万円以下には5.3%、800万円超に関しては7.0%が適用されている(2023年 4月1日現在)[7]。法人事業税法人税割の税率は地域によって若干のばらつきが存在するが、大きく異なることはない。また、400万円と800万円という限界税率が変化する閾値は、分析期間中の 2015~2021年度において移動することはない。これらの税率をもとに、課税所得に対する法定税率のスケジュールをグラフにすると、図1のように描ける [8]。先ほど述べたように、法人税と法人事業税とで課税所得に若干の乖離があるが、その点は捨象してグラフを描いていることに注意いただきたい。
[6] 本稿では中小法人として、法人事業税において普通法人に分類される者を対象として議論を進める。したがって、協同組合や医療法人等の特別法人、電気供給業やガス供給業等を行う法人等は対象としない。また、課税期間をἧえるために事業期間が12カ月の法人を対象とし、各法人の確定申告における数字を用いることとする。
[7] 対象となる法人に関しては、分析期間となる2015~ 2021年度中に、法人事業税の所得割において税率に若干の変化が生じている。限界税率は所得400万円以下、400 万円超~800万円以下、800万円超でそれぞれ異なるが、 2015年4月~2019年9月は下から3.4%、5.1%および6.7%となっている。2019年10月以降は、下から3.5%、5.3%および7.0%となっている。ただし、この変更は地域間の税源偏在を是正するための措置として2008年度から導入されていた地方法人特別税(国税)を廃止し、特別法人事業税(国税)を新設したことに伴うもので、国と地方を合わせた実質的な企業の税負担に変化はない。
[8] 前項で述べたように、他にも、法人税額を課税標準とする法人住民税法人税割や法人事業税所得割額等を課税標準とする特別法人事業税が存在するため、企業が一定の課税所得に対して直面する税率はさらに高くなる。本稿では、議論を簡単にするために国税法人税および法人事業税所得割の税率にのみ焦点を当てている点に注意いただきたい。

注)⑴ 横軸には企業の課税所得、縦軸左には税引後所得、縦軸右には限界税率を示している。⑵ 実線は課税所得額に対する税引後所得額を、破線は課税所得額に対する限界税率を示している。⑶ 課税所得400万円および800万円をそれぞれ超えると限界税率が上昇するため、実線で表された税引後所得に関するグラフは、各閾値で屈曲している。
図1より、中小企業の直面する限界税率は課税所得400万円超と800万円の閾値で引き上げられるため、図では変化がわかりにくいが、税のスケジュールは各閾値で屈曲する。特に800万円超では、国税および地方税両方の限界税率が引き上げられるため屈曲が大きい。たとえば企業が800万円の閾値に直面する場合、800万円を超えた所得に課せられる税率はこれまでの税率より高いため、課税引後所得の増加分は小さくなる。そのため、企業によっては自らの課税所得が800万円を超えないように調整する行動をとる可能性がある。特に、800万円の閾値を超える所得については限界税率がおよそ 20%から30%と大きく上昇するため、課税所得を閾値に抑える行動は顕著に起きると考えられる。
実際、イギリスの税務データを用いて課税所得分布を分析しているDevereux et al.(2014)では、中小企業が租税回避のために閾値付近に集群(bunching)することを示し、観察される集群を用いて法人税率に対する課税所得の弾力性を推定している。図2は、Devereux et al.(2014)による限界税率が引き上がる課税所得10,000ポンド(£)の閾値における集群を示した例である。この閾値で限界税率が0%から20%超に引き上がるため、多くの企業が租税回避を目的として課税所得を閾値付近に調整していることがわかる。

注)⑴ 横軸には企業の課税所得、縦軸左には企業数、縦軸右には限界税率を示している。⑵ 実線は課税所得に対する企業数の分布を、破線は課税所得が10,000ポンド付近の企業についての2004年度における限界税率を示している。⑶ 課税所得が 10,000ポンドを超えると限界税率が上昇する。
出所)Devereux et al.(2014)のFigure 2 Panel Aをもとに筆者作成。
また、課税所得は益金から損金を差し引いた額であり、これがプラスになる場合にのみ課税がなされる。法人の益金に対して損金が上回る(すなわち赤字が発生)場合は、その赤字額が欠損額として課税対象外になるためである。加えて、一定期間にḪる過去までに生じた欠損金額を、今期の所得と相殺することが可能であるため、こうした繰越欠損金が存在する企業は、今期所得からさらに欠損金を差し引いた額に課税が行われる。特に中小法人は、今期所得の全額まで欠損金を損金算入可能である [9]。課税所得がゼロからプラスに切り替わる地点で、法人税および事業税の課税が始まるため、400万円や800万円の閾値と同様に、企業は課税所得をゼロに調整することで租税を回避する誘因が生じる。したがって、課税所得がゼロの地点においても集群が生じることが予想される。
[9] 中小法人以外については、今期所得の50%に相当する額までしか繰越欠損金を控除することができない。
では、実際のデータでは法人の課税所得はどのように分布しているのだろうか。既存の集計データとして得られる課税所得に関する情報としては、国税庁による「会社標本調査」や、総務省が取りまとめている「道府県税の課税状況等に関する調」が挙げられる。これらの統計からは、所得階級や資本金階級別での法人数等を把握することができる。こうした既存の統計と同様に税務データを用いて集計を行う際の優位性としては、次の2点が挙げられるだろう。1点目に、より詳細な企業の所得分布が把握可能である。本稿で用いる自治体税務データは都道府県単位等のデータであるため、日本企業の母集団を示しているわけではないが、個票データであることから任意の切り口で集計ができる。そのため、限界税率が変化する付近の課税所得の分布の形状の分析、産業や市町村別の分布の比較等、研究者や政策担当者の目的に応じて、より詳細な分析が可能となる。2点目に、既存の集計データでは、欠損法人 [10] の状況について把握することが難しいが、自治体税務データからは欠損法人に関する詳細な把握が可能になる。既存の集計データでは、欠損法人数に関してはその総数しか把握できず、欠損規模別での法人数や欠損額に関する分布は示されていない。一方、税務データからは、欠損ゼロ付近で企業がどのように分布しているのか等を把握することができる。
[10] 欠損法人とは、課税所得がゼロまたは負の法人、もしくは繰越欠損金控除後の所得がゼロになる法人を指す。
ここでは一例として、閾値付近における中小企業の課税所得分布を見てみよう。前述のように、課税所得400万円や800万円付近、またゼロ付近では、追加的な所得に対する税率が引き上がるため、企業の集群が観察できると予想される。図3では、法人事業税の課税所得について、400万円と800万円付近の分布を示している。驚くべきことに、両者とも閾値付近で明らかな集群は見られない。特に800万円の閾値では、法人税と法人事業税を合わせた限界税率が約10%と大きく引き上がるが、特に企業は所得を調整していないようである。法人事業税ではなく、法人税の課税所得を用いた場合も同様に企業の集群は確認できなかった。

注)⑴ パネル ⒜ は課税所得400万円、パネル⒝は課税所得800万円の閾値付近の課税所得の分布を示している。⑵横軸には法人事業税の課税所得、縦軸には各ビンの法人数を示している。⑶ 中央の黒の垂直線は限界税率が上昇し課税スケジュールが屈曲する、課税所得額400万円、800万円を示している。
なぜ企業は限界税率の上昇に対して所得を調整しないのだろうか。その要因を明らかにするためには、さらに分析が必要であるが、海外の既存研究での議論を参考にすれば、企業の課税所得調整費用が大きいこと、企業が自らの所得や閾値を正確に把握していないこと等が考えられる。実は今回得られたエビデンスは、既存研究で間接的に得られていた結果とも整合する。たとえば八塩(2020)では、財務省の実施する「法人企業統計調査」を用いて、課税所得を代理すると考えられる法人利益の大まかな分布を描いており、同様に 400万円や800万円の閾値での顕著な反応は見られていない。今回の結果は、実際の課税所得でも集群が生じていないことを示すものといえる。
次に、課税所得がゼロ付近(つまり、今期所得から繰越欠損金額を差し引いた金額がゼロ付近)での分布を見てみよう。図4パネル ⒜ はサンプル全体に関しての、課税所得ゼロ付近の企業の分布を示している。ゼロを中心として企業が集群しており、特にゼロをとる企業は、グラフで示されている課税所得が300万円から300万円をとる企業のうち、実に38.5%にも上る。この傾向は、既に繰越欠損金がある企業において顕著である。パネル ⒝ では、前期にも申告を行っていた企業のうち、前期に欠損金が生じた企業かどうかでサンプルを分けている。繰越欠損金がある場合ほど、今期の課税所得をゼロに調整することがより容易だと考えられる。実際、図から明らかなように、繰越欠損金がある企業の方が、法人課税所得をゼロに集中させる傾向がより強く表れていることがわかる。この結果から、一部の企業は課税所得をゼロ(もしくは未満)に抑えることで税負担を回避しようと行動していると考えられる。

注)⑴ パネル ⒜ は全体サンプルに関しての課税所得0万円付近での分布、パネル ⒝ は前期が観測できる企業に限り、前期繰越欠損金がある企業とない企業についてそれぞれの分布を示している。⑵ 横軸には法人事業税の課税所得、縦軸には各ビンの法人数を示している。⑶ 中央の黒の垂直線は課税が開始する課税所得額0円を示している。
ここで得られた結果は、既存の集計データからではわからなかった事実の一例となる。その他、税務データを政府統計調査等の個票データと比較した場合にも、いくつかの優位性があると考えられる。1点目は、企業の課税所得や納税額に関する情報が得られる点である。既存の統計から納税額等を把握しようとする場合、上場企業や大企業であれば部分的に可能ではあるものの、非上場企業や中小企業については詳細や大規模な把握が難しい。税務データからは、これらの企業についての情報を得ることができるため、より包括的な政策効果の測定が可能になる等のメリットがある。 2点目に、サンプル調査である場合が多い統計調査と比較して、税務データは母集団情報が得られるため統計的検出力が高くなる。基本的に納税義務者になっている企業であればすべて観察できる(=域内企業の母集団に近いサンプルを手に入れられる)点が優れている。3点目に、企業の税務申告行動を観察することができる。この点は、税務申告データならではであり、たとえば企業の直面する税務コンプライアンスコストの計測や電子申告システム導入の効果分析等さまざまな分析を行うことができるだろう。
4. 日本の法人税務データを用いた研究の展望
最後に、日本の法人税務データを用いた研究の可能性について簡単に述べておきたい。日本では他の先進国と比較してこれまで税務データの研究利用が進んでいなかったこともあり、研究の蓄積はまだ少ないのが現状である。しかし、東京大学政策評価研究教育センター(CREPE)による本プロジェクトや、財務省や国税庁との共同研究形式での税務申告データの研究利用が生まれてきている。税務データには、既存の個票データと比較して数多くの優れた特徴がある。しかし、現状では行政が得ている企業のバランスシート情報や、租税特別措置や補助金等の政策利用の情報等との接続がなされていないため、十分な研究への活用が難しい面もある。これらの課題に関しては、既存の政府統計個票データ等との接続をすることで部分的には回避可能ではあるものの、より包括的な政策評価分析を行うためには税務行政機関との協働を通じた、複数の行政データの統合が望まれるところである。今後税務データの研究利用が浸透し、データに関する知見や分析が深まり、活用可能なデータが増えることで、政策評価や実施に広く活かされるようになることを期待したい。
参考文献
八塩裕之(2020)「税制が中小法人オーナーの節税行動に与える影響──法人企業統計個票を用いた分析」証券税制研究会編『企業税制をめぐる最近の展開』日本証券経済研究所、第2章。
Almunia, M. and Lopez-Rodriguez, D.(2018)”Under the Radar: The Effects of Monitoring Firms on Tax Compliance,”American Economic Journal: Economic Policy, 10(1): 1-38.
Best, M. C., Brockmeyer, A., Kleven, H. J., Spinnewijn, J. and Waseem, M.(2015)”Production versus Revenue Efficiency with Limited Tax Capacity: Theory and Evidence from Pakistan,”Journal of Political Economy, 123(6): 1311-1355.
Chen, Z., Liu, Z., Suárez Serrato, J. C. and Xu, D. Y.(2021) “Notching R&D Investment with Corporate Income Tax Cuts in China,”American Economic Review, 111 (7): 2065-2100.
Currie, J., Kleven, H. and Zwiers, E.(2020)”Technology and Big Data Are Changing Economics: Mining Text to Track Methods,”AEA Papers and Proceedings, 110: 42-48.
Devereux, M. P., Liu, L. and Loretz, S.(2014)”The Elasticity of Corporate Taxable Income: New Evidence from UK Tax Records,”American Economic Journal: Economic Policy, 6(2): 19-53.
Harju, J., Matikka, T. and Rauhanen, T.(2019)”Compliance Costs vs. Tax Incentives: Why Do Entrepreneurs Respond to Size-based Regulations?”Journal of Public Economics, 173: 139-164.
Kosonen, T.(2015)”More and Cheaper Haircuts After
VAT Cut? On the Efficiency and Incidence of Service Sector Consumption Taxes,” Journal of Public Economics, 131: 87-100.
Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T. and Guo, D.(2020)”International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the United Kingdom,” Review of Economics and Statistics, 102(4): 766-778.
Slemrod, J.(2019)”Tax Compliance and Enforcement,” Journal of Economic Literature, 57(4): 904-954.
Zwick, E. and Mahon, J.(2017)”Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior,”American Economic Review, 107(1): 217-248.
「自治体税務データ活用プロジェクト」の最新情報については、以下の文部科学省科学研究費補助金学術変革領域研究 (B)「税務データを中心とする自治体業務データの学術利用基盤整備と経済分析への活用」のウェブサイトをご覧ください!
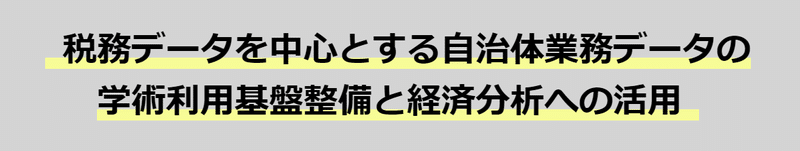
*本稿は、『経済セミナー』2023年8・9月号からの転載です。
サポートに限らず、どんなリアクションでも大変ありがたく思います。リクエスト等々もぜひお送りいただけたら幸いです。本誌とあわあせて、今後もコンテンツ充実に努めて参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
