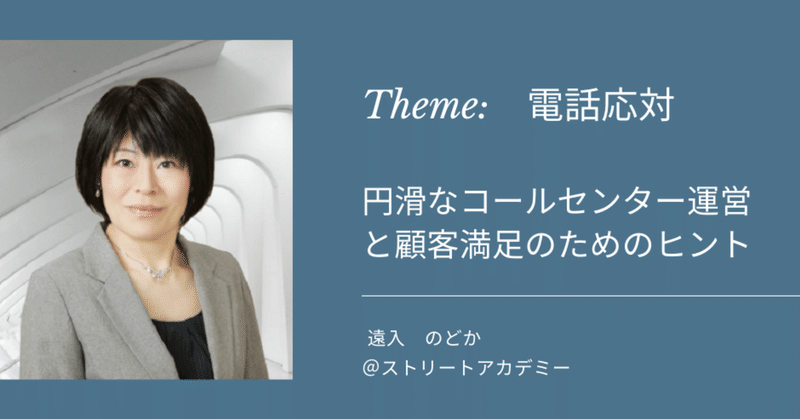
続)改善施策を考える際のポイント
前回は、改善施策の実際の運用にあたって、手間の問題はないか、繁忙になった際の改善施策の優先順位はどの位置か、メンバーからの反発が起きたらどうするか、効果が見られない場合にどの程度続けるのか、など、様々な問題を想定してから始めないと、自分のモチベーションも維持できず、当然メンバーのモチベーションも維持できず継続できなくてなんとなく終了してしまう、という話をしました。
今回は、その次の段階の話をしましょう。
2)自分以外でも運用できるか
改善施策に限りませんが、自分にしかできないことをできるだけ減らしていくことは重要です。
何か作業を増やすときに、それを自分だけで抱え込んでしまったら、それだけでできることに制限ができてしまいます。
望むべくは、普段から自分の作業を減らしておくことです。
自分の手が空いているからこそ、様々な問題に取組むことができるのです。
さて、改善施策の運用についてですが、誰でも運用できるためには、ルールを単純化することです。
これは、改善施策に限らず、重要です。
いつ自分が抜けるかもしれない、という意識を持ち、いつ誰が抜けても補完ができる体制づくりをしていくということです。
コールセンターでよくある問題が「スキルが人につく」ということです。(あなたの職場は大丈夫ですか?)
「あの人がいないから分からない」ということのないよう、可及的速やかに誰にでもできる運用にしなければなりません。
そのためには、手順が文書化されて、運用者が誰でも見える場所に格納されていることが必要です。
そして、その手順通りに運用してもらった際に、誰がやっても同じことができることを確認しておきましょう。
これは、新米管理者とベテラン管理者、など、複数の人に試してもらいたいところです。
3)”ぶれ”はないか
基本と例外を作ると、「忙しければ例外で良い」「~だから今回は例外」という各自の判断を認めてしまうことになります。
人によって、優先順位や価値観も異なるので、例外が管理者の数だけ増えていくかもしれません。
どんどん例外が増えて基本が分からなくなると、古参コミュニケーターからも、「今日は★♠Θから◎■※でいいんじゃないですか?」なんて言われて、反論ができなくなってその通りにせざるを得なくなってしまうなんてことも…。
そのうち基本が消えて、なんだかやっているだけ、になってしまうなんてありません?
最初のうちは、「昨日は◆♣だったんで、♥♠にしました」と報告されたら、「そっかぁ、◆♣だと手順通りにやるのは無理かぁ。何が無理だった?」と状況を確認しましょう。
手順に無理があるところを洗い出し、実施可能な手順に仕上げていくのです。
そのうえで固まった手順には、極力例外を作らず、どうしてもどうしてもどうしても今回は例外という場合も、全員が「確かに今回は例外だよね」と同意してもらえる場合に限ります。
そのためには、例外を作る場合の基準や手順を決めておきましょう。
・応答率が70%を切った場合はSVの指示に従って運用を変更する
・手順を変更する際は、統括SVの許可が必要
・3日以上連続で手順変更があった場合には、週次ミーティングで必ず議題に挙げる
・今回の手順が例外であることを全員に明示する
・
・
・
etc.
最初は、きちっと作ったつもりの手順書なのに解釈に差が生まれたり、「このくらいは別にどうでもいいことだろう」などと考える管理者が一人や二人はいたり、いろいろと大変ですが、いったん足並みを揃えることができれば、後の運用は楽です。
今後、自分がチェックしていく立場に回るときのことを考えましょう。
では、また。
運営・管理方法について悩んでいる方は、下記の講座をご活用ください。
電話窓口でなくとも、ヒントがあるかもしれません。
ささやかですが、下記のバナーからのお申し込みで500円OFFになります。
世界や自分自身をどのような言葉で認識するかで生き方が変わるなら、敬意を込めた敬語をお互いに使えば働きやすい職場ぐらい簡単にできるんじゃないか。そんな夢を追いかけています。
