
定番の文字の強調を整理してみました
こんにちは、スタートアップテクノロジー・デザイン部の山崎です。
私はスタテクでUIデザインだけでなく、イベントやブログなどのアイキャッチ画像を作ることがあります。
アイキャッチにどこまで手をかけるかって迷いませんか?
重要じゃないというわけではもちろんないですが、あくまでメインはイベントの内容だったり記事の中身だったり。
無限に時間があるのであれば、いくらでもこだわって思いっきり作り込むのもありだけれど、やっぱりその時々の状況で線引きは必要ですよね。
今回は、基本的な「大きくする」「色を変える」以外の
・とにかく時間がかからない
・Illustratorなどを使わなくてもできる
文字を強調するシンプルな方法をまとめてみました。
どれもよく見かける定番の方法ですが、頭の引き出しに入れておくと作業スピードがぐんと早くなると思います!
アイキャッチやバナー制作だけでなく、デザイナーではない方の資料作りなどでも役立ちますよ。
架空のイベントのバナーとして、最低限の情報量でやっていきます。
今回は「文字を強調する方法」なので、それ以外のイメージを左右する装飾や色などは基本的に省きます。

下にライン
シンプルな細いライン

一番シンプルな方法ですが、すっと1本入れるだけでもしっかり強調されますよね。
強調というと太めにしたくなるような気もしますが、細いラインだと細いフォントや優しげなフォントなどにも馴染みやすいです。

よく下線をつける機能(Uの下にラインがあるアイコンのあれです)がありますが、文字と線の距離が近すぎたり、フォントに対して線が細すぎたりする場合がありますよね。また、リンクのように見えてそこをクリックしたくなってしまうかも。
強調としての線を使う場合は、文字とは別で線を引く方が良いです。
シンプルな太いライン

簡単にしっかり目立たせるなら太いラインです。
太めのゴシックなどの場合は線もガシッと太めにするとより強調されます。
ただ、太めのラインは両端の角の四角が目立つので、丸ゴシックの場合や可愛い感じのものを作る時には、できれば線の両端を丸くした方がまとまりやすいと思います。

太い&薄いラインでマーカー風

太いラインを薄めの色にし、文字の後ろに少し重ねるだけで、マーカー風になります。
黄色やピンクなど明るい蛍光色っぽい色を付けると、よりマーカーらしくなりますね。
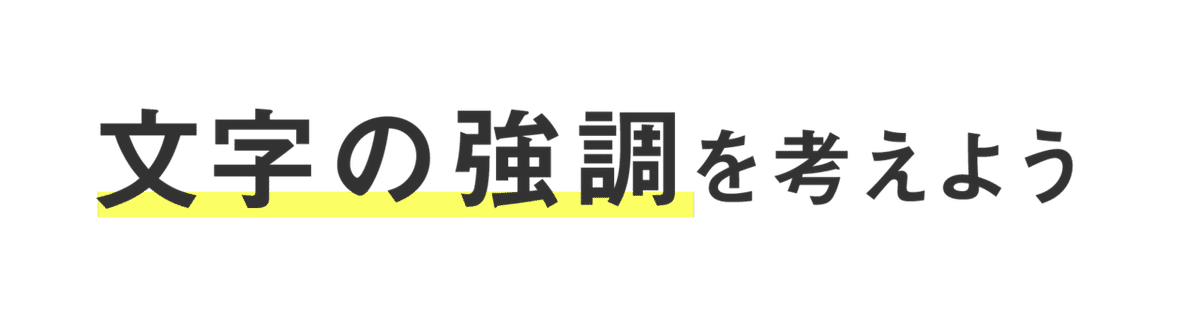
点線

点線の場合は普通のラインに比べるとカジュアルさがある気がします。
細めの点線だと軽やかなさりげない強調、太めな点線だとリズミカルでよりカジュアルになります。

手書きっぽい線

筆や鉛筆、クレヨンなどの手書きの質感があるラインにすると、制作しているものの印象を作る素材の一つとして線が使えます。
無料で配布してくれている素材サイトが色々あるので、そこで探してみると良さそうですね。
(以前は私は色々なラインを手書きして、スキャンしてベクターデータに変換し、いつでも使えるようにストックしていました)
今回はこちらのサイトから使わせていただきました!
「FREE LINE DESIGN」
(個人利用・商用利用可、画像の加工可、コピーライトの表示や利用許可は不要)
ベタ敷き
四角のベタ

背景が薄い色の場合は濃いめのベタ&薄い色の文字
背景が濃いめの色の場合は薄い色のベタ&濃い色の文字
にして、しっかりコントラストを付けるとより強調されます。

背景に模様やテクスチャ、写真などを使っている場合などは、ベタを敷くだけでしっかり読みやすくもなりますね。
丸いベタ
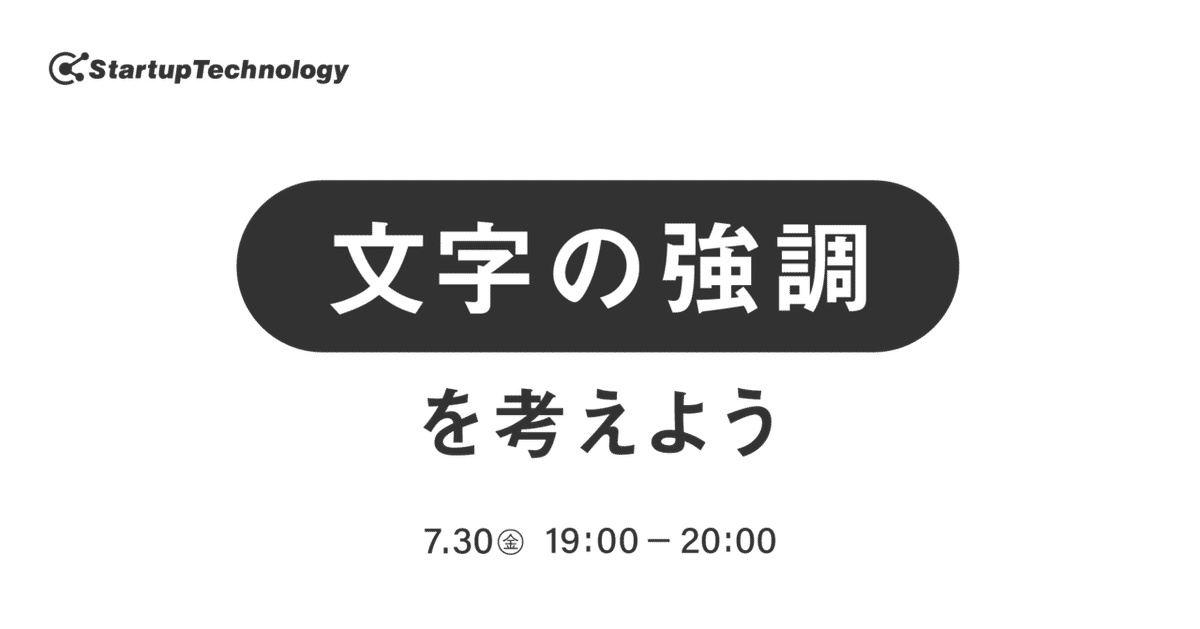
角が丸いベタの場合は、文字の周りにある程度余白を取っている方が良い気がします。
特に両端はギリギリまで文字が入っていると、四角いベタではあまり気にならない窮屈感が・・・。
意図的にギリギリにすることもあるかもしれませんが、基本的には余白をちゃんと取る方がおすすめです。
一文字ずつ

一文字ずつにベタを敷くのは、強調したい文字があまり多くない場合です。
長めの文を一文字ずつ入れている場合も見かけますが、文字がバラけて見える方法なので、個人的には読みづらさを少し感じてしまいます。
文章でベタを敷くのはちょっと重いな、単語だけを目立たせたいな、という時は、この一文字ずつのパターンも入れてみると良さそうです。
質感のあるベタ

絵の具や鉛筆などで描いたような、質感のあるベタを敷く方法です。
ラインの時と同じく、制作しているものの印象作りとしても役立ちますが、他に入れるイラストや写真、文字の内容などとテイストが合わないと、バラバラでまとまりが無くなってきてしまうので、そこの注意は必要です。
今回はこちらのサイトから使わせていただきました!
「Sui-Sai」
(個人利用・商用利用可、画像の加工可、コピーライトの表示や利用許可は不要)
枠で囲む
四角い枠

ベタはちょっと強すぎるなという場合は、線で囲むというパターンもあります。
線の太さが文字と近く、かつ余白を狭くしてしまうと、枠線と文字が馴染みすぎて、目立ち度が下がったり、読みづらさが出てきてしまうので、ちょっとだけそこの注意は必要です。
丸い枠

上記の丸いベタと同じく、余白の取り方に気をつけましょう。
一文字ずつ

ベタの一文字ずつと同じように、単語を目立たせたい時などに使うと良いです。
枠の場合は、ベタと違って枠同士をくっつけるという方法もあります。

両端を囲む
縦線

縦線2本で挟むパターンです。
数字の1のように見えてしまわないよう、フォントと太さの差をつけたり余白を文字間より広くしたり、改行したり、少し気を使う必要があります。
斜め線

上記の縦線を少し斜めにするだけで、吹き出しのようなカジュアル感のある強調ができます。
括弧を使う

灯台下暗しで意外に忘れているのが、通常使う括弧です。
文言をある程度自由に変更して大丈夫であれば、強調として括弧を使ってみるのも良いと思います。
括弧も「」だけでなく[]や【】などいくつか種類があるので、入れてみて内容やイメージと合うものを選びましょう。
ただし、約物の中では括弧類は特にアンバランス感が気になる場合があるので、タイトルなど目立つ場面で仕様する時には、デザイナーの人はサイズ、太さ、余白、ベースラインシフトなど、良い感じに調整しましょう。
文字の角度
斜め

角度を変えるだけでグッと強調されます。
斜めは勢いやスピード感など強さのある印象なので、文字も思い切って大きくしちゃうのがおすすめです。
斜め&小さく使う時は、なんとなく中途半端さを感じることがあるので、私の場合は下線など別の方法も組み合わせることが多い気がします。
縦書き・横書き混ぜ

強調したい部分だけ、他の要素と書字方向を変える方法です。
例えば横長のアイキャッチ画像の場合は横書きが定番かと思いますが、強調したい部分のみ縦書きにしてみます。
この場合、改行しづらい長めの文章や単語だと文字が小さくなってしまうので、簡潔な短い文言の場合に使うと効果的です。
その他
文字の上に点

こちらもとても簡単な強調の仕方です。
上の点が大きくなってしまうと重くなってしまうので、小さめの点で軽やかに乗せるのが良いと思います。
ひらがなやカタカナの濁点、半濁点がある時は特にですが、文字と少し距離を取るようにした方がバランスが取りやすいです。
フォントを変える

フォントの種類が色々ある場合に使える、フォントを変える方法です。
単純に違うフォントに変えれば強調されるわけではないので、他の文字より目立っているか気をつけながら選んでください。
フォントを変えるだけでなく、文字の大きさの差もしっかり出した方が良いです。
定番の文字同士は、組み合わせが難しいな・・と個人的には思います。
よく使われるような明朝とゴシックの組み合わせなどは、ただ画面がバラバラごちゃごちゃしてしまう可能性があるので、強調したい文字のところは個性のあるフォントで差を出す方が、うまくまとまりやすい気がします。
吹き出し

吹き出しを使う場合は、パワーポイントなどのデフォルトに入っている吹き出しはなんだか野暮ったくなってしまいます。
検索してもたくさん出てくると思います、「パワポの吹き出しはダサいから、図形を組み合わせて作ろう(パスを触ろう)」と。
それ以外にも、フリーの吹き出し素材を使わせてもらうという方法も、色々な形から探せて時間短縮にもなるので良いと思います!
今回はこちらのサイトから使わせていただきました!
「フキダシデザイン」
(個人利用・商用利用可(合計20個まで無料、それ以降は条件あり)、画像の加工可、コピーライトの表示や利用許可は不要)
シャドウ

色を薄くした文字を下に少しずらして重ねる方法です。
ドロップシャドウなどを使って影を作ることもできますが、ぼかし具合によってはダサくなる可能性もあるので、調整が難しい場合は文字を重ねる方法が良いのではと思っています。
ポイントは、影になる方の色はグッと薄く、です。
影の方に色を付けてみるのも良いですね。
最後に
わざわざ言わなくても、、と感じるくらいの今回のようなド定番のことでも、こうしてまとめてみることで、あらためて頭の中の引き出しにきちんとストックしておけますね。
こういうバリエーションがパパパッと浮かんでくるかどうかは、スピードにもクオリティにも関係してくるので、またぜひ自分の引き出しにある他の手法などの整理もしてみたいと思います!
(引き出しの奥底に埋もれているものは、必要な時に出てこなかったりしますしね)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
