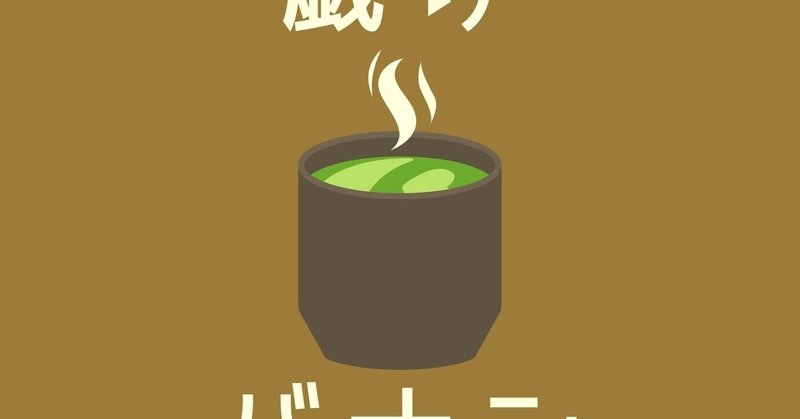
戯けちゃバナシ(第2回)〜作品の着想だってよ〜
フリーの演出家、劇作家として活動しているけちゃです。
今回から、3回にわたって、
2/mashi公演「man-hole~a man’s mental sketch~」
の裏話を紹介していきます。
Radiotalk版はこちら↓
https://radiotalk.jp/talk/517511
着想・構想について
1回目となる今回は、「man-hole」という作品ができるまでの変遷です。
この作品は第1形態〜第4形態(最終形態)まで、2年弱をかけて変化してきました。
【第1形態】2019年5月 「あげない男」
私、小林賢太郎さんが大、大、大好きなんですが、この時は賢太郎さんみたいな言葉遊びを使ってみようと、遊びで書いていた様です。
その後、自分で作った<「自己決定の自由」という法律を作った王様>という設定に興味が移ったのですね。

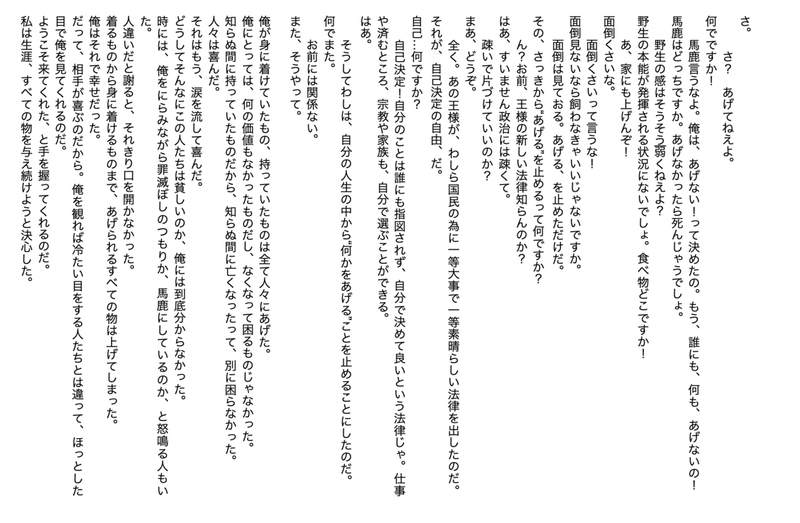

【第2形態】2019年11月 「王様の贈り物」
より長さのある話にするために、「幸福な王子」という童話をモチーフにしました。しかし、絵本風の作品になってしまい、上演には不向きな気がしました。
登場人物の”ドーナツ娘”の評判が良く、ここから彼女と長い付き合いになっていきます。
【第3形態】2020年7月 「あなのなか のぼく」
日本劇作家協会主催の新人戯曲賞の応募するために、「王様の贈り物」をより上演向けになる様に書き直しましや。ドーナツ娘と主人公の青年をメインキャストにし、穴が話の大きなモチーフになりました。
10月 ちょっくら戯曲集(Youtube配信版)でリーディング
【第4形態】2021年3月 「man-hole~a man's mental sketch~」
足掛け2年弱、飽きないもんだなあと、調べた自分がびっくりしています。
着想を固めるためにした4つのこと
いつも、新しい作品を書く時にしていることでもあるのですが、個人的に、プロットや構想を作るのと同じだと思うので、参考になったら嬉しいです。
1 関連作品をみる
自分が扱う題材やテーマがありきたりな表現にならないように、有名な作品は観ておくといいです。パクリ?と思われたら嫌ですもんね!
加えて、自分の中でまだ顕在化していない意識や価値観を、他の作品を観て共感したり違和感を感じることで気づけるかもしれません。刺激=インプットです。
※こんなのみたで
映画・・・「アルコヴィッチの穴」(スパイク・ジョーンズ)
「穴」(ジャック・ベッケル)
絵本・・・「The HOLE Book」(ピーター・ニューエル)
「あな」(谷川俊太郎)
書籍・・・「失われたドーナツの穴を求めて」、その他エッセイ等
その他、ピアスを開けた経験なんかも、自分にとってはすごく考えさせられるものでした。
ぜひ上記の作品達もお手にとってみてください。どれも面白かったです。

2 思いつくワードをひたすら書いてボードに貼る
有名な、映画の脚本術を指南している「SAVE THE CATの法則」という本は、ボードとカードを使ってプロットを組み立てていく方法を紹介しています。
私は、思いついたキーワードやエピソードを一枚のカードに一つずつ書き、ボードに貼って常に眺められるようにしています。
貼り替えたり、動かしたりしてジャンル分けしていくと、その情報群をどの登場人物が持っているのがいいのか、どんな場面で観客に見えると効果的なのか、時間をかけて落ち着いて考えることができます。
セリフを書き始めたら片付けちゃいますが、前準備に使ってます。
しっかりそう書けているかは・・・別問題です!

これは次の作品のカードで、まだ貼り始めたばかりですが、このボードが埋まっていくと自分の頭の中が並べられているみたいで楽しいですよ!
3 絵を描く
世界観や登場人物のサイズ感などを始めから言葉(ト書き)にしてしまうと、スケールダウンしがちな人間なことに気づきました。
イラストにしてみると「どうしようか?」よりも「こんなのがいいな!」と前向きなイマジネーションが働く気がします。
というのも、「嫌われる勇気」というベストセラー本をちょうど手に取っていた時期だったのですが、本文中にこんな文章がありました。
人生とは、今この瞬間をくるくるとダンスするように生きる連続する刹那(今)なのです。そしてふと周りを見渡したときにこんなところまで来ていたのかと気づかされます。しかし目的地は存在しないのです。 今という「ここ」に強烈なスポットライトを当てなさい。そうすれば薄ぼんやりした過去や未来は見えなくなります。 人生の意味は自分自身に与えるものです。人生一般には意味などない。しかしその人生に意味を与えられるのは、ほかならぬ皆さんなのだと。
「嫌われる勇気」 岸見一郎・古賀史健著 ダイヤモンド社
その時期は、コロナでみんなが”足止め”をくらっていたのですが、そんな状況に、なんだかほっとしている自分に気づいたのです。
私は、自分の人生が、ある目的に向かって一本道だと感じていたんですね。
遅れたくない、ましてや立ち止まるなんて嫌だ、と人と比べて焦っていたのでしょう。
けれど、広い牧場の様な”世界”の中を、思い思いが踊る様に”移動している”姿を想像したら、肩の力がふっと抜けたのです。
どうにかして記録したかったんですが、まだ言葉にするほど自分に落ちてなかったので、イメージをそのまま絵にしてみたんです。
その手がノリ始めて、man-holeの世界観の絵をそのまま描いたと思います。
あの感覚は、面白かったです。
4 書きたいことを人に話す
これ、本当に大事!
こんなことに興味がある、や、こんな話を書こうと思う、を相談したりアイデアをもらえたりする仲間がいることは心強いです。
それに、自分の考えが甘いところは、必ず「どういうこと?」と聞かれます。
厳しい意見ほどためになりますね。
ちなみに、この作品はラストシーンを最初に決めました。
光の球が浮かび上がっていくシーン(美しいもの)に悲しい事実をぶつけたいと思っていて、ラストがそうなるには?とストーリーを組んでいくうちに意味付けも徐々にはっきりしていきましたが・・・。
最初は、それがどんな感覚になるんだろう?という純粋な疑問から作っていましたね。
作品を作るのにそれこそいろんな方法があって、自分に向いているものとそうでないものもあると思います。
一つ一つ試して、より深めやすい方法があったら身につけていきたいので、他のやり方でオススメがあったらぜひコメントにて教えてください。
次回は登場人物についてです。
気楽に、気長に、お茶でもしばき倒しながら戯けた話にお付き合いいただけたら嬉しいです。
けちゃでした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
