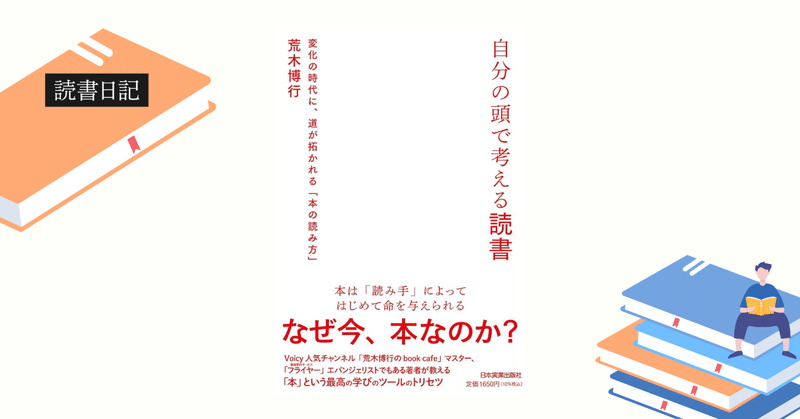
読書日記 『自分の頭で考える読書』
本を読むってことは、ある程度時間を要する。読むのは早くないから、一冊5時間くらい?
短くない時間を投資するんだから、無駄になる時間を少なくしたい。ということで「読書を最大化」するためには、「読書」という行為とは、と考えてみたいと思い、読んでみました。
他にも、ここ最近は結構な量の本を読んでいると思っています。(あくまで自分の中で)
ただ「読む」だけ。それだけなので、「本を読むこと=目的」になってしまっている感覚。本末転倒。
今までは悩みに対して答えを求めている感覚だったのが、最近では「本を読んでます。知識を入れています。」的な感じ。
そして読むだけだから、なんだっけ?ってすぐに忘れてしまう。これじゃだめだ、意味がないと思ったこともきっかけになりました。
読む前、購入した時点では目次も見ていなかったので、本の読み方やアウトプット方法などの読書にまつわることだけだと予想してました。
けど、初っ端に「全てを教えてしまうと全体像を考えなくなる」という『ええ????』という始まり方。そしてAI時代に必要な能力とは、という予想外のことが多かったです。
けど、かなり良かった。
今の悩みがあって読んだからこそパッと開ける感覚。そして予想外だったのが、仕事で悩んでいたことの解決の手助けにもなってくれました。
個人的に仕事に漠然と悩みを抱えている人に読んでもらいたい。
私自身、現状どうすればいいのか、正しい道に進めているのかという謎の負のループに入っている気がしている。
けれど、そんな時だから本の力を借りて、現状を俯瞰する。
本を活用して、ここではないどこかの世界、別次元からメタ認知することで今の謎の悩みを見つめ直すことができる。そういうことを再認識させてくれた。
それは本著だけではなく、COTEN RADIOというPodcastからも知ることができたからこそだと思います。相乗効果ですね。
特に今からの3つがかなり学びに繋がったな〜と思いました。仕事にも応用が効く考え方。
1つ目は、本を一個の情報だけで終わらせないこと。
過去に培ったものから大事なものを抽出してその本質を見出し、未知の世界に活かす。色々な人が言っている「抽象化→具体化」。
本についても抽象→具体サイクルを回すことで、学んだことがリサイクル可能な能力になる。
抽象→具体能力はAI時代にでも活きるスキル。身につけていこう。
2つ目は、徹底的に他者の力を使うこと。
著者はまだ能力が未熟な時に、講習をするというミッションを与えられました。自分より遥かに知識を有しているであろう方への講習。考えただけで嫌だ。
そんな時に本で得た知識、講習で受講生の発言。それらを全て活用して、講習を作り上げていく。基本的に自分の専門分野で戦っているつもりでも、自分より知識を持っている人なんて数え切れない。
自分が100だと思っていても、人からすれば5くらいかもしれない。そうした時に、本や人の力を借りて、いいものを作る。
0→1が苦手な僕からしたら目が鱗でした。1をたくさん仕入れて、5や10(願わくば100)にして人に提供する。それならできそうな気もする。
3つ目は、自分なりのアウトプットを持つこと。
読んだまま放置してしまうと、まず残らない。全てがとは言わないけど、ほとんど意味がない。
20分後には42%、1時間後には56%、24時間後には74%、1週間後には77%、1ヶ月後には79%忘れてしまう。
今まで聞いたことあるけど「エビングハウスの忘却曲線」っていう名前だったのか。
せっかく読んだものを忘れてしまうのは勿体無い。忘れてしまうことは諦めるにしても、忘れない量を増やすことは諦めたくない。
読んだらすぐにアウトプット。そうすれば忘れる量を減らせる。
本を読んですぐに行動に移せるものならいいけど、実際にすぐ活用できることは稀。だから自分なりのアウトプット=noteに書くことを目標としていこう。
改めてそう思うことができただけでも、本著を読んで良かったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
