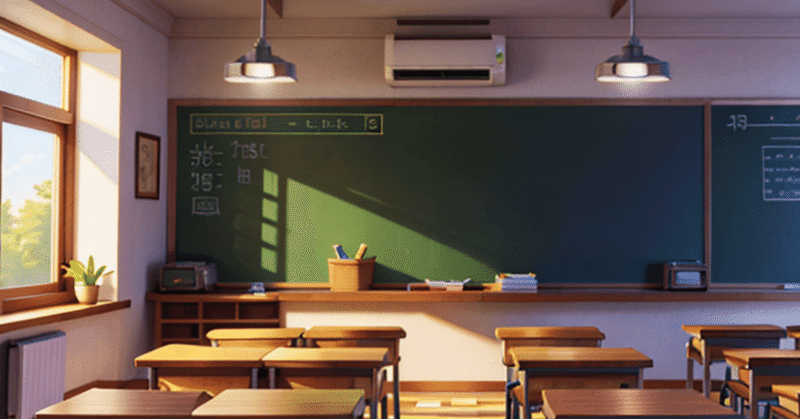
娘の行き渋りからみえた、より良い教育への鍵。
我が家の行き渋りっ子ちゃんの最近。
行き渋りに向き合って4年目。
学年の最初はいつも調子が良く
4年生になってからも
ゴールデンウィークが明けてからも
順調って見えていました。
その流れが変わったのがこの時。
この後は
何も言わずに行く時もあれば
体調不良でお休みする時もあって
で、今朝は玄関で
「行きたくない〜」
ってなりました。
行きたくないけど、行ってるんだろうな
とは思っていたけど
今朝は顕著だった。
聞いてみると
「校外学習がいやだ」
これまで一方通行的な授業がいやなのは知っていた。
けど、バスででかける校外学習、なんでだろう?
そこからいろいろと話をしていって
詳しくは書かないけど
ここが娘にとっていやなポイントなんだな
というのがわかってきた。
行きたくない理由は
一つじゃない。
3年以上向き合ってきて思うのは
本当に複雑にいろいろが絡み合ってる。
だからすごく捉えるのが難しい。
けど
言語化が上手になったのもあるし
話せる信頼関係もつくってきたから
いろんなことがクリアになってきた。
「わかる」というのは、なんて安心なんだろう。
諦めずに向き合ってきてよかった。
いろいろあったけど
私たちは私たちなりに進歩してきている。
そして、話には続きがあって
ちょうど担任の先生から電話があったので
現状をお伝えすると
「それなら今日の校外学習でこういう配慮しましょうかね」
という話になった。
それでも行くかどうかわからない、と伝えると
「校外学習は午後だから
それまで学校で過ごしてみて早退でもいいですしね」
ってことに。
娘一人のことですぐに応えてくれてありがたいし
どんどん柔軟になっていく学校を感じてきた3年間だった。
嫌なら行かなくてもいいっていう考え方もあるし
私もそう思うし、そう動いていたこともあったけど
今年は(今は)、学校に安心を広げるっていうふうに動いていて
学校もそれに応えてくださっているのもあり
いろいろと調整が大変な部分もあるけど
それを選択している。
話を戻して、
こんな話をしたよー
校外学習に行けそうならいってもいいし
早退するなら担任の先生に言ってね
と伝えた。
そしたら、
「担任の先生に言いたくない」
!?!?
そこ!?
「校長先生か教頭先生か保健の先生がいい」
そうなんだ!
もしかして
校長先生や教頭先生たちは
無理しないで帰ってもいいよって言ってくれるから?
と聞いてみると、
「うん」
となんだか嬉しそう。笑
それ以上は突っ込まなかったけど
おかあがそれを伝えて、と言われたので
それにOKをして学校に向かいました。
教頭先生がまじで面白いんだよー
という話を聞きながら、ルンルンで。
学校に入ると、やっぱり周囲の目が気になるのはあったけど
保健の先生に会ったら嬉しそうで
状況をお伝えして、バイバイした。
帰り道で考えました。
これまでも、今年だけじゃなく
「担任の先生に言いづらい」ってのが何度かあった。
ふと自分が担任をしていたことを思い返した。
自分のクラスで起きていることを
「なんとかしよう」って思っていたな。
不登校の子もいたし、暴言吐きまくる子もいたし、
いじめっぽいことが起きることもあったし、
トイレにトイレットペーパー放り込むとか、
机に「死ね」と書かれるとか、
牛乳がトイレから毎日発見されるとか、
そうじゃなくても
なかなか整列できないとか、
うちのクラスだけ授業がものすごく遅れるとか、
なんかいろいろ思い出した。笑
自分のクラス、学年で起きたことに、
どうしたって責任を感じるもの。
そして、どうにかしようと思うもの。
でも、校長先生や教頭先生や保健の先生って
クラスがどうか、はあまり関係ない。
その子がどうか
に目を向けてくれる。
しかも、今のご時世、
学校に来づらい子たち、教室に入りづらい子たちは多いので
そういう子たちを把握してチームで関わってる感じが
すごくする。
いろんな面から
責任が分散してる、というのか
さらっと対応してくれてるのを感じる。
でも、担任は
立場上どうしても
きれいにおさまってるクラスを目指したくなる。
責任を一手に引き受けているというか
なんとかしなければ、と思ってしまうのではないか。
(しかも、うちは単学級)
その違いがあるのかな、って思うに至った。
それで、ピンときたのは
チーム担任制
知ってはいたけど、
これだ!と思って調べてみると
けっこう実施されているところも多いみたい。
この取り組みに、すごく希望を感じた。
先生たちが、一人で背負わなくてもいいように
その環境をつくることが大事なんじゃないか。
教育をより良くするためのキーワードは
「ゆとり」
と思ってきたけど
時間的なもの、仕事量のこと、いろいろあるけど
こういう「ゆとり」の作り方もあるんだ
という新たな気づきになった。
私は今、地元の学校が統廃合に向けて動いているのもあって
このチャンスに教育がよりよく生まれ変わってほしいと
教育の対話会を始めたところ。
押し付けたくはない。
負担になってほしくないから。
けど、
変化しつつある教育を追っている身として
何かヒントとして伝えていけたらいいなと思うし
先生たちの負担が減って
子どもたちがもっと伸び伸びと学べる場所になってほしいと願って
活動を続けていきたい。


第2回目も開催決定。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

