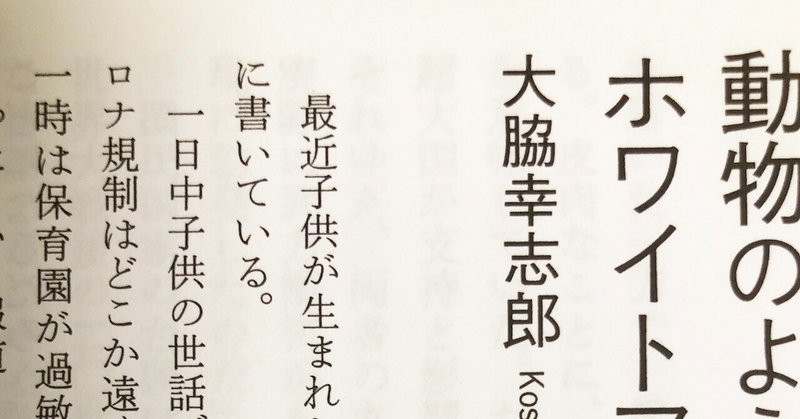
ナイチンゲールの二つの顔ー大脇幸志郎「動物のような人間とホワイトアウトしたナイチンゲール」を読んでみた
コロナ。なかなかおさまりません。今は第八波到来?とのニュースが飛び交っています。
コロナ対策については、ずっと違和感があるのですが、その違和感を説明してくれている文章に出会いました。
「動物のような人間とホワイトアウトしたナイチンゲール」(『ゲンロン13』2022年10月)です。今回はこれについて考えます。
著者は医師、翻訳者の大脇幸志郎。著書に『「健康」から生活を守る』(生活の医療社)、『医者に任せてはいけない』(エクスナレッジ)があります。なかなかアツいタイトルたちです。
人間再考
大脇はコロナ対策という観点から人間を改めて考えなおします。検討の軸はありがちな感染対策/経済ではなく、人間/動物です。
子ども
大脇は自身の子育ての経験を通して指摘します。
たしかに子供は動物的かもしれない。しかし、大人も同じくらいには動物的だ。むしろ人間性と動物性を区別しているのは、その人に対する態度ではないか。わたしたちは子供を動物のように扱うことが多く、大人は人間のように扱うことが多いという事態を、「子供は動物に似ている」と言い換えているのではないか。
私の子どもの頃の大人への違和感の一つはこれでした。大人は説明することが難しいとき、面倒なときに、子どもを子ども扱いしているのではないかと思っていました。自分(大人)が説明できないだけなのに、相手(子ども)の理解力不足を理由にする。ひどいはなしです。
動物のための医学
大脇は、子どもだけでなく、重度の認知症を持つ高齢者、重度の精神疾患を持つ人、重度の知的障害者も動物のように扱われていると指摘します。
医療上の重要な意思決定がもっぱら家族に代行され、本人が「家に帰りたい」と言っても家族の都合が優先され、「この部屋はいやだ」と言っても施設の都合が優先されるといった実態もある。そして、より重度の障害を持つ人ほど、本人の主体性は閑却される。
たいへん難しい問題です。他者の主体性の有無をどうやって判断できるのか。本人がまともに発話できている限り本人の判断を尊重すべきか、どの程度支離滅裂ならば本人の判断を無視して良いのか。
この問題は子どもにもいえます。ある程度まともに話せる三歳児に主体性を認めるかどうか。
コロナ対策についての私の違和感は、ここにありました。
私は子ども扱いされている気がする。
コロナが流行りはじめたころ、一般市民はコロナに対してある意味子ども(動物)でした。なんの知識も持っていませんでしたから。
専門家も一般市民を子ども扱いしていたのではないかと思います。そして、一般市民もそれを受け入れていました。
ところが専門家の予想が外れ続けると、専門家も子どもにみえるので、一般市民としては、どちらも子どもなのだから、対等に扱ってもらいたいと思うようになる。普通に商売させてくれとか、死ぬ間際には面会させてほしいとか要求したくなる。ところが、一般市民の主体性はなかなか認められなかったのではないかと感じています。ひどいはなしです。
では一般市民の一人である私はどう扱って欲しかったのでしょうか。
ナイチンゲールの二つの顔
大脇はフローレンス・ナイチンゲールを参照します。
ナイチンゲールには二つの矛盾する顔があったそうです。
観察を重視し、献身的に働き、人を惹きつける看護師としての顔
統計と伝聞情報を巧みに使いこなす疫学者としての顔
私は看護師としてのナイチンゲールの印象しか持っていなかったのですが、疫学者としての彼女もたいへん重要だったようです。
二つの顔を持つにいたった経緯を証明する彼女の手紙が二通、残っているそうです。
一通目(戦中の病院勤務時のもの)の要点
病院に送られてきた兵士たちが死んだのは、瀕死の状態になってから送られてきたからだ。
二通目(戦後のもの)の要点
病気はおもに病院の中で発生した。
ばっちり矛盾しています。
二通目はこういうことです。
…病院があまりに不潔で過密だったため、負傷兵を救うどころか逆に感染症により命を縮めていたのだ…。
この分析後の彼女は看護の現場にはいっさい従事せず、公衆衛生改革に従事していたようです。目的が人命救出であれば当然のふるまいです。
いっぽうで彼女は、病院に勤務している時は、兵士が病院に送られてくる時点で瀕死の状態だったために助からないと思っていたけれども、熱心に看護した。つまり患者には身体的苦痛だけでなく精神的・社会的苦痛があり、それを看護することも大切であると考えていた。
ナイチンゲールには、看護師の顔と疫学者の顔がありました。
さらに大脇はある歴史学者を参照し、統計の起源に人間がいなかったことを指摘します。どういうことでしょうか。
人口統計は、イギリスにおいて植民地の現状を本国に報告するすることが起源になっています。つまり奴隷輸送船の換気や過密状態を分析するためだったようです。ここには奴隷だけがいて人間はいません。
ナイチンゲールには人間の心によりそう看護師の顔と人間を動物とみなす疫学者の顔がありました。
ではこの二つの顔が衝突した時、私たちはどうすれば良いのか。
コロナ問題に置き換えると、看護師としては瀕死の患者に家族を会わせたい、しかし疫学者としては面会させたくないといった衝突が考えられます。
大脇の考えはこうです。
ぼくは本稿で、人間性と動物性の適度なバランスが大事だと主張している。そこで言う「適度なバランス」を定義する上位の価値基準は、おそらく存在しない。なぜなら人間に対する態度と動物に対する態度は本質的に違うからだ。人間が他者と関わるやりかたは本質的に矛盾を抱えているからだ。だから、その場その場で恣意的に、より残酷な仕打ちを受けた人に、より近い隣人に、共感するしかない。
原理的に人間は矛盾を抱えているので、私たちはその矛盾を受け入れざるをえません。つまり合理的な解がないので、論理ではなく感情で判断しようということだと思います。
では感情で判断するとして、どうすれば助けたい人を増やすことができるでしょうか。
大脇は隣人を増やすこと、そのためには、観光すること、いっしょにいる時間を増やすことが有効なのではないかと提案します。
私は猫を飼っていて、いっしょにいる時間が大切であると考えるようになりました。一緒にいる時間が長くなればなるほど、愛情(または憎悪)が深まっていくような気がします。いっぽう猫の方も来客者に対して、はじめのうちは怖がっているのですが、三回目の来訪あたりから馴れてきます。
どうやら時間は種の壁を超えるようなのです。
冒頭の問いに戻ります。
コロナ対策において、一般市民の一人である私はどう扱って欲しかったのでしょうか。
二つの顔を持つナイチンゲールに相談した上で私自身が判断したかった。つまり疫学者からのアドバイスをもらった上で、人間として自分はどうしたいか看護師に相談する。そして私の責任で私が判断する。
という結論にたどりつきます。
そのためには医療提供者にある程度の時間的な余裕が必要になりそうです。
大切なのは時間についての理解を深めることなのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
