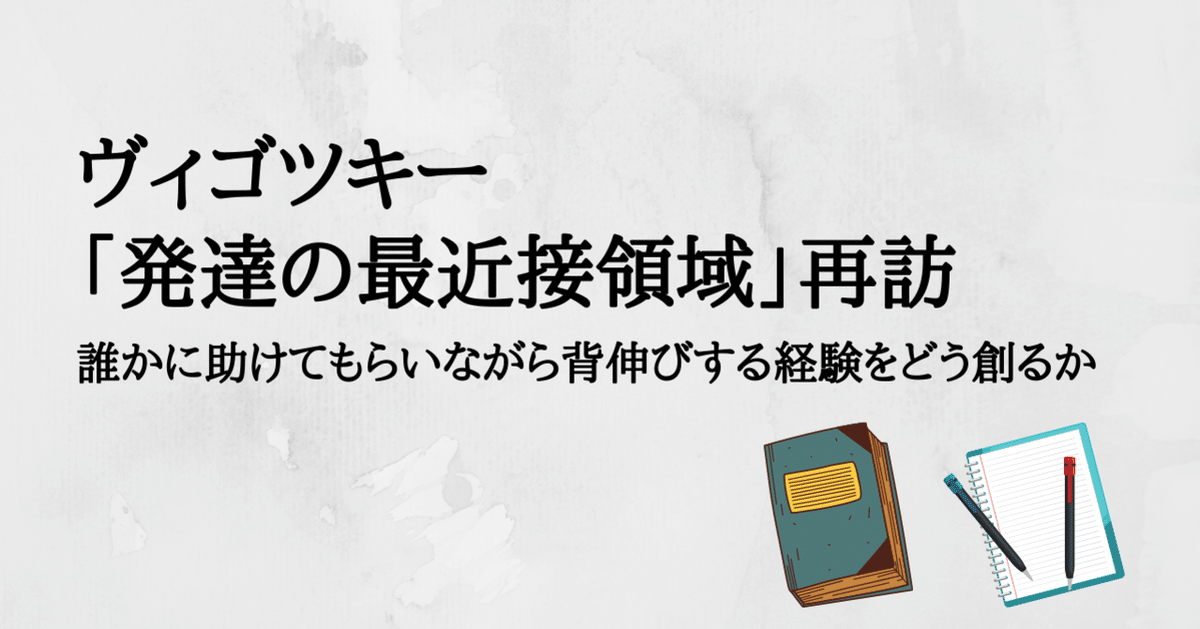
ヴィゴツキー「発達の最近接領域」再訪 ― 誰かに助けてもらいながら背伸びする経験をどう創るか ―
ソ連の天才的心理学者ヴィゴツキーが提唱した「発達の最近接領域(Zone of proximal development)」理論は、現在の教育改革を支える大切な概念の一つです。学習科学の基礎概念の一つである「足場かけ」の元ネタでもありますし、個人的には「主体的・対話的で深い学び」が「這い回る経験主義」に堕落しないための鍵概念でもあると思っています。教育学の講義では必ず触れられ、様々な教育の議論で引用されることから、その名称を知っている人は存外多いのかもしれません。
しかし、ヴィゴツキーの原典を読んだ上で、この概念を使っている人となるとそんなに多くはないのではないかと思います。かくいう私も、ヴィゴツキーの代表的理論は知っており、社会構成主義の源流の1人であることまでは知っていましたが、その原典を丹念に読んだことはありませんでした。
しかし今では、ヴィゴツキーを理解して血肉化し、教育を考えるときに自由に使えるようになりたい、と思っています。そのため、ヴィゴツキーの読解を2021年の目標の一つに据えました。余談ですが、社会人になると、ある一人の思想家を血肉化するのに1年はかかるんですよね。大学生のときは頑張れば3ヶ月に1人で吸収できたので、そのときにもっと勉強しておけばよかったなぁと思います。
話をもとに戻すと、ヴィゴツキーを学ぼうと思った背景は、2020年にデューイ『民主主義と教育』を教育仲間と精読する機会があったからです。デューイもまた、現在の教育改革の理論的基礎となる偉大な先人の1人で、私は人生で折に触れてデューイの思想を参照してきました。ただ、今回改めてデューイの原典を読んでいると「デューイには共同体や他者が存在しない」と感じることが少なくなかったです。誤解を恐れずにいえば、デューイが民主主義社会の基盤として教育を考えたにも関わらず、デューイの教育は究極的には個人主義的であると感じました。厳密にいえば、「にも関わらず」というよりは、近代の民主主義の根っこにそういった個人主義がある、ということだと思うのですが。私がヴィゴツキーを学ぶことに決めたのは、デューイを相対化するためであり、また教育と共同体の関係を考え直すためでした。
そこで、今回の記事では、ヴィゴツキーの最も有名な概念の一つ「発達の最近接領域」について、「学齢期における教授・学習と知的発達の問題」と第するヴィゴツキーの論文を読解することを通して理解を深めていきたいと思います。幸いなことに日本語に翻訳されているので、私の記述に触発された方はぜひ原典をお読みいただければ幸いです。
教授・学習と発達をめぐる三つの理論
すでに「発達の最近接領域」の概念を知っている人がこの論文を読み始めると、ヴィゴツキーの書き出しは、教授・学習と発達の関係から書き起こされていることを意外に思うかもしれません。しかし『教育心理学講義』などを読めばわかるように、教授・学習と発達の関係をどう捉えるかはヴィゴツキーにとって最も重要な課題だったといってよいと思います。ヴィゴツキーによれば、教授・学習と発達の関係をどう整理するかは、教育心理学の個々の研究の基礎となる重要な問題である一方、常に曖昧なので誤りを導きやすい難しい問題です。ヴィゴツキーの熱い宣言を本文から引用します。
この領域で出会うもっとも深刻な間違いや困難の厳選を一つの根源に帰着させるとするなら、このような一般的な根源こそ、まさに私たちによって検討される問題であるといっても誇張ではないでしょう。
ちなみに、読者の皆さんに嫌われないように先に言っておきますが、「発達の最近接領域」が出てくるのはかなり先です。でも、そこに至るまでの議論のプロセスも魅力たっぷりなので、お時間ある人は先を急がずにお付き合いください。忙しい人は「学校での教授・学習の前史」までとんでもらっても内容にはついていけると思います。
発達・学習からの発達の独立性 -- ピアジェらの批判
ここでは、ピアジェの理論を自らの視点によって要約し、批判を加えることが目的となっています。ピアジェもまた「構成主義」の源流であると位置づけられ、一般にはヴィゴツキーとは仲がいい印象があります。では、どんな理由でピアジェを批判していくのでしょうか。
ヴィゴツキーは、ピアジェの核心を、「子どもの発達は学校での教授・学習とは無関係に起こる」と考える点にあると指摘します。言い換えれば、ピアジェは、子どもは学校の助けがなくてもひとりでに抽象的な思考や因果推論といったことができるようになると考えていたのではないか、とヴィゴツキーは指摘します。
ヴィゴツキーは、ピアジェの研究の方法論を興味深い根拠で批判します。ピアジェは、科学的概念の発達を検討するために、「どうして太陽は落ちないのか?」と5歳の子どもに聞きました。ヴィゴツキーによれば、この研究手法は「子どもにまったくと消えないような質問を出す」ことで、「子どもの過去の経験、過去の知識を完全に排除」することを目的としています。確かにそう言われてみれば、これは明らかに不自然な質問であり、子どもの発達を理解するために意味のある質問ではないかもしれません。
また、方法論だけではなく、理論的にも大きな問題があります。発達がそれ自体として進展するプロセスなのであれば、教育心理学にできることは、学校に生徒が入学してきたときに教授・学習に足る十分な発達をしているかを測定・確認することであると考えられます。現代風にいえば、これは地頭信仰に近いものがあります。発達の例として、記憶・注意・思考をヴィゴツキーは挙げていますが、地頭信仰はまさにこうした認知能力を、子どもがひとりでに育んでいるもので、学校で育むことはできないと考える立場だということができるでしょう。これは教育心理学を志す研究者にとって、戦う前から敗北宣言しているようなものなのではないでしょうか。私はヴィゴツキーのそうした叫びを以下の結びの文から感じました。
教授・学習は発達の尻の後について行きます。発達はつねに教授・学習の前を行きます。すでにこれだけでもう、教授・学習の進行によって活発化するはずの機能の発達や成熟の過程において、教授・学習そのものがどのような役割を果たすのか、という問題提起のあらゆる可能性は失われてしまうのです。
蛇足ではありますが、一部のエリートが自分の地位を自身の努力に還元する傾向には、こうした地頭信仰も一役買っているのではないでしょうか。他者を「頭が悪い」と見下し、地頭がいい自分は特別だと思う思考回路がそこに見え隠れしている気がします。そのようなわけで教育心理学の話に留まらない奥深さのある批判だなと感じます。
教授・学習はそのまま発達である -- ジェームズらの批判
ヴィゴツキーは、ピアジェの地頭主義を批判したあと、その全く逆の立場もまた「教授・学習はそのまま発達である」と要約した上で批判します。
なぜ「教授・学習はそのまま発達である」という立場は批判されるべきなのか。それは、誤解を恐れずにいえば、無意識に「人間を単なる犬である」とみなす立場だからです。もう少し科学的にいえば、「発達とは条件反射の集積である」と見なすことになります。皆さんは「パブロフの犬」の実験を知っているでしょうか。犬に対して、ベルを鳴らして餌を与えることを続けると次第にベルを鳴らしただけでよだれが出てくるようになるという実験です。詳しくはググってください。
もちろん「人間は犬とは違う高度な知的生命体なんだ!」といった感傷的で雑な批判ではありません。ここでの批判のポイントは、条件反射や習慣の複合物として発達を見なすと、教授・学習には限界が規定されてしまう、ということです。条件反射や習慣の形成が「自然的法則」(=科学的法則)とみなされている限りにおいて、教授・学習はそこを超えでることができなくなってしまいます。自然法則から逸脱する建築ができないのと同様、発達を逸脱する教授・学習ができないというロジックです。私としては、発達=科学的法則が正しいならば、この批判もまた正しいのではないか、と感じるのですがどうでしょうか。ヴィゴツキーは言明はしていませんが、発達を科学的法則と見なす仮定を批判対象としているように見えます。
教授・学習と発達の二元論 -- コフカらの批判
これまでに見てきた「地頭信仰」(ピアジェ)と「人間を犬と見なす思想」(ジェームズ)がどちらも正しくないとすれば、その葛藤をどう乗り越えるかが課題になります。ソ連の研究者らしく、弁証法的な手並みで非常に美しいです。もう少し、現代で論文のイントロダクションを書くときも、弁証法を意識してもいいのかもしれません。… すみません、話が逸れました。
コフカは、発達を2つに切り分けました。私はコフカを読んだことはないので、ヴィゴツキーの言葉を借りますが、第一は「神経系の発達に直接に依存する成熟」、第二は「それ自身が発達過程でもあるところの教授・学習」になります。現代風に読み替えれば、①脳科学的・生物学な発達、②認知的・社会的発達を分けて議論しよう、というところでしょうか。地頭信仰や犬思想と比べて、非常に全うな気がします。
ヴィゴツキーもコフカの理論を一定は褒めつつ、不足している点を指摘し始めます。批判その1は、第一の発達と第二の発達の相互関係が不明確なことです。切り分けたところで、第一の発達が絶対だとなってしまえば、ピアジェの立場と極めて近くなってしまいます。逆に第二の立場を絶対視すればジェームズの仲間入りです。なので、切り分けた先にどういう関係として定義するかが、この問題に対しては最も本質的な点です。
新しい形式陶冶の理論
ヴィゴツキーは、コフカ理論の本質的な点は「子どもの発達過程における教授・学習の拡大」にあると言います。そして、ヘルバルトの形式陶冶理論を持ち出し、検討を開始していきます。
ヘルバルトの形式陶冶理論は、古典や古代文化を学ぶことを通して、子どもたちの一般的な知的発達(地頭)を鍛えることができるのではないか?と考えます。つまり、なにかを学ぶとき、知識が大事なのではなくて、それを通して地頭を鍛えられるかが大事だということです。古いように見えて新しい考え方で、例えば「数学の公式は忘れてしまったが、そこで学んだ問題解決能力は今でも役立っている」といった語りはよく目にするところです。
もちろん、形式陶冶理論は現実に反しています。ヴィゴツキーは、短い線の目測を訓練した大人も、長い線の目測には失敗する実験を挙げています。現代の学習科学の言葉でいえば、ある文脈で学んだことが他の文脈に転移することは稀です。転移は非常に難しいのです。教育を専門的に学んでいない人は転移の難しさを過小評価します。その意味で、新聞やニュースでの議論を見ていると、いつまでヘルバルトの水準にとどまってのか、と少し残念に思うことはよくあります。… また話がそれてしまいました。
つまり現実を直視すれば、「活動のあれこれの形式」は「その活動の扱う具体的材料に依存する」ことは認めなければなりません。一般的な記憶力、一般的な観察力、一般的な思考力…といったものはないのです。現代のコンピテンシー議論 --- 教科知識の教授ではなく、コミュニケーション能力や批判的思考能力を育てようという議論 ---- も同じ落とし穴にはまらないように注意しなければなりません。基本的に、私たちが育てることができるのは、個別の文脈に規定された個別の能力でしかありません。もちろん、多様な個別の能力を鍛えることによって、一般的に見える能力を育成することはできます。以上の考察は以下のように要約されます。
意識というものは観察力・注意・記憶・判断など幾らかの一般的能力の複合物では決してなくて、多数の個別的能力の総計であり、その各々はある程度まで他とか無関係な能力であって、独立的に訓練がなされねばならないことを示しています。
構造的原理の転移
ここで、コフカの批判に戻ります。どうやら、コフカの議論には、あるものを学習すれば、その対象の構造も同時に学習でき、結果として他の文脈に応用できるようになる、といった理論が含まれているようです(構造心理学と呼ばれています)。ヴィゴツキーは、この点を指して、コフカは実は形式陶冶と同じ考え方を持っており、それゆえ発達は教授・学習よりも常に広い範囲となると密かに考えているため、教授・学習そのものが発達であるという自身の言明と矛盾することを指摘しています。
現代の認知科学に基づいて、アナロジーや転移といった概念を学んでいる人からすれば、ヴィゴツキーの批判は少しやりすぎだと思うのではないでしょうか。確かにそれは起こる確率は一般に考えられているよりも低いですが決してゼロではないはずです。そんなことを考えながらヴィゴツキーの議論をたどっていくと、そのアクロバティックな筆の運びに、驚きつつも興奮を覚えます。なんとここで「発達の最近接領域」が登場するのです。
学校での教授・学習の前史
議論が紛糾したときに誰もが同意できる問題に戻ることは常套手段の一つですが、ここでのヴィゴツキーの手並みも同じです。ヴィゴツキーは「子どもの教授・学習は、学校での教授・学習がはじまる以前に、ずっと早くから始まっている」という事実に立ち戻ります。例えば、足し算を習うのは小学校1年生ですが、子どもたちは小学校入学前にも足し算の概念を部分的には習得しています。
では、学校に入学する前に子どもたちが足し算を部分的に理解しているとして、それは子どもたちがひとりでに発達した結果なのでしょうか。ヴィゴツキーはそこに否を唱えます。ここでのポイントは、学校に入学する前にも教授・学習はあるのだという事実です。つまり、「教授・学習と発達とは学齢期においてはじめて出会うのではなく、事実上、子どもの生活の初日から相互に結びついている」ことになります。ヴィゴツキーの挙げている事例を以下に引用します。
実際、子どもは大人からことばを学んでいないのでしょうか。質問をしたり答えたりしながら、子どもは大人から多くの知識を得ていないのでしょうか。大人を真似たり、大人からどのようにするべきかの教示を受けたりしながら、子どもは多くの習熟を形成していないのでしょうか。
ただし、学校における教授・学習と、それ以外の場所で行われる教授・学習には相違があります。①学校では「科学的知識の基礎の習得」を目指すが、学校外ではそうではないこと、②学校では学ぶ内容が系統的に組織されているが、それ以外ではそうではないことです。それゆえ、教授・学習と発達の関係は、学校入学以降と以前で別々に考えるべきではあります。
二つの発達水準と発達の最近接領域
問題が提起されたので、再び、誰もが同意できる命題を探しましょう。ヴィゴツキーは、「読み書きは一定の年齢に達した子どもにのみ教えうること」や「一定の年齢に達した子どものみが代数を学習しうるようになること」は争う余地のない事実であるとしてこれを受け入れます。つまり、一定のレベルに学習者が達していないとき(=発達していないとき)に、教授・学習を試みても無駄だということです。これは直観的にも同意できるのではないでしょうか。ちなみに、科学的概念を鍛えるためのPBL/探究学習は何歳から可能なのか?といったことは、未だに学習科学で問われています。また、中学までに科学的概念を学んでこなかった高校生を担当したときに、いきなり高校で教えるべき高度な科学的概念を教えるのがいい教授なのかを考えてみれば、ヴィゴツキーが同意した意図も少し共有できるかもしれません。
多くの人のアイデアはここで終わります。結論としては「学習者に合わせたレベルの授業をしよう」ということです。至極まっとうなのではないかと思えますね。よく分かる子には難しい問題を、わかっていない子には簡単な問題を出すということです。あるいは、数学を習熟度別にして、教室ごとに扱う内容を変えるといったことです。これまでの教育経験を振り返ると、何度も何度もそういった光景に出会ってきたでしょう。これは、先生の優しさゆえであり、教育学的思考に支えられた判断でもあります。しかし、ヴィゴツキーはこの判断に異議申し立てをします。今回の記事で一番注目したい箇所なので、少し長くなりますが、引用します。
私たちは、少なくとも子どもの発達の二つの水準を明らかにしなければなりません。それを知ることなしには、ひとつひとつの具体的状況において、子どもの発達の進行とその教授・学習の可能性とのあいだの正しい関係を見出すことはできないのです。その一つを、私たちは、子どもの現在の発達水準とよびます。ここで私たちが念頭においているのは、すでに完結したある発達サイクルの結果として子どもに形成された精神機能の発達水準です。本質的にいえば、テストによって子どもの知的年齢を規定するとき、ほとんどつねに、こうした現在の発達水準を問題にしているのです。
しかし、この現在の発達水準は子どもの今日の発達状態をまだ十分に明らかにするものではないということを、普通の経験は示しています。二人の子どもを検査し、両者とも知的年齢が七歳だったと仮定しましょう。これはつまり、二人とも七歳の子どもに可能な問題を解決したということを意味します。しかし、私たちがこれらの子どものテストをさらに押し進めていくと、二人の子どものあいだに本質的な差異のあることがわかります。一人の子どもは、誘導的な質問、範例·教示の助けによって彼の発達水準を二年も追いこすようなテストを容易に解くことができます。他の子どもは半年先のテストしか解くことができません。私たちは、ここで発達の最近接領域を規定するのに必要な中心的概念に直接に出会うことになります。
ここでは、発達の最近接領域の理論が明白に述べられています。現代風に翻訳するために、数学の習熟度別クラスの問題を取り上げましょう。通常、習熟度別クラスは、数学のテスト(定期テストや模試の点数・偏差値)に基づいて分けられます。しかし、これはその子が「いま一人で何をできるか」しか物語りません。ヴィゴツキーは、模試の偏差値が50の生徒が2人いて、1人(花子)は教師のヒントがあれば偏差値55になるが、もう一人(太郎)は教師のヒントがあっても偏差値50になる場合、その2人は同じ発達水準(学力)だろうか、と問います。確かにそう言われると、太郎と花子の学力は異なるように思えます。しかし、習熟度別クラスでやっているのは、その本質的には学力の異なる2人を同じレベルにあると見なし、同じ教室で同じ内容を学ばせるということになります。
模倣の位置づけ
私は最初に、デューイには他者や共同体がいないからヴィゴツキーを学びたいと言いました。「発達の最近接領域」には「模倣」の概念が深く関わっていると指摘されるところは、まさにヴィゴツキーが「社会」における学習の問題を考えているところの現れです。
教育の世界では「他者の助けがあって成し遂げたことは、その人の実力ではない」とみなされる傾向があります(本日行われている共通テストは日本での典型的な例の一つでしょう)。しかし、本当にそうでしょうか。日常生活を考えてみましょう。例えば、仕事をしているときは上司に助けてもらうことは当たり前です。また、教科学習以外、例えば部活動や文化祭・体育祭では助け合うことはむしろ奨励されています。
こうした例を考えると明らかに分かりますが、「誰かに助けてもらってできることは、後々できるようになる可能性が高い」と言えます。助けてもらってもできないことは、自分一人でできる可能性はかなり低いでしょう。どうやらヴィゴツキーと同時代にはケトラーという生物学者がいたようで、彼が動物実験を通して「模倣できる行為は可能性の範囲内にある」ことを見出しました。ヴィゴツキーはそれを援用して、「模倣は理解と緊密に結びついている」と言明します。これを教育に当てはめたのが次のパラグラフです。非常に明快な記述なので、ぜひ原文を味わってください。
子どもにおける模倣の本質的な特色は、子どもが自分自身の可能性の限界をはるかにこえた --- しかしそれは無限に大きいとは言えませんが、一連の行為を模倣しうる点にあります。子どもは、集団活動における模倣によって、大人の指導のもとであるなら、理解をもって自主的にすることのできることよりもはるかに多くのことをすることができます。大人の指導や援助のもとで可能な問題解決の水準と、自主的活動において可能な問題解決の水準とのあいだのくいちがいが、子どもの発達の最近接領域を規定します。
私たちは、子どもには無限の可能性があるとしばしば言います。しかし、今現在に限っていえば、ある子どもには無限の可能性があるわけではありません。一方で、それは子どもには全く可能性がなく、いまテストでできるレベルに留まり続けるのだということも意味しません(もっと強くいえば、困難校で疲れ果ててしまった教師がいうように「打つ手はない」状態にいる子どもはいないと信じることでもあります)。
教育の専門家に求められているのは、子どもの無限の可能性を無邪気に信じる理想主義者でもなく、この子には打つ手はないと諦念にからめとられるのでもありません。ヴィゴツキーにしたがえば、「この子はどういう支援があればどこまで伸びていけるのか?」と問いとして持ち、日々の関わりの中でその問いを探究していくことです。
なお、企業での人材育成もまったく同じ構造で捉えることができます。ただし、企業で後輩を育成している場合は、無限の可能性があると信じる人はほとんどいないでしょう。むしろ、「こいつはなにをやってもだめだ」「こいつは成長しない」という諦めに陥らないように注意する必要があります。どんなに小さな一歩でも、その後輩が成長できる領域は必ずあります。それを信じること、それを探すことが育成の第一歩になります。
発達診断学と教育学
先程、私が数学の習熟度別学習に対して行った批判を、ヴィゴツキーもここで繰り返しています。テストで明らかになった知的水準より先には教授・学習は進んではならないのだとの考えは誤っているのです。ここでヴィゴツキーが出すのは、知的に障害を持っている児童・生徒です。第二次世界戦前のソ連の研究者が書いたとは思えないほど、いまの日本でもしばしば議論になる話とも通底するので、一部引用します。
周知のように、知的遅滞児は抽象的思考の能力が弱いことを、研究は明らかにしています。ここから、障害児学校の教育学は、このような子どものすべての教授・学習は直観性に基礎をおかねばならないという正しい結論をひきだしたかに思われました。しかし、この方面の多数の経験は、障害児教育学に深い幻減をもたらしました。もっぱら直観性に基礎をおき、教授から抽象的思考と結びついたいっさいのものを排除したこのような教授・学習システムは、子どもが自分の自然的欠陥を克服するのを助けないばかりか、子どもをもっぱら直観的思考に慣れさせ、このような子どもにもやはりいくらかは存在する抽象的思考のか弱い萌芽をおし殺すことによって、その欠陥をさらに強化することがわかりました。
現代でいえば、「一人ひとりの子どもに合わせた教育」「アダプティブラーニング」「個別最適化」といった言葉を目の前にしているとき、それが生徒の「今日の発達水準」に合わせているのか、それとも「発達の最近接領域」を捉えているのかは注意深く見なければならないと思います。(私はその意味では、AIドリルと呼ばれている一連のEdTechのほうが人間の行うアダプティブより信頼できる面が多いと思っています)
コンプレックス・システムと思考
まだ「発達の最近接領域」の概念が知られていなかった頃の論争が簡単に触れられています。一言でいえば、「学校に入学するとき、子どもたちは思考のコンプレックス・システムを持っているので、体系的思考の形式は合わないのではないか」という主張のようです。ヴィゴツキーは、確かに子どもたちの思考はコンプレックス・システムだが、明日の観点から設定すれば、教授・学習の目的は体系的思考になるだろう、としています。
ことばと高次精神機能
続いて、ヴィゴツキーの有名な内言理論が言及され、それと発達の最近接領域の関係が考察されていきます。ここもヴィゴツキーの教育理論において、他者や共同体と教育の関係を見ていく上で重要なところです。まず、ヴィゴツキーの主張が端的に述べられます。まず最初に社会的活動があり、その後に個人的=精神的活動になると考えます。発達においては、個人があって社会があるのではなくて、社会があって個人があるという順序なのです。
あらゆる高次精神機能は子どもの発達において二回あらわれます。最初は集団的活動・社会的活動として、すなわち、精神間機能として、二回目には個人的活動として、子どもの思考内部の方法として、精神内機能としてあらわれます。
ヴィゴツキーは、ことばと意志の発達という2つの例を引きます。まず、ことばについては、以下のステップです。①周りの人間とのコミュニケーションの手段として発生する→②内言(自分と対話するための言葉)となり、思考の基本的方法となる。ことばを考えるための手段として使えるのは周りの人間とコミュニケーションをとった後だ、というのがポイントです。次に意志の発達では、①集団的遊びの中で自分の行動を規則にしたがわせる→②自分自身の内部機能として行動の意志的調整が発生する、という発達の流れになっていると指摘します。どちらも集団や社会との関わりがまず最初にあることが重要なポイントです。
したがって、教授・学習にとって重要なことは、子どもたちの発達を促すような集団的・社会的活動(現在風にいえば協調Collaboration)を設定し、子どもたちの参画を促すことになるといえるでしょう。
いまは子どもにとってまわりの人たちとの相互関係、友だちとの協同のなかでのみ可能であることが、発達の内的過程が進むにつれて、のちには子ども自身の内的財産となる一連の内的発達過程を子どもに生ぜしめ、覚醒させ、運動させるという事実にある、と断言してもよいでしょう。
それゆえに、本論文のメインテーマである、教授・学習と発達の観点は以下のように定義されることになります。
正しく組織された教授・学習は、子どもの知的発達を先導し、教授·学習の外では概して不可能であろうような一連の発達過程を生じさせます。
子どもの教授・学習と大人の教授・学習
ここでは、少し補足的に子どもと大人の場合で、教授・学習の役割がどう違うのか、比較を行っています。表面的な違いとしては、子どもと大人では習慣の変えやすさが異なる点があります。しかし、ヴィゴツキーは本質的な点として、子どもの教授・学習は、書きことばや数的・科学的概念の習得に関わるため、「精神過程のまったく新しい、きわめて複雑な発達サイクル」を生じさせることになることを挙げています。当時としては面白い分析だったかもしれませんが、知識基盤社会が到来し、大人も脱学習(unlearning)が必要な時代となったため、現代にはあまり示唆のない部分かなと思います。
発達と教授・学習の非同一性と複雑性の依存関係
最後に、ヴィゴツキーはここまで述べてきたことをまとめ、今後の研究の展望を示します。一言でいえば、この論文で言いたかったことは、「発達過程は、発達の最近接領域を創造する教授・学習の後を追って進む」という命題になります。では、この発見を踏まえると、どんなことを私たちは考えていくべきなのでしょうか。
第一に、教授・学習によって「発達の最近接領域」を生み出したあと、子どもの思考の発達における複雑な一連の内的過程がどのように進んでいるかを明らかにすることです。これはつまり、何かを教えたらそのまま子どもがそれを習得すると考えるのではなく、教えたことによって子どもの思考がどう進化するかを捉えなければならない、ということを意味しています。これを「教授・学習過程と発達の内的過程の統一性」という言葉で呼んでいます。
第二に、それぞれの具体的な教科内容が、子どもの一般的な知的発達に対して、どういう役割を持つかを調べることです。本文でも述べられていたように形式陶冶はまやかしであり、実際には何を教えられるかでどんな能力が伸びるかは変わってきます。ヴィゴツキーは「何かある一つの公式によって解決」はできないと断言し、「児童学に具体的研究の無限の広場を導入」することを提起しています。必要なのは、抽象的な理論ではなく、具体的な研究であり、それによって一つひとつの領域で教授・学習と発達の関係を明らかにしていくことだ、といいます。私の知る限り、こうした研究は現在に至るまで決して蓄積が進んでいるわけではありません。
終わりに
さて、発達の最近接領域の理論を原文にそって読解してきましたが、どのような印象を持ったでしょうか。現在でも「学校なんていらない。子どもは経験の中でひとりでに成長するのだから」と考える人がいる一方で、「とにかく授業の技術を磨くことが大事。ちゃんと教えれば子どもは成長する」と考える人もいます。しかし、そのどちらでもなく、「子どもが少し背伸びしたら解ける問題に、他者と協調しながら取り組んでいく」経験をいかにつくるか。それこそが教育にとって最も本質的な問いになります。
また、今後は教育のICT化が今後一気に進み、コロナ禍の影響でソーシャルディスタンスを取らざるを得ない状況が今後も続いていきます。そこで、子どもが先生や同級生とともに学ぶことの意義もまた問い直されることになると思います。「発達の最近接領域の観点」の観点から見れば、2mの距離を取って対面で協調するよりは、ZoomとGoogle Slideでオンライン上の協調をしたほうが効果を持つのではないか、といった仮説も浮き上がってくるでしょう。大切なのは、①子どもにとって、一人ではできないが、他者の助けを得ればできることはなにか、②そういった経験や活動をどのように創造・支援していくか、③そのような経験・活動から子どもが思考を発達させるためにはどうすればいいか、といった問いです。きっとヴィゴツキー的な目線で再考することで見え方が変わる場面もあると思います。
また、ややマニアックな気付きですが、ヴィゴツキーやピアジェとの立場の差異を明らかにしてくれたことで、ピアジェは「構成主義」で、ヴィゴツキーは「社会構成主義」と整理されるときの「社会」の2文字に決定的な意味があることを改めて得心しました。もともと教室が生活経験の場として編成されている日本の教育現場においては、この「社会」の2文字が意味することは少なくないと思います。
長い文章になってしまいましたが、お読みいただき、ありがとうございました。時間があるときに、次はヴィゴツキー『教育心理学講義』の読解ノートを作成したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
