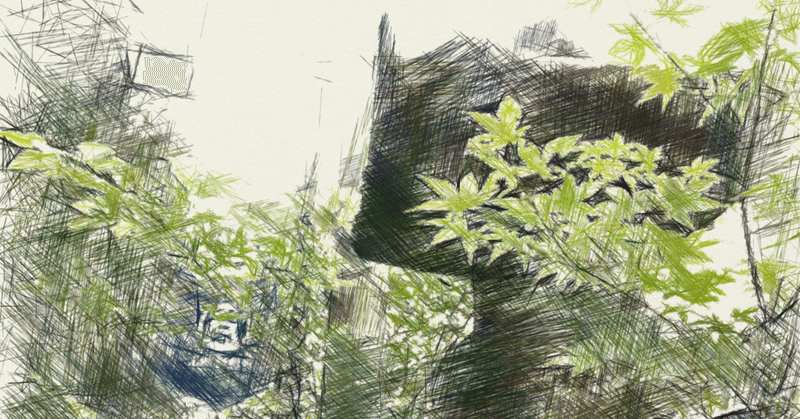
言葉をどこで獲得してきたのか
保育の専門学校で働いていた時のこと。
専門学校と聞くと高校を卒業した子たちが入学するイメージがあったけれど、私が勤めていた専門学校はむしろ高校卒業したての子が入学するのは半数以下。
そして、大学卒業してそのまま入学してくる既卒生や、社会人経験をした人が入学する人数が半数以上いる学校だった。
クラス編成をすると、7割が20〜40代ということになった。
・・・
彼女たちの前で話をしているときに感じた事は、言葉を知らない子が多いということだった。
例えば、幼稚園や保育園の実習の際に服装の注意をするとき、ダボダボのズボンももちろん避けるべきだが、あまりピッタリとしたスキニーパンツやデニムも膝が出るので、ストレートのサイズが合ったものを履くようにと指導していたのだが、その際に「膝が出るってなに?」と聞かれた。
膝をついて作業をしたり、子供に目線を合わせてしゃがむことが多いから…と話す途中で、「ダメージ加工だと破れるってこと?」「それでも膝はでなくない?」など、まぁ見当違いの解釈が目立った。
また、ある時も同じことを何度も説明しているので耳にタコができると思うが…と話していると「タコってオクトパス?」と。
まぁそういうムードメーカーというか、とぼけた子はクラスに2.3人はいるものなのだが、驚いたのは高校卒業上がりの18.19の子ではなく、既卒生などを含む20代に多いことだった。
・・・
当時、私も25〜7くらいだったので「最近の若い子は」と言うつもりもないし、知らないことに対して見下すつもりもない。
たしかに、本を読まない習慣が言葉を知らないまま大人になってしまったということも少なからず考えられるが、私だって知らない言葉はまだまだあると思うし、それ自体が悪いとは思えない。
それに「膝が出る」という言葉や「耳にタコ」などの慣用句は、本から学んだというよりも、家族や周囲の人との会話によって得るものが多いのではないかと思った。
少なくとも、私はそうだった。
読書から得る言葉は文語が多いのに対し、会話から得る言葉は口語であることが多い。
そして、人の話をよく聴いていると、自分の中にない言葉や語彙・言い回しなどを知ることができる。
幼い頃からその役割を親が担ってくれていた。
親が話す言葉や慣用句・ことわざなどを当たり前のように耳にしていたので、専門学校生の彼女たちよりもちょっとだけ多く言葉を知っていただけなのだと思った。
・・・
父がよく、「親の小声と茄子の花、千に一つも無駄が無い」と言っていた。
そういうお小言を鬱陶しく思う時期もあったけれど、今になってその言葉の意味を噛み締めている。
そして、読書と同じくらい会話をしたい。
人の話を聞きたいと思っています。
今後も有料記事を書くつもりはありません。いただきましたサポートは、創作活動(絵本・書道など)の費用に使用させていただきます。
