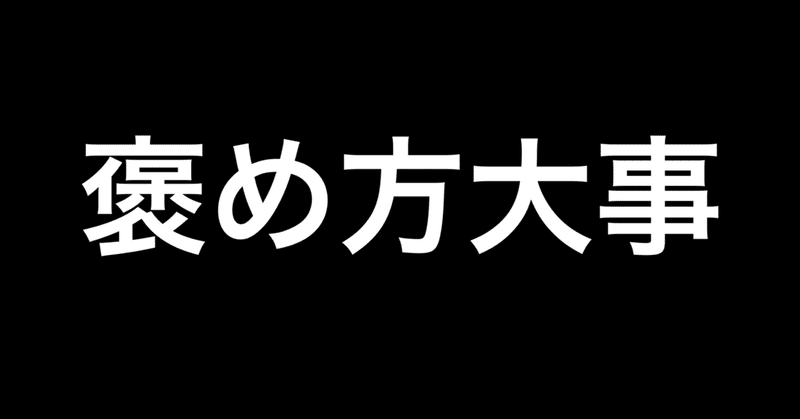
人が成長する褒め方、人をダメにする褒め方
大学受験を控える高校3年生の娘が、模試で学校1位の成績をおさめ、嬉しそうに報告してくれました。他のお父さん同様、私は娘には甘いため、小さい頃から常に褒め続けてきました。当然、娘も父はいつも何かあったら褒めてくれる人ということを認識しています。高校生にもなると、なかなか褒める場面も少なくなってきますが、「いつも遅くまで勉強してた成果が出てすごいね」と自分のことのように喜んで、「すごい」と褒めちぎりました。
「褒める」のは簡単です。ただ、人(とくに子ども)を褒める際には、褒め方によって、良い方向にいくこともあれば、悪い方向にいくこともあるのをご存じでしょうか? というわけで今回は褒め方についての話を書いていきたいと思います。
以下は子どもの心理を探ったアメリカの研究の話です。
400~500人の小学5・6年生のグループを2つにわけて、最初は両方のグループに簡単なIQテストをやってもらいます。簡単なものなのでみんなが好成績を残すことができます。ここでAグループは「すごく頭がいいね」「良い点数だね」と結果・知性の部分を褒めます。これに対してBグループは「よく準備してきて偉いね」「普段からちゃんと勉強しているんだね」と過程・努力の部分を褒めます。
続く第2段階として難しいテストと簡単なテストを用意して各自に選択させると、知性を褒めたAグループの約7割は簡単なテストを選択。逆に努力を褒めたBグループは9割が難しいほうを選んだそうです。
第3段階は選択肢を与えずに両方のグループに難しいテストをさせます。すると、Aグループがすぐに諦めてしまうのに対して、Bグループは一生懸命取り組んでテストに挑む過程を楽しもうとします。そして最後にもう一度、最初と同じ簡単なIQテストをおこなうと、なんとAグループは点数が20パーセントもダウン。対するBグループは30パーセントアップという研究結果が出たのだと言います。
この研究結果が何を意味しているかというと、褒め方によってマインドに変化が起こるということです。結果・知性を褒められたAグループの子どもたちは、最初に結果を褒められたので「良い結果を出すことが大事」というマインドになり、2つ目のテストでは良い結果を求めて簡単なほうを選択し、3つ目のテストで難しくてできないと、「結果が出ないなら意味がない」と、すぐに諦めてしまいます。
一方、Bグループの子どもたちは過程や努力を褒められたため、「大事なのは頑張ること」、「チャレンジすることが大事だ」というマインドになっています。その結果、第2段階では、より成長するために難しいテストに挑み、第3段階のテストで問題が解けなくても、粘り強く取り組むようになりました。
成績の善し悪しはあくまでも結果であって、大事なのは結果そのものよりも、そこに至るまでの過程であり、成長するためにチャレンジすることです。人は結果を恐れるとチャレンジすることができなくなります。しかし、結果よりもチャレンジすることが大事だとわかれば、失敗を恐れずにチャレンジできます。挑戦し続ける人間と、失敗を恐れて何もしない人間とでは、どちらがより成長するかは明白です。まだまだ成長過程のお子さんがいる親御さんは、ぜひ褒め方の参考にしてみてください。
成長過程でどんな褒められ方をしてきたかは、社会人になってもその違いが如実に表れている気がします。部下に仕事を頼んだときでも、「失敗したくない」というマインドが強く、0~100まで指示をしてほしいというタイプもいれば、方向性だけ指示すればそこを目指して自分で考えてチャレンジするタイプもいます。
100パーセントの指示待ち人間と、自分で考えてチャレンジして時には失敗もする人間。1年後にどちらが優秀な人材になっているかは言うまでもないでしょう。
社会に出たら、親に褒めてもらうように、上司に褒めてもらいたい、先輩や同僚に褒めてもらいたい…と考えるのはやめましょう。大人になったら誰かにマインドを育ててもらうのではなく、自分で育てていくべきです。だから自分が勉強したこと、チャレンジしたことは、自分自身で褒めましょう。誰かに褒めてほしいという甘えん坊精神では社会で生きていけません。
一方、人を評価する立場の人は、結果だけで物事を見てはいけません。結果に至る過程の部分をしっかり理解したうえで、人を評価できるといいですね。
ちなみに、この褒め方は勉強や仕事への取り組みについての話なので、恋愛の場面で彼女に使うことはオススメしません。「結果はあれだけど、頑張って化粧したんだね」なんて言ったらおしまいです。そこは自分で考えてください。
おわり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
