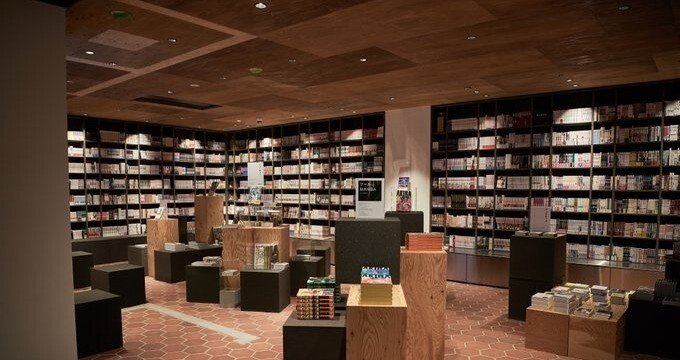
- 運営しているクリエイター
2023年1月の記事一覧
【楽しい初出版55】「著者買取り」というシステムがあります。著者自らが出版社、または書店さんから自分の書籍を買うことです。正価で買う場合もあれば、いわゆる7~8掛け(本体価格の70~80%)で買う場合もあります。数十冊~千冊単位まで、目的によって求められる冊数は異なります。

【楽しい初出版54】重版を狙う場合、著者が売上げを動かしやすいポイントは3つあります。①発売前後②Amazonなどでのキャンペーン期間③メディアで取り上げられる時。いずれもあなたのSNSやブログ等で積極的に発信できます。まずは、多くの人の目に触れる機会を増やすことが先決です。

【楽しい初出版53】重版は狙えるものでしょうか。結論から言えば、狙えます。いえ、狙わなくてはなりません。10万部売れている書籍でも、初版は数千部という場合がほとんどです。版を重ねて、結果として10万部になったのです。しかし、狙わなくては10万部という数字は達成できません。

【楽しい初出版52】商業出版の収益として、重版は非常に重要です。ぶっちゃけて言えば、よほど大部数でない限り、初版だけでは出版社の利益はほとんど出ません。多くの書籍が重版で利益を得るという原価構造になっているのです。重版は、原価が初版よりも安く済むので、利益率が高くなります。

【楽しい初出版51】宣伝広告に「発売前重版」「発売即重版」という景気のいい文言が並んでいるときがあります。「発売前重版」は、注文が好調などの理由で発売前に重版が決定すること。「発売即重版」も注文・売上げが好調で、発売直後に重版を決定したということ。思わず読みたくなりませんか?

【楽しい初出版50】各出版社で重版決定の指標は異なります。発売から1週間の売れ行き(初動といいます)や発売から1カ月の売れ行きを重視することが多いようです。書店さんからの注文数やメディア露出のタイミング、それに編集者や販売担当者の経験値を掛け合わせて、重版が決定されます。

【楽しい初出版49】本を発売したら狙いたいのが重版。「Amazonで在庫切れなのに、なぜ重版しないのか…」先輩著者のそんな嘆きを聞いたことはありませんか?出版社は重版に、とても慎重です。在庫切れは解消したいが、返品は避けたい。そんな中で、データを駆使して重版を決定するのです。

【楽しい初出版48】本の発売前後に、記念講演会やセミナーを開催しましょう。読者や応援してくれる人に会える絶好の機会です。もちろん、リアルでなくても構いません。参加者の反応や本の感想が、次作やあなたの新しいコンテンツのヒントになります。あなたに接して、ファンになる人も多いでしょう。

【楽しい初出版㊼】Amazonレビューのアンチコメントを気にする著者の方は多いですね。「消せませんか?」と相談してくる方もいらっしゃいます。気にするのはわかりますが、悩んでも仕方ありません。アンチが出てくるのは、あなたの注目度が上がっている証拠です。「アンチもファンのうち」です。

【楽しい初出版㊻】編集者が決める1冊ごとの工程表とは別に、自分だけの工程表を作ったほうが未来が見えます。出版パーティの日を決め、それに合わせて原稿執筆や修正作業、宣伝プロモ―ションの日程を決めるという作家の方もいます。ギリギリの日程ではなく、バッファを持たせるようにしましょう。

【楽しい初出版㊺】出版によるブランディングは、一朝一夕にはできません。初出版でブランドの構築に成功するには、“ベストセラー”と言われるほど売れることが必須条件です。それでなければ、年に1冊でも2作目、3作目と出版し続けることが、その分野での専門家として認定される前提になります。

【楽しい初出版㊹】ビジネスのために出版をする――そんな目的を明るみにすると嫌う編集者もいますが、どんな著者も潜在的にはこの目的を心に秘めています。あなたのビジネスでも露骨な売込みや営業が嫌われるように、本の中で「私の商品を買ってください」と表現すれば、読者は離れてしまいます。
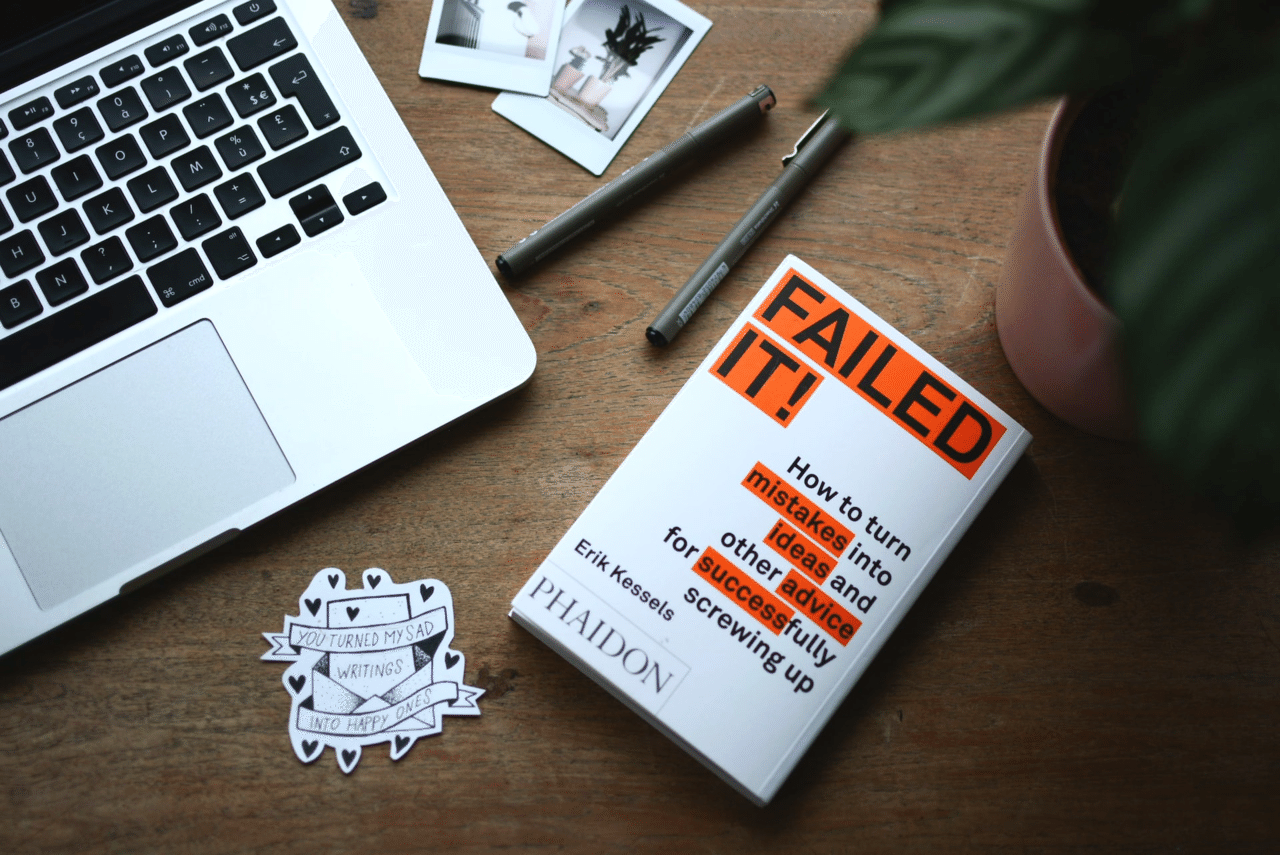
【楽しい初出版㊸】マスメディアでの露出は、確かに本の売上げに効果があります。ただし、その影響は基本的に一時的です。単行本は、長期的に読者のもとに届けるもの。もちろん発売当初の初速は大事ですが、書店さんや図書館に何十年も残る本は数多くあります。ロングセラーを狙っていきましょう。

【楽しい初出版㊷】出版するとメディア取材を受ける機会も出てきます。取り上げられ方によりますが、瞬間的に本の売上げに直結するのは、やはりテレビです。要約サイトや経済・ビジネス系の定評のあるネットメディアも効果があります。本を紹介するYouTubeチャンネルも影響力を増してきました。


