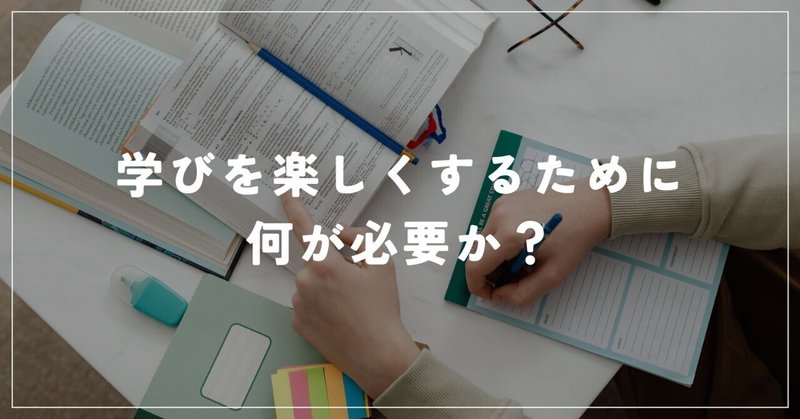
学びを楽しくするために何が必要か?(6)- 自分で選択するということ(1)
学びを楽しくするために必要なものの3つめとなる要素が、「自己決定」(自分の意思による選択)です。
社会心理学者のデチャームは、人間には、「自分は、自分の行動の源泉でありたい、自分の行動の主人公でありたい」という根源的な欲求があると言っています。子どもの学びにおいてもこのことがあてはまります。
簡単に言うと、誰かにやらされているという感覚をもちながら学ぶよりも、自分で選んだという感覚をもちながら学ぶ方が楽しく学べるということです。
例えば、自己決定理論を提唱した心理学者エドワード・デシの研究です。ソーマパズルというパズルを使った実験で、1つのグループには、どのパズルを解くか、パズルにどれだけの時間を費やすかを選択させる。もう1つのグループには、どのパズルを解くか、どれだけの時間で解くかを指定します。その結果は、選択の機会が与えられたグループの方は、課題の時間が終わってもパズルに取り組んでいた(楽しいと感じたのでパズルを続けてしまった)が、選択の機会が無いグループではそのような行動は見られなかった。と報告しています。
また、スワンによる実験でも似たような報告がなされています。子どもに絵をかくことを含む、いくつかのリストの中から自分で選ぶ(実際には、絵をかくことを選ぶように巧妙に設計されている)グループと、子どもに選択させずに絵を描くように言われるグループ、それぞれに絵をかいてもらいます。その後、「時間があまったから好きなように過ごしてて良いよ」と伝えます。その結果、自分で絵をかくことを選択した子どものグループは、余った時間も引き続き絵をかく子どもが多かったのですが、一方、絵をかくように指定されたグループの子どもは絵を描くことを止めてしまいました。
こういった報告を受けて、60~70年代のアメリカでは「オープン・スクール」というスタイルの学校が増加しました。この学校では子どもが自分の学び方を自分で自由に選択できるように設計されています。いつ何をどのように学ぶのかを先生のサポートのもとで子どもが自分で決めることができるので、誰かに「学びをやらされている」という感覚が生まれません。
このオープン・スクールの効果を実証的に検討した研究の多くで、オープン・スクールのもとでは、伝統的な学校にくらべ、学校や学習に対する肯定的な態度が形成されたことが確認されています。(*1)
このように、子ども(というか人間全般)には、「自分は、自分の行動の源泉でありたい、自分の行動の主人公でありたい」という根源的な欲求があり、その欲求を満たすように学びの環境をデザインすることができれば、学びを楽しくすることができるということになります。
この理論を、実際に子どもの学びの環境にくみこむにはどのような方法があるのでしょうか?次回は、いくつかの実践例を見ながら、どのような方法が可能なのかを考えてみたいと思います。
(*1 ) ただし、オープン・スクールスタイルの学校は、アメリカではその後減少しています。オープン・スクールで期待した成果が得られないケースも多くなってきたからというのが理由です。オープン・スクールスタイルの学校運営は教師の負担も大きく、高いスキルも求められるにもかかわらず、そういった十分な体制が作れないまま、形ばかりのオープン・スクールスタイルを導入した学校も相当数あったため、そのことがオープン・スクールスタイルの評判の悪化につながったとも言われています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
