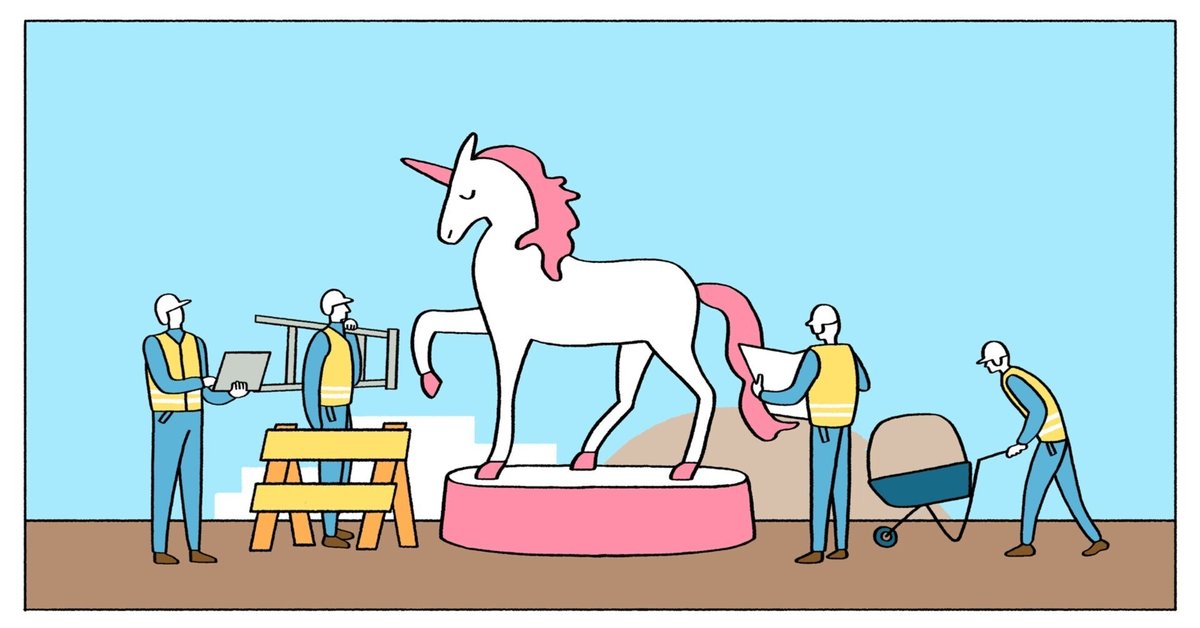
スタートアップで地域建設業をおもしろくするために、noteを再開します。
皆さま、ご無沙汰しております。
最後にnoteを投稿して以来、約1年振りの投稿になります。
これまでの活動を振り返って
“地域建設業をDXでおもしろくする“という仮説で2021年3月にnoteを開始し、これまで世の中にあるデジタル・IT系のプロダクト・サービスを調べては、社内で導入・運用し、試行錯誤を図ってきました。
※最初に投稿したnote(今読み返すと懐かしい…)
具体的には、施工管理アプリ、遠隔監視、3Dスキャン・測量、ドローン、ICT建機、原価管理システム、コミュニケーションアプリなど、利用可能なモノは色々と試させていただき、また、それだけでなく、大学教授、DXに力を入れられている建設会社の方、建設スタートアップの起業家など、さまざまな方に出会い、意見交換をさせていただきました。
しかし今日まで、このような活動や仮説検証を行った結果として、大変残念なことに、“DX”(デジタル・トランスフォーメーション)と呼べるような大きなインパクトを創出することはできませんでした。
新しく導入したモノは、もちろん無いよりはあった方が良い。トライアルでしっかり効果が確認され、今でも継続的に利用しているモノもあります。
ただ、別に無くてもそこまで困らない。
地域建設業とは全く異なる世界からやってきた私が、「DXだ!」と息巻いて現場に提案したモノは、現場で働く人々のペインポイント(困り事)を解消し、バーニングニーズ(切迫したニーズ)に応えるようなものではなかったのです。
むしろ途中から、手段であるはずのDX自体が目的化しているような感覚さえしていました。
何がダメだったのか?
改めて地域建設業の問題を考えてみると、「人手不足」「高齢化」「技能伝承」という、ごく一般的かつ慢性的な問題がすぐ頭に浮かび、そしてその対応策として「デジタル・IT活用による生産性向上」が脳裏をよぎります。
しかし、この段階で早くも思考停止してしまっていたようです。
これまで投資やコンサルの仕事をしてきて、「課題」は何ですか?「課題」と「解決策」はフィットしていますか?そこに「顧客ニーズ」はありますか?と言ったことを上から目線で、起業家や経営者に問いかけてきたにもかかわらず…
自分自身が業務の解像度は低く、課題の深堀も全くできていなかった。
ソリューションありきで導入を推進、あとは現場で何とかしてくれるだろう!という安易な気持ちでパルプンテを期待、神頼みになっていたのです。
そんなアプローチでは、DXと呼べるような大きなインパクトを創出できるわけがありません。今思えば至極当たり前のことですが、ようやく今になって気づいたのです。
例えば、施工管理やバックオフィス業務において、紙やエクセルの情報を単にデジタル化・オンライン化するだけでは、あまり大きな効果は得られませんでした。大企業のようにデスクワーカーが沢山存在し、大量の情報を取り扱っているならば話は別ですが、中小零細の地域建設業では、集約化だけではあまり効果がありません。デジタル化した先の出口、情報をどう活かしていくかがもっと重要です。
一方で、「人手不足」という問題にアプローチするならば、管理側ではなく職人側にペインがあるため、極論すると、施工自体の生産性を上げないことには抜本的な解決にはならないのかもしれません。
どれだけ施工管理が高度化しても、現場で施工する職人さんの総数が減り、(一人あたり生産性の高い)熟練した職人さんが引退していくと、地域建設業界全体の生産性は、今後、向上どころか低下していくと予想されます。
中小現場で利用可能な建設ロボットに期待したいところですが、それはそれで技術・コスト面のハードルが非常に高く、もしかしたら、IT・デジタルは渋々諦めて、「外国人労働者の活用」についてちゃんと考え直すほうが現実的な解決策なのかもしれません。
しかし、周りを見渡す限り、技能実習制度もあまりうまくいっていないように思われますし、ニッポンは実習先としての魅力が相対的に低下してきているため、それはそれで前途多難です。
地域建設業の抱える慢性的かつ根深い課題を解決しようと思うと、非常に多くの困難が想定され、おそらくこのまま成りゆきで行き着く先は、地域インフラの整備・維持管理について供給制約が生じている未来だと思われます。(供給が需要に追いつかない…)
近年では、街中で工事をしていると、静かにしてくれ、渋滞を何とかならんのか、といったクレームを頂くことも増えています。地域社会に必要とされていないのならば、供給力を無理して維持しようとする必要もないのかもしれません。
いま当事者として、地域建設業や家業のおかれている状況を理解し、10年・30年先の未来を考えると、考えるだけで大きな徒労感に襲われます。
レガシー産業をテクノロジーでアップデートだ!なんて大きなことを言っていられたのは3年前の話。何かが変わること、何かを変えることは、そんなに簡単なことではないし、中小零細企業は存続し続けること自体、とっても難しいことなのだと今は感じています。
これからどう取り組んでいく?
しかし、あきらめたらそこで試合終了です…!
これからは、これまでの反省や気づきを踏まえつつ、現状の業務プロセスを正しく理解するとともに、しっかり解像度を高め、課題をきちんと整理するところからはじめていこうと考えています。
「デジタル・トランスフォーメーション」なんて大口はもう叩かないので、地に足をつけてコツコツと本質を見極めて、生産性向上に取り組んで参ります。これまでのように有り物を単に導入するだけではなく、業務プロセスの見直しとセットで考えていく必要があります。
また、これまでは、生産性向上=業務効率化(省人化)という思考に凝り固まっていたようにも思います。生産性=付加価値/労働投入量ですので、分子を増やすか、分母を減らすかの議論もありますし、「付加価値」にも、工事出来高のような経済面だけでなく、安全面や環境面等、様々な観点が考えられるはずです。
さらにもっと言うと、今やどこへ行っても「生産性向上、生産性向上」と耳にしますが、そもそもそれ以外にも重要な経営課題があるはずです。
実は、ここ一年ほどは、このような地域建設業界の課題解決に取り組むスタートアップに期待し、探し回っていました。しかし、国内建設業の業界構造も相まって、なかなか協業先を見つけることができませんでした。
有望なスタートアップがいたとしても、スタートアップ経営の立場に立つと、大手~中堅・地場ゼネコンクラスと協業したほうが、明らかにビジネス・技術開発の両面で効率が良く、地域建設業はターゲット顧客にはなりにくいものです。大きな成長を目指すスタートアップにとっては、加藤工務店は協業相手として力不足です。
協業先を見つけられないなら、自らが主体となって取り組むしか道はありません(かなり中二病的ではありますが…)。
具体的には、①仮説を立てる、②観察・ヒアリングする、③課題を整理する、④思い込みを捨てる、というプロセスを愚直に回していこうと考えています。このアプローチは、スタートアップなどが新しいプロダクトやサービスを開発する過程において実施することです。
言われれば当たり前のアプローチなのですが、愚直に続けるのは余程の情熱がない限り、想像以上に難しいことなのかもしれません。加藤工務店がスタートアップとしてVC等から資金を調達し、もの凄いスピードで走っていくわけではないですが、このアプローチには多いに学ぶべきところがあります。
“スタートアップで地域建設業をおもしろくする”
今後は、このようなコンセプトで、再始動して参ります。
もし、この領域に関心を持たれた方がいらしたら、ぜひお声掛けください!特に起業家の方におかれましては、スタートアップ型の経営や資金調達の部分でお役に立てる部分もあるかと思います。
今後、noteの投稿に足るようなおもしろいアップデートができるか不安ではありますが、引き続き状況報告させていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
