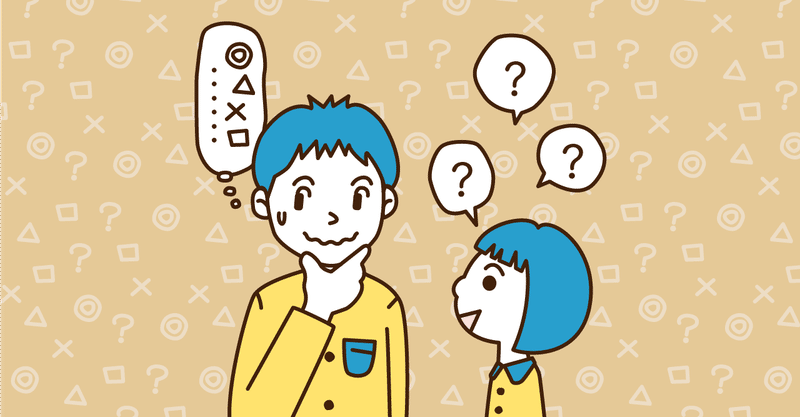
中国人と日本人との文化的な溝は埋めることができるか?
『異文化理解力』という本を読んでいるのだが、この本がかなり面白い。
国によって、ハイコンテクスト、ロウコンテクストと座標軸で分けていくと、日本や中国等東アジア、東南アジアはハイコンテクストな文化、欧米はロウコンテクストな文化と分けることが可能だが、同じ文化でもものをはっきり言わなかったり、言ったり、遠回しに言ったりする事例がたくさん挙げられている。
例えば、同じハイコンテクストな文化である中国と日本では、かなり違いがみられる。日本ははっきりと相手にネガティブなことを伝えないが、中国はストレートに言う。日本はタイやインドネシアに近いという。
欧米の例で言うと、
フランスでは、ポジティブ・フィードバックはほのめかして伝えられることが多く、ネガティブ・フィードバックはそれに比べ直接的に伝えられる。
アメリカ人のマネージャーはたいていポジティブ・フィードバックを直接的に伝え、ネガティブ・フィードバックは前向きな、励ましの言葉と一緒に伝える。
これは事前に理解していないと、最初本当に混乱すると思う。実際、仕事で両国の人と関わったことがあるが、本当にこんな感じなのである。フランス人はドストレートでどぎついなあというイメージで、アメリカ人はおだてすぎやわ〜と思ってたら実はDisられてたという苦い思い出がある。
筆者は、異文化理解については、性格の違いに寛容になるだけでは足りない、と主張する。
文化の差は関係がないと思って人と接すると、自分の文化のレンズを通して相手を見ることが標準となってしまい、それをもとに判断をしたり判断を誤ったりしてしまう。
これは外国で暮らす多くの人にあてはまるであろう。上海で見る日本人達はまさに「自分の文化のレンズ」を通して中国や中国人を見ており、「これだから中国は」とか「中国人は何を考えているのか分からない」とかぼやいたりする。
異文化を理解する為には、文化や個人の性格かではなく、文化と個人の性格が問題となる為、両方を理解する必要があるのである。また、互いの文化が互いのことをどう見ているかを理解する必要もあると筆者は強調する。
ひとつの文化でしか過ごしていない人は、地域差や個人差にしか目がいかないことが多く、そのため「この国の文化はハッキリとした特徴を持っていない」と結論付けてしまう
中国人と日本人におけるハイコンテクスト文化
筆者は、言語以上に、その国の歴史がコミュニケーションの指標における位置づけに大きな影響を与えるとし、日本と中国のハイコンテクスト文化についてこう指摘する。
日本は単一民族の島国社会で数千年におよび歴史を共有しており、その歴史の大部分は他の国から閉ざされた状態だった。数千年をかけて、人々は互いのメッセージをくみ取る能力に長けるようになった。※数千年は正直いいすぎだと思う…
中国は広大な国で、地域によって特色がずいぶん異なっている。あらゆる点で中国のビジネス文化をひとくくりにして考えるのは難しい。世代間の差も大きいし、官と民の違いも大きい。(中略)中国では、表面上のメッセージは必ずしも本当のメッセージではありません。中国人の同僚たちが何かを遠回しに言って、私がそれを受け取れないことがあります。後になって、思い返してみると、私が大事なことを受け取り損ねていたと気づくのです。
中国は図のかなり右側に位置しているが(ハイコンテクスト文化)に位置しているが、日本よりはかなり率直にものを言うため、日本人は中国人の遠慮ないフィードバックに腹を立てるかもしれない。
よく巷でも言われることではあるが、日本は「以心伝心」と言われるように、「おい、お前、何をやればいいか言わなくても分かってるよな」と暗黙的に相手から了承をとりつけるようなやり方が多く、中国人の場合は言葉を遠回しに発言して、「おい、こういう意図だからお前ちゃんと汲み取ってくれよな」となる。(特に利益が絡む話となるとこれが顕著になる)
これはネガティブ・フィードバックに特に顕著にみられるやり方なのだが、日本の場合ポジティブ・フィードバックは殆どないように思う。中国人がネガティブ・フィードバックをどストレートに言う時は、相手との力関係が中国人側が上か、その人に対しての発言がその人のメンツであったり、「核心的利益」の「量」に影響を与える場合に、爆発的に発揮される傾向にあるだろう。
この記事でも色々中国人が「核心的利益」と考える部分についても触れているので、併せてお読みいただきたい。
中国人のメンツに関する考察についてはこちらのNOTEをどうぞ。
中国人と日本人との文化的な溝は埋めることができるか?
これは結論から言うと、文化の溝を埋めることは無理だが、理解し相手に寄りそう形でコミュニケーションをとることで、相互理解が進みよりコミュニケーションを行いやすくなる、ということが言えるであろう。
自分用のレンズを通して、相手の文化を見ることがないように今後も気を付けていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
