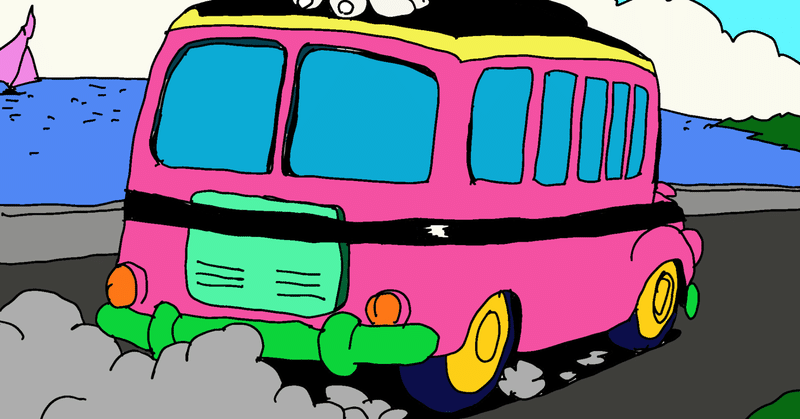
【つくること】 LIBRARY BOOK CIRCUS 那須塩原市図書館みるる 1日目
様々な業界の方とともに【きく】→【かんがえる】→【つくる】という循環から、これからの?図書館?をつくる旅に出かけたわたしたちですが、遅くなりましたが、5月末の土日を使って、「那須塩原市図書館みるる」にて、【つくる】第1弾とも言えるLIBRARY BOOK CIRCUSを開催しました。その模様を『「聴く」の文化を広げていく』という素晴らしき活動をされている、インタビュアーの中田 達大さんにまとめていただきましたので掲載いたします!2日間にわたり行われたイベントのその1日目です!
あなたの街にサーカスがやってきたら
サーカスが街にやってきた ——
小学生だった頃、母親の運転する車から外をぼんやり眺めていると、遠くに赤と白のストライプ模様の三角テントが見えた。サーカス小屋だ。
「ママ、サーカスが来てるよ!」
私は運転席に向かって叫んでいた。
「本当だ。どこから来たんだろうね?」と母は言った。
確かに、どこから来たんだろう?
そして、どこへ行くのだろう?
サーカス小屋は見慣れた景色を特別なものに変えて、気づけば次の街へと旅立っていった。
そんな風景を20年以上ぶりに思い出したのは、私が暮らす街にサーカスがやってきたからだ。2022年5月28日(土)29日(日)、栃木県那須塩原市の黒磯駅前にある「那須塩原市図書館 みるる(以下、みるる)」にて「Library Book Circus(ライブラリーブックサーカス)」という名の2日間限りのイベントが開催された。「Library」の名のごとく図書館を舞台としているが、「みるる」から約300mのところにある「那須塩原市まちなか交流センター くるる(以下、くるる)」も会場として使われる両館の合同イベントである。

「図書館の本はまるで曲芸師のようです。その一冊一冊は、開くと私たちを驚かせ、感動させ、楽しませてくれる。本が曲芸師なら、図書館はさながらサーカス小屋のようだと思ったんです」
「Library Book Circus」の発案者である染谷拓郎さん(株式会社ひらく代表取締役社長)はイベント名の由来をそう語る。つまりこの2日間は、図書館をサーカス小屋に見立てて、様々な催し物があちこちで行われるようだ。事前に配布されたパンフレットにはこんな風に書かれていた。
「好奇心をチケットにして、ライブラリーブックサーカスで会いましょう」
サーカスと言われても、どんな2日間になるのか想像することは正直難しかった。ただ、車窓から三角テントを見つけたあの日のように「私の街にサーカスがやってきた」ことだけは確かだった。あとは、そのワクワク感をチケットとして持っていけばいい。本レポートは、黒磯に暮らす一市民である私が「Library Book Circus」に参加した2日間について書き綴ったものである。

中田 達大 / Nakada Tatsuhiro
1990年生まれ。東北大学大学院修士課程修了。新卒入社した会社では新規法人営業や直営の小売店で売り場企画/運営を経験。21年に夫婦で東京から栃木・那須塩原へ移住。現在はインタビュアーとして独立。ライティングも行う。学生時代にはバックパッカーとして世界一周するほど旅が好き。
実は「みるる」と私の間には不思議な縁がある。2021年、妻と一緒に東京から黒磯に移住することを決めた最後の一押しは「みるる」の存在だった。
少しだけ遠回りになるが、前日譚としてそこから書き始めたい。
ワクワクさせてくれたのは図書館だった
2021年5月に私たち夫婦は黒磯に移住した。那須エリアに移り住むことは決まっていたものの、どの街に腰を落ち着けるかは最後まで迷っていた。そんな折、黒磯駅前に2階建てガラス張りの洗練された図書館があることを知った。「みるる」は2020年9月に開館したため、私が出会ったときはオープンからまだ1年経っていないようなタイミングだった。

館内に入ると「わっ」と思わず声が出た。
「みるる」の設計を手掛けた建築スタジオUAoを率いる那須塩原市出身の伊藤麻理さんは「まるで森の中のように自由に歩き回ることで、共感覚を生み出し、新しい気づきや学びにつながること」を意図してこの図書館を設計したそうだが、確かに「森」というイメージがしっくりきた。
1階は、駅の利用者が通り抜けていく役割も担っているのか、ゆったりとした通路が館の中央を貫いており、その両脇に書棚やカフェ、展示スペースが配置されている。さながら森の中の散歩道のようだ。構造的にシンプルな1階に対して、ラーニングスペースなど図書館の機能的な部分が集約されている2階は、より森の中に入っていく感覚がある。2階の天井には木のルーバーが多面的に張られており、まさに自然の中に入ったようなぬくもりを感じるし、中央の新刊コーナーから放射状に書棚が伸びているがゆえに小さな空間がいくつも生まれており、それも森が生み出す調和とカオスの空間を想起させる。例えば、窓際には一人掛けの椅子がいくつも配置されているが、奥まで入っていかないと遠目では気づかない。初めて訪れたときは、まるで木の実を隠す木陰を探す小動物のように図書館中を探検したものだ。
私が勝手に抱いていた「街の図書館」のイメージと、明らかに「みるる」は違った。

そして、ひときわ目を引いたのはブックディレクター幅允孝さんが手がけた「言葉の彫刻」だ。本から抜き出した一節が書棚の上を自由に泳いでいるといえば、最初に見たときの驚きを少しは表現できているのだろうか。その言葉に誘われて本棚に近づいてみると、テーマごとに選書された本が並べられている。
これだけ図書館の「当たり前」を軽やかに飛び越えてくる場所なので、何も不思議ではないが、様々なトークイベントやアートの展示などの新しい企画が、日々開催されているらしい。これも利用者には嬉しいだろう。
「こんな素敵な文化拠点がある街なら、楽しく暮らしていけそうだ」
「みるる」を見たときに、黒磯での生活のイメージがぱっと広がった。大げさに言えば、私たちの移住先を決めるラストワンマイルを埋めたのは「みるる」だった。

さて、時計の針を「Library Book Circus」の当日に戻す。
移住して1年の月日が流れ、私にとってもはや暮らしの一部となった「いつもの図書館」はこの2日間どんな場所に様変わりするのだろう。好奇心のチケットを握りしめて、私はサーカス小屋に向かった。
素敵な明日を願っている
前日の雨も上がり、すこんと晴れた空からは初夏の日差しが降り注いでいた。朝、マンションを出ると、いつも挨拶するおばあちゃんがいた。「今日はちょっと風が強いね」なんて立ち話。那須山から吹き下ろす風が、昨日の雨の湿気をどこかへさらっていく。Tシャツ一枚で心地よい季節が那須にも訪れたみたいで、なんだか嬉しくなった。
到着すると、青空をバックにいつもの図書館がそこにあった。いつもと違うのは、この日は「Library Book Circus」の装飾があちこちで目に入ったこと。駅の反対側に当たる西側の入り口にはイベントロゴが描かれた大きなタペストリーが掲げられ、館全体を囲うように配置されたフラッグが風でぱたぱたと揺れていた。
つばめの親子がびゅーんと空をかけ昇ってゆく。
いい1日になりそうな予感がそこにあった。

私は、この2日間を通じて「日常」は容易に「非日常」へと姿を変えることを知ることになる。いや、もしかすると「非日常」は、普段は「日常」という仮面を被っているだけで、本当は常にそこにあるのかもしれないとさえ思った。その仮面が剥がれ落ちたとき、いつもの場所は、見慣れた風景は、知ってるつもりのあの人は、ふっと違う顔を見せるのかもしれない。そういえば、染谷さんは落ち着いた口調でこう語っていた。
「物事を『どうおもしろがるか』を自分なりに見つけていくこと。それが大切だなぁと最近の僕は思っていて。例えば、西日が差してるだけでも、伸びる影を見ておもしろいと感じたり、シルエットの綺麗なポイントを見つけたり、おもしろがることができる人もいると思うんです。西日や、たった1つのなんでもない石ころでも」
物事を、どうおもしろがるか。
振り返ればこの問いが、通奏低音のように「Library Book Circus」には流れていた。その具体例の一端をお伝えするためにも、時計の針を前に進めてみよう。
午前10時。
私の「Library Book Circus」は「くるる」で開催された音楽ライブから始まった。両館同時開催のため、タイムスケジュールを見ながら、気になったイベントにそれぞれ参加するスタイルだ。
「くるる」には、駐車場を抜けて入り口に向かう途中、開かれた屋根付きの半屋外スペースがある。今日はそこがステージになっていた。歩いて会場に向かっていたのだが、100mくらい手前から地元の栃木県立大田原女子高等学校フォークソング部の学生の歌声が聴こえてきた。お客さんの手拍子の音も一緒だ。

演奏していたのは、Vaundyの『怪獣の花唄』。私が会場に到着してまず目に入ったのは青色のアコースティックギター。演奏する学生の肩にかけられたそのギターは、今日の空の色を映してピカピカ光っていた。彼女たちは少し緊張しているようだったが、まっすぐな歌声が、まるで青空に跳ね返り黒磯の街へと広がっていくようだった。「心地いいなぁ」。この感覚が「Library Book Circus」が連れてきた最初の小さな「非日常」だったかもしれない。

MC役の2人が「次はMr.Chirdrenの『HANABI』です!」と今度は5人の女子高生をステージに送り出した。演奏が始まると、後ろのスクリーンには、この日のために準備したのだろうか、歌に合わせて歌詞のフレーズが投影されるひと工夫が。
“誰も皆 悲しみを抱いている
だけど素敵な明日を願っている”
大好きな歌。これまで何百回も聴いてきたフレーズ。
でも、この先に未来しか待っていないような彼女らが歌うと、その日はなんだか違う響きを持って届いてくる。
「素敵な明日」とは何だろう。「Library Book Circus」も、誰かの願う「素敵な明日」のイメージが、今から幾重にも折り重なっていくような気がした。
そこにあるもので「おたのしみ」はつくれる
ライブを楽しんだ後に「みるる」へ戻ると(2拠点開催のため、両館を何度も歩いて行き来することになるが、ちょうどよい距離感なので苦にならない)、入り口にある駅前広場で、コーヒーを飲みながら読書をしている人を発見。よく見ると芝生には大小のラグがあちこちに敷かれ、木陰にはテーブルと椅子がいくつかセットされている。
この2日間はモリコーネとの合同企画である「ブックピクニック」が開催されていた。モリコーネとは「みるる」の1階に併設されたカフェのことだ。地元でジャージー牛の放牧酪農を営む森林ノ牧場のカフェブランドの一つで、ここが提供する搾りたてミルクを使ったソフトクリームは絶品である。「ブックピクニック」は、ドリンクに加えて、那須のお土産としても人気の「バターのいとこ」特製ドーナツと一緒に、図書館の本を広場に持ち出せるという特別企画だ。そのため今日は、図書館の外にモリコーネの特設カウンターが設置されていた。


本と言っても、その届け方がユニークだ。3冊ごとにイベントロゴをあしらった帯が巻かれ、1つのセットになっており、そこに「ちょっと暮らしを変えてみる」だったり「猫が好き。」といった言葉が書かれている。どうやら、ワンテーマごとに関連書籍3冊が選書されているようだ。つまり、本の中身を確認しないまま、テーマを頼りに直感的に選ぶ仕掛けだった。普段本を選ぶときは、無意識に自分の「癖」のようなものが反映されてくる。そのため、あえてこういった本との出会いが演出されているのは楽しい。「たまにはこういうのも、いいでしょ?」という声が聴こえてくるようだった。
私は「『知らないことだらけ』でいたい」というテーマの3冊を持って、木陰のテーブルへ移動した。

この季節の那須は、陽光と風が開放的な気分にしてくれる。近くでは小学校低学年の男の子とお母さんがラグの上でうつ伏せになって寝そべりながら絵本を楽しんでいた。話を伺うと、近所にお住まいらしく、図書館のSNSで「Library Book Circus」のことを知って遊びに来たそうだ。男の子に絵本の感想を聞いてみると「楽しかったー!」と元気な返事が。
そして、お母さんの方はこう言って笑う。
「私たちだけでなく、義理の母も『くるる』で『本の持ち寄り交換会』があることを今朝知って『それなら持っていきたい本がある!』と勢いよく出かけて行ったんです」

「本の持ち寄り交換会」とは、「くるる」の屋内広場に設置された木箱に、各々が自宅の本を持ち寄って、同じように誰かが持ってきた本と交換する企画だ。「こんなふうに読んでほしい」というコメントカードも書いて残すことができる。
会場まで行ってみるとすでに何十冊も本が置かれていた。私は谷川俊太郎さんの『二十億光年の孤独』を木箱にそっと入れた。ちょうど10年ほど前に読み、本棚に残していた一冊。若干の寂しさも感じつつ、この機会に別の人の手に渡っていくことを想像すると、別のおもしろさもあった。
こんな風に「木箱」と「遊び方」がその場にポンと置かれるだけで「おたのしみ」はつくれてしまう。芝生とコーヒーと本があるだけで嬉しくなっちゃう「ブックピクニック」も同じだ。「物事をどうおもしろがるか」という染谷さんの言葉を思い出す。ありふれて見えるものから、おもしろさが顔を出す。
本を持って出かけていったお義母さまに、新しい本との出会いがあったのなら、それはとても素敵なことだと思った。
攻めの行政と、街の活性化
「Library Book Circus」では2日間に渡ってたくさんのトークイベントが開催される。オープニングを飾るのは「みるる」の山田館長と「くるる」の石塚館長。「館長に聞いてみよう!みるるとくるる編」というテーマで初日の午前中に開催された。普段施設を利用しているだけではなかなかお会いできない両館長のお話を伺える貴重な機会だ。
トークイベントの会場は「みるる」2階のアクティブラーニングスペース。階段を登ると広々とした空間が広がっている。普段は勉強をしたり、読書をする人で賑わっているが、この日は段差を活用して30席ほどの椅子が並べられた特設ステージに変わっていた。

聞き手の染谷さんの進行でトークイベントが始まると「『みるる』と『くるる』がこの規模で合同企画を行うのは、実は今回が初めてのことです」と中央に座わる山田館長が口火を切った。
2020年9月にオープンした「みるる」と2019年7月オープンの「くるる」は、開館時期、その名称からも分かるように、ある意味で双子のような位置づけである。ただ、当時すでに猛威を振るっていた新型コロナウイルスの影響もあり、この規模での合同イベントは実現に至らなかったそうだ。そのため、「Library Book Circus」の話が初めて「みるる」に持ちかけられたとき、山田館長は真っ先に「一緒にやらないか?」と石塚館長に声をかけたという。実はお二人はもう40年来の付き合い。上司と部下として働いたことも、同じ立場で汗を流したこともあり、「くされ縁です」と笑うお二人からは、その関係性が伝わってくる。ちなみに地元も同じだそうだ。
「山田館長のその一言は、この企画が動き出すきっかけでしたね」と石塚館長が言うと、「どうなるか未知でしたが、お祭りのようなものだと思って誘っちゃいました」と山田館長が返していたのが印象的だった。

トークも終盤に差し掛かったところで、お二人から「攻めの行政」という言葉が出てきた。石塚館長が語るには、「みるる」は「人が集まる場所」から「人を集める場所」に徐々に変わりつつあるという。そして、その背景にあるものが「攻めの行政」を意識する姿勢であると。
それを聞いたときに、私の中ではハードとソフトという言葉が浮かんできた。立派なハコ(ハード)があれば最初は人が自然と集まるかもしれない。でもその場所を磨き続け、コンテンツを用意して、外に開いていくようなソフト面の弛まぬ努力が無ければ、人を集める場所にはなりえない。今回のイベントも、従来の街の図書館のイメージからすると、相当「攻めている」ように感じる。
では、なぜそこまで攻めるのか?
お二人の話からその原動力の一端が分かった気がした。それは、この街の歴史に由来する。
「この辺りは、もともと荒れた原野でした」と石塚館長。潮目を変えたのが、1886年に開業した黒磯駅。交流・直流電流の切り替え地点だったこともあり、黒磯駅には特急の列車が止まったため、その利便性から周辺に住宅が建ち始めた。それに伴いお店も増えていき、多くの人が行き交う賑わいのある場所に変わっていったそうだ。「黒磯駅のあたりにいけばどうにかなる」が人々の間の共通認識。当時学生だったお二人もよく買い物などに訪れていたそうだ。
しかし、時は流れ、駅前のお店も街を歩いている人も徐々に減っていったそうだ。その現状を「どうにかしたい」とつくられたのが「みるる」であり、「くるる」だった。
「だから『みるる』だけが盛り上がってもだめなんです。賑わいが外へ広がっていかないと街の活性化にならないんですよね」

山田館長と石塚館長をはじめ、「みるる」や「くるる」の皆さんが見据えているのは、両館に限定しない街そのものの賑わいであった。貸出冊数が増えればそれでいい、というわけではない、そのスコープの大きさこそが「攻め」の原動力なのだと思った。なんだか、両館長の人柄をぐっと近くに感じたトークイベントだった。
そういえば、山田館長から「活性化」という言葉が出たときに、聞き手の染谷さんがぽつりとつぶやいたことも印象的だった。
「活性化って『自分が主催者側になる』人が増えることと関係していると思うんです」
自分が主催者側になる。
この2日間を通じて、その言葉が頭のなかをふわふわと泳いでいた。
美しいと思う瞬間
「中田さんが美しいと思うものって何?」
これまでの人生で「面接」と言われる類のものをいくつも受けてきたが、そのなかで最も鮮明に覚えているのは、転職活動のとき、ある面接担当に問われたこの場面だ。意表を突かれた私の口から「誰かが真剣になっている瞬間」という言葉が出てきた。私の回答はさておき、それからこの問いは大切なものになった。なぜなら、その人がどんな眼差しをこの世界に向けているのか、その一端に少しだけ触れられる気がするからだ。
カラぺハリエのイベントに足を運んだとき、気づけばこの問いを投げかけていた。
カラぺハリエとは、カラぺ(カラーペーパー)とハリエ(貼り絵)を使って「みんなちがうからおもしろい」を体現する活動である。まさにその名前を冠するNPO法人「みんなちがうからおもしろい」が行っている。

12時から代表の今井絵理さんのトークイベントが「くるる」の屋外広場ステージで行われた。会場の隣には地元の無農薬野菜が並べられ、地域の方が買い物で行き交う。そのごちゃ混ぜ感が、またいい。

カラぺハリエは、2016年に活動開始。その1つのプロジェクトとして、絵本をつくるワークショップを各地で開催しているそうだ。あらかじめ絵本の物語部分が用意されていて、そこから連想される絵を各々がカラぺとハリエを使って自由に表現し、最終的に一冊の絵本をつくり上げていくワークショップだ。なかには、3ヶ月かけてつくることもあるという。出来上がった絵本を大切な人に贈る方も多いそうだ。
大人は特にそうだが、カラぺハリエのワークショップでは、普段使っている思考モードの脳から、より感覚モードに自然とスイッチが切り替わる。それにより深層心理も含めてその人の本質的な部分が1冊の絵本に現れてくるという。
「そうやって絵本をつくった時間は『今年の思い出BEST3』に入るくらい印象深いものになるかもしれないですよね」と今井さんは言う。
ちなみに「Library Book Circus」初日限定で開催されたワークショップは、この日のための特別バージョン。「みるる」と「くるる」という名前のキャラクターを主人公にしたオリジナル絵本をカラぺハリエの皆さんがつくってきてくれていた。その絵本を見て感じたままに「みるみるめがね」と「くるくるステッキ」を一緒につくろうというワークショップだ。

会場に入ると、男の子がお母さんと一緒に「みるみるめがね」をつくっていた。それを横目に今井さんと、同じくカラぺハリエの柏倉さんにお話を伺った。今回の経緯としては、栃木県下野市で開催された第1回「Library Book Circus」に参加したご縁だそうだ(「Library Book Circus」は今回が2度目の開催)。
「カラぺにはこれはダメというのがない」
「一瞬一瞬、同じものは2つとしてない」
というお二人の言葉には明るさの中に強さが宿る。

ふと、大切なあの問いを投げかけてみたい気持ちが湧いた。
「ワークショップをしていて美しいと思う瞬間ってどんなときですか?」
気づけば、質問していた。
「急に聞いても戸惑わせてしまうよなぁ」と一瞬後悔したが、柏倉さんは「そうだなぁ」と言いながら、隣にあったパネルをおもむろに指さした。それは、誰かの手と、その人が握る筆の先に、綺麗な水彩の赤、青、黄色が塗られている写真だった。
「これ描いているの、100歳のおばあちゃんなんです」
「……え!100歳!」
「そう。ワークショップには子どもも大人も本当にいろんな方が参加されるんですね。このおばあちゃんに『自由に色を選んでください』とお伝えしたときに、この明るい色をすっと選んだんです。この方がこういう色を選ぶんだとはっとするとき、美しいといつも思います」
今井さんにも聞いてみると「大人のなかには感情があまり表に出ない方もいます。そういう人が自分で色を選んでいくうちにだんだんと深いところに入っていき、ふと涙を流されることがあって。そのとき美しさを感じますね」という答えが返ってきた。
そしてこう言った。
「カラぺの前では言葉は必要ないんですよね」
紙と絵の具。手に入れようと思えば、すぐに手に入るもの。だけど、ずいぶん遠ざかっていたような気もした。身近にあるものから、美しさは立ち現れてくる。そんなことを私に教えてくれたカラぺハリエの愉快な皆さんだった。

走りながら、おもしろがる人
昼食を挟んで再び「みるる」のトークイベント会場へ向かう。その途中で、1階カウンター横の壁面いっぱいを使って「この街、この一冊」と題した選書企画が展開されているのが目に入った。

「この街、この一冊」は、那須塩原で活躍する28名の方にお気に入りの本を1冊セレクトしてもらい、コメント付きで紹介する企画だった。「みるる」の業務責任者であり、今回の「Library Book Circus」の運営にも深く関わる物井友和さんは、「図書館がただ本を置いてそのまま待っているだけでは、おもしろくないですから」と優しく静かな口調で話す。
物井さんは「この街、この一冊」の実現にも尽力したそうだ。
「那須塩原市長をはじめ、JRの方や、JAXAの方、国連の方、ボランティアの方などに選書していただきました。企画におけるやりとりを通じて、多種多様な業界の方々と繋がりを持てることも図書館の仕事の醍醐味だと思います。積極的に図書館の外へ出ていく気持ちで、いろいろな人と関係性を結んでいく姿勢を大事にしたいですね」
物井さんのように現場で走りながら何事も「おもしろがる人」。そういう人がきっとたくさんいるから、今日という日が実現しているのだ。
図書館と牧場のふしぎな関係
会場からは那須山が遠くに見え、昼間の陽光がピカピカのフローリングに当たってキラキラしている。この空間の光、温度、湿度。すべてが心地よく、窓が開け放たれた部屋の陽だまりにいるようだ。
13時になると、トークイベント「図書館について語るときに我々の語ること」が始まった。同イベントは、これからの図書館を考えるためのトークシリーズというコンセプトで、株式会社図書館総合研究所と株式会社ひらくが各地で様々なゲストを招いて開催している。この日は「Library Book Circus」のための番外編。モリコーネをはじめ、地域で様々なブランドを展開する森林ノ牧場の代表取締役・山川将弘さんがゲストとして迎えられた。聞き手は染谷さんと図書館総合研究所の廣木響平さんが務めた。

森林ノ牧場は前述の通り、那須町の森の中でジャージー牛を放牧している。牧場内は一般の方も散策ができ、敷地にはカフェを併設しているため、搾りたてのミルクなども楽しめる。日本の国土の大半を占める森林。その多くはまだまだ活用しきれていない。「人の手が入らなくなった森林を放牧地にすることで、牛たちは人間が食べられない草を食べて、ミルクに変えてくれるんです」と山川さんは力強く語る。山川さんは地域で仕事を生み出していくことで『「田舎で暮らす」をつくる』を目指しており、最近は栃木県益子町に新たに第2牧場をつくったばかりだ。
モリコーネをつくった背景にも『「田舎で暮らす」をつくる』という想いはあったことだろう。ただ、牧場が図書館にカフェをつくるという話はあまり聞いたことがない。どういった経緯があったのだろう?山川さんは当時のことを思い出しながら「ここに図書館ができると聞いた瞬間になんかワクワクしちゃって」と少年のように笑った。もともと本が好きだったが、それと同じくらい人が本を読んでいるシーンそのものが好きだったという。
「そのシーンに牧場のソフトクリームがあったら、牛たちも幸せなんじゃないかなって」

そんなある種の直感をきっかけにして、モリコーネは生まれていったことを知る。ちなみにモリコーネというブランド名は、映画『ニュー・シネマ・パラダイス』の音楽を手がけた作曲家エンニオ・モリコーネに由来する。「あの映画における音楽の立ち位置のように、図書館のシーンをつくるカフェにしたいという願いを込めた」と山川さん。ある日の深夜2時にビビッと来て「これだ!」と思いついたそうだ。

さらに話を聞いていくと、山川さんはワクワクすることを原動力にしていることが分かってきた。「もともと旅が好きだったこともあり、一時はネパールに移住するか、牧場をつくるかの2択で迷いました」と話したときは、一瞬はてなが浮かんだものの、「ワクワクすること」として2つは同じテーブルに乗っていたのだと考えると納得した。
イベントの終盤で染谷さんが「図書館について語るときに、図書館のことを直接聞いてはいけないと考えている」という禅問答のようなことを言った。そして、自分の業界の「これから」を考えるヒントを別の業界から探すのも大切だと続けた。今回のトークイベントでは酪農業界で起きていることを中心に話を聞いていたが、その理由を知って「なるほど」と得心した。ヒントは、街のなかで一見別の仕事をしている人のなかにも眠っているのだ。山川さんの語る言葉に、目指す世界に、みんなと一緒にワクワクさせられながら、そんなことを思った。

図書館への入り口は本だけではない
「Library Book Circus」という器の大きさを象徴していたのが、初日の午後に1階のみるるホールで開催された「ボードゲーム体験会」だったかもしれない。ボードゲーム専門家のオーレさんを招き、テーブルを囲んでみんなでボードゲームを一緒に楽しもうという企画だ。参加は無料、飛び込み参加も歓迎である。ボードゲームが好きな私は、本日最後のイベントに持って来いだと思いながら、駆け足で会場に向かった。
そこでは『カタン』や『枯山水』といった、一般的には珍しいボードゲームがいくつか用意されており、子どもたちや20代くらいの若い人たちがすでにゲームに興じていた。

私は『枯山水』のテーブルに案内された。オーレさん、同じテーブルに座った男性、そして最後に来た女性と私の4人でゲーム開始だ。お二人は「この体験会があると知って、今日は図書館に来たんです」と楽しみな気持ちを隠さずに話していた。「Library Book Circus」が受けとめるものの間口の広さが、確かに図書館に人を集めているようだった。
そういえば、染谷さんがこんなことを話していた。
「本って、読み慣れている人は手に取ってくれたりするけど、そうでない人に『本を読んでください』と直接提案しても届けるのはなかなか難しいと最近感じていて。本のおもしろさを伝えていくのはもちろん大事ですが、その手前にあるものをこちらがもっと用意することが大切だと思っています」
「Library Book Circus」と銘打ったイベントに「ボードゲーム体験会」があるのも、その好例だろう。
「本の手前にある『好奇心の種の見つけ方』みたいなものを図書館でどうつくっていけるかを考えています。なので『Library Book Circus』では本に限らず、みんながすっと入っていける、楽しさを共有しやすいものも企画しました。入り口は違っても、その先に本と繋がっていけばいいなと」と染谷さんは丁寧に言葉にしていく。

さて、『枯山水』に話を戻すと、最初にルールを聞いたときは複雑に感じたものの、実際に手を動かしながら遊び始めると、みんな自然とこのゲームの楽しみ方を理解していったようだった。残念ながら負けてしまったが、初対面の大人同士が1時間ほど夢中になって遊べたことが、それだけで素晴らしい。こうやって打ち解けられるのもボードゲームの持つ魔法なのだろう。
一緒に参加していた方々とも「またやりましょう」という話に。女性は「ボードゲームが好きだから一緒にできる人を探していた。『くるる』でも企画したい!」と言い、私たちは「ぜひ企画してください!」と盛り上がった。
後ほど、ボードゲーム体験会の運営を担当していた「みるる」の井上さんにお話を伺うと「最初は運営に徹する予定でしたが、つい私たちも一緒にゲームを楽しんでしまいした」と笑っていた。そういう自由な雰囲気が確かに会場にあった。みんなが、自分事としてあの風景のなかにいた。午前中のイベントで染谷さんが言った「主催者になれる人が増えていくこと」という言葉をふっと思い出した。



先に私は、この2日間を通じて「日常」は容易に「非日常」へと姿を変えることを知ったと書いた。「非日常」は「日常」という仮面を被っているが、本当は常にそこにあるのかもしれないとも。
おもしろがるとは、見慣れた風景のなかから「ねえ、ここにもあったよ」と「非日常」を見つけることなのかもしれない。私たちの暮らしのワンシーン。そのなかではサーカスの曲芸師たちがそこかしこで踊っている。1日目を終えた西日に照らされた帰り道、そんなことを思った。
仮面がぽろっとはがれ、いつもの場所が、いつもの人が、ちょっと違って見える瞬間。
この日、それは確かに何度もあったのだ。
(1日目おわり)
