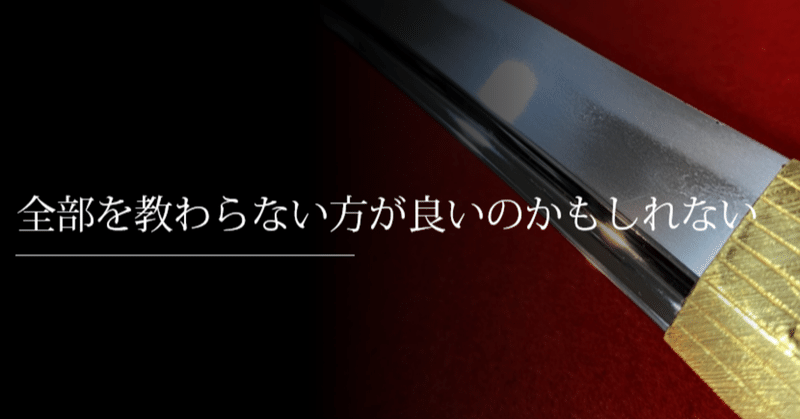
全部を教わらない方が良いのかもしれない
刀屋さんで刀を見せて頂く時。
例えば茎を隠した長光を見せて頂いたとして、誰に見える?みたいな遊びをしながら色々教えてくれるわけですが、「乱れ映りがあるから備前だよ」とか「帽子が三作帽子になってるから長光だよ」というようなアドバイスはされた事が無い気がします。
しかし暫く見せて頂いた後に無言で次の刀、例えば景光や兼光など同派のものを時代をずらして見せて頂ける。
時には「匂口を見てみて」ぐらいのアドバイスを頂ける事はありますが基本は黙々と見ている時間が長い。
刀について何も分からない時は、その刀の見所をピンポイントで教えてほしいなと思った時期もあるのですが、今思えば見所を教えないのは何か意図があったからでは、と最近は感じます。実際は分かりませんが。
というのも考えてみれば、もし「この刀の見所はここだよ」という風に教えられたとすれば、恐らく教わった瞬間からその部分にしか目が行かなくなるのではないか。
それでは刀剣本によく書いてあるような典型作の照らし合わせ作業をするだけになってしまい、刀そのものを純粋な目で見ることが出来なくなってしまうのではないか。
というよりも、そもそもその刀の見所は誰が決めるのか。
本来見所は見る人によって変わるのではないか?
見所を教えられたとしてその人の見方を押し付ける事に繋がるのではないか?
自分自身で見所を見つけられた方が長い目でみて良いのではないか?
などと次々と疑問が生まれます。
先の「匂口を見てみて」という言葉の意図を改めて考えてみると、誰の作かが大事なのではなく、名刀とされている刀の匂口はどういうものなのか?をしっかり見て覚えておきなさいよ、という事なのではないか、そう最近は感じます。
事実刀を渡されて10分くらい無言で見続けていると、姿から始まり、はばき元から切っ先の刃文や地鉄、棟まで隅々に目を向けるような気がします。
その中でこの刀はここが素敵だなとか、ここがあの刀工の作になんとなく似てるなとか自分なりの解釈が作られていく。
長光であれば三作帽子だから、という感じではなく、姿や刃文、匂口、地鉄、映り、地景などのトータルの雰囲気がなんとなく今まで見てきた長光に似てる気がするから長光では、という感じ。
勿論間違ってることも多いのですがそれはそれで気にしない。
間違えた時も「ここが掟と違う」とかそういう説明はされません。
(そもそも掟というワードを使われた記憶が無い)
ただ「〇〇の作だよ」と教えてくれてまたじっーと見るの繰り返し。
何度もじっくり見るのでその刀工についての情報がアップデートされていく。刀工によっては直刃や丁子刃などと異なる刃文を焼いている場合もあるが、それも作風としてアップデートしていく。
それを繰り返していると自分の中の長光像が作られていく。
なので最近は逆に見所を教えてくれなくて良かったなと感じます。
その分、その刀を自分自身の視点でじっくり見れている気がします。
ただこの方法の唯一の注意点とすれば、見る刀がちゃんとしたもので無ければならない、という事でしょうか。
なのでしっかりしたお店やコレクターの方に見せて頂かないと軸がぶれてしまうはず。
今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
