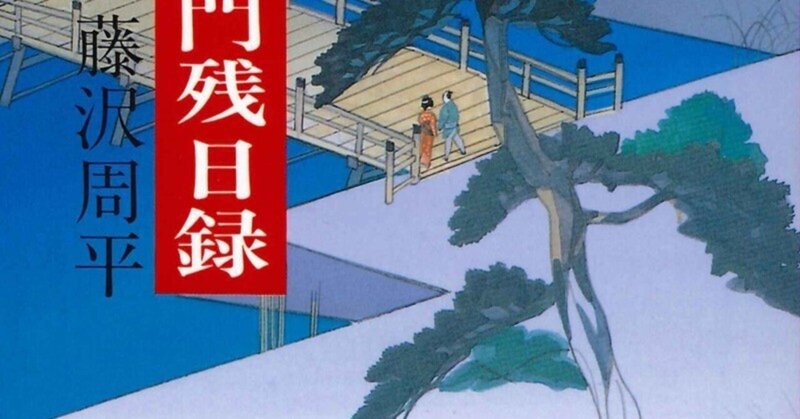
お正月のテレビ番組と、「三屋清左衛門残日録」、そして「シニア人材の活用」について
年末年始のテレビ番組はあまり面白くない。
紅白も数年前から見ていない。これだけ音楽ジャンルが多様化した時代に、1つの歌番組であらゆる世代に対応するというスタイル自体がもはや「無理ゲー」だと思う。テレビ東京の裏番組「年忘れにっぽんの歌」が健闘しているらしいが、これは現在の紅白のありように対するアンチテーゼなのかもしれない。もっとも、僕はどちらも見ていないが。
そんな中、チャンネルを回していて、「三屋清左衛門残日録」という時代劇ドラマが目にとまり、そのまま終わりまで見続けてしまった。藤沢周平の小説を数年前にテレビドラマ化したものである。主演は北大路欣也である。結局、大晦日から正月3ヶ日にかけて、「三屋清左衛門残日録」「同 完結編」「同 三十年ぶりの再会」「同 陽のあたる道」と4作品を続けて見た。
藤沢周平の原作小説は、ずっと以前に読んだことがある。原作は短編の連作集であるが、ドラマの方は短編の幾つかの中身をうまく組み合わせて再構成してある。ただし、一部オリジナルのエピソードも入っていたようである。
三屋清左衛門なる人物は、藩主の用人にまで昇りつめて、先頃、先代藩主の死去に伴い、家督を息子に譲って、隠居生活に入ったばかりである。年齢は52歳とある。当時の平均寿命を考えれば、現代人の感覚では70代前半くらいに相当するのではなかろうか。
用人というのは、秘書官みたいな職務である。藩主の側近くに仕えて、公私にわたって補佐する職務であるから、藩主からよほどに信頼され、かつ実務能力が優れていないと務まらない。用人になる前は、江戸藩邸の留守居役、つまり藩の外交官のような仕事に就いていたとある。三屋という人物は、門閥でもない平藩士としては、まずはこれ以上ないくらいの順調なキャリアを歩んだ人物ということであろう。
三屋は早くに父親を亡くし、若くして家督を継がざるを得ず、学業も剣術修行も中途半端なままで終えたことをずっと悔いていた。隠居生活を始めて間もなく、30年ぶりに若者に交じって道場や漢学塾に通い始めたのはそのせいである。他には趣味である釣りの楽しみに目覚めたり、「涌井」という馴染みの飲食店を見つけたりと、毎日、それなりに楽しい隠居生活を過ごしていたのだが、周囲が彼を放っておかず、いろいろな難題が持ち込まれるようになり、やがては藩内の政争にも巻き込まれて行くといった話である。
前に紹介した映画「マイインターン」の主人公のベンと少し似ているかもしれない。ベンはまったく畑違いの業界に飛び込んで、ゼロから自力で自分の居場所を見つけたのに対して、三屋の方は隠居したとはいえ、自分のキャリアパスや力量をよく知る人たちが周囲に大勢いる環境に置かれていること、つまりアウェイではなくて最初からホームゲームである点において、ベンよりは三屋の方が相当に有利であるといえる。もちろん、三屋は再就職志願者ではなくて、自らの意志で隠居生活を選択したわけだから、ベンと比較するのはそもそも適切ではないかもしれない。
「シニア人材の活用について」という記事に書いたとおり、定年退職を迎えて、第一線を退いたとしても、人間は社会に参画することで誰かの役に立ちたいと考えるものである。趣味を楽しむのも悪くはないが、それだけでは生きている手応えのようなものを得るのは難しい。
したがって、三屋清左衛門も隠居生活に入って最初のうちであれば、若い頃を思い出しつつ剣術修行や学問に励んだり、釣りに出かけたりして日々を過ごしていても、相応に充実感があったのかもしれないが、そのうち飽きてしまったであろう。たとえ隠居であっても、藩内であれこれと人の役に立っているという手応えが、彼の隠遁生活に張り合いや充実感を与えることとなったのは間違いない。
マズローの「欲求5段階説」にあるように、「生理的欲求」「安全欲求」だけではなく、「社会的欲求」(社会から受け容れられたい)、「承認欲求」(他者から認められたい)、「自己実現欲求」(「あるべき自分」になりたい)といった思いは、たとえ幾つになろうと消えるものではないからである。
そういう意味では、前に紹介した「マイインターン」「トップガン マーヴェリック」、そして「三屋清左衛門残日録」は、シニア人材の活用を考える上で必見の作品ではないかと思った次第である。
社会としてシニア人材をどう扱うかについて考える教材にもなるだろうし、高齢者自身も自分の余生を生きる上で、是非とも、これらの作品に触れてみることをおススメしたい。年金を貰って、カルチャーセンターに通ったり、OB会に顔を出したり、たまのゴルフに興じたりしていても、それで本当に充足感が得られるかという話である。
余談であるが、こちらも年始にテレビでやっていたドラマの話になるが、「剣客商売 剣の誓約」というのを見た。どうも、時代劇の話ばかりで恐縮である。
ストーリーの詳細は省くが、池波正太郎の「剣客商売」シリーズの主人公である秋山小兵衛は、かつては四谷で道場を構えていたこともある無外流の剣術の達人で、現在は孫くらいに年齢差のあるヨメと鐘ヶ淵(現在の墨田区)でお気楽な隠居生活を送っている。シリーズ自体は小兵衛が59歳から75歳くらいまでの話が描かれている。
若い頃は、あまりピンと来なかったのだが、自分がある程度の年齢になると、秋山小兵衛の生き方というのは、ある種の憧れの対象であるとともに、高齢者の余生の過ごし方として1つの理想的なロールモデルではないかとさえ考えるようになってきた。
誰に対しても媚びることも、おもねることもなく、かと言って偏屈なわけでもなく、洒脱で世事にも長けており、何事に対しても好奇心旺盛、身分の上下に関係なく人との交わりにも如才ない。カネ払いもケチ臭くなくて、美味いものには目がない。若い女房を貰うくらいだから女嫌いでもない。
で、ぶらぶらと日々を無為に過ごしているわけではなくて、周囲から相談を持ちかけられたり、あるいは自分から首を突っ込んだりしつつ、問題を解決したり、悪人を懲らしめたりと、結構、世のため人のために働いているし、周囲から頼りにもされているのだ。
僕も、こういう年の取り方をしたいものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
