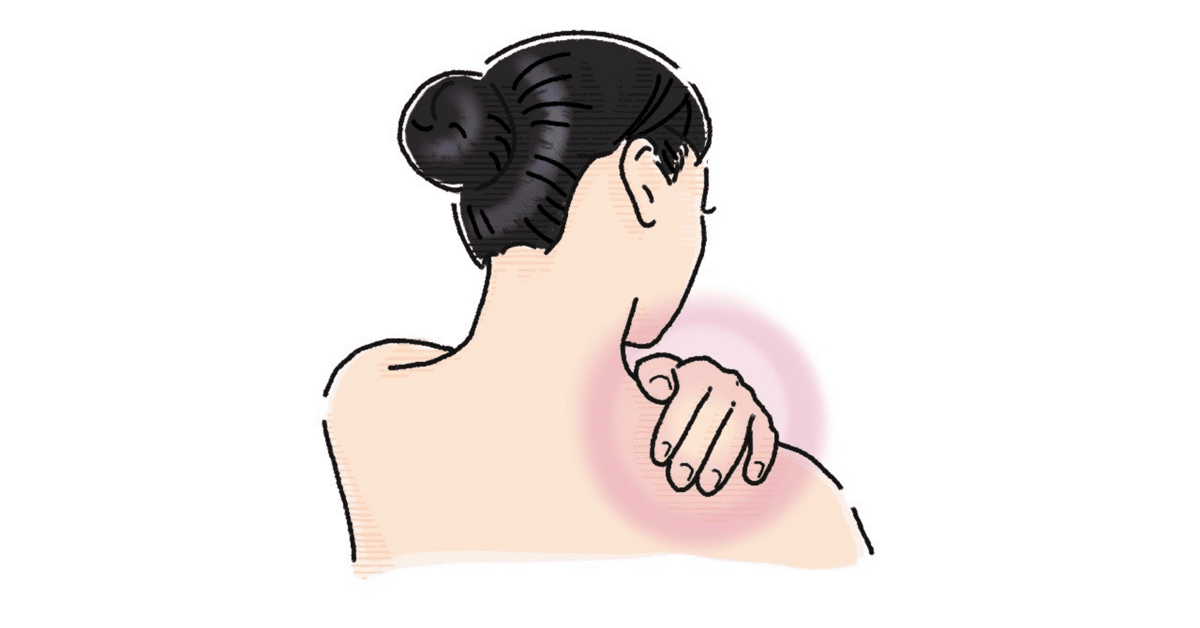
東洋医学・代替医療・民間療法
自分は根っからの文系人間だが、母は理系だし、父親にいたっては数学者である。
父親が教え子に手を出して孕ませ(今だったら大問題だろう)、堕して学業を続けるという話も出たらしいが、まあ中退して籍を入れるということで穏便に済んだらしい。そんなわけで、自分は娑婆苦の充ち満ちた世界へと生まれた。それにしても、こんな話、よく子どもに聞かせられるな、と呆れたものだ。未来の可能性は無限だなんて陳腐なことを言うつもりはないが、妊娠のせいで学問による自己実現をフイにしてはいけない、学業は終えるべきだったのではないか。
それはともかく、自分の場合、思春期にありがちな父への反発が文系を選択させた部分もあると思うけれど、何よりも算数が苦手な子どもだった。そして、映画を観たり小説を読んだりするのが三度の飯より……いや、それほどではないにせよ、好きだった。食べることはいつだって大好き。
それが歳を重ねると、どういうわけか(あまりにもモノを知らないからであろう)通俗科学本を読むようになる。言うても、講談社ブルーバックス、早川文庫の〈数理を愉しむシリーズ〉、新潮文庫のScience&History Collectionなどである。その中でも、まあ数式の(少)ない初級者向けのものばかり選んでいる。
鍼灸院で施術中に思い出したのが、サイモン・シンの『代替医療解剖』である。
この本の中で、鍼はホメオパシーやカイロプラクティックなどと並んで、プラセボ効果以上の効果なしとされている。つまり、治療効果に科学的なエビデンスがない。どういうことかというと、詳細は本書に譲るとして、本当の鍼治療と偽の鍼治療を被験者に施し、その結果を比較してみたところ、ともに治療効果があったが、そこにとくに差は見られなかったというのである。
自分は翻訳書を全て読んでいるほどサイモン・シンのファンであるけれど、この実験結果(そして、方法)には懐疑的である(別にシンが構想した実験ではない)。人に感化されやすいくせに、疑い深いところがあるのである。
しかし一方で、マーティン・ガードナー(数学者)、カール・セーガン(天文学者)、スティーブン・J・グールド(古生物学者)、リチャード・ドーキンス(動物行動学者)などの通俗科学本に影響されてきた自分にとって、実験で否定された医療効果が、体験的には確実にあるというのは一種のジレンマなのである。
本当に鍼は効くのだろうか? 十数年前に肩凝りが霧散したのは、単なるプラセボ効果だったのだろうか、それとも放っておいても自然と治癒したのだろうか。
*
さて、モーレツな頭痛・肩凝り・睡眠不足に悩まされて鍼灸院に駆け込んで、早速鍼の治療を受けた時のことである。
担当の先生(女性)は田中さんと言って、ベテランらしい。マスクにのため目しか見えないから年齢不詳だが、若くないことはたしかだ。こちらの首、肩、背、腰と順番に触れていって、まるで鉄板でも入っているみたいに全身がガチガチに凝り固まっていると言う。
先ずは首だ。プスと鍼が皮膚に刺さり、トントンと指で叩かれて、だんだん入ってくる。不思議と痛くない、チクリともしない。一本目、二本目、三本目……次から次へと打たれてゆく。首と肩の周辺が剣山のようになっているのではないか。
「ここ、響きますか?」と先生が訊いてくる。
「は?」
響くという表現がその時はよくわからなかった。思えば当初、先生はネコを被っていた、本性を現していなかったのである。
一通り施術が終わると、ハーブティーをいただく。頭がぼーっとしているけれど、とりあえず、肩はまわるし首もひねることができる、ほっとした。夜勤まで一眠りできそうだ。もう、プラセボだろうが気のせいだろうが、何でもいい、ありがとう。
「まだまだです、まだまだですから」と田中先生は鼻息荒い。小柄なおばさんが鍼の後、でかいおっさんの凝りに凝った首・肩・背中・腰を揉みほぐしていったのだから、当然と言えば当然だ。「とりあえず、動けるようにしたので、本格的な治療は来週からです」
「え?」
一回こっきりじゃないの?
こうして、週に一度、定期的に鍼灸院へ通うことになったのである。
『ココロとカラダと』第四回
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
