
陶淵明「桃花源記」~「洞天」の別世界、「小国寡民」の理想郷

ユートピアと桃源郷
理想郷を語る時、わたしたちは、しばしば「ユートピア」や「桃源郷」という言葉を使います。
「ユートピア」は、ギリシャ語で「どこにもない場所」という意味で、
16世紀イギリスのトマス・モアの著書に由来します。
一方、「桃源郷」は、中国・東晋の詩人陶淵明の文章「桃花源記」に登場する架空の土地の呼び名です。
漁夫がふと迷い込んだ別世界、俗塵から隔絶された桃源郷は、東洋の理想郷の代名詞です。
「桃花源記」は、漢文教材に採られることも多く、我々日本人にも馴染み深いものです。通常は、田園詩人・隠逸詩人と呼ばれる陶淵明の思想を反映した文学作品として読まれています。
基本的にはそれでよいのですが、ただそうした扱い方だけでは、桃源郷の世界の全体像は見えてきません。
「桃花源記」は、古代中国の民間信仰に基づいて書かれたもので、その背景に、宗教的、思想的、歴史的な要素が絡み合いながら存在していて、たいへん奥行きの深い作品なのです。

陶淵明の「桃花源記」
まず、「桃花源記」のあらすじをご紹介しましょう。
記事の末尾に「桃花源記」全文(原文、書き下し文、現代日本語訳)を載せてありますので、ご参照ください。
晋の太元年間、武陵の漁師が川で漁をしていて道に迷ってしまった。ふと桃の林に出逢った。桃の花があたり一面に乱れ舞う光景を不思議に思い、更に川を上って行った。すると桃の林は水源の所で尽き、そこに山があった。山には小さな洞窟があり、中から光が射している。漁師はそこで舟を乗り捨て、洞窟に入っていった。
初めのうちはとても狭く、しばらく進むと、急にパッと目の前が開けた。そこには広々とした美しい田園風景があった。人々は野良仕事に汗を流している。男も女も俗世間の人と同じ服装をしている。老人も子供も皆のんびりと楽しそうだ。
ある村人が漁師を家に招いてもてなした。このことを聞いた村の人々が集まってきた。村人の話によると、彼らの祖先が秦の始皇帝の時代の戦乱を避けてこの土地にやって来て、それ以来一歩もここを出たことがないとのこと。彼らは、漢という時代があったことを知らず、魏晋のことなどもちろん知らない。漁師が俗世間のことをいろいろ語って聞かせると、皆深いため息をついた。他の村人たちも漁師を自分の家に招き、酒や食事でもてなした。
こうして漁師は数日間滞在して、いとまごいを告げた。桃源郷の人たちは、漁師に向かって、「どうか俗世間の人に我々のことを話さないでください」と言った。
やがて漁師はそこを出て、自分の乗ってきた舟を見つけ、道に目印を付けながら帰った。町に戻った漁師は、郡の長官の所へ行き、かくかくしかじかのことがあったと話してしまった。長官は人を派遣して漁師の目印を頼りに捜させたが、ついに見つけることはできなかった。その後、その地を訪れた者はなかった。

この文章の後に、32句に及ぶ長編の五言詩が続いていて、『陶淵明集』の巻六に、「桃花源記並びに詩」というタイトルで収められています。

「桃花源記」と民間伝承
さて、この「桃花源記」ですが、実は、これを陶淵明の作品と呼ぶことには少々問題があります。
と言うのは、陶淵明の時代、「仙界遊行譚」、すなわち仙境に人が迷い込む話が、数多く民間に伝承されていて、桃源郷の話は、そうした民間伝承の中の一つであったのです。
『捜神後記』という当時の民間説話を集めた書物がありますが、この中に「桃花源記」とほとんど同じ話が収められています。
『捜神後記』は、全部で100話余りの短い話を載せていますが、桃源郷の話は、その第5話として収録されています。
そして、その前後の数篇(第2話から第7話まで)は、いずれも、洞窟にまつわる話が並んでいて、しかも、これらの話には「桃花源記」とよく似たモチーフが多く使われています。
羊を追って山の洞窟に入ると、急にパッと開けて、中は広々として草木が香しかった。
山に洞窟があって、やっと一人が入れるほどの狭さだったが、進んでいくと目の前が開けて、肥沃な田畑が広がっていた。
笠で身を守りながら洞窟に入ると、やっと人が通れるほどで、数十歩進むと明るく開けて、俗世とは異なる世界があった。
などというように、「桃花源記」と似たような話になっています。
また、『捜神後記』以外にも、六朝時代の書物の中には、「桃花源記」と似たプロットを持つ話がたくさんあります。
例えば、『異苑』という書物に見える話は、こうです。
蛮人が鹿を追って洞窟に入ると、その中に梯子があり、上っていくと豁然と開朗し、木々の生い茂る広い土地に出た。帰り道の木々に目印を付けておいたが、再び訪れることはできなかった。
という話で、「桃花源記」との類似は一目瞭然です。
また、『述異記』には、次のような話があります。
武陵源は、山に桃と李ばかりで、桃李源とも呼ばれる。水源に石の洞窟があり、秦末の戦乱の際に、人々がここに難を避けた。桃李の実を食べれば仙人になれる。
という話で、武陵、桃、洞窟、秦末の戦乱など「桃花源記」に出てくるものと同じ言葉が並んでいます。
こうしたことから、洞窟に迷い込んで異世界に出る、という説話が、当時すでにさまざまなバージョンで広く語り伝えられていたことがわかります。
「桃花源記」は、これらの民間伝承を素材にして、陶淵明が手を加えて再構成したものにほかならないのです。
つまり、「桃花源記」は、陶淵明個人の着想による創作ではなく、民間伝承を借りて作った文章であって、それに詩を組み合わせて、一つの文学作品に練り上げたものなのです。
ですから、「桃花源記」は、理想郷の話である以前に、まず洞窟の話であるという捉え方をしなければなりません。
穴とトンネル
そもそも山は、俗世間の人間には非日常の場であって、古代人にとっては、畏怖の対象であると同時に、神秘的な領域でもありました。
山中の洞窟は、山の持つ暗さ、静けさが増幅され凝集された空間として、よりいっそう神秘的な場所です。それゆえ、洞窟には、古来さまざまな民間信仰が付いて回っています。
とりわけ、その形状が「穴」であり、また多くの場合「トンネル」であることから、洞窟は別世界への入り口として設定されることが多いのです。
これは洋の東西を問わず、世界中の文化圏に例を見ることができます。
インドの説話では、蓮の茎が現世と地獄を繋ぐパイプとなっていますが、蓮の茎は中が空洞でトンネルの形をしています。
19世紀イギリスのルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』では、少女アリスは兎の穴に飛び込み、暗いトンネルを落下して不思議の国に出ます。

もっと身近な例を挙げれば、宮崎駿監督のアニメ『千と千尋の神隠し』では、一家が引っ越しの途中でふと見つけた古いトンネルに入っていき、そこで、神々の棲む不思議な異次元空間に迷い込みます。

また、『となりのトトロ』もそうです。女の子は「ひみつのトンネル」を通って、森の中の別世界を体験します。

さらには、ヤマザキマリの漫画『テルマエ・ロマエ』でも、古代ローマの浴場設計士が、公衆浴場の奇妙な排水口に吸い込まれて、現代日本にタイムスリップします。
もう一つ加えれば、川端康成の小説『雪国』も、ある意味でそうではないかと思います。
冒頭に、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」とありますが、主人公の島村にとって、雪国の温泉地は、芸者駒子との美しい情緒の世界、非日常の世界です。
東京から越後湯沢に行く列車は、トンネルを通るわけですが、そのような地理的な必然性だけではない響きをこの言葉は持っているように思います。
中国古典小説の別世界
中国も例外ではなく、洞窟を通って別世界に出るというプロットは、六朝時代の小説によく見られます。
唐代以降の怪異小説においても、さまざまなバリエーションがあります。
例えば、唐の『博異志』という書物に収められた話は、こうです。
ある男が井戸を掘っていたところ、急にストンと落ち込み、地面に足が着いた。すると、そこは地下の仙境の山頂だった。
という話ですが、井戸というのは、いわばタテのトンネルです。
また、「黄粱一炊の夢」の語源となった唐代小説「枕中記」も同様です。
あらすじは、以下の通りです。
邯鄲の宿屋で書生が不遇を嘆いていた。道士から青磁の枕を借りてうたた寝をするうちに、夢の中で波瀾万丈の半生を送った。
宰相となり将軍となり、功成り名を遂げて富み栄え、欲望をすべてかなえて死んだところで、ハッと目が覚めた。それは宿屋の主人が蒸していた黄粱がまだ煮えぬ間の一瞬の夢だった。

これは夢幻の世界を描いた物語ですが、実は、ここでも穴を通って別世界へ迷い込むというモチーフが使われています。
書生は、道士から青磁の枕を借りてうたた寝をしますが、磁器の枕は、中が空洞になっていて、両端に穴が開いています。夢幻の世界への入り口は、やはり一種の穴であったのです。
桃源郷はどこにある?
さて、「桃花源記」に話を戻しましょう。
桃源郷は、いったいどこにあるのでしょうか。
漁夫が洞窟に入る場面は、次のように書かれています。
山に小口有り、髣髴(ほうふつ)として光有るが若(ごと)し。便(すなわ)ち船を捨て口より入る。
初めは極めて狹く、纔(わず)かに人を通ず。復(ま)た行くこと数十歩、豁然(かつぜん)として開朗(かいろう)なり。
「山に洞窟があり、中から光が射していた。洞窟に入ると、はじめは狭かったが、しばらく進むと、急にカラリと目の前が開けた」とあります。
この記述を素直に読めば、トンネル状の山の洞窟を抜け出た場所に桃源郷があるように読めるでしょう。
ところが、実は、そうではありません。
山の空洞の「中」に別世界が存在しているのです。つまり、桃源郷は山の向こう側ではなく、山の内部に存在するのです。こうした世界を「洞天」といいます。
山の洞窟の中に、もう一つの世界、一つの完結した小宇宙が開けている、という発想です。
そこには、太陽があり、月があり、平野が広がり、山々が連なり、風も吹けば、雪も降ります。
「髣髴として光有るが若し」とありますが、洞窟の中からぼんやりと漏れ出た光は、山の向こう側から射し込んできたものではなく、洞天の太陽の光だったのです。
洞窟に関する信仰が、こうした洞天の構想へと展開したのは、東晋の頃、つまり陶淵明の生きた時代でした。
「桃花源記」の骨組みを作っているものは、この洞天という発想にほかならないのです。
洞天の宇宙
洞天という発想の裏には、中国人独特の宇宙観があります。
古代中国人は、宇宙というものを無限に広がる時空であると同時に、この世の至る所に遍在する別世界、大きくなったり小さくなったりする伸縮自在の小宇宙として捉えていました。
東晋の道士葛洪の著と伝えられる『神仙伝』という書物の中に「壺中天」の話がありますが、この話は、そうした宇宙観を端的に示すものです。
壺公という老人が市場で老人が薬を売っていた。夜、店じまいすると、老人は壺の中にひょいと入っていった。
それを見ていた男が、翌日、老人の案内で、いっしょに壺の中に入った。すると、そこには別天地が広がっていて、仙人の棲む宮殿があった。
とあります。壺の中に入っていくと、そこに仙人の棲む別世界が広がっていたという話です。
ちなみに、「壺中天」の「壺」は、一般には「つぼ」とされていますが、本来は、ヒョウタンのことです。
ヒョウタンは、「瓠」と書きますが、「壺」と「瓠」は、発音が同じで、古代では通用していました。そのため、いつの間にか混同されるようになったのです。
ヒョウタンは、水や酒を入れる容器ですが、薬の入れ物でもあります。
ですから、昔は、薬屋の看板にはヒョウタンが吊されていました。仙人や道士は金丹(不老不死の仙薬)をこれに入れます。
そしてまた、ヒョウタンは、時空を閉じ込める器としてのシンボリズムを持っています。一個のヒョウタンが、一つの宇宙を呑み込んでいる、という発想です。
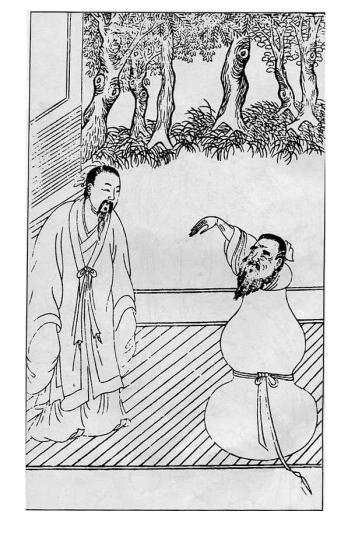
このように、小さなものの中により大きなものを呑み込む、あるいは閉ざされた狭い空間の中に広い宇宙を包み込む、という発想は、古代中国では、しばしば見られるものです。洞天や壺中天は、まさにそうした発想を典型的に示すものです。
前掲の「枕中記」の場合も、小さな枕の中で展開された別世界ですから、やはり同じ発想です。
洞窟と人体のアナロジー
こうした洞天、そして、洞天に象徴される宇宙観は、道教と関わりがあります。道教は、中国土着の宗教で、現世ご利益、不老長生を説くものです。
元来、洞窟は、霊気が充満する静寂で聖なる場所として、道士たちの修行の場でした。
神仙が棲むという山奥の景勝は「洞天福地」と呼ばれ、道教の聖地とされます。また、道教の経典には、「洞真」「洞玄」「洞神」など、「洞」の字が多く用いられています。
道教では、宇宙を一個の巨大な洞窟に見立てます。
無限の空間であると同時に、閉ざされた空間でもある、という宇宙観は、茫漠とした闇の広がりであり、かつ閉鎖的な内部空間である洞窟のイメージに近いのです。
そして、道教では、洞窟と人体とのアナロジーを説きます。
「人体は洞窟の如し、洞窟は人体の如し」というわけです。
確かに、内視鏡で見る人間の体内の映像は、まるで洞窟を探検するような感じがしますし、また、鍾乳洞の中に入っていくと、人体の内部を遊覧しているような錯覚を覚えます。
こうした類似性から、道教では、洞窟と人体とを結びつけ、そして、洞窟を媒介として、宇宙という「マクロコスモス」と、人体という「ミクロコスモス」とを結びつけます。
つまり、「宇宙=洞窟」、「洞窟=人体」、ゆえに「宇宙=人体」という図式です。
このように、宇宙を人体とのアナロジーで解釈するという発想は、道教に限らず、中国の古代思想によく見られるものです。
天地創造の神話では、盤古という巨人が死んで、その左目が太陽、右目が月、血が川、歯や骨が金属や岩石になったと語っています。
また、『荘子』には、「大地のあくび、その名を風という」という一節があり、宇宙は人間のように呼吸をすると記されています。
さて、この人体とのアナロジーを「桃花源記」に当てはめてみると、どうなるでしょうか?
隘路を通って、しばらく行くと、急に目の前が広がる、とありますから、これは、まさに子宮です。
子宮は、母胎回帰願望の心理が働く場所、人間にとって最も安らぎを得られる場所とされます。
この文脈から考えると、桃源郷は、閉鎖的に外部から守られた場所、人々が安心して暮らせる場所、という一面を持つようになります。
道教の終末思想
さて、もう一つ別の観点から見れば、洞天の構想は、道教の終末思想とも関係があるとされています。
道教の終末論は、この世の終わりが、天地の運行の法則に基づいて必然的に起こる、とするものです。
陰陽五行の調和が失われ、大洪水が発生して天地が崩壊し、悪人はすべて死に絶え、善人だけが救済を得て、大災の後に出現する太平の世を迎えることができる、と説いています。
この終末論は、東晋の時代に、道教徒の間で広く信奉されていました。
天地壊滅が近いとされていたその当時、人々は、災厄の及ばない洞天に逃れて生き延びることを願いました。洞天は、まさに「ノアの方舟」だったのです。
そして、終末の時期は、干支で言うと「丁亥から壬辰の間、または甲申の前後」と予言されていました。これらは、いずれも、東晋では太元年間に当たります。
東晋の太元という年号は、「桃花源記」の中に出てきます。
冒頭に、「晋の太元中、武陵の人、魚を捕らうるを業と為す」とはっきり書かれています。
これが偶然の一致とは考えにくいでしょう。
「桃花源記」は、道教の終末思想と何らかの関係があって、それを意識した上で、わざわざ物語の時代を東晋の太元年間に設定しているのであろう、と考えられます。
このように、洞天は、元来、道教において小宇宙を具現する場として構想されたものでした。それが、やがて民間伝承に取り入れられ、宗教・信仰から説話に変わり、いつの間にか仙境や理想郷として語られるようになったのです。
子宮であれ、ノアの方舟であれ、洞天の理想郷は、「ユートピア」というよりは、むしろ安全や休息を求めて避難する閉鎖的かつ排他的な場所、すなわち「シェルター」という意味合いを強く持つものなのです。
老子の「小国寡民」
もう一つ視点を変えて、「桃花源記」の思想的背景を考えると、老子の「小国寡民」との関係に触れないわけにはいきません。
魏晋の文人の多くがそうであったように、陶淵明もまた道家思想への傾倒が顕著でした。

『老子』第八十章には、老子が想定した理想の社会形態が、次のように記されています。
小さな国土に少ない人口。文明の利器はあっても使わない。民は死を重んじ、遠くへは行かない。舟や車があっても乗ることはなく、武器があっても列ねて用いることはない。
民は縄を結んで意思疎通をする。質素な食事に満足し、粗末な服を美しいと思い、あばら屋に居心地よく生活し、自分たちの風俗習慣を楽しむ。
隣国がすぐ近くに望み見ることができ、鶏や犬の鳴き声が聞こえてくるほどであっても、民は年老いて亡くなるまで互いに往来することはない。
国土が狭く人口も少ない閉鎖的な自給自足の農村共同体であり、人々は、原始的な生活に甘んじ、平和に暮らしている、という社会形態です。
「小国寡民」の理想社会の構想は、自然復帰の思想で貫かれています。
老子は、儒家の説く仁義道徳や学問知識、つまるところ、文明そのものが諸悪の根源であると見なし、それら一切を取り払って原点に立ち返ることを唱えています。
桃源郷には、この「小国寡民」の社会と共通した点が多く見られます。
桃源郷の人々は、外の世界から隔絶された閉鎖的な社会で生活し、昔ながらの農耕生活を営み、気質は淳朴で心優しく、のどかで平和な日々を送っています。
「桃花源詩」の理想郷
「桃花源記」の後には、長編の五言詩が続いています。
『陶淵明集』では、この文と詩がセットになって、一つの作品として収録されています。
「桃花源記」は、これまで述べてきたように、民間伝承を再構成したものですから、陶淵明の創作とは言いにくいところがありますが、一方、五言詩の「桃花源詩」の方は、純然たる陶淵明自身の創作です。
一般的には、「桃花源記」のみが広く知られていて、「桃花源詩」はその存在すらあまり知られていませんが、陶淵明本人としては、作品のメインは「桃花源詩」の方であったはずです。
つまり、作品の母体はあくまで「桃花源詩」であって、「桃花源記」は、その詩を作る上で素材とした物語を紹介するために、詩の前に置いた序文のようなものです。
ですから、陶淵明の思想と文学を語る時には、むしろ「桃花源詩」の方に着目しなければなりません。
「桃花源記」の行間からも「小国寡民」風の社会の様子が十分に伝わってきますが、陶淵明の思想をより直接的に反映している「桃花源詩」では、更に具体的に、その様相が示されています。
草榮識節和 草 栄えて 節の和するを識(し)り
木衰知風厲 木 衰えて 風の厲(はげ)しきを知る
雖無紀歴志 紀歴の志 無しと雖も
四時自成歳 四時 自ら歳を成す
というように、村人たちは、暦さえもない停滞した原始的、非文明的な生活を送っています。そして、
怡然有餘樂 怡然として余楽有り
于何労智慧 何に于(おい)てか智慧を労せん
というように、知恵を無用のものとして排斥する精神は、老子の主張と一致しています。
このように、「桃花源記」を道教を背景とした説話と捉えるか、道家思想を背景とした文学として捉えるかによって、桃源郷は、それぞれ異なる姿を我々の前に現します。
前者の視点からは、「シェルター」としての洞天という一面、そして後者の視点からは「小国寡民」風の理想的共同体という一面が浮き彫りになってくるのです。
仙境か、絶境か
さて、東晋は、道教が広く信奉され、神仙説が流行した時代です。
「桃花源記」のもとになった洞窟説話は、概ね仙境の話です。そこには、仙人や仙女も登場します。
「桃花源記」自体も、仙界のシンボルである桃を使ったり、再び訪れることができないというモチーフを使ったりして、仙境の雰囲気に包まれていますが、登場する村落の様子は、仙境ではなく、絶境として描かれています。
「仙境」は、仙人の棲む架空の世界ですが、「絶境」は、人里からいかに遠く離れていようと、あくまで俗世と同じ次元の人間世界です。
「桃花源記」に登場するのは、ごく普通の人間であり、神や仙人ではありません。農耕生活を営む素朴な民であり、身なりも俗世間の人間と全く同じです。

ところが、唐代に至ると、詩人たちは桃源郷をもっぱら仙境として扱うようになります。
仙境としての桃源郷は、山水の風景をロマンチックに彩るには絶好の素材であり、「桃源」という言葉が、別世界を美的に表現する詩語として定着します。
王維の七言古詩「桃源行」は、その代表的な作品です。その末尾は、次のように歌っています。
春來遍是桃花水 春来りて 遍く是れ桃花の水
不辨仙源何處尋 仙源を弁ぜず 何れの処にか尋ぬ

しかし、次の宋代では、主知的、合理主義的な宋代の時代風潮も手伝って、桃源郷を仙境とする見方が否定されます。
北宋の詩人蘇軾は、「陶の桃花源に和す」という詩の序文の中で、「漁夫が出逢った人々は、不老不死の仙人などではない。秦の戦乱を逃れてきた者の子孫である。仙人であったなら、どうして鶏を割いて食べることがあろうか」と述べて、仙境説を一蹴しています。

実在する桃源郷
この議論の顛末はさておき、仮に絶境として捉えると、またもう一つ、「桃花源記」の新たな解釈が可能になります。
それは、この話が、歴史的事実を反映した物語である、という解釈です。
東晋の時代は、外からは、北方の夷狄の脅威にさらされ、内部では、軍閥の権力争奪や農民一揆が相次ぎ、各地で血生臭い戦乱が続きました。
多くの民が、戦禍を逃れて山奥の絶境に移住したことが、『三国志』や『晋書』などの歴史書に記されています。
集団逃避した流民たちは、山岳地帯に「塢(う)」という閉鎖的な共同体を形成し、自給自足の生活を維持したとされています。
塢の実態が「桃花源記」に描かれたような理想的な社会からは程遠いものであったとはいえ、そうした共同体が伝説化され、美化されて、やがて桃源郷の物語に変わっていった、という説があります。
そのように考えると、桃源郷が「隠れ里」としての意味合いを帯びてきます。ここでは、洞天のシェルターではなく、現実社会でのシェルターということなります。
「桃花源記」は、むろん架空の物語であって、現実の出来事の記録ではありません。しかし、桃源郷の村人たちの言葉に「秦時の乱を避け」云々、とあるように、確かに史実の影が窺えるのです。
そして、この説を一歩進めると、「桃源郷は実在した」という主張が起こってきます。
さらにもう一歩踏み込むと、実在したのであれば、では「桃源郷の場所はどこなのか」という議論になります。
「桃花源記」の中では、漁師は武陵(湖南省)の人とはっきり記されています。にもかかわらず、唐代から今日に至るまで、北から南まで、中国各地のいろいろな地名が、桃源郷の所在地としてノミネートされてきました。
清代には、清朝考証学の興隆と相俟って、実在説が確かなものとなり、桃源郷の所在地が詳密に考察されるようになります。
20世紀には、陳寅恪の「桃花源記傍証」(1936)をはじめ、数多くの学術論文が、桃源郷の所在地の特定を論じています。
現在は、桃源郷にちなんで観光地化した場所が、中国各地にあります。
桃林、清流、丘陵、小屋などを造成して、「桃花源記」の風景を再現し、桃源郷を疑似体験できる森林公園やテーマパークになっています。
もともと俗世間から隔絶され、人々の来訪を拒んだ場所であり、そもそも虚構の世界であるはずの桃源郷が、ついに、観光客が入場料を払って訪れる場所になってしまいました。

以上のように、一般的には、詩人陶淵明の描いたユートピア文学として扱われている「桃花源記」ですが、視点を変えて、これを民間伝承として捉え、その背景にある宗教・思想を考察すると、まったく違った一面が見えてきます。そして、平和な農村の物語の裏には、当時の戦乱の史実も見え隠れしています。
「桃花源記」は、こうした宗教的、思想的、歴史的な要素が絡み合いながら原型が造られ、詩人陶淵明の手によって「桃花源詩」と併せて一篇の文学作品として昇華されたものなのです。
中国古代人の発想や宇宙観、思考様式を窺い知ることのできるとても興味深い作品であると思います。
山岳型、農村型、懐古主義の理想郷
さて、最後に、陶淵明の「桃花源記」に代表される中国の理想郷と、トマス・モアの『ユートピア』に代表される西洋の理想郷とを比較してみます。すると、両者が、極めて対照的であることがわかります。
時代もジャンルも異なり、同じ土俵にありませんので、そもそも無理な比較で、乱暴な一般論にはなりますが、おおよそ次のようなことが言えます。
まず一つ目は、理想郷の設定される場所の違いです。
理想郷の類型には、海洋型と山岳型、つまり「島の楽園」と「山の楽園」があると言われますが、西洋の理想郷は、多くの場合、島として設定されています。
トマス・モアの『ユートピア』では、理想郷は大きな三日月型の島にあります。もともとは大陸と繋がっていたのが、建国者によって切り離されて、孤島となったものです。

他にも、フランシス・ベーコンの『ニュー・アトランテイス』、トマソ・カンパネラの『太陽の都』などでは、理想郷は、島もしくは海を隔てた陸地に設定されています。
一方、中国の理想郷は、ほとんどの場合、山に設定されます。
理想郷は、俗世と地続きの場所にあり、多くの場合、訪れようと意図していない人間が偶然に訪れるという話になっています。
「桃花源記」では、漁夫が川を遡った山奥で、たまたま桃源郷に迷い込みます。他の民間伝承や説話でも、ほぼ同じパターンで、仙境などの別世界は、たいてい山の中にあります。
これには、中国が大陸であるという地理的要因の他に、道教との関連が考えられます。前述のように、道教では山を神聖視し、道士は山奥の洞窟で修行をします。また、伝説では、西方の崑崙山は、神仙が棲む仙境とされています。
なお、中国でも、別世界が海にある場合があります。
不老不死の仙薬があるとされる仙境、蓬莱・方丈・瀛洲のケースです。
しかし、この場合も、渤海の蜃気楼で出現した山が、仙境に見立てられたものであり、「東海の三神山」と呼ばれるように、島ではなく、海に浮かぶ山として認識されています。
二つ目は、理想郷の社会形態の違いです。
西洋の理想郷は、基本的に都市型です。
ユートピア島は、54の都市から成る国家であり、共産主義的な社会体制になっています。
これに対して、中国の理想郷は、基本的に農村型です。
桃源郷は、村人が田畑で耕作をして生活する小さな農村です。
これには、文明そのものに価値を認めない道家思想の影響が強いと考えられます。
人間の知恵や欲望を否定する立場からは、理想郷のモデルは、必然的に、純朴な農村社会ということになります。老子の「小国寡民」のように、民が無知無欲で、為政者が無為自然の政治を行うのが理想とされるのです。
そして、三つ目は、理想郷の時代設定の違いです。
西洋の理想郷は、基本的に、未来の時代にこうありたい、という想像の世界です。ユートピア島は、人々が平等で平和な共同生活を送る理想的な未来社会の青写真であると言えます。
現状に対する不満や反撥が土台にあって、それとは逆の世の中、あるいは遥かに進歩した世の中を未来に想定し、それが全くの虚構であれ、実現不可能なものであれ、その理想に向かって進もうとする前向きな姿勢です。
これに対して、中国の理想郷は、基本的に、遥か遠い過去の世に定められます。とりわけ、太古の時代、伝説上の古代帝王、堯舜の天下太平の治世に理想を求めます。たとえそれが伝説とはいえ、大昔に存在したとされる平和な世の中に理想を求めるのです。
これは、中国古来の懐古主義、あるいは尚古主義の考え方で、古き良き時代に対するノスタルジアです。将来に期待するのではなく、過去を追憶する後ろ向きな姿勢です。
大ざっぱにまとめれば、西洋の理想郷が、海洋型、都市型で、未来を向いているのに対して、中国の理想郷は、山岳型、農村型で、過去を向いているものと言ってよいでしょう。

【付録】「桃花源記」全文(原文+書き下し文+現代日本語訳)
原文:
晋太元中、武陵人捕魚為業。縁渓行、忘路之遠近。忽逢桃花林、夾岸数百歩、中無雑樹、芳草鮮美、落英繽紛。漁人甚異之、復前行、欲窮其林。林尽水源、便得一山。山有小口、髣髴若有光。便捨船従口入。
初極狭、纔通人。復行数十歩、豁然開朗。土地平曠、屋舎儼然、有良田美池桑竹之属。阡陌交通、鶏犬相聞。其中往来種作、男女衣著、悉如外人。黄髪垂髫、並怡然自楽。
見漁人、乃大驚、問所従来、具答之。便要還家、設酒殺鶏作食。村中聞有此人、咸来問訊。自云、先世避秦時乱、率妻子邑人来此絶境、不復出焉、遂与外人間隔。問今是何世。乃不知有漢、無論魏晋。此人一一為具言所聞、皆嘆惋。餘人各復延至其家、皆出酒食。停数日、辞去。此中人語云、不足為外人道也。
既出、得其船、便扶向路、処処誌之。及郡下、詣太守、説如此。太守即遣人随其往、尋向所誌、遂迷不復得路。
南陽劉子驥、高尚士也。聞之、欣然規往、未果、尋病終。後遂無問津者。
書き下し文:
晋の太元中、武陵(ぶりょう)の人 魚を捕らうるを業(ぎょう)と為す。渓(たに)に縁(そ)うて行き、路(みち)の遠近を忘る。忽(たちま)ち桃花の林に逢い、岸を夾みて数百歩、中に雑樹無く、芳草鮮美、落英繽紛(ひんぷん)たり。漁人甚だ之を異(あや)しみ、復(ま)た前(すす)み行きて、其の林を窮(きわ)めんと欲す。林は水源に尽き、便(すなわ)ち一山を得たり。山に小口有り、髣髴(ほうふつ)として光有が若(ごと)し。便ち船を捨て口より入る。
初めは極めて狹く、纔(わず)かに人を通ず。復た行くこと数十歩、豁然(かつぜん)として開朗なり。土地は平曠(へいこう)、屋舍は儼然(げんぜん)として、良田美池桑竹の属(たぐい)有り。阡陌(せんぱく)交(こもご)も通じ、鶏犬(けいけん)相聞こゆ。 其の中に往来種作(しゅさく)し、男女の衣著(いちゃく)は、悉(ことごと)く外人の如し。黄髪垂髫(すいちょう)、並びに怡然(いぜん)として自ら楽しめり。
漁人を見て、乃ち大いに驚き、従(よ)りて来る所を問う。具(つぶさ)に之に答う。便ち要(むか)えて家に還(かえ)り、酒を設け鶏を殺して食を作る。村中此の人有るを聞き、咸(みな)来りて問訊(もんじん)す。自ら云(い)う、「先世 秦時の乱を避け、妻子邑人(ゆうじん)を率いて此の絶境に来りて、復た出でず。遂に外人と間隔す」と。今は是れ何の世なるかと問う。乃ち漢有るを知らず、魏晋に論無し。此の人一一為(ため)に具に聞く所を言うに、皆嘆惋す。余人各々復た延(まね)いて其の家に至らしめ、皆酒食を出だす。停まること数日、辞して去る。此の中の人語(つ)げて云う、「外人の為に道(い)うに足らざるなり」と。
既に出で、其の船を得、便ち向(さき)の路に扶(そ)い、処処に之を誌(しる)す。郡下に及び、太守に詣(いた)り、説くこと此くの如し。太守即ち人を遣(や)りて其の往くに随い、向(さき)に誌せし所を尋ねしむるも、遂に迷いて復た路を得ず。
南陽の劉子驥(りゅうしき)は、高尚の士なり。之を聞き、欣然(きんぜん)として往かんと規(はか)るも、未だ果たさざるに、尋(つ)いで病みて終わる。後遂に津(しん)を問う者無し。
現代日本語訳:
晋の太元年間のこと、武陵の漁夫が谷川に沿って舟を進めるうちに、どれほどの道のりを来たかわからなくなってしまった。その時、ふと桃の花の咲く林に出逢った。川の両岸数百歩にわたり、すべて桃の木ばかり。芳しい草が色鮮やかに美しく、桃の花びらが辺り一面に乱れ舞っていた。漁夫は大変不思議なことだと思い、更に進み行き、林の先を見極めようとした。林は水源の所で尽き、そこに山があった。山に小さな洞穴があり、中からほのかに光が射している。漁夫はそこで舟を乗り捨て、洞穴の中に入っていった。
初めのうちはとても狭く、やっと一人が通れるほどであったが、更に数十歩進むと、急にパッと目の前が開けた。そこは広々とした平らな土地で、家屋は整然と建ち並び、肥沃な田畑や美しい池、桑や竹などがあった。あぜ道は縦横に行き交い、鶏や犬の鳴き声が聞こえてくる。その中を行き来して耕作している人々は、男女とも俗世間の人間と全く同じ格好をしていた。老人も子供もみなのんびりとして楽しそうだった。
ある村人が漁夫を見てたいそう驚いて、どこから来たのかと尋ねた。漁夫はそれに詳しく答えた。すると村人は漁夫を家に招いて、酒を勧め鶏を割いてもてなした。こんな人がやって来たと聞いて、村中の人が集まってきて、あれこれと尋ねた。村人が言うには、自分たちの祖先が秦の時代の戦乱を避けて、妻子や仲間を連れてこの人里離れた土地に来て、それ以来ここを出たことがなく、そのまま外界の人々と隔たってしまったとのこと。そして、今は何という時代なのかと尋ねた。なんと漢という時代があったことさえ知らず、ましてや魏や晋は言うまでもない。漁夫が自分の聞き知っていることを一つ一つ事細かに語って聞かせると、皆深いため息をついた。他の村人たちもそれぞれ漁夫を招いて家に連れていき、酒食を出してもてなした。こうして数日間とどまって、いとまごいをすることになった。ここの人たちは漁夫に「外界の人にはお話にならないでください」と告げた。
やがて漁夫はここを出て、自分の舟を見つけ、やって来た道に沿って、あちこちに目印を付けた。郡の城下に戻った漁夫は、太守の所へ行き、かくかくしかじかのことがあったと話してしまった。太守はすぐに人を遣って漁夫の後について行かせ、先に付けた印を捜させたが、迷ってしまい、道を見つけることはできなかった。
南陽の劉子驥は高潔な人物であった。この話を聞いて、喜んで行こうとしたが、目的を果たさぬうちに、まもなく病気で亡くなった。その後はもう誰もそこを訪れようとする者はなかった。
関連記事:
