
辞書作りにとりつかれた人々ー博士と狂人 ~世界最高の辞書OEDの誕生秘話~
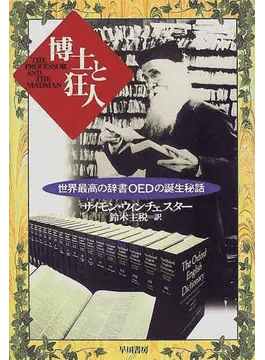
<『小さなことばたちの辞書』の予習として読んだ>
『小さな言葉たちの辞書』(ピップ・ウィリアムズ著:2021年)を読み始めて、オックスフォード英語辞典(OED)のことをもっと知らなければこの本のことはわからないな、と思ったのが本書を読んだきっかけだ。ウィリアムズは、この本を、「大変面白く読んだものの、<辞典>(OED:筆者補足)はじつに男性中心の事業だったという印象が残った」(『小さなことばたちの辞書』あとがきp.505)と述べて、『博士と狂人』が同書を執筆する一つのきっかけだったことが示唆されているからだ。そもそも、『小さな辞書の物語』は、OED編纂のさなかに、編集主幹のマレー博士がたった一つ紛失したという《Bondmaid》という言葉のカード(本書p.252)を巡って話が始まるのだ。
そういうわけで、(ある種の)イギリス文学(もちろん翻訳)が好きなくせにOEDを開いたことさえないのだから、とりあえず読んでみようと手に取ったが、読み始めてあまりの面白さに一気に読んでしまった。この本の凄いところは丹念に資料を集めて積み上げられたノンフィクションだということ。事実は小説よりも奇なりを地で行く面白さである。1998年の原著発売直後からベストセラーとなり(『ニューヨークタイムズ』で24週連続など)、日本でもいち早く翌年に翻訳された。2020年にはメル・ギブソン、ショーン・ペン主演で映画化された。いったいに、辞書をめぐるベストセラーは多いような気がする。『小さな言葉たちの辞書』も原著の出版されたオーストラリアやイギリスでベストセラーになっているし、日本でも『辞書を編む』がベストセラーになり、映画化もされた。
みんな辞書の話が好きなんだね、と思う。
<そもそもOEDとは?―シェイクスピアには参照すべき辞書がなかった!>
お隣のフランスでは、17世紀にはリシュリューによってアカデミー・フランセーズが創設されてフランス語の統一に着手していたのに、同時代のイギリスでは体系的な辞書はなかったという。シェイクスピアは『十二夜』に、<「エレファント亭」という宿屋があります>と書いたけれど、エレファントがどんなものか、彼には全く調べるすべがなかったのだという。なるほど…。宿屋やパブの名として当時よくあったらしいエレファントという言葉をシェイクスピアはどんなイメージで使っていたのだろう、とおかしくなる。このあたりの辞書を巡るイギリスの事情もなかなか興味深く一読の価値がある。
やがてイギリスでも次第に辞書の編纂が進み、1755年には43500の見出し語を持つサミュエル・ジョンソンの『英語辞典』(outsの定義を「穀物の一種で、イギリスでは馬に与えるのが普通だが、スコットランドでは人が食べる」と記載したという有名なエピソードがある)が誕生した。
OEDの刊行はそれから百年後のことである。
<OEDのすごさー70年がかりで完成>
OEDは、見出し語約29万語、全20巻、累計21,730ページという膨大なもので、1857年、イギリス言語学協会によって構想されたが、第一巻が刊行されたのが1884年、完全版の刊行は1928年のことだ。70年がかりだったわけで、編集主幹のジョン・マレーの死後10年以上経っていた。
1989年には第二版が刊行され,2000年にはこの第二版をもとにオンライン版がリリースされ、今でも年4回更新されている。また、現在、第3版刊行に向けての全面改訂作業が始まっているとのこと、まさに生きた辞書なのだ。
OEDの特徴について、《 How to use the OED The Oxford English Dictionary: 日本人及び国内利用者向けリソース》には次のように説明されている。)
「Oxford English Dictionary (OED)は(中略)28万項目以上の見出しで、過去から現在まで、英語圏で使われてきた60万語以上の単語の意味、発音とその歴史的変遷の遡及を可能にしています。OEDは、歴史主義をベースにした編纂を特徴としており、全ての収録単語において初出例(英語の記録として最も古い用例)まで遡ることができる点で、現代英語辞典とは一線を画しています。OEDでも、現在の意味を確認できますが、古典文学から、専門誌、映画の脚本、料理本に至るまで幅広いソースから350万件以上の用例を収集し、各語の形成、発展過程をたどることを可能にしています。」
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/resources-for-japanese-users/
改めてすごい辞書だと感動してしまう。
<戦争神経症の殺人犯の独房から、古今の用例が届く>
さて、ジョン・マレーは、辞書に必要な用例を収集するのにボランティアの協力を仰いだ。この収集に大きく貢献したのが、本書のもう一人の主人公、ウィリアム・チェスター・マイナーである。マイナーはアメリカ人で、おまけに殺人を犯して服役中の人間だ。
彼がOEDの編纂にかかわるようになったのには複雑な背景があった。マイナーの略歴をざっと紹介すると、彼はアメリカの名門出身(先祖は、17世紀、メイフラワー号のすぐ後に新大陸に渡り、その一門はコネチカット州の創設者だとか)で大金持ち、イェール大学で学び軍医となる。しかし彼が従軍した南北戦争の戦場は史上有名な残酷なものだった。そのため彼は一種の戦争神経症になる。脱走兵への残虐な処罰を命じられ、これが原因となって発症したのだという。その兵士がアイルランド人だったため、彼は生涯アイルランド人を恐れ続けることになる。この事実の真偽については異論もあるらしいが、マイナーが日常生活に支障をきたすほどになってしまったのは確かで、かれは退役し、生涯「傷痍軍人」として年金をはじめ、軍の保護を受ける身となった。
そして、気分転換を求めてヨーロッパにわたり、ロンドン滞在中に殺人をおかしてしまうのだ。彼が殺したのは工場の早朝勤務に向かう途中のごく普通のまじめな労働者だった。マイナーは「アイルランド人に襲われる」という妄想に取りつかれて霧の立ち込める深夜の路上でピストルを発射してしまったのだ。その場で逮捕され、裁判の結果、精神異常による犯行として保護処分となり、バークシャーにある刑事犯精神病院に収容される。しかし、アメリカ合衆国退役軍人であり、大金持ちでもあるマイナーは塀の外に出ることは許されないものの、かなり快適な生活が保障されていた。被害者の一家にはウィリアム本人をはじめマイナー家が手厚い経済的補償を行い、残された妻イライザとの間には一種の友情のようなものも芽生えたようだ。マイナーのためイライザは定期的に頼まれた本を買って届けるようになったのだ(彼は独房を二部屋与えられ、そこを書斎、というよりミニ図書館にしていた)。

1880年代のはじめ、OEDの編集主幹マレー博士は単語の用例を集めるためのボランティア募集の「訴え」を作って広く配布した。イライザの持ってきた本の包みのなかにそのビラが入っていたのは間違いない、と著者は見る(p.149)。こうしてマイナーは自らの膨大な蔵書や辞典編集室から届けられる文献を精査して用例を送り始める。辞典編纂室のほうでも、「これこれの語の用例、派生語などについてお知らせください」と要求を出せば的確で完璧なデータが送られてくるようになったのだ。
マレーとマイナー、二人の出会いには劇的なエピソードが語られている。マレーはマイナーが囚人だということを知らず、金とひまのある田舎の紳士だと思い込んでおり、住所のブロードムーアが刑事犯精神病院だということに衝撃を受けたというのだ。しかし実際にはマレーはマイナーの身の上を1887~1889年ころには知っており、深く同情していた。二人は辞典の編纂という共通の目標のための同志であり、強い友情で結ばれたようだ。マレーはしばしばブロードムアを訪ね、その交流は30年におよんだ。のちにマイナーの病状が悪化して妄想から自分の体を傷つけるに至り、アメリカにいる弟から祖国での静養を懇願された際に帰国のための努力をしたのもマレー博士だった。
1910年、マイナーは仮釈放され、弟に伴われて帰国し、故国アメリカで余生を送ることになる。マレーは1915年に亡くなったが、マイナーは、病状は悪化してはいたが、1920年まで生きた。
マイナーの病気は、戦争の悲惨な体験のPTSD(心的外傷後ストレス障害)が原因となって発症した「統合失調症」だという。今なら、治療法や効果的な薬もあり、症状の軽減も可能となっている。しかし、当時は病棟に閉じ込めておくしかなく、患者にいっそうのストレスをかける状態であったのだ。
<辞書の不思議で魅惑的な、そして男性たちの世界>
この本は辞典の魔力のとりつかれた人間たちの物語である。来る日も来る日も文章を読み、用例を探し、これより古い例はないかと探し回る。恐ろしく地味な仕事だが、なんと魅力的なしごとでもあるだろうか。そこは、本(言葉)の魔物や妖怪がうじゃうじゃと潜んでいて、一度嵌ったらのがれることのできない世界なんだろうな、と思う。
だが、ピップ・ウィリアムスの指摘通り、当時その世界には女性の入り込む余地はあまりなかったようだ。いや、たくさんの女性ボランティアや協力者がいたにもかかわらず彼女たちの存在は目に見えなかったのだろう。例えばたくさんの用例や派生語を送ったイーディス・トンプソン(『小さな言葉たちの辞書』では準主役として活躍する女性史家、作家)がいる。彼女は、OEDの編纂に多大な貢献をした協力者として名前をあげられているものの、辞典の完成を祝う大晩餐会に招待された形跡はないという(マイナーはもちろん招待され、その欠席を参会者たちは不思議がったとか)、というより、女性の協力者は、編纂室のメンバーとして活動したマレー博士の娘たちを含めて一人も姿が見えない。また、掲載される言葉、語義、用例にもジェンダー・バイアスがあったことは事実のようだ。
ただし、この本がジェンダーの問題を無視しているからといってそれはないものねだりである。これについては、ピップ・ウィリアムスに任せるべきであろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
