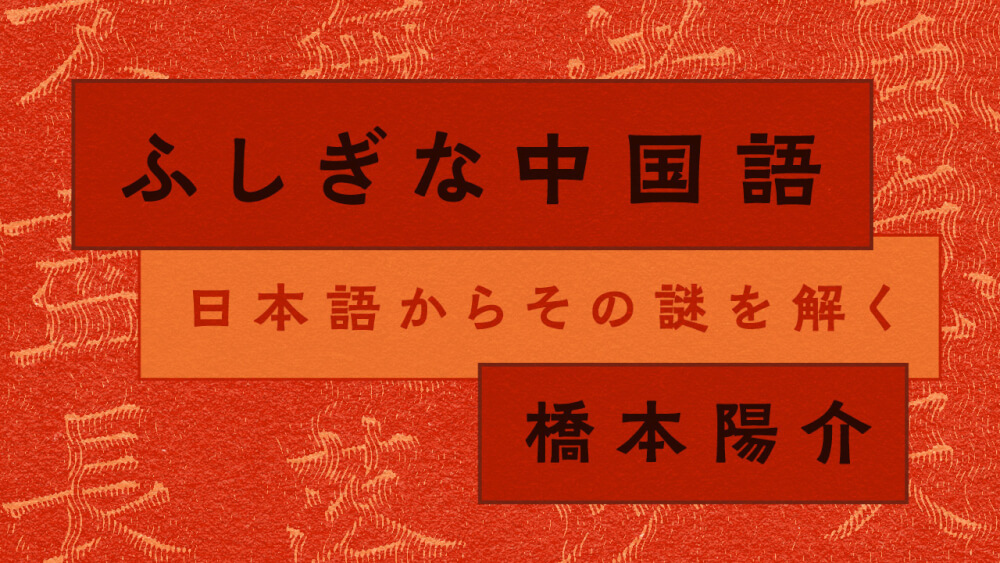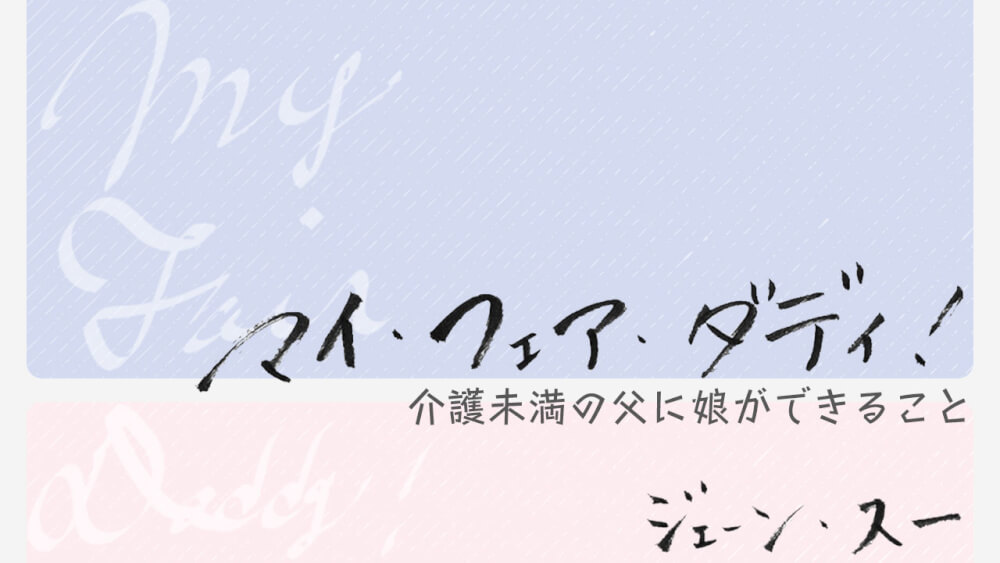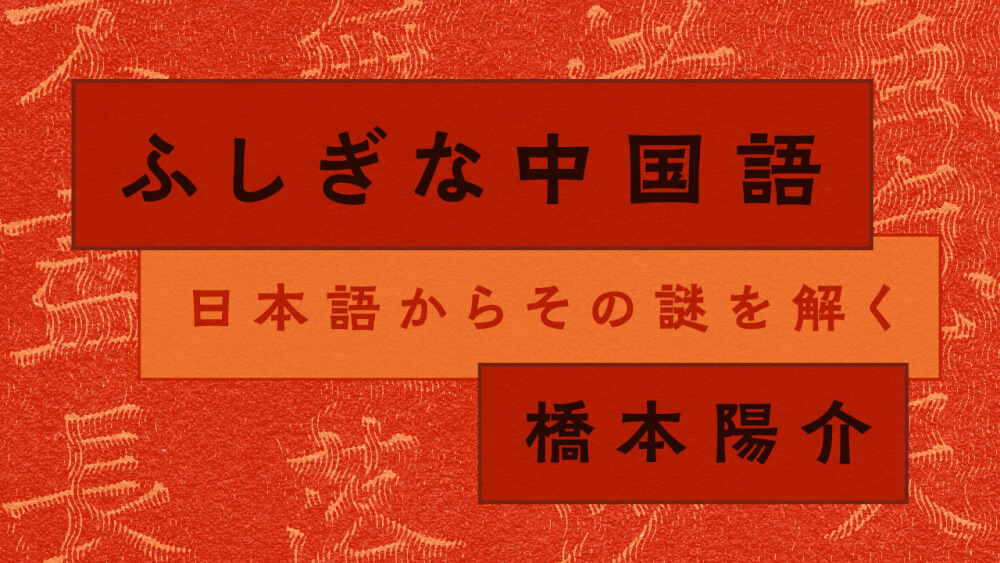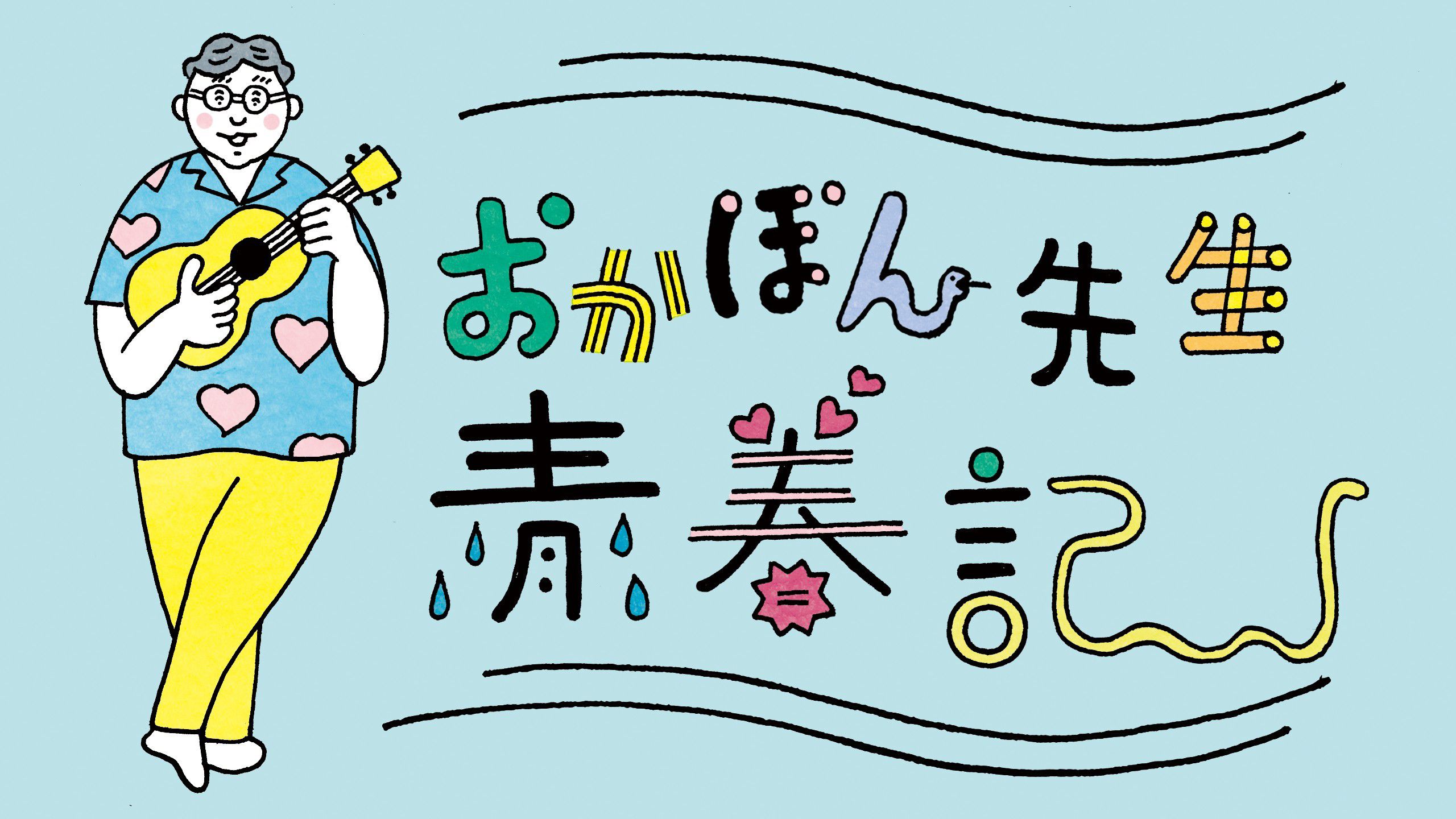ヤマザキマリ×清水克行「歴史は民衆によって作られる」!(No. 949)
考える人 メールマガジン
2022年2月10日号(No. 949)
ヤマザキマリ×清水克行「歴史は民衆によって作られる」
室町時代という「最も日本らしくない」時代の庶民を生き生きと描いて話題となった『室町は今日もハードボイルド』。
著者の清水克行氏は、『テルマエ・ロマエ』や『プリニウス』で古代ローマの生活文化を描き続けるヤマザキマリ氏にずっと親近感を持ってきたという。
一方のヤマザキマリ氏も、清水氏の同書を「思い込みや予定調和から解放される本」と絶賛。
中世日本と古代ローマをとおして人々やその生活文化について考え続けてきたお二人が、コロナ下の日本と世界について縦横無尽に語り合いました。
前篇 室町時代は「自習の時間」?
後篇 『テルマエ・ロマエ』と『タイムスクープハンター』の意外な共通点
ドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』監督が語る!
山戸結希×菊地健雄「ドラマとか演出とか背中とか」
大きな反響を呼んだ、2021年4~6月放送のドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』(テレビ東京「ドラマ24」、現在はAmazonプライム・ビデオなどで配信中)。原作は、父と25年前に亡くなった母のことを綴ったジェーン・スーさんの同名エッセイ。ドラマの監督を務めた山戸結希さん(1、2、9~12話を担当)と菊地健雄さん(3~8話を担当)が、演出における試行錯誤を振り返りながら、あらためて作品の魅力を語ります。
前編 映画監督ふたり、テレビドラマを撮る
後篇 原作の「背中」を撮る
五木寛之×碧海寿広「私たちはなぜ親鸞に魅了されるのか」
昨年10月、新潮選書から親鸞聖人を論じた2冊の本が刊行されました。
ひとつは、五木寛之氏の『私の親鸞 孤独に寄りそうひと』。その出会いから50年以上親鸞を追い続けてきた作家による半自伝的親鸞論です。もうひとつは、近代仏教研究者・碧海寿広氏の『考える親鸞 「私は間違っている」から始まる思想』。
近代以降の論客たちが、いかにして親鸞の魅力や影響を語り続けてきたのか――それぞれの親鸞論を読み解いた一書です。その両者が、あらためて親鸞の魅力を語ります。
五木寛之『私の親鸞 孤独に寄りそうひと』
碧海寿広『考える親鸞 「私は間違っている」から始まる思想』
アクセスランキング
■1位 山戸結希×菊地健雄「ドラマとか演出とか背中とか」
前編 映画監督ふたり、テレビドラマを撮る
■2位 橋本陽介「ふしぎな中国語――日本語からその謎を解く」
第9回 アメリカはなぜ「美しい国」なのか
■3位 ジェーン・スー「マイ・フェア・ダディ! 介護未満 の父に娘ができること」
16.「いざ」という時に必要なこと
最新記事一覧
■橋本陽介「ふしぎな中国語――日本語からその謎を解く」(2/7)
第15回 「過去形」はなくても問題ない
中国語に「過去形」がないって本当??
■岡ノ谷一夫「おかぽん先生青春記」(2/8)
鳴くのは鳥だけじゃない
鳥の鳴き声を研究していた岡ノ谷さん、ついにハダカデバネズミの鳴き声を調べてみることに……!
「考える人」と私(48) 金寿煥
政治学者の中島岳志さんによる連載「親鸞と日本主義」は、「考える人」2010年冬号から2012年冬号までの9回にわたって続き、2017年に新潮選書として刊行されました。
初めて中島さんにお会いしたのは2005年ですから、かれこれ17年近くのお付き合いになります。その名前を耳にしたのは、さらに遡ること3年、2002年のことだったと記憶しています。2002年といえば「考える人」が創刊された年で、私は兼任する書籍編集の仕事で京都に滞在していました。この年から梅原猛さんの『京都発見』シリーズの単行本編集を引き継ぐことになったのです。
当時中島さんも京都大学大学院に籍を置いていたはずですが、直接お目にかかったわけではありません。私は学生時代の友人から「京都に八文字屋という面白い酒場があるよ」と聞き、足を運びました。八文字屋は写真家の甲斐扶佐義さんが営むバーで、作家やアカデミシャン、新聞・出版関係の客の多いことが東京でも知られた店でした。深夜になると小動物が店内を走り回るお世辞にも綺麗な店だとは言えないのですが居心地はよく、初見にもかかわらず長居をした私は甲斐さんに「京都で面白い人はいますか?」なんて無粋な質問をしました。
「中島さんはどうかな?」と甲斐さんから渡された本が、中島さんのデビュー作『ヒンドゥー・ナショナリズム 印パ緊張の背景』(中公新書ラクレ)でした。印象に残ったのはプロフィールです。そこには「1975年生まれ」とあり、生年で私と1年しか変わらなかったのです。その時中島さんは27歳で、私は26歳。小説はともかく、同世代の研究者で著作を発表している人はまだまだ少なく(少し上の世代である1971年生まれの東浩紀さんが『存在論的、郵便的』を上梓したのは1998年のことです)、かつ、その人がなぜインドの地域研究に関わるようになったのかなど、強く印象に残りました(けれど本はしばらく「積ん読」だったような……)。
2005年4月、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)が刊行されます。中島さんの2冊目の著作にして出世作、多方面で話題となった本です。私は「あの中島さんだ!」と慌てて本を購入して読み、「すぐに会いに行かなければ」と版元である白水社の編集者に連絡をしました。
その担当編集者にご仲介いただく形で(それまでの経緯もいろいろあるのですがここでは割愛します)、中島さんとお会いしました。3年前の八文字屋でのエピソードや著作の感想を伝え、「ぜひ中島さんの本を作りたい」と伝えたところ、中島さんは「実は……」とカバンから原稿を取り出しました。なんとすでに完成間近の原稿をお持ちだったのです。聞けば、別の版元から出版予定だったものが、いろいろあってペンディングとなり、「新潮社から刊行できるか検討してもらえませんか?」とのことでした。
それが『インドの時代 豊かさと苦悩の幕開け』(2006年7月)です。不思議な縁を感じざるを得ない経験でした(中島さんと交流するなかで、このような不思議な縁を経験することが他にもしばしばありました)。
前述のように2010年から「考える人」で連載が始まり、それが終了した直後の2013年には『「リベラル保守」宣言』(この本も刊行まで紆余曲折ありましたが、ここでは割愛。詳しくは同書「あとがき」をご参照ください)を担当、そして2017年に『親鸞と日本主義』を刊行します。
同世代の研究者・論客・物書きとして中島さんがいる――そのことの心強さを感じながらの17年でした。そしてこれからも「指針」となる存在であることは間違いありません。17年にいたる付き合いで担当書が3冊というのが多いのか少ないのかわかりませんが、これからもそれは自然と増えていくものだと考えています。ウエブマガジンとなった現在の「考える人」にも、近いうちにご登場いただければ――そう願っております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■note
https://note.com/kangaerus
■Twitter
https://twitter.com/KangaeruS
■Facebook
https://www.facebook.com/Kangaeruhito/
Copyright (c) 2020 SHINCHOSHA All Rights Reserved.
発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71
新潮社ホームページURL https://www.shinchosha.co.jp/
メールマガジンの登録・退会
https://www.shinchosha.co.jp/mailmag/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もしサポートしてくださったら、編集部のおやつ代として大切に使わせていただきます!