
『雲仙記者青春記』第9章 1994年4月、牟田隊長事件
『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』
(1995年11月ジャストシステム刊、2021年3月17日第9章公開)
警察の災害警備隊
長崎県警島原署の災害警備隊は、隊長の牟田好男警視ら16人の体制だった。このほか、24時間交代で派遣されている約40人の機動隊員が、警備隊の指揮下に入っていた。
牟田隊長は、同期拝命の警官の中でもっとも早く警部に昇進。また、一緒に警部になった中でも最初に警視になり、長崎県警の出世街道のトップを走るエリートだった。
しかし、出世のために上司の顔色をうかがうようなタイプではなく、体を張って仕事する行動派。島原市出身でもあり、災害警備隊が発足した1991年10月から初代隊長を勤めていた。
快活な性格でハンサム。テレビなどの取材も多く、どうしても目立つ立場になった。

長崎県警の災害警備隊隊長だった
牟田好男さん(左)
宮崎和子さんの孫・香蓮ちゃんは
女優になり ドラマでよく見かける
しかし、牟田隊長も警備隊発足当時は苦労したようだった。
「神戸ちゃん、俺が来たころは警察なんてあてにならん、ていう風潮でな。自衛隊のことばかりが評価されて悔しくてなぁ。どうしたら警察の活動がわかってもらえるか、と悩んだよ」と漏らしたこともある。
縦割り行政は、組織の対抗意識を強める。ある自衛隊員は「俺たちは危険区域の中が仕事場、警察は安全なところで住民の誘導。たまらんな」と言いながらも胸を張っていた。自衛隊は火山を24時間監視し、遺体の回収のため警戒区域への突入も辞さない。「最前線にいるのは我々だ」という意識が強いのだ。
一方、警察は人命を守ることが第一。警戒区域への住民の立ち入りを規制する当事者である。しかし、これは「できるだけ家財を出したい」「少しでも故郷の近くで生活したい」という住民感情とはどうしても衝突する。
牟田隊長の苦悩は、円滑に業務を進めるためにどれだけ住民に信頼されるか、にあった。自衛隊災害派遣隊のオレンジ色の帽子に対抗してか、警備隊も普賢岳のデザインを縫い取った紺のチームキャップを作り、市民に活動をアピールした。
土石流警戒の現場に同行
実際に警察が災害時にどう行動するのかをナマで見たかったのだが、災害が起こればぼくら記者も原稿を書くのに忙しい。
そこで、土石流や火砕流で大きな被害が出た1993年の9月になってから、「今度土石流が起きたら、牟田隊長と一緒に行動して、密着ルポを書きたいのですが」と浜野さんに頼んだ。
9月3日、台風13号が近づいた。昼から警備隊に行って、逐一をメモした。午後1時から打ち合わせが始まった。
「台風の最接近は午後8時から9時の間です。今の様子では、直撃される可能性は薄そうですが、上陸後はスピードアップすると思われます」との状況報告を受けた牟田隊長は、「住民の避難状況を確認してくれ」と部下に指示した。
気象台からのファクスを受け取った隊員は「午後3時から4時の間に、暴風雨圏に入ります。島原地方に20mmから40mmの雨雲が近付いています」と牟田隊長に報告した。
午後3時過ぎ、警戒班から「泥流は川幅いっぱいだが、橋げたまではまだ余裕がある」と報告が入った。「まもなくかな」と牟田隊長が雨ガッパを着込んだ。4輪駆動車に牟田隊長らと乗り出発。隊本部とは無線でやりとりする。
土石流の震動を九大観測所の地震計がキャッチした、と報告が入った。牟田隊長が「隊長車傍受」と返すと、川の流域など16カ所に張り付いている警戒班が続いて「遊動1、傍受」「遊動2、傍受」と順番に報告する。「こうして全員が聞いていることを確認しているのか」と感心した。
水無川の土石流被災地を通る国道251号で停車した。車窓を雨が横から殴りつける。次第に無線の頻度が増え、続々と情報が入り始めた。
「土石流の震動波形を観測中。大野木場(に設置した地震計の針が)、振り切れ」
3時49分、「もう国道に流れ込んでも不思議はないな」と、牟田隊長が言う。同乗の隊員が「この状態では、30分もちませんよ」と相槌を打つ。
「よし、4時10分から通行を止めよう。島原市と深江町に連絡を。雨の状況によっては、もっと早くするかもしれないと言え」。
あっという間に泥水でセンターラインは見えなくなった。車はしぶきを上げて「今のうちに通り過ぎよう」と急ぐ。助手席の牟田隊長が、振り向いて言った。
「神戸ちゃん、住民にはやっぱ生活があるもんな。国道が止まったら大変よ。なるだけ通してやりたいんさ。
だから、俺はいつもこの前の土石流でどこが削れて低くなったか、これから水がどこに流れるのかを考えて歩くんだ。一番危険だと思った場所に自分が行く。自分が危険を感じたら、ほかの隊員に避難を指示するんだ。一番早く判断できるし、隊員に危険も少ない。ただじっと本部にいるよか、合理的やろ」
市民の間には「警察はすぐに道を止めよる」という反発があった。しかし、現実にはここまで気をつかっていることに驚かされた。「もし牟田隊長がやられたら大変なことになるな」とも思ったが、牟田隊長は自分の現場認識に絶対の自信を持っているようだった。それだけ歩いている、という自負なのだろう。
午後4時。泥水に混じって岩が道路の上に転がり出した。
「もうバイクは通れんぞ。車の流れが切れた段階で通行止めだ」
市街地側で待機している警官に、バリケードを張るよう指示が飛ぶ。
4時7分、「山の寺の震動波形が振り切れ」と無線が入る。牟田隊長は「あそこが振り切れになると、ドコッと土石流が出てくるぞ」と言った。隊長車はその場を離れた。24分、水無川のガードレールが土石流で吹き飛ばされた、と報告。「正解だったな」「瀬戸際だったですね」と、車内の空気が緩んだ。
警察関係者によると、牟田隊長は公安畑出身で相当なやり手だったらしい。本人に聞くとくわしくは答えてくれなかったが、「ソ連が崩壊したときは、これまでやってきたことが正しかったと思ってうれしかったな」と言っていた。
この感覚は警察官一般に共通する認識だ。ぼくには違和感もあったが、とにかく災害警備の仕事ぶりと人柄に関しては、全面的に信頼していた。
牟田隊長は1994年3月初め、県警本部の留置管理室長に異動した。日の当たるポジションではないが、署長や県警本部課長と同格の「所属長」という立場である。次はどこかの署長になるんだろう、と思っていた。ある地方テレビ局は、牟田隊長の離任式の特番まで組んだ。
毎日新聞島原支局でも4月1日付けで、浜野真吾記者が久留米支局長に異動、西部本社報道部から柴田種明(たねあき)記者が新支局長として赴任した。
ところがこの牟田警視が、とんでもない騒ぎに巻き込まれた。
「不祥事」発覚
「まもなく、島原で大変なことが起こるよ」と、情報が入ったのは3月末。
大規模な公共工事が展開されている島原で、今もっとも懸念されるのが汚職だ。それとなく聞き回っていると、長崎支局から「どうやら牟田さんのことらしい」という情報が寄せられた。まさかとは思ったが、もし汚職をしていたら、牟田警視といえども絶対に許すことはできない。
しかし、夜回りをしても、はっきりしたことはつかめない。ただ、牟田警視に関わることで、地元紙の長崎新聞が、ほぼ概要をつかんで近々特ダネを打つ気でいることははっきりしてきた。
長崎新聞の朝刊が来たらすぐに読めるよう、本部1階のソファーで寝ていた4月8日。ガタッと音がして、ぼくは目覚め、表の新聞受けから朝刊を取り出した。牟田警視の件が大々的に載っていた。
「警戒区域内で撮影
災害写真大量に売る
公務中の前島原署災害警備隊長
全紙大20枚組12万円
県警が事情聴取始める」
「なんだ、これは」というのが最初の印象だった。
牟田警視の撮った写真なら隊本部にもたくさん飾ってあるし、報道機関はよく提供してもらっていた。
ぼくも火口の写真を1面カラーで使ったこともある。「持っていけよ」と言われ、いただいたこともあった。後で、写真の焼き付けはほとんど自費で牟田警視が払っていることを知って申し訳なかった。

山頂にあった、溶岩の池
牟田隊長から提供してもらい
1面にカラーで掲載した
長崎新聞の記事にはこうあった。
売られていた写真は、牟田前隊長が隊長就任以降、警戒区域内で撮影した溶岩ドームや普賢神社、赤々と燃えるドーム間近の溶岩塊など。
関係者によると、前隊長は撮影した写真の現像を知人の写真店に依頼、全紙大やワイド四ツ切りのサイズに拡大、その写真は前隊長や知人が売りさばいていた。
売買価格は全紙大が20枚組で12万円、ワイド四ツ切りが1枚1000円。
同市内の写真店の話では、全紙大のプリント料は1枚6000円、ワイド四ツ切りが同800円という。
(94年4月8日、長崎新聞)
まだ6時ごろだったと思うが、柴田さんに連絡してからすぐに取材を始めた。
写真をもらっていたらしい人間は知っていた。ドアを叩いて彼を起こし「どうなっているのか」と問いただしたが、「俺は買っていない」と弁明した。
もう1人の心当たりの家に行った。目をこすりながら出てきた彼に「写真を買ったか」と聞くと、すぐに認めた。
彼は入院していた時期があり、内祝いには迫力のある牟田警視の写真が一番いいと思って、頼んで実費で分けてもらったという。枚数は約150枚。「あんたの責任だぞ!」と、どやしつけた。「俺は記事にしなきゃならない。全部きちんと説明しろ」と迫った。
彼は長崎新聞を読んで「全部俺の責任だ。隊長は嫌がっていたんだが、俺が頼み込んだ。譲ってくれなければ、自分で山に行って撮るって言ったんだ。牟田さんは悪くない。名前を出して構わないから、書いてくれ」と慌てた。
夕刊用の原稿は、県警本部を担当する長崎支局で書いた。ぼくからの一報を受けて、支局の記者がすぐに牟田警視に話を聞き、県警本部の対応を取材していた。牟田警視は「欲しいという人に頼まれて譲った。枚数は500~600枚。実費をもらっただけだ。軽率だったかもしれない」と述べていた。
警備隊の写真は、西川清人さんの写真館で焼いていることを、ぼくは知っていた。
電話すると、西川さんは「応援に来た警察官が、土産にしたいと欲しがるから、と焼き増しを頼まれたんだ」と説明した。
島原署の警官も「米空母のエンタープライズが佐世保に入港して大騒ぎになったときの写真を持っている。一生懸命自分がやった仕事の記録を手元に残しておきたいのは人情だよ」と話す。
夕刊の紙面がファクスで流れてきた。見出しは4段で「市民に600枚売る」。ぼくはカチンときて、長崎支局のデスクに「売るっていうのはまずいですよ。長崎新聞が『売りさばく』って書いたのと同じようなもんです」と電話した。話し合って、長崎に届く朝刊早版は「実費で譲る」に変えた。
普通の不祥事露見ならこんな配慮はしないが、牟田警視の人柄をよく知っていたうえ、実費以上に金を取っていた証拠は何もない。
西川さんの写真館では、全紙大の焼き付け価格は1枚6000円で、20枚組が12万円なら差額はない。ワイド四ッ切りは1枚1000円で、これも実費。「売りさばく」という表現は扇情的に見えた。
「書かれる側」になる恐怖
夕刊処理が終わった後、ぼくは前線本部で考え込んでいた。この問題は牟田警視だけの問題では終わらないことがわかっていたのだ。
正直に告白すると、ぼくは牟田警視らと普賢岳の溶岩ドームのそばまで登ったことがある。1993年11月3日のことだった。
火砕流が起きるのは北東の中尾川、東の水無川、南の赤松谷川方向。ドームが出現したのは旧山頂より低い東側で、西側は安全だった。
もちろん、噴火後は警戒区域となり、立ち入りは禁止されている。普賢岳の北側斜面は、長引く噴火活動で樹木が枯れ果て、保水力がまったくなくなっており、下流の有明町にも土石流の被害の恐れが出ていた。現場の土を踏み、自分の体で北側斜面の状況を実感したかったのだ。
警戒区域内の取材をめぐる論議はすでに堂々めぐりになっている。上司や先輩はぼくの希望を認めることはできまい。だから、休暇を取り、会社の誰にも無断で登った。休暇を取っていたなら、ぼくは毎日の社員として登ったことにはならない。
それでも、もしドームからの落石で頭を打ってぼくが死んだりしたら、やはり会社は非難を浴びるだろう。事前に何度も悩んだが、結果的にぼくはサラリーマンであるより、「新聞記者」でありたいという感情を優先した。
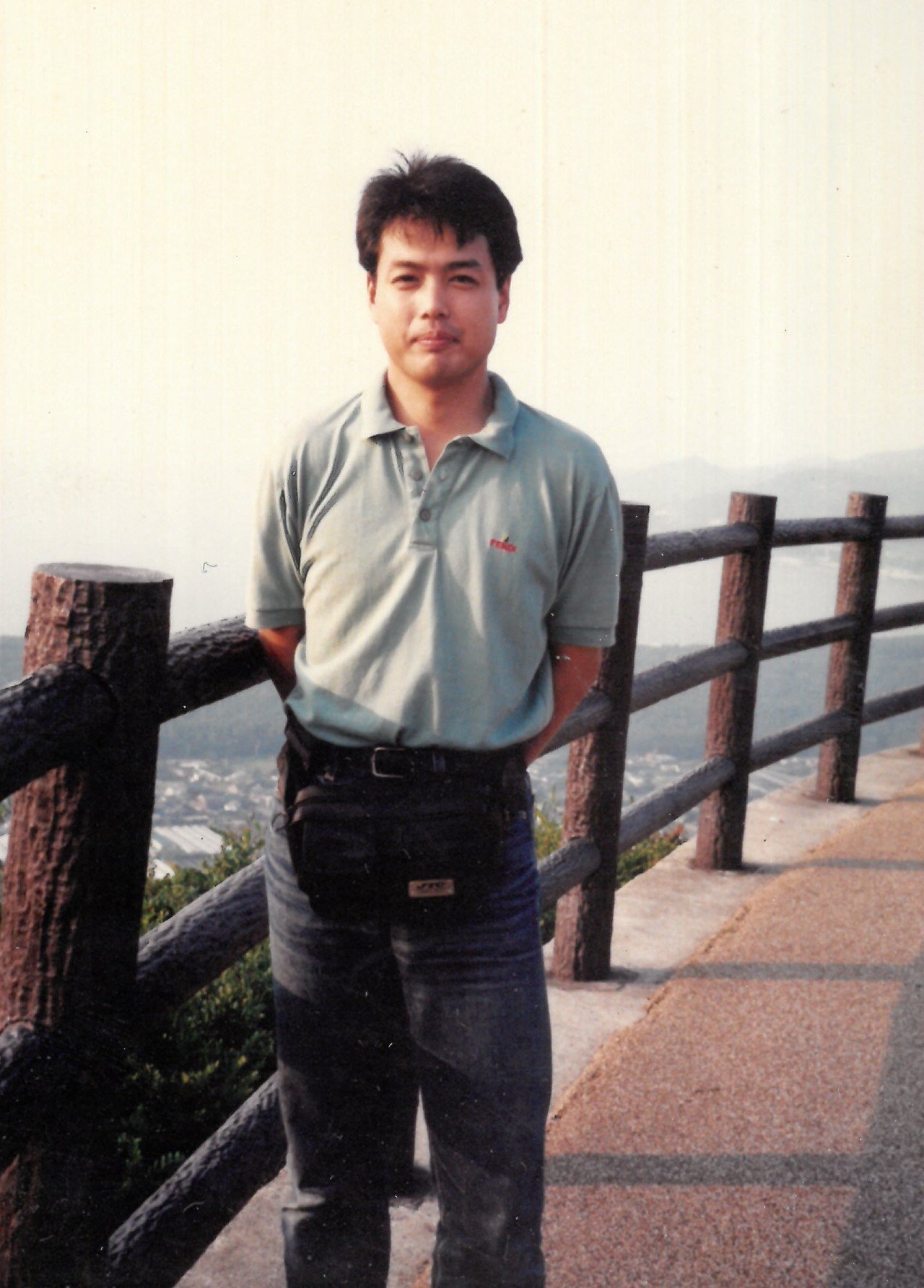
このころの私
警戒区域にからんで報道が抱えるジレンマを、牟田警視にはよく話した。だから、「今度偵察に行くけど、付き合うかい」と牟田警視は誘ってくれたのだった。
ドームの成長は弱まっており、西側への落石もほとんどなかった。ぶら下がりで研究者の日々の分析を聞き、何度も安全性を検討したうえで、数人の警官と登った。
間近で見るドームは大きかったが、「ヘリから見るのとあまり変わらないな」という印象。感動はそれほどなかった。

普賢岳山頂付近から見た溶岩ドーム
松島健撮影
「雲仙普賢岳991-93年噴火」
(日本火山学会)より
それよりも驚いたのはやはり北側斜面だった。木はすべて白く枯れ、溶岩ドームの成長で押し出された地面はボロボロで、ちょっと雨が降れば崩れていくのは明らかだった。
それから1カ月後、ドームが重く大きくなりすぎたため、地下のマグマは出口を探そうと、ぼくが歩いた北側の地面を動かし始めた。3カ月間で30mも地面は押し出され、長さ数十mもの亀裂が大きく走り始めた。
ぼくは山頂に登った経験をもとに「局所的な山体崩壊の恐れ高まる」という記事を何度も書いた。幸いマグマの動きは止まったが、山頂での体験がなかったら、あれだけ危機感を持って報道しなかっただろうと思う。
この秘密は浜野さんには心苦しかったが、「10年経ったら告白しよう」と決めていた。
浜野さんと上木場の「定点」に行ったのは、この入域より3カ月後の94年2月末だった。上木場も警戒区域には違いないが、残った家財を持ち出そうと、隠れて入域する住民は後を絶たなかった。この点、山頂は意味が違う。こっそり登って写真を取る住民もわずかにいたが、生活には無関係の土地だった。
そこへぼくが登ることを決めたのは、江川紹子さんの影響も大きい。彼女と飲んでいて「住民が本当に知りたいことを報道しないと」と言われると、返す言葉がなかったのだ。西川清人さんにも「マスコミが警戒区域内のことを何も書かんけん、住民が入るんさ」と言われたことがある。
牟田警視が窮地に立ったのは、ぼくと山に登ってから5カ月後。長崎新聞は前隊長疑惑でキャンペーンを張る様子だった。「抜かれた」と思った他社も、「別のスキャンダルで抜き返そう」と取材合戦を始めた。
ぼくのことが明るみに出るのは、時間の問題に思えた。
新聞記者になったのは、事実を報道するため。まさか自分が書かれる側になるとは、思いもしなかった。
自分の取った行動にやましさはなかった。しかし、スキャンダルの続報で「前隊長、毎日記者を無許可でドームへ同行」という記事が他社の新聞に載れば、会社には相当迷惑をかける。きっぱり辞表を出す覚悟をして、上司になったばかりの柴田種明支局長にすべて話した。明日の朝刊に部下の名前を見つければ、赴任したばかりの柴田さんはびっくりしてしまうだろう。
柴田さんはフンフンと聞いた後で、「何かまずいことがあるんか。記者なら当然じゃないか。それより、なんでこんなに警察官が写真を買っているんだ。県警の管理体制のほうが問題だ」と答えてくれた。とりあえずホッとした。
問題は、この件をぼくがどういう立場で報道していくかだ。前線本部の机に向かいながら、いろいろなことを考えた。
牟田警視が写真を譲ったことは軽率だったかもしれない。それを転売した輩もいるらしい。しかし、無断で普賢岳に登って撮影し、写真を数万円の高値で売る不心得者は実際にいた。その裏には暴力団がいるという噂もあり、「牟田警視は自分の写真を実費で世間に出すことで、写真の価格を引き下げようとしたんだ」と見る関係者もいた。
しかし、毎日新聞が牟田警視の行動を突っ込んで報道していく過程で、他紙がぼくの名を出したら「あいつは自分を弁護したかっただけじゃないか」と思われるのは間違いない。毎日新聞自体の報道姿勢を疑われてしまう。
それなら、いっそのこと、開き直って自分で「私も行った」と書いてしまおうか? いや、それはまずい。登ったのはぼくの独断で、会社としての判断ではない。黙っているべきか。
数時間悩んだ後で、こう決めた。
「ただ批判したり、経過を客観的に書くのは簡単だ。
しかし、それでは読者は『牟田は裏でそんなことをしていたのか』としか思わないだろう。それは実像とまったく違う。牟田さんを見殺しにすることになる。自分かわいさにペンを折ったら、ぼくの記者生命も終わりだ。
ぼくが入域したことが出たら出たときのこと。どうせ辞表提出まで覚悟したんだ。なぜ牟田さんがああいう行動を取ったのか、実情を正確に伝えよう」
まず、翌日の朝刊長崎版にコラムを書いた。
一昨年秋、本紙1面に普賢岳の真っ赤な火口の写真が掲載された。見出しは「不気味な溶鉱炉 普賢岳今もなお」。
火山活動の監視のため、当時の島原署災害警備隊長が警戒区域で撮影した写真で、関東の友人から「今もこんなにひどいのか」と電話が来た。災害の長期化を訴えるすばらしい写真だった。
その前隊長が、同じ時期に撮った写真を市民に実費で譲り渡したとして、県警の内部調査を受けている。写真提供を受けた記者として複雑な気持ちだ。
「大部分は応援に来た警察官らが土産に欲しいというので焼いてくれと頼まれたものだった」と焼き付けた写真館の主人。譲ってもらった人は「断るのを無理に頼み込んだ。こんなことになり申し訳ない」と話す。
私も新聞に掲載された写真を譲ってくれ、と頼まれたことがあり、前隊長の気持ちは理解できる。
公私の区別は確かに指摘される。彼の仕事への情熱を知っているだけに、残念でたまらない。
(1993年4月9日、毎日新聞)
翌日各社の紙面はそれぞれだった。
朝日は社会面で「500枚売る」、読売の記事は地方版だったが、見出しは「前警備隊長、大量に売りさばく」ともっとも直裁的。九州ブロック紙の西日本新聞だけは「警視が有料で配布」と、冷静な筆致だった。
一方、長崎新聞は「知人の入域を黙認 別の民間人も同行?」と続報を打ってきた。記事には「前隊長が知人らを同行させて入域した、との関係者の話もある」とあった。
背筋が寒くなったが、もう引くわけにはいかない。ぼくも入域黙認の話は知っていた。長崎新聞に匿名で取り上げられた男性は、前章でもとりあげた、92年に山頂の写真を撮影して写真週刊誌「フォーカス」に提供、島原署に始末書を取られた人物だ。
長崎新聞によると、この人は93年にも山頂でばったり牟田警視と会ったことがあるという。ぼくが長崎新聞を見た朝、最初に詰問した男性だ。
彼は「この前登ったら、こがん太か亀裂があってな。突然ズボッと腰まで落ちて、やばいと思ったよ」とぼくによく話していた。「危険だからやめたほうがいい」と言ったが、すっかり火山の美しさの虜になっていた男性は聞く耳を持っていなかった。
登山口に警官が張りついたところで、地理にくわしい住民が監視の目を逃れて登るのは簡単だ。本当にやめさせるとしたら、警察は小さな抜け道まで24時間体制の監視をつけなければならない。それは事実上不可能だ。
前隊長「追及」キャンペーン
島原新聞の清水真守(まもる)記者も、一連の報道に憤っていた。「清水さん、島原新聞で主張せんですか」とぼくが言うと、同意してくれると思った清水さんは口をにごした。
「市民にこれだけ読まれている島原新聞が書けば、影響は大きいですよ」とさらに突っ込むと、清水さんは「うちはね、朝刊配達の多くを長崎新聞の販売店に頼っているんだよ」と苦しそうに言った。そうか、と思った。しかし、清水さんも悩んだ末、翌日紙面から論陣を張り出した。
「売る」と「譲る」では読み手の受ける感覚は天地ほども違う。
…(略)…
言う人に言わせれば、今回指摘されているのは「他愛もない事」。自分が生まれ育った故郷の安全確保のために昼夜の別なく走り回り、一方で写真提供など報道各社も世話になってきた経緯を秤にかければ、なんともペンが強すぎる。
余談だが、住民有志による「嘆願書」提出の動きも出始めてきた。
(1993年4月10日、島原新聞コラム「外野さじき」)
長崎新聞の報道には、牟田警視とともに火山と戦ってきた吉岡市長、横田町長をはじめ防災関係者の多くが「ひどすぎる」と眉をしかめていたのは事実だ。
特に反発を買ったのは4月10日付けの1面コラムだ。
警備隊長といえば、警戒区域への立ち入りなどを取り締まる最高責任者。ところが、ご本人は自由に入って迫真の写真をものにする。しかも公務中に撮った写真を大量に売っていた。
…(略)…
島原や深江では多くの被災者が苦しんでいる。警戒区域であるために自宅へ戻れず、家財道具も運び出せない。無念だろう。前隊長のカメラアングルには、被災者の心情など全く入っていなかったと見える。
(1993年4月10日、長崎新聞)
ある若い新聞記者は「事実と正反対だ。現地記者として怒りを感じる」とぶちまけた。
しかし、長崎新聞は記事を連発した。
追及第3弾は、あの紺のチームキャップを知人らに提供、販売したというニュース。「一部市民はその帽子をかぶり、警備隊と色彩が似通った作業服を着て、隊員と見間違う格好で、警戒区域に頻繁にはいるなど悪用していた」というのだ。
帽子ならぼくも持っている。牟田警視は2つ持っていたので、1つぼくにくれたのだ。「Yoshio Muta」と縫いとりまである。帽子は隊員のポケットマネーで作ったものだった。
その後の取材で、ぼくはこの帽子をかぶることにした。深江町役場に行くと、職員が「おっ」という顔でぼくの頭を見た。「おいおい、いいのか」と言う人もいたが、防災担当の職員は「俺も持ってるんだ」と出してかぶり、「ワハハ」と笑った。そして、「隊長の何が悪いのか、わからないよ」と言った。
机の上には、消防団が率先して始めた牟田警視の嘆願署名が広がっていた。
第4弾は「収賄疑惑」。
これが本当なら大変なことだが、警戒区域内の資材倉庫に放置されたまま、取りに行けなかった木材の運び出しを黙認、牟田警視らが火山を監視し、謝礼として「高価なテーブル」を受け取っていたというものだった。
テーブルについて、県内の大手業者に「ピンからキリまであり、現物を見ていないので一概には言えないが、天然木の1枚板製は商品化すれば10万円以上する。40~50万円が相場だろう」と語らせている。このコメントを理由に「高価」と書いたらしい。
しかし翌日、県警の記者会見を伝える長崎新聞の記事は、「テーブル(1~2万円相当)を業者から受け取った」となっていた。そのうえ、牟田警視はお返しに清酒5本をこの業者に贈っている。これは警官として当然の配慮だ。この記事を見て、柴田支局長が怒った。
「昨日と全然違うじゃないか。シレーッと値段を変えてる。毎日だったら訂正ものだ。牟田が名誉棄損で訴えたら勝てるぞ。神戸、こんな報道はいかん。よく覚えておけ」
市や町の職員、消防団員に長崎新聞の講読をやめる人が出始めてきた。彼らは「ノー・モア・ナガサキ」としゃれ、行く先々で不買運動を呼びかけた。ぼくは横からさりげなく「カム・バック・マィニチ」と続けた。他紙も、第1報以後は「追いかけるほどのニュースではない」と取りあわなくなっていった。
しかし一方で、新たな“牟田スキャンダル”を狙う社もあった。ぼくが聞いただけで、2社が「マスコミを内緒で登らせたのでは」という情報を追いかけていた。
各社とも警戒区域に入らないのは「自主規制」だったはずだ。それを問題にすること自体がおかしい。
しかし、自分の間近まで取材が迫ってきたときはさすがに焦った。事情を知る知人から「神戸ちゃん、もうやばいぞ」という連絡も入ってくる。
ここで江川紹子さんが島原にやってきた。
彼女に言わせれば、牟田警視は「警察の中じゃ、珍しく信頼できる人」。この騒ぎを知り、駆けつけてきたのだ。マスコミの報道姿勢を監視するのを得意とする彼女は、この問題を雑誌で取り上げるつもりだった。ぼくや清水さんの話を聞いて、彼女は言った。
「警戒区域に入れない、ってことがこの災害の最大の特徴で、みんなそれに苦しんできたんでしょ。なんの補償もなくて、法律に欠陥があることがわかってるんでしょ。
牟田さんがやったことって、警戒区域の荷物をなんとか出してやったり、法律の穴を埋めることばかりじゃないの。一番わかってるはずの地元紙が、なんでこんな記事を」
まったくその通りだった。
牟田警視に問題があるとすれば、柴田さんが指摘したように「写真を譲り受けたり、荷物を出させてもらったりした人が、全員ではなくて一部だったことが問題じゃないのか。どうせなら写真販売展やら、荷物運び出しデーとかすればよかった」ということではないだろうか。
テーブルを贈った男性に会いたかった。「もう新聞には何も言いたくない」という男性をなんとか説得し、江川さんと一緒にインタビューした。
彼の自宅は上木場だったが、家は残っていた。砂防工事で買収されるが、契約の前に火砕流で焼けてしまえば、土地しか補償の対象にならない。それで前年、安全を見計らって県職員と調査入域したのだという。
そのとき、警備していた牟田さんは「思い出深い品をこのまま残しておいたらもったいない。出すようなら連絡してくれ」と言った。
男性は「被災者の立場に立って、自分の身を張ってくれる人だった。その勇気に惚れた。私は隊長に甘えてしまったわけですよ。出した木材で、お礼のテーブルを作ったんだ。高価なテーブルなんてとんでもない。迷惑をかけてしまい、毎日寝られん」と頭を抱えていた。
嘆願署名と陳情団
江川さんや清水さんと毎晩「サンパン」で話し合った。同じ気持ちだったテレビ長崎の槌田禎子記者も長崎市から電話で参加し、情報交換した。
嘆願署名はものすごい勢いで集まっていた。島原市の吉岡庭二郎市長、深江町の横田幸信町長も名を記した。防災工事に反対していた住民は、敵対していた吉岡市長に面会を求め、「牟田さんを助けてやってくれ」と懇願した。
「長崎新聞はさすが地元紙だ。復興をめぐりあれだけ対立していた行政と住民を1つにまとめたんだからな」という皮肉を飛ばす防災関係者もいた。
九大観測所で一番若い研究者の馬越孝道助手は、取材に来た長崎新聞の記者に1時間近くも文句をぶつけた。「彼が書いたのじゃないことは知っていたが、我慢できなかった」という。
一連の記事の執筆者は、島原支局ではなく長崎市にある本社の記者だった。

まがまがしい噴気を放つ 溶岩ドーム
そのうち、「どうも牟田さんの処分が早まるらしい」「免職やむなしらしい」いう情報が飛び交った。署名集めに走る住民に緊迫感が走り、「署名の数を増やすより、処分が出る前に早く行動を」と県警本部へ嘆願に行くことが決まった。
長崎新聞本社前での抗議行動も検討されたが、共同通信の早崎貞俊さんが「ことを荒立てるとまずい」とマージャン仲間の石川嘉則深江町消防団長らを説得し、抗議行動は直前で中止された。
「疑惑」発覚から1週間目の4月14日。平日にもかかわらず、住民約100人がバス3台に分乗して長崎市へ嘆願に向かった。江川さんも同乗した。「このままでは余りです!牟田さんを助けて…」「牟田前隊長なくして島原の復興はない」などの横断幕も用意され、住民は県警本部の前で頭を下げた。
石川団長らが代表して7000人分の署名を小林徹警務部長に手渡したが、面会時間はわずか数分だったという。石川さんは涙を流して悔しがった。
「警察は本当に恐ろしかばい。署名を渡して頭を下げてお願いしたら、もうドアを開けて出ていけと言わんばかり。これまで生きてきて、あがん悔しかことはなかった」
牟田前隊長への処分
こうした県警の厳しい対応から、この時点で牟田警視に免職処分が出るのは、ほぼ確定的だったと推測される。
あるテレビ局は「悪いことをした警官を守るのはおかしい」と、嘆願運動があったこと自体を報道しなかった。これもおかしな話だ。問題はすでに住民を巻き込んだ社会現象となっていた。
ぼくはこの嘆願運動の深層を社会面で解説しようとしたが、「原稿が牟田側に傾きすぎて一方的だ」と加藤デスクから断られた。長崎支局に頼むと「署名記事ならいいだろう。明日の地方版を開けよう」と快く認めてくれた。
視点は「なぜ逸脱行為と批判される行動を牟田警視はとったのか。地元住民はなぜ擁護に立ち上がったのか」。
有明町の自営業者(43)は「警察が止めても、山に登りたい人は勝手に登る。写真を譲ったのも、登る理由をなくすためだった」とかばう。
…(略)…
地元では、前隊長への寛大な処置を求め、1市2町の消防団長が連名で作った嘆願書など、5種類以上の文書が出回っている。
ある消防団員(55)は「降雨で国道を通行止めにする場合でも、警察としてはすぐに止めてしまいたい。しかし、前隊長は半島の経済への影響を考え、ギリギリまで判断を待った。常に住民のことを考えてくれた人を見殺しにはできない」と署名集めに奔走している。
確かに警察官、しかも幹部として「逸脱行為」はあったかもしれない。しかし、一警察官へのこれほどの嘆願運動は極めて珍しい。
普賢岳災害を長期間取材しているフリーライターの江川紹子さんは「自然災害は法律など関係なく広がっている。前隊長はあえて規律を破ってでも、災害と直面する被災者の立場で行動したからこそ、住民内部からこれほど擁護する声が出た」と分析している。
(1994年4月15日、毎日新聞)
ぼくの記事が出た翌日、長崎新聞は「住民に波紋広がる」という分析記事を載せ、「地元では功績を踏まえ、“美談”として受け止める空気もある」と記したうえで、「職務と違法行為は別問題。問題のすり替えは決してできない」という警務部長のコメントを添えて反論してきたが、流れは少しずつ変わってきた。
ぼくの記事に続いて、まず西日本新聞が「災害が生んだ連帯意識 公私の区別希薄に」と分析、スキャンダルとは一線を画した見方を示した。
翌日、読売新聞が中立的に関係者のコメントを並べた。この中で、九大観測所の太田一也教授が寄せた「長期化するほど問題は複雑になり、通り一遍の規則では何もできなくなる。前隊長はきわどいまでもみごとな指揮ぶりだったが、島原市出身だけに、自分がやらねばという使命感が強かっただろう。心情的にその判断と行為を肯定する」というコメントは、嘆願運動を進める住民を強く励ました。
毎日新聞の長崎支局長も「処分に当たっては警察庁に相談しなければならないだろう。だが、中央に対する心遣い以上に、長崎に顔を向けた結論になることを切に願いたい」と長崎版の支局長評論で書いた。
江川紹子さんも島原新聞に署名記事を持ち込んだ。島原市内でどの新聞より読まれている島原新聞での3回連載は強烈なインパクトがあった。掲載は清水記者の大英断である。
彼女は、執筆した長崎新聞記者にまで取材している。彼の「牟田氏は島原出身だからもともと知人が多いし、そういう人は彼にとって悪いことは言わない。特別世話になった人も同じで、住民は口裏を合わせている」というコメントは読者の反発を買った。
報道されたことは、すべてがウソとは言わないが、事実を歪曲したり、ごく一部を誇張したりしたもので、真実の姿からはほど遠い。
体を張って住民のためにした行為が、マスコミから叩かれ、警察の取り調べを受け、職を脅かせるようなことがあれば、「上から言われたことだけをやればいい」という風潮が出てしまう。そうなった時、一番困るのは地元住民だ。
…(略)…
マスコミは犯罪者を作るのに加担すべきではない。
…(略)…
今回の一部報道には、コトを大きくしようという下心さえ感じる。こんなことを続けていては、マスコミは一般市民から垂離するばかりで、結局自分の首を締めることになるだろう。
(1994年4月19日~21日、島原新聞「牟田氏に関する一連の報道に思う」)
ぼくもコラムを長崎版に書いた。
島原署の前災害警備隊長の件で、嘆願運動をしている住民から取材本部によく電話がある。ありがたいことだが、朝早くかけてこられるとさすがに閉口する。
数日前、寝ぼけまなこで受話器を取ると、「あんたも前隊長に義理があるんだから、何か書けよ」と言われた。眠いところをベルでたたき起こされたせいもあって、「ふざけるな!」と大声を出してしまった。
記事を書くのは、書かなければならない必要があるから。恩義のあるなしで記事が左右されるなら、こんな怖い話はない。ここを踏みはずすと、偏見や悪意で書くのと同様、記事は“ペンの暴力”になる。
それにしても、「ふざけるな」とは失礼でした。私の記事が“暴力”となったことがあったかも。その朝、自分の声で目が覚めてから、しばらく自戒した。
(1994年4月19日、毎日新聞)
署名は最終的に2万人を越え、スキャンダルを追いかけていた社も、さすがに書ける雰囲気ではなくなった。
4月27日、県警は牟田警視の処分を「10%の減給2カ月」と発表した。牟田警視の行動は、欠陥だらけとはいえ警戒区域入域を禁じた災害対策基本法に触れる恐れがあり、処分自体はやむを得なかった。出世の道もかなり厳しくなったが、免職の方向だったのを住民パワーが変えたのは間違いない。
市役所で、町役場で、九大観測所で、寛大な処分を喜びあう光景が見られた。
6月になって、牟田さんから手紙が届いた。
異動後2ケ月が過ぎ、ようやく精神的にも落ちついてきました。
長崎新聞の報道の際には貴兄の理解ある記事でどれだけ精神的に救われた事か。すぐにでもお礼の電話をしたかったけど、住民運動も私がさせているのではないかと疑われる中では、とにかく静かにしているしかないと思い、礼状も遅くなってしまいました。
報道内容のひとつひとつにはかなりの誤解がありますが、今は弁解しません。落ちついたら警備隊の発足の経緯から説明し、私のとった一連の行動について理解してもらおうと考えております。
その前に会って話す機会があると思いますが、とにかく神戸ちゃんの記事で私の気持ちがどれだけ救われたか、その一言を言いたくてペンを取りました。本当にありがとう。感謝しています。
処分されたことについても後悔はしていません。自分の信じる事を、信念を持ってやった結果であり、自分自身の責任であるからです。
報道、防災、そして警察関係者には「災害でヒーローになってしまった牟田警視に対する県警内部の嫉妬が事件の原因だ」と推測する見方が強かったが、真偽のほどはわからない。
ただ、東京の警察庁でこの件を取材した江川さんは、島原新聞のコピーを手にした広報官から、「よく書いてくれましたね。警察の関係者から見れば、内輪もめだってことはすぐわかりますよ」と言われている。
彼女は「私はいつも警察の悪いことばかり書いているから、取材を断られることもあるのに。こんなに丁重に扱われたのは初めてだったよ」と電話越しに笑っていた。
「記事を書ける」ことの意味
「牟田事件」を通じてともすれば暴走しがちだったぼくの諌め役は、柴田支局長だった。長崎新聞の1面コラムに対して反論を書こうとしたとき、柴田さんは「ただ感情的にケンカを売るだけでは意味がない」とぼくに注意した。このとき言われたことははっきり覚えている。
「新聞という主張の場がお前にはあるが、ほかの人たちにそんな場はない。その場を使って言いたいことを言えば気分はいいだろうが、それでは紙面を私物化しているだけだ。お前は、あくまで毎日新聞の記者だから書けるんだ」
その通りだった。
報道部の加藤デスクが原稿を突っぱねたのも「一方に偏している」という理由だった。「現地では偏っているわけではなく、こちらのほうが真実なのだ。ただ両論併記するだけでは事実とずれる」とそのときは立腹したが、加藤さんの言うことももっともである。紙面は島原の人たちだけが見るわけではないのだから。今となってみれば、上司たちの言うことは十分理解できる。
この牟田事件の本質は、不備な法律の下で長期災害に苦しむ被災地の矛盾そのものだったのだと思う。警戒区域の設定という「異常事態」でなければ、牟田さんの行動もなかったのである。
長崎新聞の報道には、「売りさばく」という言葉に象徴されるように煽動的な面がたしかにあった。牟田さんの行動を、もっと冷静に分析して批判する姿勢であったら、「やむを得ない批判」として住民にも受け入れられたのではないだろうか。もし、その視点で特ダネを書かれれば、ぼくも同じように追いかけざるを得なかったはずだ。
住民があれだけ熱を入れて牟田さんを守ろうとしたのは、彼の行動が感情として理解できたからである。それは、「自然災害には補償はありえない」という国の頑なな態度への反発でもあったのかもしれない。
「警戒区域に立ち入ってはならない」という形式論だけで批判された牟田さんの姿は、長期災害を想定していない法律の条文に切り捨てられていく被災地の姿とオーバーラップしたのではないか。今となって振り返ると、そう思えてならないのだ。
処分が発表された後で、1200人ものユダヤ人をナチスから救った実業家、オスカー・シンドラーを例に上げて、長崎版に最後のコラムを書いた。ユダヤ人の命を救うため、シンドラーが取った手法は、まさに違法な賄賂だった。
彼もナチス体制という「異常事態」の中で、平時ならとても許されない一線を何度も越えた。今、歴史はナチスを裁き、彼の行動を認めた。
(1994年4月28日、毎日新聞)
牟田さんの「逸脱行為」への批判は十分になされた。
もう彼の名誉を回復する時期だろう。在任中、土石流で1人の死者も出さなかったことは、きちんと評価されるべきだと思う。
そして、ぼくにとってもこの騒動は忘れられない。
書かれる側に立つ恐怖と不安を嫌というほど味わい、「不祥事」を起こした警官の行動を是認する方向でペンを執った。ともに新聞記者として極めて珍しい体験である。
1994年4月、島原は熱かった。
(第9章 了)
『雲仙記者青春記』第10章「被災地に生きる」に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
