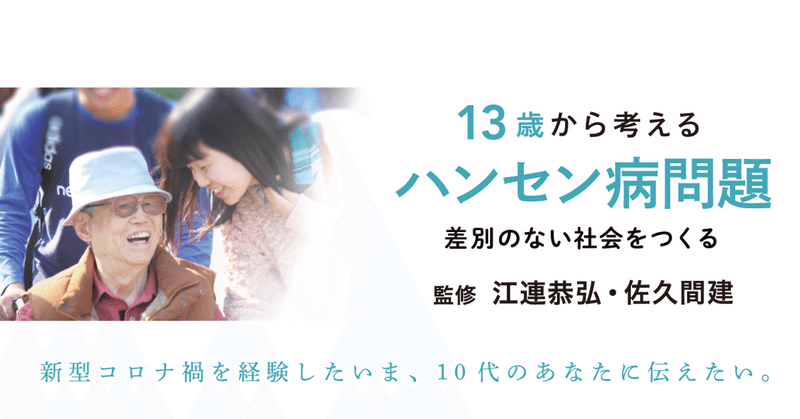
連載⑧ 胎児・臓器標本の謎 ―― これほどの人権侵害があるのか(2)
今年5月、江連 恭弘・佐久間 建/監修『13歳から考えるハンセン病問題 ―― 差別のない社会をつくる』を刊行しました。(以下の本文では『13歳…』と略します。)
編集を担当した八木 絹(フリー編集者、戸倉書院代表)さんに、本に寄せる思いを書いていただきました。不定期で連載します。

解剖と臓器標本―― なぜこのようなことが……
検証委員会による胎児標本調査が行われる中で、各地の療養所には死亡した患者・回復者を解剖して摘出した臓器等が保管されていることがわかりました。その数2000体超。保管方法も、胎児標本と同様に杜撰で、一つのバケツに多くの臓器等が入れられ、個人情報もつけられていないものが、複数の施設で多く見られたといいます(「別冊報告」)。
長島愛生園と邑久光明園(おくこうみょうえん)(岡山県瀬戸内市)の1980年ころまでの解剖遺体数は、死亡者の90%以上に相当していました(「別冊報告」)。邑久光明園ではその後調査を進め、2022年11月に報告書を公表。同園が開園した1938年から98年までの死亡者の71%にあたる1184人が解剖されていたとしています。
菊池恵楓園でも、2020年、1911年から65年までに、少なくとも389人が解剖されていたという調査結果をまとめています。
一般に、手術などで摘出された臓器等は、病因を調べるために病理標本を作成し、検査・研究に使用しなかったものは、医療廃棄物として適法に処理されるのが医学的常識です。それがそのまま長期にわたり大量に保管されるのは、常軌を逸しています(「別冊報告」)。
この事実は衝撃的で、なぜこのようなことが起こったか、想像すらし難いものです。「別冊報告」は、臓器標本の作製に関しては、光田健輔が病理学者であった事実が大きな影響を与えたこと、光田を慕って多くの医師がハンセン病に関わるようになったことを指摘しています。そして、2つの文献が引用されています。
「解剖は光田門下生にとって、この上ない重要な学問であった。不幸な病友は癩のほかに種々の余病を併発するのである。なかでも、結核、腎臓、肺炎などの死亡率が高い。その遺体の一つ一つが私たち医局員の貴重な研究資料として提供された。それは日曜日だろうと祭日だろうと敢行された」(桜井方策編著『救癩の父 光田健輔の思い出』ルガール社、1974年)
もうひとつは、神谷美恵子医師(精神科)が医学生だった1943年の夏休みに、光田が園長を務める長島愛生園で実習した際の回想です。
「患者たちは食糧自給のために無理な労働を余儀なくされ、平均2日に1人は死んで行った。そのつど、解剖が行われる。〔…〕立川先生は言う。『しかし、自分のみた患者は必ずあとで解剖するんですからね、いい勉強になりますよ。何しろ臨床診断と解剖の結果とがあまりちがうと園長のごきげんが悪いんでね。医局にはいりたての者はビクビクもんですよ。だからここでは臨床の腕は非常に上がりますね』」。神谷はその後解剖を見学。執刀していた光田が語ります。「何しろ昨日解剖で見られた通り、ここには研究の材料が無限にころがっているんですからね。ただそれを使う人がないばかりに、むざむざ放って置くだけなんだ」(神谷美恵子『新版 人間をみつめて』朝日選書、1974年)
患者をたんなる材料として扱う医師たち。そこには人間としての尊厳などというものはありません。第二次世界大戦のとき、陸軍に存在した研究機関・731部隊(関東軍防疫給水部本部)が、捕虜を「マルタ」と呼び、人体実験をしていた事実を想起してしまうのは、私だけではないでしょう。
解剖された患者の遺族のたたかい―― 木村仙太郎の生存記録を追う
この問題に遺族として立ち向かっている人がいます。木村真三さん(獨協医科大学准教授)です。愛媛県出身。祖父の兄・木村仙太郎さんがハンセン病患者でした。仙太郎さんは30年間自宅療養していましたが、1948年、ハンセン病療養所に入所します。ハンセン病と診断されたあと、離婚せざるを得なかったのではないかと真三さんは考えています。木村家に後継が不在になったため、真三さんの祖父が後を継ぎます。「癩病患者を出した家」として、過酷な差別を受けたといいます。
放射線衛生学者である真三さんは、チョルノービリ原発事故、福島第一原発事故の調査に関わり、福島の人たちへの差別と向き合う中で、ハンセン病差別と通底すると感じ、仙太郎さんの行方をたどることにしました。

(写真:木村真三氏提供)
真三さんは、仙太郎さんが入所したのが長島愛生園だとつきとめ、遺族として資料の開示を請求。そこにあったのは、仙太郎さんが入所後わずか2年で結核で死亡し、その後解剖された事実でした。死亡時のカルテには、入所時にはなかった褥瘡(じょくそう)の所見があったことから、入所してから結核の病状が悪化し、寝たきりにさせられていたことが推測できました。そこに貼られた写真は、真三さんが初めて目にした仙太郎さんの姿でした。亡くなる直前に取れるはずのない解剖承諾書も存在していました。
2021年3月、長島愛生園の開園翌年の1931年から56年までの死亡者のうち、少なくとも1834人の解剖録が存在することが確認されました。32冊の書物に立派に製本されており、解剖の日付や入所者の名前、手書きの検体図などが記されていました。廃棄予定だったものを、同園の非常勤の医師が「入所者の生きた証」として、10年以上保管していたのです。
そこには解剖への同意を示す書類も存在していました。同意の日付の多くは死亡の3〜7日前で、当時の医師と類似した筆跡もありました。存命の入所者が「(懇意の入所者が亡くなった時)園側から代理での同意を求められて応じた」と証言しています(朝日新聞デジタル、2021年3月26日付)。これまで、全国の療養所入所者の多くが、入所時に解剖承諾書に署名させられたと証言していましたが、死亡時に解剖同意書が捏造(ねつぞう)されていた疑いも生じているのです。
こうした事態を受けて、木村真三さんは、長島愛生園の解剖録の分析を行うことを園に申し出ました(愛媛ニュースウェブ、2023年7月12日付)。解剖録から、戦前、戦中など時代別に無作為に抽出し、個人情報を削除した形で提供を受け、時代ごとにどのような医療行為が行われていたかなどを、カルテと合わせて分析することにしています。
企画展「蘇るハンセン病患者とその家族 ―― 木村仙太郎の生存記録:長島愛生園 1939−1941」
と き 2023年7月25日〜12月26日
ところ 重監房資料館(栗生楽泉園内、群馬県吾妻郡草津町草津白根464−1533)
入場無料 月曜休館
◉次回の連載予定
最終回 療養所のこれから(多摩の住民として)
*本稿は、多摩住民自治研究所『緑の風』2023年11月号(vol.280)にも掲載されます。

『13歳から考えるハンセン病問題 ―― 差別のない社会をつくる』
クリックすると購入ページにとびます

◉『13歳から考えるハンセン病問題―差別のない社会をつくる』目次から
第1章 なぜハンセン病差別の歴史から学ぶのか
ハンセン病患者・家族が受けた激しい差別/ハンセン病とはどんな病気?/新型コロナ差別にハンセン病回復者からの懸念/過去に学び、今に生かす
第2章 ハンセン病の歴史と日本の隔離政策
日本史の中のハンセン病/世界史の中のハンセン病/日本のハンセン病政策/日本国憲法ができた後も
第3章 ハンセン病療養所はどんな場所か
ハンセン病療養所とは?/療養所内での生活/生きるよろこびを求めて/社会復帰と再入所
第4章 子どもたちとハンセン病
患者としての子どもたち/家族が療養所に入り、差別された子どもたち/生まれてくることができなかった子どもたち
第5章 2つの裁判と国の約束
あまりに遅かったらい予防法の廃止/人間回復を求める裁判/家族の被害を問う裁判
第6章 差別をなくすために何ができるか
裁判の後にも残る差別/菊池事件 裁判のやり直しを求めて/これからの療養所/ともに生きる主体者として学ぶ
