
連載⑦ 胎児・臓器標本の謎 ―― これほどの人権侵害があるのか(1)
今年5月、江連 恭弘・佐久間 建/監修『13歳から考えるハンセン病問題 ―― 差別のない社会をつくる』を刊行しました。(以下の本文では『13歳…』と略します。)
編集を担当した八木 絹(フリー編集者、戸倉書院代表)さんに、本に寄せる思いを書いていただきました。不定期で連載します。

115体の胎児標本が見つかる
「『らい予防法』違憲国家賠償請求訴訟」で国の責任を認める熊本地裁判決(2001年)を受けてつくられた「ハンセン病問題に関する検証会議」が、全国のハンセン病療養所と研究施設を調査したところ、115体(*1)の胎児標本が保管されていることが判明しました(以下は、「検証会議最終報告書 別冊 胎児等標本調査報告」、05年3月、〔「別冊報告」〕を主に参照しています。全文はウェブ上で閲覧可能)。
*1 報告書が出た後にさらに1体見つかったことから、ここでは115体としました。
胎児標本があったのは、国立ハンセン病療養所5園とハンセン病研究センター(東京都東村山市)の合計6カ所。ここに含まれていなかった沖縄愛楽園(沖縄県名護市)の元職員が、1980年代に同園南東部の浜で胎児標本を火葬したという証言をしています(「琉球新報」デジタル、2023年6月17日付)。このように、ほかの全てのハンセン病療養所にも胎児標本があったと考えられます。
これらは、人工妊娠中絶手術で母胎から摘出され、ホルマリンづけにされた胎児です。標本の作製時期は1924年から56年の32年間で、最も多いのは36〜45年ころ。50年以上施設内で保管されていました。
連載⑤⑥でも言及した光田健輔(みつだ けんすけ)医師は、全生(ぜんせい)病院(東京都東村山市、現多磨全生園・たまぜんしょうえん)の院長だった1915年に、ハンセン病患者に初めて断種手術(男性への不妊手術)を行い、その後全国の療養所に広まります。ほぼ同時期に女性への妊娠中絶手術も開始されたと推測されます。したがって、標本は24年以前にもつくられ、それらは解剖され研究に使われたため残っておらず、戦争期に研究に利用する医師が減ったことから、その後は標本がつくられただけで放置されたと考えられています。標本の半数には個人情報の記録がありません。体長から推測して妊娠32週(8カ月)以降の胎児が約25%、36週(9カ月)以降が14%でした。妊娠37週から41週が正期産なので、出産まぎわでの妊娠中絶です。「胎児を引っ張り出したらもう大きくなっており、一人前に声をあげて泣いたのですが、婦長はこの子どもを私の目の前でうつぶせにし、押さえつけて殺してしまいました」という証言が多くあります。

各療養所に慰霊碑が建立されている(筆者撮影)
胎児標本の状態は、研究や実験に使用したとすれば残るはずの切開痕や臓器摘出の痕跡がないものが80%でした。標本化の目的は何だったのでしょう。中には、無惨に両眼だけくりぬかれたものもあり、「解剖の常識を逸脱した」「生命そのものの尊厳をいたく冒涜(ぼうとく)」(「別冊報告」)するものが含まれていました。
保管方法は杜撰(ずさん)で、ポリバケツに複数の標本が雑然と入れられ、その存在すら忘れられていたものもありました。空調のない、夏冬の温度差が激しい環境下で保管され、ホルマリンが蒸発し、ミイラ化した胎児も多数ありました。
発見当時、この事件は国会でも取り上げられましたが、標本が最後につくられた1956年から年月が過ぎ、殺人罪の時効が成立していたことなどを理由に、厚生労働省は自らの組織の医師・看護師らを刑事告発しませんでした。
1944年に星塚敬愛園(鹿児島県鹿屋市)に入所したAさんは、妊娠7カ月で人工妊娠中絶させられ、胎児を標本にされました。しかし35年間、その事実すら知らされていませんでした。あるときAさんは、施設内で偶然、自分の名前が貼られた胎児標本を見つけます。Aさんは同じように子どもを奪われた母親たちとともに、「家族として自分たちに供養をさせてほしい」と、1万6000筆の署名を集め、厚労省に提出しました(Aさんの事柄については、樫田秀樹「わが子をこの手に取り戻したい」『週刊金曜日』2006年5月19日号参照)。しかし、標本のほとんどは、療養所ごとに国によって火葬されてしまったのです。
『13歳…』では、強制堕胎で子どもを失い、菊池恵楓園(けいふうえん)(熊本県合志市)で、人形の「太郎くん」とともに暮らす女性を紹介しました。全国の療養所には、このような高齢の入所者が多くいます。生まれることすら許されなかった子と、子を失った親の無念を思うと切なくて、私はハンセン病療養所を訪れるときには、必ず胎児慰霊碑に手を合わせています。
なぜ強制堕胎が行われたか―― 優生思想とハンセン病
では、なぜ強制堕胎が行われたのでしょうか(以下の記述は、主に「検証会議報告 第七 ハンセン病政策と優生政策の結合」を参照)。

1909年、癩(らい)予防法に基づいて開院した全生病院医長に光田健輔が着任。光田は患者の結婚を認めず、男女の居住区画を分けることを主張しましたが、女舎(おんなしゃ)を板塀で囲う程度しかできず、思惑通りにはいきませんでした。生まれた子どもは、光田が私費で里子に出したり、親が東京市内まで捨てに行ったりしていました。
そこで光田は、患者管理の手段として性欲を利用することにします。男女一緒に収容し、療養所の患者作業を性別役割分業的に行うことで、経費を節減する意図もありました。アメリカで始まっていた男性への精系離断法(断種手術)をハンセン病患者に開始。同意なく行えば、断種手術は刑法の傷害罪、人工妊娠中絶は堕胎罪に問われる恐れがあることから、同意を虚構しながら行った強制断種、強制堕胎でした。

日本は台湾・韓国の植民地でも国内と同様の療養所運営をしていた
(写真:延和聰氏提供、2001年撮影)
こうした政策の背景には、19世紀後半にヨーロッパで広まった優生思想があります。「悪質」な遺伝形質を「淘汰(とうた)」し、「優良」な遺伝形質を保存することで、集団の遺伝的な質を向上させようというものです。ハンセン病患者は「社会的低格者」で「民族の衰退」を促すとされ、生殖に介入してでも「発生予防」すべきと考えられていました。遺伝病でないハンセン病の患者に断種手術をすることが正当かの検討はされず、その理由は、ハンセン病患者の子が社会生活を営むのが困難で、悲惨な状況になるからという点と、ハンセン病にかかりやすい体質の遺伝を防止する点に求められたのです。
日本政府は1940年、ナチスドイツの「遺伝病子孫防止法」を参考に国民優生法をつくり、「遺伝性精神病」「遺伝性身体疾患」「遺伝性奇形」など5項目を指定し、人工妊娠中絶を合法化しました。同法案作成にはハンセン病患者の断種の実態が参考にされたといいます。
そして戦後の48年、「不良な子孫の出生を防止」することを目的とする優生保護法ができました。戦前の国民優生法の規定に加え、任意の優生手術を認める対象に「本人又は配偶者が、癩疾患に罹(かか)り、且(か)つ子孫にこれが伝染する虞(おそ)れのあるもの」(第3条3項)として、遺伝病でないハンセン病を追加し、同じ理由で人工妊娠中絶も認めたのです(第12条)。これによりついに、ハンセン病患者への断種・人工妊娠中絶の手術が合法化されます。
すでに治療薬プロミンが開発され、投与が始まり、ハンセン病は治る病気になっていました。表面上の理由は「幼児感染を防ぐこと」とされました。しかし、その40年も前の1909年、第2回国際らい学会で、幼児感染を防ぐためには出産後に親から分離すればよいと勧告されていたのです。人権を無視し健康を損なう断種や妊娠中絶を日本でなぜ強制し、嬰児(えいじ)殺しまでする必要があったのか。その目的はハンセン病患者を未来永劫(えいごう)、絶滅させることだったのです。
らい予防法が廃止されたのと同年の96年に優生保護法が廃止(*2)されるまで、ハンセン病を理由とする断種手術は1400件以上、人工妊娠中絶手術は3000件(*3)以上行われました。
*2 優生保護法から優生思想に基づく部分がなくなり、母体保護法となった。
*3 件数は、「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟熊本地方裁判所判決(2001年)から。
★本稿は、多摩住民自治研究所『緑の風』2023年11月号(vol.280)にも掲載されます。
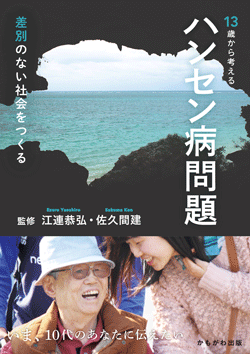
『13歳から考えるハンセン病問題 ―― 差別のない社会をつくる』
クリックすると詳細ページにとびます

◉『13歳から考えるハンセン病問題―差別のない社会をつくる』目次から
第1章 なぜハンセン病差別の歴史から学ぶのか
ハンセン病患者・家族が受けた激しい差別/ハンセン病とはどんな病気?/新型コロナ差別にハンセン病回復者からの懸念/過去に学び、今に生かす
第2章 ハンセン病の歴史と日本の隔離政策
日本史の中のハンセン病/世界史の中のハンセン病/日本のハンセン病政策/日本国憲法ができた後も
第3章 ハンセン病療養所はどんな場所か
ハンセン病療養所とは?/療養所内での生活/生きるよろこびを求めて/社会復帰と再入所
第4章 子どもたちとハンセン病
患者としての子どもたち/家族が療養所に入り、差別された子どもたち/生まれてくることができなかった子どもたち
第5章 2つの裁判と国の約束
あまりに遅かったらい予防法の廃止/人間回復を求める裁判/家族の被害を問う裁判
第6章 差別をなくすために何ができるか
裁判の後にも残る差別/菊池事件 裁判のやり直しを求めて/これからの療養所/ともに生きる主体者として学ぶ
