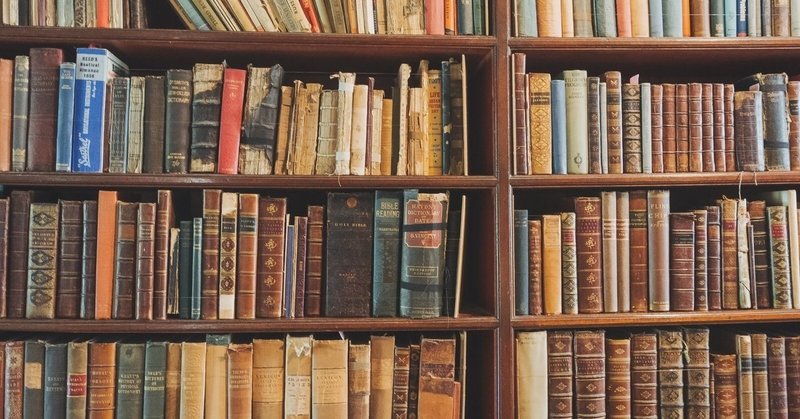
情報と解釈のバランス
おはようございます、神島竜です。
以前の記事でネットで読書の感想を発信することについて話しました。
今日は、発信するにあたっての注意しなければいけないことについてはなします。
それは、インプット中の情報と解釈のバランスには気をつけなければいけないという話です。
一昨日の記事で、脳みそを一つの部屋としてたとえました。
その部屋にはプリンターがずっと稼働していて、放っておくと紙がどんどん貯まる。だからこそ、脳の何かしらの部位が印刷された紙を書き足したり、整理したりする。
僕も脳の専門家じゃないんで、どの部位がそれをするかは知らないので、仮にこれを頭の中の執事と言い換えましょう。
プリンターから印刷された紙が情報です。その情報に意味を持たせるために執事はその紙に書き足します。これが解釈。情報と解釈が合わさって本棚に入ることで一時的な記憶となり、それが何度も引き出されることで優先順位が高くなり、いつでも使えるものになります。
僕たちはある程度の解釈力があることで、暗黙の了解や説明のない描写でも何かしらの意味を読み取れます。しかし、だからといってこの解釈力だけを高い状態でインプットをすると、誤読や誤解を重ねてしまいます。
何かを学ぶ時は、目の前の情報だけを記憶して、人に発信するときに、自分は解釈を一つの情報にどれだけしているかを意識してください。
もし、それで2割以上の解釈で人に話している場合は注意が必要です。その解釈が話していくうちに3割、4割となって最終的にすべて解釈だけで物事を話す日が来るかもしれません。そしたら、その解釈は妄想になります。
頭のいい人でも、頭の中だけの考えを過信しすぎると目の前の情報を捻じ曲げてしまうこともあります。
解釈は道具であって個性ではないんです。
なにかをインプットしたり、アウトプットする時は気をつけましょう。
頂いたサポートは本に使います。
