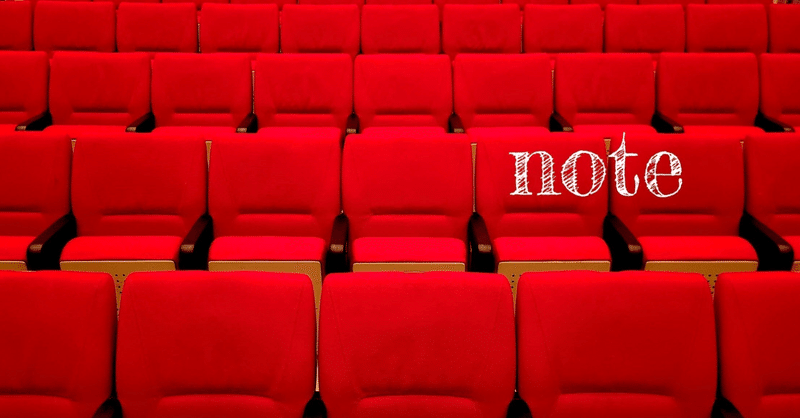
演劇の感想:『VR 能 攻殻機動隊』|『さんかく小屋のフェイ』(明・飛世ver)|ポケット企画×あづき398『ゆうむすぶ星』
『VR 能 攻殻機動隊』
1月15日(土)16時/札幌・hitaru
大好きな攻殻機動隊と、今をときめくVRと、日本伝統の能。個人的に興味のある三つが融合している様を、ぜったいに見ておきたいと思った。そして、見てよかった。
攻殻機動隊シリーズで一番有名(ぼくもそこから入った)なのは、アニメシリーズの『SAC』だと思う。特徴としてはSF的要素を前面に出していること。『ARISE』や『2045』なんかもそんな感じ。原作では精神的な部分というか、スピリチュアル的要素が強かったりする。耐性のない人には、アニメでも十分強いかもしれないけど。
今作は割と原作に近いトーンで、能との食い合わせがいいんだと思う。たぶん。能について詳しければ、もっと楽しめるんだろうな。ただ、不勉強なぼくだからこそ「能を見たぞ!」感があって楽しめた。きちんと攻殻としても成立してた気もする。
VRも含めてこの3つの融合は、なんていうか「これ以外ありえないな」っていう組み合わせだと思う。企画した人すごい。テクノロジーと物語のかけ算で、もうエグい相乗効果がある。そしてそれが(たぶん)能のトーンにもなっている。もう一回見たい。
どうでもいいんだけど、「素子は何処」ってセリフ聞くだけで、「あ、こいつバトーやん」って分かるのすごい。
VR。これは今まで「生み出す」技術だと思っていたんだけど、今作を見て「消す」技術なんだと思った。まず舞台上にあるVR映像は、実体のある演者と見分けがつかない。実はひとりも実体はいないのではと疑うくらいには。実物と虚像が違和感なく混ざり合った状態から、ふっと消える。しかも実物だと思っていた方が消える。これがエグい。攻殻との親和性が高い部分でもある。
消えているのはもちろん映像なんだけど、実体が消えたのかもしれないという体感が、現実感を消していく。これは個人的な感覚だけど、実体の価値というか、実体である必要性みたいなものが消えていった感じ。目の前のこれが肉体でも幻でもどちらでもいい、という感覚になる。それでも目と脳は区別をしたがるもので、その度に裏切られての繰り返しだった。幻に実体感を与えて現実に馴染む技術だと思っていたVRは、結果的に、現実の実体感を消すことでリアルと溶け込む技術だった。
舞台上に美しいものが現れて、ただあって、消えていく。その瞬間を見たいと思う。し、それは能の専売特許な気がする。実体と虚像、現実と仮想が混ざる。これは攻殻の得意技。その融合は、そりゃあおもしろいよな。
さんかく小屋のフェイ(明・飛世ver)
ゲネプロ/札幌・BLOCH
リハーサルを観劇。元は長谷川健太・寺地ユイペアのために町田さんが書き下ろした脚本。逸人さんと早哉香さんペアの上演にあたって、ところどころ書き換えられていた。
短いこともあって話はかんたん。兄妹ふたりは今は敵国同士の人間で、面会室でのみ会える環境。仕事を辞めては探す妹と、国のために戦う兵士の兄。むかし話で開戦のころを思い出す。ふたりはまだ幼く、自転車で、フェイが管理する小屋に向かっていた。爆撃に遭いながらたどり着いたさんかく小屋。まるい窓から見えた町の惨状。フェイは「忘れるな」と言った。言っていたね、なんて思い出した。それから兄は妹に「話をしよう」と切り出す。むかしばなしむかしばなし。
ラストの落としはどんなメッセージなのか、見ているときは気づけなかったけど、“アクリル板=境界”に対するアクションなのかも。アクリル板に向かって放つ、兄の「ジャマだな」とか。
敵国との面会にアクリル1枚ってどうなのとか、軍情報漏らして警告音で済むのはどうなのとか、面会室に銃を持ってきちゃうのとか。パッと見で気になることが多かった。それほど切羽詰まった状況下だとも思える。ふたりは、なんだかんだと和やかに話をしているけど、実はそれどころじゃないんだ。兄も、妹も。
仕事を辞めたという妹も、自ら辞めたのかどうか分からない。本当は戦争のせいかもしれない。国のために戦うという兄は、本当は戦わさせられているのかも。舞台上の違和感が、現在を疑わせる。だからこそふたりの、過去へのあこがれに共感できる。ふたりは取り戻したいだけだ。ただ、なにを取り戻したいのか忘れている。さんかく小屋のフェイは、取り戻したいものは何だったかを取り戻す話。令和って感じ。
それから、ふたりは嘘をついている。と、ぼくは感じる。逸人さんと早哉香さんは、嘘つきに見える。悪い意味じゃなくて、すごいことだ。彼らがかぶる仮面はいつも、人間臭くて泥まみれだ。それなのに心には迷いがない。迷いを表に出すことにも迷いがない。だから違和感がある。そんなに弱い人間が、ずいぶん強いじゃねえか、と。
ふたりの言葉の多くは、ぼくには嘘っぽく聞こえる。取り繕っているように見える。ふたりは、親しげに話しているけど、たぶんそれは本心じゃない。心の距離感を、もう忘れてしまったのかも。憎んでいるとか、関心がないとかじゃなく、数年ぶりに会う親戚と話す、あの感じ。しかもそれが別の親戚の葬儀だったりして、話題にも困る。「最近、天気ひどいね」みたいな当たりさわりないことしか言えない。そういう現在地。
ふたりは未来へ向かうために、過去を思い出そうとしているのかな。ここではじめに書いた、兄の「話をしよう」を思い出す。彼がアクションした「境界」はなんだったのか。物理的には「国境」。あるいは精神的な距離。その距離を大きくしているのは、記憶の境界。むかしは良かったよね、もうよく思い出せないけど、という境界。
『さんかく小屋のフェイ』は、ずいぶん令和的だなと。というか、コロナ禍って感じ。ニューノーマルだと言われて、意外とそんな生活も悪くないよねと思いはじめ、でもやっぱり人にふれたい。そのときにはもう、どんな会い方をしていたか分からない。そういう人も多そうだ。
ぼくの記憶のなかのフェイは、なにを見ているだろう。人のいなくなったすすきの交差点とかかな。そう思うと急に、胆振東部地震のことも思い出したりするのだけれど。
ポケット企画×あづき398『ゆうむすぶ星』
2月27日(日)17時/札幌・ことにパトス
今回は読めるタイトルだ。「ゆうむすぶ」という言葉ははじめて目にした。「糸遊結び」という言葉があるらしいが、関係あるのだろうか。なんにせよ、やさしく、それでいてキュッと固く結ぶ。そんなイメージのある言葉で、とてもうつくしいタイトルだ。
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』をモチーフのひとつにしているとのことで、開場中に星めぐりの歌が聞こえる。いつも思うのだけど、なにかをモチーフにした作品って、それを知らない人のことをどこまで考えるべきだろうか。知っていても、知らなくても楽しめる。それが理想的なのかもしれない。でも、知ってる人にしか伝わらない感動を分かち合う、秘密の関係性をつくりたい。そんな気持ちにもなるんだよな。
言葉遊びとはなんだろうか。音で遊ぶことか、意味で遊ぶことか、どちらもか。今作は音で遊んでいた印象。耳触りが気持ちいい。じゃあ音ってなにかって、リズムとメロディと言葉だ。ここに体も音楽性をもって乗っかってくるから、『ゆうむすぶ星』は視覚的なオーケストラみたいだった。うつくしいハーモニーは、それだけで人を感動させる。
一方で、ポケット企画推しのぼくとしては物足りなさがある。作品がきれいすぎる。これまでのポケット企画作品には、作家・演出家・俳優が好き放題で、表現がどこへ向かうのか分からない危うさがあった。この不安定さが、次の瞬間を見続ける強い動機になっていた。
ところが『ゆうむすぶ星』は安定していた印象だ。悪いことじゃない。でもぼくとしては、手放しで良いとも言えない。『エダニク』の感想にも似たようなことを書いたが、上手にできたらおもしろくなるわけじゃない、とぼくは常々思っている。
同じ方向を見ることはものづくりに必要だ。それは集団の方向性を確かにしつつ、しかし、個性のゆらぎみたいなものを失わせる。作品の中身ではなく、チームづくりの話だと思う。良いチームには、カオスがあるといいな。
とはいえやっぱり次作も見たい注目の人たちだ。ポケット企画だけじゃなく、あづき398もとても好き。みんな間違いなくおもしろいし、少なくともぼくより演劇に詳しいと思う。新しいエネルギーが、これからも新しくありつづけてくれたらうれしい。とともに、俺だってなんかしなくっちゃなぁと、あらためて。
購入&サポート、いつもありがとうございます!すごく励みになります。 サポートいただいた分で、楽しいことをつくったり、他の人のよかった記事をサポートしたりしていきます!
