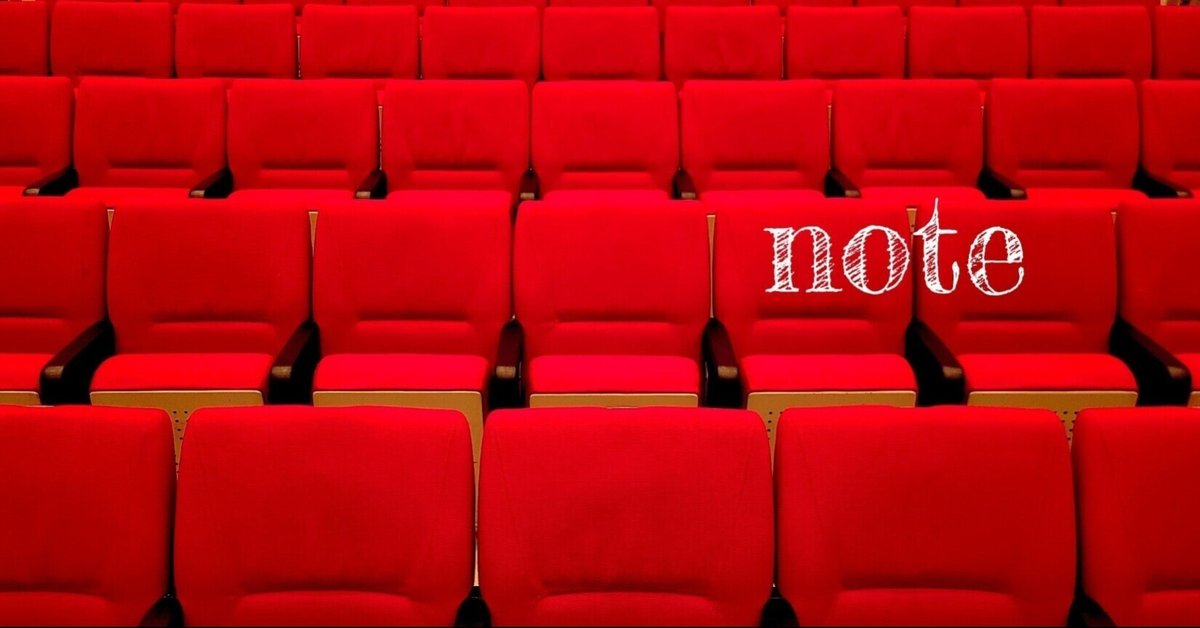
演劇の感想:劇団fireworks『畳の上のシーラカンス』|ポケット企画『受付』|劇団words of hearts『ニュートンの触媒』
劇団fireworks『畳の上のシーラカンス』
7月4日(日)12時/札幌・BLOCH
だいたい90分くらい。休憩込みで100分くらい。作品の良さもあって、もう少し見ていたいと思う、ちょうどいい体感時間だった。
1991年、平成3年を主な舞台にして、さらに昔と今(2021年)がすこしずつ交じわる。フォークソング、共同アパート、夢を追う若者など、ノスタルジックな気持ちを叩き起こして、ファイヤーワークスの真骨頂、ちょっとしたファンタジーで味付け。とても気持ちよく見終わった。
NHK連続テレビ小説とか、24時間テレビのスペシャルドラマとか、そういう感覚。優しくて、個性的な人たちがたくさんいて、憎たらしいやつはいるけど、悪人はいない。リアルなドラマじゃなく、あくまでフィクション。でも、ああこの世界に入ってみたいと思うような、すてきなフィクションだった。
昔は良かったな的な感情になるのは、正直あんまり気持ちよくはないけど、この作品はきちんと現代に終わりを持ってきていて、それが良かった。いま、楽しそうに生きているおじさんおばさん達は、もしかするとああいう青春時代を過ごしていたのかもしれないなぁ。
どうでもいいんだけど、1991年当時大学院生だった桜子さんが、2021年にノーベル賞を受賞しているのはすごい。めっちゃ若い。しかも日本人女性では初のノーベル賞受賞だ。きっとメディアはとんでもなく盛り上がっていると思う。そりゃひよどり荘も取材とかされてるんだろうな。
女性が科学者で、男性が小説家という組み合わせ。当時の女性の大学進学率はどのくらいだったんだろう?主人公の小説家ではなく、その隣の部屋に住んでいた法学部の学生と結婚している女性科学者。ほんのりとビターな味付けが最近のfireworksには多い気がする。それとも昔からそうなのかしら。
コメディですって言っていたけど、コメディなんだろうか。コメディってなんだろう。悲劇の対称としての喜劇、という元の意味に近いコメディなんだろうなきっと。閉塞感のある現代に、フィクションとしての過去を見せる。ぼくらは過去を実際に見ることはできなくて、想像しかできないから、それはある意味で未来を見ているような気持ちになれるね。
ポケット企画『受付』
7月18日(日)/札幌・BLOCH/森・山下ペア
まず三瓶くん(演出)が出てきて、ひとり芝居をしている。別役実の言葉を引用しながら、自分たちの試みについて抽象と具体を織り交ぜて説明してくれる。これが上手なんだよな。見れちゃう、たっぷり。もう少しやってほしい。笑 このイントロからセット建て込み、本編への流れがごくごく自然で、すでに引き込まれている。
高校生応援企画ということで、札幌高文連大会と同じ条件で上演する。セット建て込みは10分以内、本編は60分以内。その後に幕間討論をやるのかと思ったけど、そこまではなかった。でも彼らなら、コロナ禍でなければやっていそうだ。この取り組みに目がいきがちだけど、シンプルに高校生の入場料を安くしているのが良い。形だけじゃなく、実際に高校生にとって見やすい、応援するというスタンス。
作品は別役実。ぼくはずっと「べつやくみのる」だと思っていたんだけど、「べっちゃくみのる」と読むことも多いらしい。初めて知った。日本の不条理演劇を確立した第一人者でうんぬん、と語られることは多いけど、不条理とかは難しいので、人間らしさを不思議で抽象的な言葉で表現する作家、くらいに認識することにしている。ちなみに舞台にはでんしん柱がよく立っている。
この作品も例に漏れずでんしん柱が立っていて、その前に神経内科の受付が設置されている。建て込みの時点では受付には電話とかプレートがおいてあって、いかにもな受付なんだけど、本編がはじまった途端にそれを全部片付けて大量の手(ゴム手袋?)がばらまかれる。はなから具象の世界で戦うつもりがないファイティングポーズを取られて、こちらも心地よく身構える。
普段から非常にあいまいな言葉のうえで戦っている人たちという印象があるので、別役実の話をごく当然のように解釈して舞台にあげていた印象。たぶんこれって、すごい訓練をくり返しているんだろうけど、そもそもそれが楽しいんだろうな。
言葉が内向きで、立ち居振る舞いが外向きという違和感をどう感じるか。あるいは言葉古くて、立ち居振る舞いは新しいのか。特に気になったのは、笑わせ方。なんだか表層的に見えてしまった。ずいぶんと受け手にサービスしてくれているように感じたけど、そんなに気をつかってもらわなくても大丈夫だよ、とぼくは思った。みんなはどう思ったんだろう。気になる。
「舞台を通る風」を感じることがコンセプトだとしたら、その風は感じられたんだろうか。ぼくはまだ滞留しているように感じた。別役実の世界から吹いてくる風を、いまはまだ身に纏っている。これからこの風はどっちに抜けていくんだろうか。そんなことを思いながら、いまの創作を楽しんでいるような印象だった。それはすごくワクワクすることで、もちろん見ている側だって、その探求のそばにいることはできる。ぜひ舞台以外にもいろんな発信をしてくれたら喜びます(願望)。
パンフレットにまちがい探しがあった。客席でのおしゃべりを控えてもらうための工夫、アイデア、デザイン。次はクロスワードがいいです!(まちがい探し苦手。笑)
ところで、ポケット企画のホームページを見ていたら、「2022年本格始動」と書いてあった。え、まだ本格じゃないの?
いま一番たのしみなチームなので、本格始動、心待ちにしています。
劇団words of hearts『ニュートンの触媒』
7月31日(土)13時/札幌・コンカリーニョ
ぼくには、ウォーレス・カロザースが子どもに見えた。精神的に未熟という意味じゃなく、いやそうなんだけど、愛に飢えた子どものように見えた。
作中、彼はナイロン66という、世界を変えるような発明をする。上司には「荒唐無稽」と見放された研究の末に完成させた。現代でもナイロン製品は多く出回っていて、彼の発明がいかに大きなものだったかは手に取るように分かる。彼は、この世界になかったものを生み出した。
これだけの偉業の割に、物語のなかでは、彼のはたらきを評価する声が妙に少ない。事実として、カロザースは企業に所属する研究者だったため、彼の発明は企業秘密にされ、製品化に至るまでその研究内容や研究者について一切を隠匿されていた。そのため社会のなかでカロザースが見つけられないのは、かわいそうな出来事だけど、納得はする。しかし彼の友人や上司、婚約者は、彼の熱心な研究とその成果を目の当たりにしているはずだ。それなのに、彼のはたらきに対する賛辞はあまりに少なすぎる。
「天才」という言葉は、その人の「努力」を無視する発言だ。天才と呼ばれる人たちが為すことは、ぼくのような凡人には、まるで魔法のように見える。いや、魔法だと信じたい。くれぐれも、自らも努力すればあの偉業を成し遂げられた可能性なんて、信じたくないのだ。魔法のように、はじめから適正があって、生まれ持っての才覚によってのみ為せることにしておきたい。だから、彼らの努力をすべて無視して、「天才だ」「さすがだ」と中身のない褒め言葉で自らを守る。作中に登場する婚約者も上司も友人も、天才と同じ科学者だったのだから、その防衛機制はより大きかったんじゃないだろうか。実際、婚約者はカロザースの生き方に「憧れている」らしい。
カロザースはただ認められたかったのだと思う。それは彼の周りが認められる程度の、彼にとって些末な研究ではなく、ただこの世界にないものをつくりたいと願ってたどり着いたナイロン66、その努力と結果を認められたかった。
彼の婚約者は、研究にばかり耽って自身を見てくれないカロザースに愛想を尽かして、家を出ていってしまう。もし彼女が研究者ではなく、科学について無知の人間であったら、カロザースの「がんばり」を認めてあげられたのかもしれない。もし彼の友人が、カロザースの同僚の科学者でなければ。もしグレッグ(作中に登場する日系アメリカ人)が、彼の家政夫ではなく友人だったら。もし上司、会社が、彼のはたらきをいち早く世界に伝えていたら。
そんなもしをたくさん考えてしまうが、史実に基づく物語にたらればはなく、彼は自ら死を選ぶ。ウィキペディアでも書き換えられないくらい、紛れもない死にたどり着く。せめてフィクションの板の上では、とも思うけど。
彼の死が伝えられたあと、婚約者と友人と上司が集まって、彼の死を悼むシーンがある。彼らは一様に「どうして死んでしまったのか」というテンションで存在するのだけど、こんなに滑稽なことがあるだろうか。カロザース本人の嫉妬や執着、虚栄が目につく作品ではあるが、しかしカロザースを死に追いやったのは、彼らの嫉妬や執着、虚栄であることも明らかだ。
カロザースは負の感情こそ人間臭さだと考えるなら、同様に彼らも人間臭いと愛せるが、カロザースは自らの負の感情を克服できなかったから死ぬことになったと考えるなら、彼らの負の感情こそがカロザースを殺したと憎むことになる。
舞台も光もていねいで、また言葉も強くなく淡々と。どこまでも美しくつくられた世界のなかで、最後に怒りを覚えるとは思ってもみなかった。
ぼくがここまでカロザースに感情移入して見てしまうのは、ぼくが数理系の人間だからに尽きないと思う。カロザースがはじめてナイロン66を完成させた瞬間。ついに手に入ったその夢に、目を見開き、背中を丸め、つま先を立て、体を小さくばたつかせながら、言葉にならない声を叫ぶ。ぼくはそんな経験をしたことがない。あれだけ純粋で強い想いを見せられれば、彼の味方になりたくなるのは当然だと思う。
経験をしたことがないと書いたけど、たぶんある。それは子どものころ、たとえばブロック遊びで大きな車をつくったときとか、むずかしい算数の問題を自力で解けたときとか。そんなときは、少し似たような感覚があったと思う。でも、数字で測れないその成果も、表に出ない思索の努力も、誰かに認められたことはない。彼はそんな子どものころのドキドキを、ずっと持っている人間だったのかもしれない。
物語のことばかり書いてきたから、最後に気になったことを書いておく。ひとつはアナザー(飛世さん)の存在。カロザースの内面的存在とパンフレットに書かれていて、彼の精神の病について表現する要素なのかと思っていたけど、実際は単純な「もうひとりのぼく」状態で。彼の心情を観客に伝えるための装置に見えてしまった。そして井上嵩之の演技も底が深いものだから、さっき見せてくれたことを、もう一度言葉で伝えられているだけな気がして。
もう一つはエピソードと、カロザース以外の人物と、装置などのすべてが、カロザースを魅せるために作られていた印象。井上は付き合いも長いし、彼の演劇が好きだから、ぼくとしては大満足なんだけど、よくここまで思い切れたなあと驚いた。一歩間違えてカロザースにフォーカスを当て損なったり、感情ではなく事実=お話をメインに見てしまうと、途端に平坦で面白くない作品になってしまうんじゃないかな。どうなんだろう、見た人の話を聞いてみたい。
購入&サポート、いつもありがとうございます!すごく励みになります。 サポートいただいた分で、楽しいことをつくったり、他の人のよかった記事をサポートしたりしていきます!
