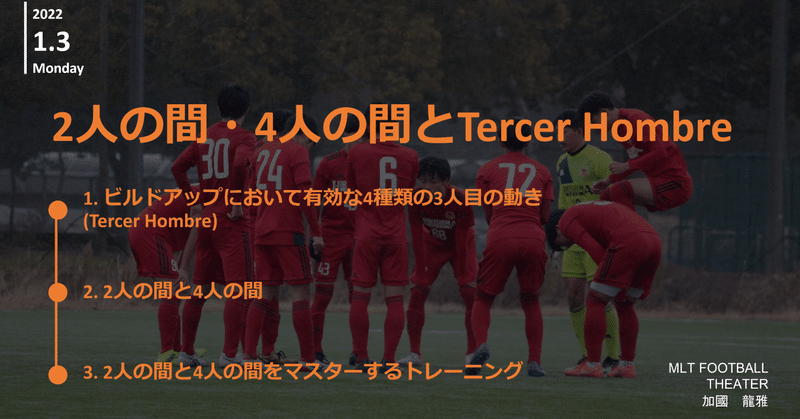
01_2人の間・4人の間とTercer Hombre
はじめまして!シアター生の加國と申します。
高田様よりお話を頂き、本日より1週間に一度、記事を投稿致します。内容としては、これまで私がシアター動画を通して身に付けた知識を、指導現場で実際にアウトプットした上で整理した、私なりのサッカー観を書いていこうと思っております。ぜひご一読いただき、感想等お聞かせいただければ幸いです。よろしくお願い致します!
第1回目の今回は、私自身大好きな、組織的攻撃・ビルドアップ局面についてです。ビルドアップを成功させるためにはどのようなポイントがあるのか?私なりに整理した内容を皆さんにお届けします!
※記事の内容は、あくまで私自身の解釈で再定義したものとなっております。シアター生の皆様が動画や記事でご覧になったものとは異なることがありますことをあらかじめご了承ください。
※第1回 内容一覧
1. ビルドアップで有効な3人目の動き(Tercer Hombre)
まずは、ビルドアップで非常に有効となる集団戦術アクション、「3人目の動き(Tercer Hombre)」について解説していきます。
3人目の動きとはどのようなアクションだったかというと、
ボールホルダーから直接アクセスできない味方選手に、他の味方選手を経由してアクセスするアクション
でした。3人目の動きにもさまざまな種類がありますが、私が考える、ビルドアップにおいて有効な3人目の動きは以下の4つです。
・Pase de cara(落とし)
・Pase Paralelo(平行)
・Pase Diagonal(斜め・フリック)
・Cuatro Hombre(4人目の動き)

順番に見ていきます。
まずは、Pase de cara(落とし)です。
私自身はこのアクションを「遊びのパス」と表現しています。私はビルドアップのトレーニングを行う際、必ずDFラインの選手に対して「遊べ!」とコーチングします。それほど重要なコンセプトだと考えています。
私自身のPase de cara(落とし)の定義は、
より遠い味方選手と繋がるために、あえて近い位置にいる味方選手とパス交換をするアクション
です。直接遠い位置にいる味方選手への縦パスを狙うのではなく、あえて近い位置にいる味方と距離の短いパス交換を行い、縦パスの成功確率を上げるのが最大の狙いです。
続いては、Pase Paralelo(平行)です。私はこのアクションを、
あえて相手を背負った味方選手に縦パスを入れて、相手を食いつかせた状態で横パスを行い、プレスを回避するアクション
と定義しています。わかりやすいのは、以下のような例でしょうか。

WGがSBからの縦パスをワンタッチでOMFへ渡すことで、WGに対して強くアプローチしてきた相手SBのプレスを回避することができました。
このように、縦パスを受ける選手に対して相手選手が食いついてきたときに有効なのが、Pase Paralelo(平行)です。
次に、Pase Diagonal(斜め)です。よく指導現場などでは、「フリック」とも表現されているかもしれません。このアクションは、私の中では先ほどのPase Paralelo(平行)とほとんど同じ定義です。違いは何かと言うと、
相手選手が縦パスを受ける選手に対して斜めにアプローチしてくるのか、まっすぐにアプローチしてくるのか
の違いです。先ほどは相手選手が斜めにアプローチしてきていたため、横(平行)のパスとなりましたが、今回は相手選手がまっすぐにアプローチしてくることを想定しているため、斜めのパスも可能となります。要は、パスが相手選手の足に当たるかどうかでパスの方向を変えているだけで、その目的である、「相手をあえて食いつかせてプレスを回避する」ことは変わらない、ということです。
最後は、Cuatro Hombre(4人目の動き)です。
このアクションは、先ほど紹介したPase ParaleloとPase Diagonalを組み合わせたようなイメージを持っていただければと思います。縦パスを受ける選手に対して、相手選手が斜めにアプローチしてきた際に、横パスを一度挟んだうえで縦パスを通し、相手選手の背後のスペースをとるイメージです。つまり、縦パスを受けた選手がPase Diagonalで直接パスをするのではなく、さらにもう1人経由してそこへ届けるから、Cuatro Hombre(4人目の動き)となるのです。
以上、紹介してきました4種類の3人目の動きが、ビルドアップで有効なアクションです。次項では、具体的にそれらをどのように実践していくのかを見ていきます。
2. 2人の間と4人の間
ここでは、ビルドアップにおける立ち位置と、先ほどの3人目の動きを絡めながらより実践的なお話をしてきます。
まずは、僕自身が定義した言葉である「2人の間」と「4人の間」についてお話していきます。「2人の間」とは、
相手選手2人を結ぶライン上に立つこと
であり、「4人の間」とは、
相手選手4人で形成される四角形の重心に立つこと
です。まずは、2人の間に立つときのキーファクターからお話していきます。
2人の間に立つとき、もっとも重要なのは、
パスの出し入れは必ず斜めに、角度をつけて行うこと
です。2人の間に立つときに利用したいのは、先ほど紹介した3人目の動きのコンセプトのうち、Pase de cara(落とし・遊びのパス)です。2人の間に立つ選手とパス交換をすることで、門を閉めさせ、新たなパスコースを生じさせることが、2人の間に立つ最大の狙いです。そのためには、パスを出し入れする際に角度をつける必要があります。これがもしまっすぐだと、縦パスのコースが空きません。

次に重要なのは、
2人の間に立つ選手が、Pase de cara(落とし・遊びのパス)のコンセプトと、相手がそのプレーを読んできた、あるいは違う対応をしてきたときのターンの選択肢とを両方考えておくこと
です。少し長いですが要は、「相手の対応・動きを見て、柔軟に判断を変えましょう」ということです。
確かにこの場面で有効活用したいのはPase de cara(落とし・遊びのパス)のコンセプトですが、その通りに相手が対応してくるとは限りません。そういったときにギリギリまで相手の動きを見て、判断を変える必要があります。「決め打ちでプレーをしない」とも言い換えられるかもしれません。
さて、次は4人の間に立つときについて。この場合は、
①4人の間に立つ選手が、4人のうちどの選手が寄せてくるのかを見ておくこと
②寄せてきた選手の背後にできたスペースへボールを届ける手段を正確に判断すること
の2つが挙げられます。4人の間に立つ最大の狙いは、相手選手4人で形成される四角形を歪ませることです。四角形が歪めば、必ず新しいスペースが生まれます。そこへとボールを届け、チャンスを広げたいわけですが、そのためには、4人の間に立つ選手の判断の正確さが求められます。まずはどの選手が寄せてきていて、どこにスペースが生まれるのかを見ておくこと。そして、そこへ届ける手段を正確に判断すること。その手段とは先ほどもお話ししましたが、
Pase Diagonal(斜め・フリック)
Cuatro Hombre(4人目の動き)
のいずれかになると思います。自分から直接、寄せてきた選手の背後へボールを通せそうならPase Diagonal(斜め・フリック)。それが角度的に難しそうなら、Cuatro Hombre(4人目の動き)。また、2人の間の時にもあったように、ターンの選択肢や、4人のうち自分の前の選手がプレスバックしてきたときのリターンも考えておかなくてはいけません。ここに関しては、反復したトレーニングが求められます。

3. 2人の間と4人の間をマスターするトレーニング
この項では、これまで紹介してきた2人の間と4人の間、そして、4種類の3人目の動きをマスターするために有効と考えるトレーニングを見ていきます。
①3on3+3F

まずは、長方形のグリッドの長辺に1人ずつサーバーを置いた3on3+3Fのトレーニングです。
守備側は3on4の数的不利ですので、3人でスライドを繰り返しながら逆サーバーへのパスを防ぎ続ける必要があります。攻撃側はその中で、4人のうち両サイドの2人が目一杯幅を取り間のパスコースを広げ、間に立つ2人で守備3人の間に立ち、パスを出し入れすることを狙います。
このトレーニングでは守備は1ラインしか存在しませんが、縦パスが通った後の展開をイメージするのなら、縦パスの後に素早くサーバーからの落としのパスをもらえるよう攻撃選手に対して呼びかけるコーチングがあってもいいかもしれません。
②4on4+3F

続いて紹介するのは、マンチェスターシティの監督であるペップ・グアルディオラが行っている事でも有名な4on4+3Fのトレーニングです。
このトレーニングでは4人の間に立つ選手の判断にフォーカスします。初期配置の上で既にポジション優位を得ている中央のフリーマンの選手に対して、それを囲う4人の守備選手がどのようにアプローチしてくるのかをきちんと把握すること。そして、新しくできたスペースに正確にボールを届けること。そこにひたすらこだわってトレーニングを行います。
まずは、中央のフリーマンに対してどの相手選手が寄せてくるのかをきちんと認知すること。その上で、先ほど紹介した選択肢、Pase Diagonal(斜め・フリック)、Cuatro Hombre(4人目の動き)、ターン、リターンのうちからより素早く、正しい判断を下していけるようにコーチングしていきます。
トレーニングの特徴として、起きる現象の再現性が高く、ある程度パターン化されますので、時には一度ストップして、起きた現象を細かく説明し、その状況に応じた判断は何なのかを選手に理解させるのもありかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?こういった感じで、次週からも記事を書いていきます。次週は、私がこだわってトレーニングしている個人戦術「Desmarque」について書いていきます。
次週もどうぞよろしくお願い致します!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
