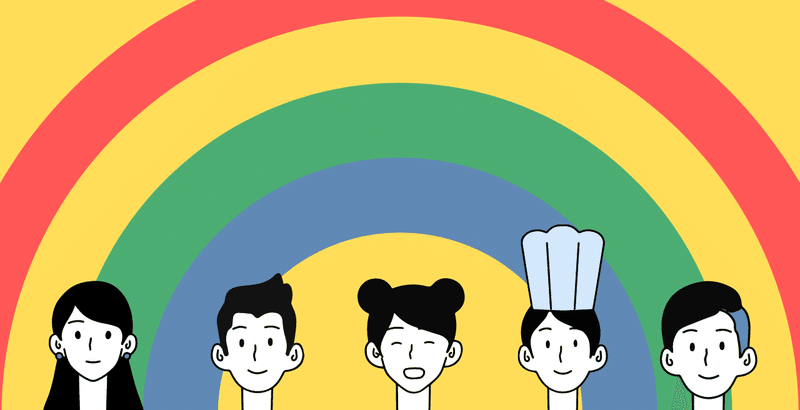
僕たちは好きなことで生きていくしかない
「好きなことで生きていく」
YouTubeが自身のプロモーションとして掲げたキャッチフレーズですが、まさに今の若い世代の感情を捉えている言葉だと感じます。
Sipherの調査では、500名の20~39歳の男女に対して働く上で大事にしている価値観について調べたところ、63%もの人が「好きなことをやる」という回答をしました(2020年2月調査)。
しかし、一方で「好きなことを仕事にする」に対して否定的な声も耳にすることがあります。「仕事というのはそもそもお金を稼ぐためにすることだ」「辛いからこそ仕事なんだよ」「自分のことばかり考えないで、とりあえずお金を稼ぎなさい」といった価値観もたしかに存在するようです。
つまり、「好きなことを仕事にしたい」という仕事に意味を求める価値観と、「仕事とはお金を稼ぐためのものであり稼げることをやればいい」といったような、仕事を割り切っていて、ある種のゲームのように数字を追いかけていく価値観は現代において対立する価値観となっているように見えます。
果たしてこれは何が原因によって生み出されているのでしょうか。
個人レベルの話だと、お金に苦労した過去があってお金にコンプレックスを感じているケースやお金を稼ぐことそのものがアイデンティティとつながっているケースだと後者のような価値観が醸成されていく可能性が高いでしょう。反対に、生まれながらにほぼすべてのものが満たされていた場合は、わざわざ割り切ってお金を追い求めることに必要性を感じないため、せっかくなら好きなことをやりたいという価値観が作られていくことが考えられます。
次にもう少し大きな視点でみたときに、この対立の原因の一つは世代の違いによるものと洞察できます。
乾けない世代と「好きなこと」
IT批評家の尾原和啓氏は著書『モチベーション革命』にて、生まれた頃からすでに何もかもが揃っている30代以下の世代を「乾けない世代」と呼び、上の世代のサラリーマンに代表される「乾いている世代」との間には幸せを感じる要素に大きな価値観の違いがあると述べています。
上の世代は、「達成」と「快楽」を追求する人が多い世代でした。まさに「目標を達成してワインで美女と乾杯」です。つまり、「快楽」を満たすための手段としての「達成」でした。
一方で、「乾けない世代」は、「良好な人間関係」や「意味合い」を重視する人が非常に多いのが特徴です。仕事よりも、個人や友人との時間が大事。何気ない作業の中にも、”今、自分がこの作業をやっている意味”を見いだせないと、とたんにやる気が起きなくなる。「没頭」タイプの人も多く、「いくら稼げるか」よりも「仕事に夢中になって時間を忘れてしまった」ということに喜びを感じます。[尾原和啓(2017)『モチベーション革命』]
「乾いている世代」とは、世の中の空白を埋めるように仕事をしてきた世代です。つまり、社会にないものを生み出して、収入を増やして、家のテレビを白黒からカラーに変えていくという「達成」が、同時に社会貢献につながっていた世代なのです。
一方で、30代以下の「乾けない世代」は生まれながらに物質的な豊かさがほぼ達成されている世代です。すでに作り上げられている社会の上に立たされていて、したがってどんどんお金を稼いでどんどん社会を発展させていくといったような大きな物語に共感できないでいると考えることができます。
だからこそ、先の若い世代への調査では「好きなことをやる」が回答として選ばれたのだと推察できます。「好きなことをやる」とは「お金を儲ける」とか「出世する」といったような、外部的な「達成」を目的としない仕事を求めているということであり、尾原氏が指摘するように仕事に対して「意味」を求めていると解釈できます。
「意味」と「意義」の違い
この「意味」という言葉は今後長く用いていく重要ワードなので、よく混同されがちな「意義」との違いも踏まえて詳しく説明しておきます。この2つの違いについては論理学などで議論され様々な捉え方がありますが、僕たちがしっくりくる感覚をもとに定義してみたいと思います。
精神科医である泉谷閑示氏の著書『仕事なんか生きがいにするな』をもとに引用します。
現代に生きる私達は、何かをするに際して、つい、それが「やる価値があるかどうか」を考えてしまう傾向があります。このような、「価値」があるならばやる、なければやらないという考え方に、「意義」という言葉は密接に関わっています。つまり、私達が「有意義」という時には、それは何らかの「価値」を生む行為だと考えているわけです。(中略)しかし、一方の「意味」というのは、「意義」のような「価値」の有無を必ずしも問うものではありません。しかも、他人にそれがどう思われるかに関係なく、本人さえそこに「意味」を感じられたのなら「意味がある」ということになる。つまり、ひたすら主観的で感覚的な満足によって決まるのが「意味」なのです。[泉谷閑示(2017)『仕事なんか生きがいにするな』 p.105]
「意義」とは客観的に価値があるとされるものを指すニュアンスとしてよく使われます。「有意義な休日を過ごす」といったスローガンに代表されるようになんらかの価値のあることをしましょうというのが「意義のあること」です。現代ではとくに、「価値のあること」が「お金になること」や「スキルが身につくこと」などの何かの「役に立つこと」に偏ってしまっている傾向があるため、「意義」が「役に立つこと」と同じようなニュアンスで使われてしまっています。
一方で「意味」とは主観的な満足によって決まる概念であり、そこに客観的な「価値」が入り込む余地がありません。休日にダラダラとゲームをすることが、他の人によって客観的に「有意義じゃないね」と言われることがあっても、当の本人がゲームをやることに充実感を覚えているのであれば、それは本人にとって揺るがなく「意味がある」ということです。
さて、これらを踏まえると「好きなことを仕事にする」というのは、どれくらいお金が手に入るかといったような「意義=価値」に着目しているのではなく、まさに自分自身が主観的にそれに熱中できて、楽しいと感じ、満足できるかかという「意味」に重きを置いている選択肢だと言うことができます。
「自分にとって意味のある仕事」で生きていく
ここまで書いてきて、僕のポジションを明確にしておくと僕は「好きなことを仕事にする」ことを強く支持しています。むしろ、好きなことを仕事するしかないとさえ思っています。
ただし、この「好きなこと」はかなり抽象度が高い言葉であり誤解を生みやすいと思うので少し補足させてください。僕の定義する「好きなこと」は「やりたいこと」と表現したほうが誤解が少ないと思います。なぜ「好きなこと」という表現では微妙かというと、消費としての好きなことをイメージしがちだからです。
たとえば、「ゲームが好き」といったような趣味を仕事にすることをイメージする人が多います。そうすると、「ゲーム実況」を仕事にしようみたいな話になってしまうのですが、これが陥りやすい罠だと思っています。どういうことかというと、ゲーム実況者として稼いでいくためにはみんなに見つけてもらう必要があったり、みんなに楽しんでもらう必要があるため、自分が本当はやりたくないゲームをやらなきゃいけなくなったり、ポケモンセンターでの回復縛りみたいな謎の縛りプレイをして注目を引いたりしなければならず、趣味として完全に自分のためだけにやっていた楽しいゲームの時間が消失してしまう可能性があります。
つまり、消費としての好きなことにとどまらず、自分の中にあるポジティブな感情の湧くもの、主観的に活力が湧いてくるものを仕事にするということです。そして、この「やりたいこと」とは前述の言葉でいうと自分にとって意味のある仕事(以後、「意味仕事」とも呼ぶ。)と表現できます。
ビジネスの終焉
この意味仕事はもはやこれからの働き方のスタンダードになっていくと確信しています。なぜなら、「意味」を求める反対の動きともとれる、ひたすらに「利潤」を追い求めていく行為=どれだけのものを作り出せるのかを明らかにするための指標であるGDPを求めていく行為が、私たちの望むべき社会と整合性がとれなくなってしまっているからです。
物質的不足という問題を大きく抱えていた時代にあっては、「どれだけのモノを作り出したのか?」を測るGDPという指標にはそれなりの意味があったのでしょう。しかしすでに前節において解説したとおり、少なくとも先進国においては、この「物質的不足」という問題は解決されてしまっています。すでに遍(あまね)く物質が行き渡った社会において「どれだけのモノを作り出したのか?」という指標を高い水準に保とうと思えば、それは必然的に浪費や奢侈を促進し、モノをジャンジャン捨てることが美徳として礼賛される社会を生み出すことになります。しかし、そのような社会を私たちは本当に望んでいるのでしょうか?[山口周(2020)『ビジネスの未来』p.50]
山口氏の『ビジネスの未来』では、様々なデータを元に、モノやサービスに溢れた今の成熟した日本において、物質的な不足を克服という文脈での仕事はその使命を終えたと説明しています。そして、そんな成熟社会においては、量的な成長を追い求めるのではなく質的な豊かさを追い求めていく道を示してくれています。
このようなコンサマトリー(筆者解説:手段自体が報酬だったり、利得を自分の中に求めたりするような概念)な社会においては、「便利さ」よりは「豊かさ」が、「機能」よりは「情緒」が、「効率」よりは「ロマン」が、より価値のあるものとして求められることになるでしょう。そして、一人一人が個性を発揮し、それぞれの領域で「役に立つ」ことよりも「意味がある」ことを追求することで、社会の多様化がすすみ、固有の「意味」に共感する顧客とのあいだで、貨幣交換だけでつながっていた経済的関係とは異なる強い心理的つながりを形成することになるでしょう。[山口周(2020)『ビジネスの未来』 p.175]
意味仕事にこそ意義がある
さらに、山口氏はビジネスにおいて「役に立つ」ポジションこそ、ごく少数の勝ち組企業しか生き残ることができない茨の道であると著書『ニュータイプに時代』にて述べています。
二極化が進行する世界において、すべての企業は「役に立つ」という市場において、生き残りをかけて熾烈な戦いに身を投じるか、「意味がある」という市場で独自のポジションを築いていくかという選択を迫られることになります。この2つのうち、どちらを選ぶかはなかなか難しい問題ですが、ただ一つだけ指摘できるのは、従来の定石に囚われすぎてしまい、深く考えることもなく「役に立つ」市場でスケールを目指そうとするのは、間違いなくオールドタイプの思考様式だということです。なぜなら、グローバル化が進めば進むほど「役に立つ」市場の頂上は「高く、狭く」なり、ごくごく少数の「グローバル勝ち組企業」以外は生き残ることができない「真っ赤っかのレッドオーシャン」になるからです。
一方で、なんらかの「意味」にフォーカスを絞ることで独自のポジションを獲得するニュータイプは、「グローバル×ニッチ」という「爽やかなブルーオーシャン」を自らの居場所にすることになります。[山口周(2019)『ニュータイプの時代』p.114]
たとえば、日本におけるトヨタや日産が販売している車種のほとんどは「役に立つ」ポジションを確立しています。快適な移動手段としての機能を私達は買っているわけです。
しかし一方で、ドイツのBMWやベンツが販売している車種のほとんどは「役に立つ」だけではなく「意味」もあります。それはまさに「ベンツに乗るのってかっこいい」といったような主観的な満足の感情に根ざした購買行動といえるでしょう。さらには、イタリアのフェラーリなどの超高級車(新車で数千万円〜億)、いわゆるスーパーカーにいたっては、もはや「役に立たないけど、意味がある」ポジションであるといえます。スーパーカーの多くにはたくさんのエンジンが搭載されているにも関わらず、そのほとんどは2人しか乗ることができませんし、車高も低くすぐに擦ってしまうなどとても快適な移動手段としては評価できません。
しかしこういった「意味」に特化した車だからこそ、その唯一無二の「意味」を求めて高いお金を支払う人がいるわけです。
市場のグローバル化が進めば、グローバル市場での最終戦争=ハルマゲドンによる勝者総取りが発生し、世界中のほとんどの企業は生き残ることができません。(中略)生き残れるのも一人だけということになります。典型例が検索エンジンでしょう。検索エンジンはまさに「役に立つけど、意味がない」という市場を代表するサービスです。人が検索エンジンにもとめているのは「スジの良い検索結果」だけであって、そこに意味が介在する余地はまったくありません。(中略)実際にどういう状況になっているかというと、2019年現在、グーグルの検索エンジンにおける市場シェアは36過酷で90%を超えている。[山口周(2019)『ニュータイプの時代』p.116]
あなたがサービスの個人開発者になったときに、世界のすべての物を売り買いできるECサイトを作ろうと思った瞬間に競合はAmazonとなってしまいます。Amazonと同じようなサービスを作ったとして果たして勝ち目はあるでしょうか。Amazonと同じジャンルを扱い、同じ機能を持つのであれば「Amazonでいい」となってしまいます。これがまさに勝ち組だけが勝ち続けていくということです。
しかし、ここに「意味」を乗せる、つまりあなたの強烈な「好き」を乗せた場合は少し話が変わってくるかもしれません。たとえばあなたが、とにかくものづくりが好きで、その中でも特にあたたかみのある手作りのインテリアにとくめくという強烈な「好き」があった上で、手作りのインテリアに特化して「造り手」と「買い手」をつなげるようなサービスを作ったら、もしかしたらあなたのストーリーに共感した人があなたの周りに集まってきて、小さな循環が生まれ始めるかもしれません。
こうした「意味」のあるWebサービスの実例として、個人的によく思い浮かべるのが「サウナイキタイ」です。サウナイキタイはサウナ好きが集まり、サウナ室内で立ち上がったプロジェクトです。元はサウナ好きの人たちがばらばらにサウナに関する情報をまとめていたところ、ひょんなことがきっかけで一緒にサウナにはいることになり、気がつくとチームとしてスタートしていたとAboutページに記述があります。2020年時点で、登録施設数は8,130件、サ活数は60万件にものぼり、日本最大のサウナ検索サイトとして多くのサウナーに親しまれています。
その他にも、昨今、個人が始める「オンラインサロン」が流行っていますが、こういったコミュニティの市場も「意味」が活きやすいビジネスだと捉えることができます。コミュニティのビジョンに共感して人が集まり、そこに創出される「人間関係」は、必ずしも「量」が多ければいいというわけではなく、「質」の面が特に評価される「意味」の市場だと思います。
こういった「意味」の市場こそ、個人や小さなチームが輝ける市場ではないでしょうか。
ビジネスモデルに「意味」を取り入れる
これまで「意味」の持つ魅力について書いてきましたが、一方で「自分が仕事に意味を感じているかどうかと稼げるかどうかは別物だろう」という声が聞こえてきそうです。
たしかに、ただ自己充足的に「意味」を見出したところで、それが必ずしも現実的な「稼ぎ」に直結するとは言い切れません。これまで趣味で(加えて経営学科出身というのもあり)数々の企業の事例を見てきましたが、そこには必ず「顧客への提供価値」と「競争優位性」があります。つまり、「どうやってお客さんに喜んでもらうか」と「どうやって勝ち続けるか」を地に足つけて設計しなければならないということです。
しかし、自分の好きな分野で稼ぎを得るためのチャンスははるかに昔よりも今のほうが増えていると思います。なぜなら、「インターネット」が僕たちの生活に溶け込んでいるからです。インターネットは遠くにある人たちをつなげる性質があるため、あなたの偏った「好き」に共感する人を世界中から探し出すことが可能なのです。これにより1つの動画をYouTubeにアップロードするだけで何万人にも見てもらうことが現実的であるように、ITをうまく使いこなすことで多数の人を対象に価値提供をすることができるます。つまり、昔よりも容易に「顧客への提供価値」の量を実現することができるため、まさに「好きなこと」で稼ぎやすい時代であると言えるでしょう。
さらに、これまで述べてきた「意味=ブランド」が、「競争優位性」をいかに担保するかという点においても重要な位置にあると捉えることができます。
競争優位性としての「意味=ブランド」
PayPalの共同創業者であるピーター・ティールは遠い未来に大きなお金の流れを生み出す企業(独占企業)の特徴の1つとして「ブランド」を挙げています。これは、これまで述べてきた「意味」とかなり親和性の高い概念であることがわかります。
ブランドとは、そもそも企業に固有のもので、強いブランドを作ることは独占への協力な手段となる。今一番強いテクノロジー・ブランドはアップルだ。iPhoneやMacBookの魅力的な外観と慎重に選ばれた素材、アップルストアの垢抜けたミニマリスト的デザインと顧客体験への厳格なコントロール、いたるところに見かける広告キャンペーン、ハイエンドメーカーとしての価格設定、そして今も残るスティーブ・ジョブズのカリスマ性といったすべてが、アップル製品を独自のカテゴリとして位置づけている。[ピーター・ティール(2014)『Zero to One』p.79]
スティーブ・ジョブズは会社のミーティングで、自分たちが売っているものは仕事をするための箱ではなく「情熱を持った人々が世界をより良く変えることができる」という世界観なのだということを話している動画があります。これは、まさに会社が存在する意味=ブランドが洗練されていった瞬間でした。
企業の「ブランディング」を個人の働き方に適用すると、その仕事をやっている意味=なぜその仕事をしているのか?ということであり、それは自分の中の小さな活力源のようなものから始まるような、そしてそれをすることそのものが目的ともなりうるような、とても主観的な概念であることがわかると思います。
低価格競争に巻き込まれないための「意味=ブランド」
機能で差別化をしようとすると、どうしても低価格競争に巻き込まれていくケースが多くあります。なぜなら、機能とはコピーが可能だからです。競合のサービスが新機能を開発し成果がでているようだったら、競合はただ「パクる」だけでいいのです。
このような「機能」とは基本的には便益の点で「正解」があるカテゴリーなので、どこも似たりよったりになり、特許や本当にすぐれた技術力がない限りは差別化の要因になりません。したがって、機能に頼りすぎてしまうことは価格競争の波に飲み込まれていく可能性のある危険な行為であると見ることができます。
一方で、「意味」はパクる余地がありません。なぜなら、それはそのプロダクト・サービスをなぜ提供しているかという唯一無二のストーリーであり全く同じになることはないのです。仮に、発するメッセージが一言一句同じであったとしても、その人の生まれやルーツ、経歴や思想などによってそのメッセージの色味や形が受け取り手には異なって伝わるため、これもまた全く同じということはありえません。私たちは感情をもつ生き物なので、何を言うかも重要ですがそれより、誰が言うかのほうがもっと重要でそれによって言葉の解釈さえも変わってしまうのです。
アップルの中核的な強みは、そのデザインにある、とよく言われますね。しかし、本当にそうでしょうか?現在、アップルが提供しているスマートフォンやノートパソコンと、ほとんど見分けがつかないほど似ている製品が他社から発売されています。アップルの強みが本当にデザインにあるのだとすれば、見分けのつかないほど似たデザインを提供している他者(原文ママ)のシェアや時価総額は、なぜアップルほどには高くないのでしょうか。(中略)最大のポイントは「テクノロジー」も「デザイン」も、非常に「コピーされやすい」という点です。(中略)では何がコピーしにくいのかと考えてみると、ここに「意味」というキーワードが浮かんできます。その製品やブランドが持っている固有の「意味」はコピーできないのです。(中略)アップルというブランドが持っている固有の「意味」は、1970年代の末からアップルとその創業者であるスティーブ・ジョブズという人物が、世界に与え続けてきた情報の蓄積に支えられて形成されています。[山口周(2019)『ニュータイプの時代』p.122]
このように「意味=ブランド」こそ、機能による比較に代表されるような他人との相対比較軸に乗らない最強の資本であると言えます。そして、その「意味」とはまさに自分の中から生まれるものであるため、小さく自分でビジネスを始める場合には「自分らしさ」を活かすことこそ究極の競争優位性だと言えるでしょう。
人工知能も「意味」は奪えない
僕はこれまで5年以上プログラミングを生業として来たのですが、これは人間から仕事を奪う仕事をしてきたと言っても過言ではありません。人間が面倒くさいと感じる作業や複雑な作業を機械に代替させることで所得を得てきました。
しかし、だからこそ、ふと僕たちは最終的に何を仕事にして生きていくのだろうと考えている自分がいます。非効率な仕事、やる意味のない仕事はどんどん機械に置き換わっていくことでしょう。その先に、僕たちは何をして生きていくのでしょうか。
僕は思うに、残る仕事(というよりもう少し概念の広い「活動」のようなものは)は、どうしても人間がやったほうがいい活動や人間を人間たらしめる活動であり、それはまさにこれまで述べてきた意味仕事だろうと考えています。
究極的にはベーシックインカムのような仕組みを取り入れ、働きたくない人は無理して働かなくてもいい社会が実現できないものだろうかと考えることもあります。しかしながら、それは「仕事=辛いもの」という価値観に立脚しているような気もしています。
一番の理想はこれまで書いてきたような、自分の中でその活動そのものに充足感を感じて、それが他者への貢献となっているような活動により持続的に社会とつながることができる人が増えることだと考えています。つまり会社員OR独立のような二者択一的な今の常識から抜け出して(あえていうなら皆がフリーランスのように様々なプロジェクトを横断するような形で)、皆が自分の個性を活かして、楽しく、自分らしく、他者に感謝されながら、持続的に働くという「意味仕事」をしている人に溢れる社会を想像しています。
そのために意味仕事をしている事例を研究し、意味仕事をしたい人を支援するための活動(物書きなのか、サービスづくりなのか現時点では不明)に強い関心があります。
こうした意味仕事が広がり、みんなが「つい働いてしまう」社会が到来したとき、今よりも全体の幸福度は高まるのではないかと考えています。
さいごに
「意味仕事」とは僕の人生のテーマでもあります。なぜなら、僕はITエンジニアらしく、これまで「効率性」を重視して生きてきたからです。今はフリーランスのITエンジニアとして週に15時間ほどリモートで働く仕事をしているのですが、過去の自分にとって理想的な生き方を実現するために効率的に人生を送ってきました。効率的にプログラミング技術を身に着け、また効率的に稼げないだろうかとWeb制作やYouTubeを始めたりしてきました。
しかし、30歳を目前にして「効率的に生きる」ことが果たして幸せなのだろうかと自分に問いかけてしまったのです。そういえば、子どもの頃はもっといろんなことに興味を示して、目の前のことに没頭していたなと。そこから、狂ったように1ヶ月に200時間近くSplatoon2というゲームをやるなどして人間性を取り戻していきました。
そして、もっとせっかくなら「それがいくら稼げるか」がわからなかったとしても、やりたいことを色々とやってみようという気持ちになってきました。自分で小規模ながら色々とビジネスをやってきたし、その知識をもとに必要最小限の設計だけして、あとは色々とやってみながら考えることにしようと決めました。
その活動の一つが、このnoteのような物書きの活動です。「お金を稼ぐ」ための効率性だけでみると、わざわざ書く気にならなかったと思います。それでも、僕自身が大学生のころからずっと向き合ってきた「働き方」のテーマについて、これまで読んできた沢山の本から得た情報のエッセンスだけでも整理してみたいという小さなモチベーションが僕を動かしてくれました。「意味」や「ブランド」、「ビジネス」について改めて考えて、またそれを言葉にすることそのものが楽しくて、3連休のほとんどの時間を物書きに費やし、気づいたら1万字を超えていました。笑
先に述べたとおりに、僕は今、意味仕事、ひいては意味のある人生を送りたいと思う人のために何かできることはないかと模索している段階です。そしてひとまず、自分にとって意味がある活動の第一歩が踏み出せたので満足しています。
【追記】2022年8月現在、コーチング等を通じて、理想のライフスタイルを実現するにあたっての問題発見および問題解決の支援を行っています。
みなさんにとっての「意味仕事」を実現するためのヒントとなるような情報を公式LINE(無料)で不定期メルマガのような形で発信しています!(不興味のある方はお気軽に友だち登録してください!
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
