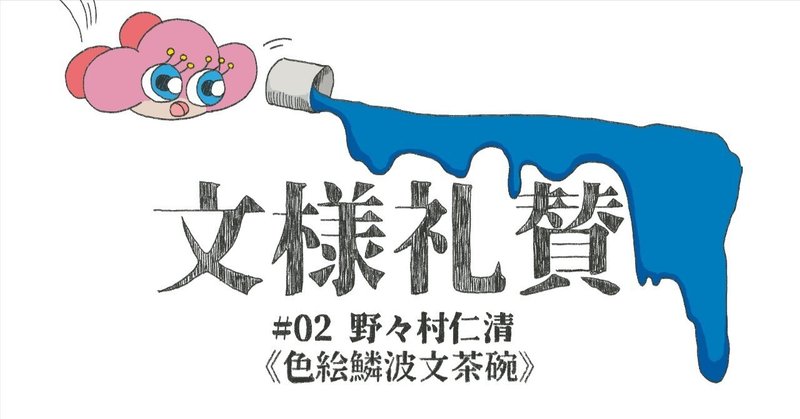
文様礼賛 #02野々村仁清《色絵鱗波文茶碗》
はじめに
皆々さまこんにちは。麗しい初夏のころ、いかがお過ごしですか?

文様礼賛の第2回。
今回は、江戸時代の陶工野々村仁清の作品と文様について、考えていきたいと思います。
取り上げたい作品は《色絵鱗波文茶碗》。

というのも、この作品の文様には、名品が名品たるための仕掛けが潜んでいると考えられるからです。
野々村仁清について
まずは仁清の基本的な情報から押さえましょう。
仁清は17世紀後半に活躍した、京焼の陶工です。生没年は不明ですが、早くから京都で修行をはじめ、1647年頃に洛西に窯を構えたとされています。
仁清の作品の何よりの特徴は、金や銀、赤・青・緑で彩られた繊細で可憐な文様です。

《色絵結文香合》高2.1 幅8.4 奥行6.1cm 根津美術館
《色絵瓔珞文花生》高33.1 口径26.4 底径15.5cm 仁和寺
この繊細な絵付の技術は、色絵上絵付法と称されるもので、当時の京都における新しい様式でした。仁清はこの技法を極めた陶工として高く評価されていきます。
さらに、仁清が革新的であったのは、文様を単に並べて付けるのではなく、絵画のように構成して付けたことです。

この点については、伊藤嘉章「色絵藤花図茶壷」『仁清 金と銀』淡交社、2019年、136〜139頁でも詳しく考察されていますので、ぜひ読んでみてください。
こうした数々の仁清の作品の中で、今回は、冒頭にあげた《色絵鱗波文茶碗》を中心に、その文様の魅力を考えていきたいと思います。
仁清のベタ
まず押さえておきたいことは、仁清は可憐な文様の使い手であるだけではなく、ベタの名手でもある、ということです。
いきなり別の作品を持ち出してしまいますが、たとえば仁清の代表作である《色絵金銀菱文重茶碗》は、ベタで構成された作品です。
はじめに目を引く菱形部分には、金銀のベタが施されています。また、茶碗下部の蓮弁文の部分は、その背景の赤と青のベタの潔さが目をひくでしょう。そして何より、「見込み」と呼ばれる茶碗の内側は、漆黒のベタで覆われていて、茶碗を覗き込む者を吸い込んでしまいそうな魅力を放っています。

銀菱:高9.2 口径9.9 高台径4.9cm
金菱:高8.1 口径8.9 高台径4.9cm
MOA美術館
あるいは、茶壺の中でも《色絵吉野山図茶壺》は、吉野山の空が深い黒のベタで塗り込められています。全てを消し去ってしまいそうな暗闇の中で、満開の桜に彩られた山が、幻想的に浮かび上がっているのです。

イラスト化に挫折したので、ぜひ実物を見てください……。
とはいえ、ベタ表現というものは、他の作家も使うものであり、決してめずらしい表現ではありません。
その中で、仁清の特異な点は、ベタを前面に持ってきたところにあります。
その結果、ベタが単なるベタでは無くなった作品が、《色絵鱗波文茶碗》なのです。
茶碗の特徴
さて、茶碗の特徴を見てみましょう。
《色絵鱗波文茶碗》では、「鱗文様」と呼ばれる三角形の文様が、茶碗の表面を8段にわたってぐるりと覆っています。

三角形を連ねる模様は、遥か昔から世界中で使われてきたものです。しかし、古代中国で、この形を龍の鱗に見立てて使っていたことから、日本でも鎌倉時代の頃より、鱗文として使われ始めました。
仁清の茶碗では、この形にさらに意匠が凝らされています。青で描かれた大きな鱗の中に、金の小さな鱗がリズム良く描かれているのです。これは、三角形のフラクタルな性質を見事に活用したデザインと言えるでしょう。
さて、問題はベタです。この作品で最も特徴的なのは、鱗文を覆い隠すようにつけられた、青い釉薬のベタでしょう。
このように釉薬を掛け流す手法は、「掛け切り手」と呼ばれます。

この「掛け切り手」という手法を使った仁清の作品は、他にも2つ存在しています。

《色絵鉄仙花文茶碗》高8.6 口径12.2 高台径5.2cm、根津美術館
《色絵青海波文茶碗》では、波をあらわす青海波文様と、その合間に打ち寄せたかのように波頭の文様が描かれています。記号的な波と、写実的な波の取り合わせが面白いのですが、これら2つの波を、掛け切り手によるベタが覆っています。
《色絵鉄仙花文茶碗》に描かれている花の文様は、鉄仙花です。洋名のクレマチスと呼んだ方が馴染みがあるかもしれません。室町時代に中国からもたらされた植物で、仁清の生きた江戸時代においては、新鮮な印象を放つ文様であったことでしょう。
「鉄仙花(鉄線花とも書く)」という名は、この植物が、鉄の線を思わせるような強い蔓を持つことに由来しています。そのため、文様の意味としても、強いつながりを願う吉祥の意味が込められるようになりました。
仁清の茶碗では、この鉄仙花文様を、細やかに碗全体に巡らせながら、白濁した釉薬のベタをかけることで、部分的に途切れさせてもいます。
いずれの茶碗も、技巧を凝らして描かれた文様の形と、偶然流れた釉薬の形の対比が味わい深くい作品だと言えるでしょう。
名品の謎
しかし、ここで謎があります。
この3作品には、共通して「掛け切り手」の技法が使われているにもかかわらず、名品として取り上げられることが特に多いのは、《色絵鱗波文茶碗》なのです。

これは一体何故なのでしょうか?
それは、この茶碗の文様が「鱗」であることに起因すると思われます。
先に述べた通り、鱗は、龍の鱗に見立てられた文様なのですが、この伝説上の生き物は、水辺に棲むものと考えられていました。
それゆえに、龍の文様は、波文様など水に関わる文様と共に描かれることが多いのです。

そのように考えると、この《色絵鱗波文茶碗》の掛け切り手によるベタは、鱗文をさえぎるための形ではなく、水を表す文様であると考えられます。
つまり、この茶碗の文様は、水からあがってきた龍の鱗に水が滴っている情景を表しているようにも見えるのです。
もちろん、他の2つの茶碗における掛け切り手のベタも、水の文様として捉えることはできるでしょう。
しかし、そのことによって、《色絵鱗波文茶碗》のように、茶碗が見せる情景がガラッと違って見えてくることはないように思います。
(波と水の組み合わせは意外性がありませんし、鉄仙花と水の組み合わせも花に水をやるという普通のコンテクストを発生させるにすぎないように思います)。
《色絵鱗波文茶碗》が、際立って名品として扱われる理由のひとつは、鱗文と組み合わせられることで、掛け切り手のベタに別の意味が与えられ、茶碗からまったく新しい情景が立ち現れるからだと考えられるのです。
おわりに
もちろん、仁清はこのことを意図して制作していたと考えられます。というのも、この茶碗だけ《色絵鱗波文茶碗》と、波が名前につけられているからです。
たくさんの文様を使いこなした仁清だからこそできる、粋な取り合わせですね。
この茶碗から、名品は、形の美しさからだけでなく、文様の意味からも作り得る、ということがわかりました。

以上で、#2野々村仁清《色絵鱗波文茶碗》を終わりにします。
仁清が好きなばかり、いろいろと考えてしまい難産となった回でした。この他にも、仁清の良さはいろいろとありますので、ぜひ分析してみてください。
Twitter:@kakei_nanako
(日常生活の中で見つける模様・文様について呟いています。)
Instagram:@nanako_kakei
(文様を使った作品を作っています。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
