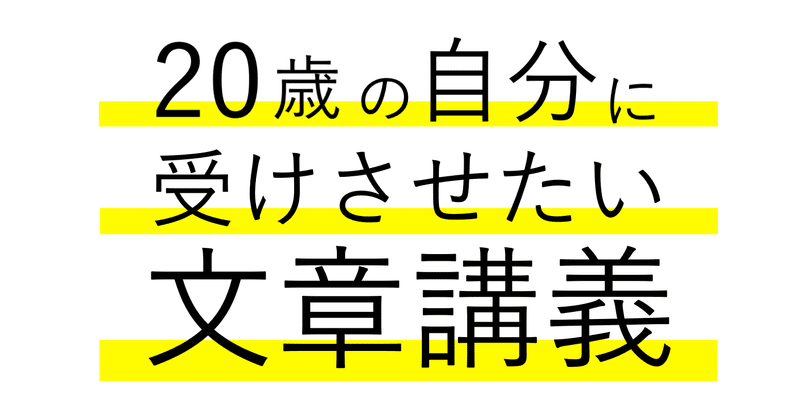
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』古賀史健 「良い文章がきっと書ける」と、自信を持って
このnoteは、まだ本を読んでいない人に対して、その本の内容をカッコよく語る設定で書いています。なのでこの文章のままあなたも、お友達、後輩、恋人に語れます。 ぜひ文学をダシにしてカッコよく生きてください。
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』古賀史健

○以下会話例
■文章の教科書
「文章が上手くなる本か。そうだな、そしたら古賀史健さんの『20歳の自分に受けさせたい文章講義』がオススメかな。この本は、『嫌われる勇気』の著者の古賀さんが「話せるのに書けない」と悩む人に向けて、文章の書き方を授業形式でまとめた本なんだ。文章を書く上での大前提から、効果的な句読点の打ち方などのテクニックまで解説してる良書なんだよ。きっと「文章の教科書」として手元に置いておきたくなるよ。
■6つの文章術
この本では、文章術が大きく分けて6つ書かれているんだ。1つ目は「リズムの良い文章の書き方」、2つ目は「読みやすい構成」、3つ目は「リアリティのある文章の書き方」、4つ目は「誰に向けて書くか」、5つ目は「推敲方法」、そしてこの5つの大前提として「文章を書く心構え」が書いてあるんだよ。ぼくは特に「リアリティのある文章の書き方」と「誰に向けて書くか」そして「文章を書く心構え」が心に残ったんだ。ここからはこの3つを中心に紹介していくね。
■ぐるぐるを翻訳する
まず、「文章を書く心構え」について。ぼくは文章を書く時、どうしても「話せるのに書けない」という壁にぶつかってしまうんだ。何か書きたいことが浮かんで、「さあ書こう」と思って原稿用紙(パソコン)の前に座ると、途端に固まってしまうんだよ。おそらく文章を書くのが苦手な人は、同じような経験をしてると思うんだ。
この状態を打破するには、古賀さんは「頭のなかの『ぐるぐる』を、伝わる言葉に翻訳する」べきと書いてるんだ。
まず、頭のなかの「ぐるぐる」とは、「ぼくらの頭のなかで駆けめぐっている、たくさんの思い」のことなんだ。何かを見たり聞いたり体験して、ぼくらの頭には色んな「思い」が作られるよね。それは、言語とは限らなくて、不鮮明な映像だったり、色だったり、ぼやぼやした予感だったりするよね。古賀さんは、そのぼんやりした「感じ」とか「思い」を「ぐるぐる」と表現しているんだ。話すときは、その「ぐるぐる」を喜怒哀楽の声や表情で伝えることができるけど、文章だとそれはできないよね。
そこで必要な感覚が「翻訳」なんだよ。文章上で考えて書こうとするのではなくて、「頭のなかのぐるぐるを翻訳して、文字情報に書き起こす」という意識で書けば、パソコンの前で固まることがなくなるって言ってるんだ。
僕らは翻訳のおかげで、あらゆる言語の小説や映画を受け取ることができるよね。他にも、例えばテレビで池上彰さんが、難しい世界情勢をわかりやすく解説してくれたりするよね。話せない言語や理解できない事柄を、分かるように変換する。古賀さんは、この「よくわからないもの」を「わかるもの」に変換する行為を翻訳って言ってるんだ。つまり、「まるで外国語のような頭の中のぐるぐる」を「ぼくにも理解できる言葉」に置き換えること、これが文章を書く上で一番大切なことなんだ。
■細部を書こう
次に、リアリティのある文章の書き方について。結論から言うと、
「面倒くさい細部」を書いてこそ、リアリティを獲得する
と古賀さんは書いているんだ。
例えば帰省ラッシュの渋滞について文章で伝える時に、「延々と続く大渋滞だった」って書かれてもあまりピンとこないよね。ここに「50 キロにわたる大渋滞だった」と数字を入れると、さっきの「延々と続く」が「50キロ」という値に置き換えられて、具体的な長さをイメージできるよね。でもこれだと、渋滞の様子を上空のヘリから見下ろしたような描写で、リアリティという意味では一歩足りない。そこで「ほとんど動けないままサザンのベスト盤を聴き終えてしまう大渋滞だった」と書いたらよりリアルに伝わるよね。車の中の細部が書くことで、全く動こうとしない車の中で、時間だけが虚しく過ぎていく様子がイメージできるんだ。
日常の何気ない細部を書くことで、リアリティが生まれて、このリアリティが、状況をわかりやすくしているし、文章の説得力を増しているんだよ。
■あの人に向けた文章
あるカフェを思い浮かべてみて欲しい。そのカフェはコーヒーも料理も美味しいし、清潔で店の雰囲気も悪くない。センスのいいオーナーで、それなりに苦労してオープンした、念願のカフェなんだ。だけど席に座ってみると、椅子やテーブルがぐらぐらする。
この店のオーナーは、新しいコーヒー豆を仕入れたら自分の舌で確かめるし、新メニューの考案にも余談がない。だけど、店の椅子に座ってコーヒーを飲んだことはないんだ。お客さんの席に座ってコーヒーを堪能してみることが、良いお店づくりでは一番大切なことだよね。
文章も同じなんだよ。「読者の椅子」に座って文章を書くことが大切なんだ。読者をイメージして、その人にどう読んで、どう思って、どう感動して欲しいか、それを持つことが「良い文章」を書く第一歩になるんだよ。
そこで、どんな読み手を想像すれば良いのか。古賀さんは2人どちらかにするのが良いと書いているんだ。それは、①特定のあの人、②過去の自分、の2人なんだ。
①の特定のあの人は、友人なり先輩なり恋人のこと。文章を友人に書く時と先輩に書く時では、表現が変わってくるよね。身の回りの人誰かひとりに向けて書くことで、その文章の方向性が定まって、「そのほかの人」にも届きやすくなるということなんだ。
そして②の過去の自分について。例えばいま自分が、上手なプレゼンの仕方とか、良いデートスポットとか、何か有益な情報を手に入れてるとする。その情報は、「もしこれを10年前に知っていたら」と思わせるものでもあるんだよ。10年前に知っていたら、会社で出世していたかもしれないし、恋人とうまくいってたかもしれない。
そういった有益な情報を書きたい場合、「10年前の自分」に向けて書けば良いんだ。10年前の自分に語りかけるように、あの時の自分が会社でどんな立場にいたのか、恋人とどういう関係になっていたのか。どんな言葉を使い、どう伝えれば納得してくれるのか、全て手に取るようにわかるはずなんだ。そして「過去の自分」に向けて書いたその文章は、「伝えたい」という気持ちが乗っかった、主張がはっきりとしたわかりやすい文章になるんだよ。
そして「過去の自分に向けた文章」は決して独りよがりにはならないんだよ。なぜなら
いま、この瞬間にも日本のどこかに「10年前のあなた」がいるから
なんだ。受験、就職、恋愛、家族、イジメ、なんでもいい。10年前のあなたと同じ問題を抱えている人がどこかに必ずいるんだよね。だから「過去の自分」に書いた文章は、「今の誰か」に届くんだよ。
だからこの本のタイトルは、「『20歳の自分に』受けさせたい文章講義」になっているんだよ。
なるほどなって思うよね。例えばLINEとかメールは、その文章の読み手が頭に浮かんでいるから、その人に向けたくっきりとした文章を書けるよね。友達なり取引先なり恋人なり。特定の誰かに向けて書いた文章は、大抵はその人に正確に伝わるよね。でも作文とかnoteでの文章になると、途端に「読み手」を意識しなくなって、誰に向けて書いたのかわからない、曖昧な文章ができてしまう。だからどんな文章を書くときも、「特定のあの人」に向けて書くことで、その文章がよりくっきりするんだ。
■大阪LOVERのすごさ
話は少し変わるけど、この前かまいたちのYoutubeチャンネルで、「カラオケで女性に歌ってほしい曲ランキング」を決めていたんだよ。
そこで、ドリカムの『大阪LOVER』をランキングに入れていたんだ。「どんな曲だっけ」って歌詞を調べたら、まさに古賀さんが言ってる文章術が達成されていたんだよ。
新大阪駅までむかえに来てくれたあなたを見たら
いつもはいてるスウェット
今日も家へ直行か
万博公園の太陽の塔
ひさびさ見たいなぁ!明日さたまにはいいじゃん!
「そやなぁ」って行くの?行かないの?
とても良いよね。大阪人ではないぼくでさえこの歌詞を読むと、彼女の思いと彼氏の曖昧さがリアルに伝わる。恋愛ソングは世の中にたくさんあるけど、恋とか愛とか漠然と大きなことを言ってる歌詞はあまり記憶に残ってないよね。でも大阪LOVERのように「面倒くさい細部」をきっちりと、「特定の誰か」に書いてる歌詞は、こんなにも響くんだよ。
「東京の彼女と大阪の彼氏の遠距離恋愛」のシチュエーションに合致する人なんて、日本でごく僅かのはずなのに、こんなにも多くの人の心に届いているんだよね。やっぱり「細部を書く」ことと「特定の誰かに書く」ことは、伝わる文章を書くうえで大切なことなんだ。
■まとめ
この本は、文章を書くうえで大切なことが授業形式でまとめられているんだ。ぼくはその中でも、「リアリティのある文章の書き方」と「誰に向けて書くか」そして「文章を書く心構え」が心に残ったんだ。このポイントを念頭にこれからも文章を書きたいと思うよ。きっとためになると思うから是非読んでみて。」
お賽銭入れる感覚で気楽にサポートお願いします!
