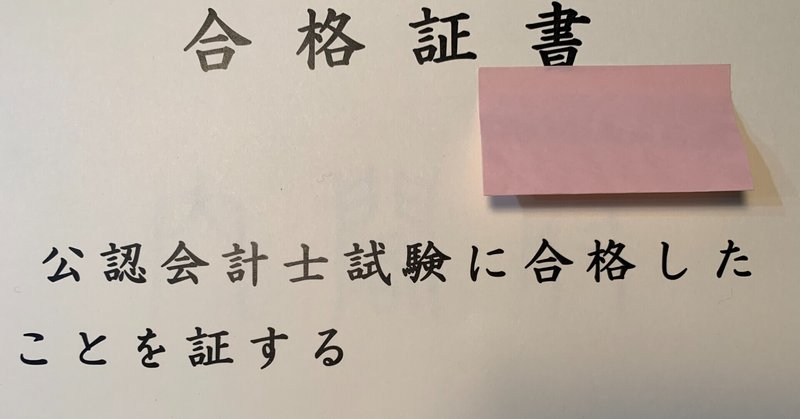
法曹が会計士試験に合格するために行った勉強の全て その2
前回からの続きです。今回は租税法と監査論、そして免除科目の企業法と民法を取り上げます。
租税法は100点の配点のうち40点が理論(記述)で、60点が計算です。監査論はもちろん全て理論(記述)ですので、法曹は租税法・監査論で偏差値52を確保することが求められます。
特に租税法は必須科目であるものの短答式試験の科目ではないため、一般的な受験生も比較的手薄なステータスで論文式試験に突っ込んできます。
4.具体の勉強法と、振り返って「やっておけば良かったと思ったこと
(3)租税法
租税法もまずはテキスト(講義)でインプットするところから入ります。
しかし残念ながら、租税法は会計学と大きく異なり、「なぜそういう処理をするのか明確なロジックがない」というのが厄介です。
また、計算の対象範囲も「法人税法」「所得税法」「消費税法」と3分野あり、これも地味につらいです。それぞれの税は目的から異なるのですから、一から覚えていくしかありません。
LECのテキスト(講義)は少し変わっていて、最も頻出(毎回出てくる単元)のものからスタートしますので、いきなり配当関係から始まりました。これも正直面食らいました。
司法試験で例えれば、民法を学ぶときにいきなり「抵当権」から出てくるようなものです。
その意味では租税法は「一周」するところまでは苦行かもしれません。法人税の計算式も完全暗記が求められており、20代のときのような暗記力がない法曹にとっては鬼門です。
しかし気を付けてください。所得税の計算ルール(特に所得控除関係)は所得税法に結構きちんと書いてあります。余計なものまで覚えてしまって脳のキャパとモチベーションを下げてしまわないよう、法律には何が書いていて、何が書いていない(つまり当日参照できない規則・通達にのみ書いている)ものかをしっかり意識しながら勉強すべきです。
計算問題はとにかく時間が足りません。導出に時間がかかる問題であっても、一瞬でわかるような(あるいは問題文を転記するだけのような)問題も同じ点数です。ですから、わかる計算・数値だけをとにかく解きまくるという取捨選択の能力が極めて重要になります。
理論も、書き方に少し工夫が必要です。解答行数が3行程度なので、法律文章のような「問題提起⇒規範定立⇒あてはめ」はできません。必要不可欠な条文番号と記述のキモのみをスナイパーのように記述することができないと点が伸びないようです。
【補足】租税法:私がもう一度受験をするなら
まず先に条文を素読しておいた方がよかったなと思いました。何が書いていて何が書いていないかを知るのが遅かったため、余計なことまで暗記してしまっていて、そこは非効率的でした。
予備校の講師も、法文に書いていることまで覚えさせようとします(これは次の監査論でも同様)。
おそらくこれは、会計士受験生の条文を引く速度が遅いためかと推測します。
しかし我々法曹は条文を引いてナンボの商売ですから、条文を引く速度はかなり早いはずです。ですのでそのデメリットは気にしなくていいです。
計算については特にありません。弱点ノートを作成し、直前までそれをひたすら暗記していました。本番では計算の素点が5割を超えたので、このようなアプローチで十分かと思います。
その意味では、過去問を解いておいた方がよかったかもしれません。
答練のレベルと本試験のレベルでは、私にとっては本試験の方が簡単に思えてしまいました。答練は予備校が凝りすぎているきらいもありますから、過去問も直近3年くらいは1回か2回くらいしておけばよかったかなと思っています。
(4)監査論
法曹にだけ通じるネタかもしれませんが、監査論は「内容は訴訟法」ですが、試験としての性質は「憲法」です。
つまり、何を書けば点につながるのかわからない、取れているときと取れていないときの差を分析しづらい、ということです。
とにかく監査論は内容自体は法曹にとって最も理解しやすく、テキスト(講義)を読むのも、問題を解くのも苦にはならないでしょう。
監査論は「監基報」と呼ばれる基準集を参照しながら答えられるのですが、これもまた、予備校はなぜか内容を暗記させようとしてきます。
しかし先述のとおり、我々法曹はドキュメントから必要な箇所を引いてくる能力は高いはずなので、「監基報」に載っていることは覚えず、それがどのページにあるのかをしっかりと把握しておけばよいです。
そして「監基報」のそれぞれの規定がなぜそのような規定なのか、について理解すれば(これは当日参照不可の「監査基準の改訂に関する意見書」というのに記載されています。絶対に読んでください)監査論の下準備は完了です。
なお、「監査基準の改訂に関する意見書」は平成14年、平成17年、平成30年は極めて重要なので、これを印刷して勉強のおともにしてください。
【補足】監査論:私がもう一度受験をするなら
過去問を直近5年はやりこみます。
理由はたった一つです。
予備校の答練が、本試験の問題を再現できていないから、です。
おそらくこれは作問者のレベルだと思います。はっきり言って、監査論の問題のレベルは答練とは比べ物にならないくらい練られています。
答練の問題は「監基報から適切な記載を見つけてきて引用する」、というゲームなのですが、本試験の問題は明らかにそういう安易な構造ではないです。
なぜか会計士受験生界隈は「過去問不要。答練重要」という文化なので(意味は不明)、私もそれを信じて監査論の過去問は一切やっていませんでした。
しかし当日に初めて出会い、「全然答練と違うやんか」と驚いたことを今でも思い出せます。過去問の予備校解答が正しいかどうかは正直疑問ですので、過去問をきちんとこなすこと、及び、世間に出回っている監査論の偏差値が高い「開示答案」を読んだ方が近道かなと思います。
(5)企業法
私はリーガルクエストを2周しました。
直近5年分の過去問を見て「どの程度のレベルの問題が、どのような分野から出ているのか」を確かめました。基本的には「機関」「組織再編」あたりが多かったので、リークエのその部分を重点的に見ていました。
私の開示答案を見ていただければわかるとおり、司法試験では比較的平凡な回答でも2位になります。法曹の人は肩の力を抜いて、とにかく「問題提起⇒規範定立⇒あてはめ」を貫徹すれば偏差値60はいくと思います。
(6)民法
過去問を見てもらえればわかるとおり、民法の問題は「判例百選」を題材に出してきます。
令和3年も転用物訴権が出てきており、試験直前でようやくそこまでたどり着いた私としてはビビりました。
法曹ならわかると思いますが、民法百選に記載しているようなロジックを初見・現場で編み出すことは不可能です。なので、民法は理論のくせに暗記ゲーという意味で「計算」に近いです。
判例百選ⅠとⅡを一周するので精一杯でしたが、その時間さえ無さそうという方は民法は免除のままにするのもありかもしれません。
民法が何名受けているかは知りませんが、7位でも偏差値57.5というのはリスクにも思えるからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
