
対策はとっていますか?高齢者の『熱中症』に注意しましょう。
熱中症の対策はとっていますか?室内でも室外でも熱中症は起こり得ます。特に高齢者は熱中症になるリスクが高く、事前の対策を行わないことは症状を悪化させる恐れがあり、危険だと言われています。
そのため熱中症にならないよう、これを機に高齢者の熱中症対策について考えてみてませんか?
高齢者が熱中症になりやすいのはどうしてですか?

高齢の方は加齢に伴い、身体の老化は身体にさまざまな変化が起きます。夏の暑さに対して次のような傾向がみられます。
・気温が高くなっても、暑さを感じにくい
体温調節機能が、高齢になることで低下します。私たちは暑ければ汗を書いたり、寒ければ身体を震わせ体温を上昇させようとします。しかしそれらの働きが鈍っている高齢者は、身体が対応することができません。暑くい場合は汗をかかず熱をため込んでしまったり、寒い場合でも体温が上がらず冷えてしまいます。そうなると、周囲の気温に応じた行動も取ることができません。暑くてもエアコンを付けずに過ごし、熱中症になってしまう高齢者がいるのはこのような理由です。
・体内の水分量が少なくなってしまう。
高齢者は老化により身体の水分保持の能力が低下します。若年の人は体内の60%が水分でできていると言われています。若年者より体内の水分量は少なくなっている高齢者は、体内の水分量が50%になることがわかっています。そのため、汗を書いてしまった場合、若年者に比べ脱水症を引き起こしやすいと言われています。
・喉の渇きを感じにくい
人は身体から水が失われる=脱水状態になると、水分を体内に取り込もうと喉が渇くように機能が備わっています。しかし、老化によってこの機能も低下してしまうと言われています。そのため暑さによって体内の水分が失われても水分の補充ができないため、脱水症のリスクが高まってしまうわけです。
・無理をして、暑さを我慢してしまう
高齢者は周囲に迷惑をかけることが悪いと思い遠慮してしまう方や、「これくらい大丈夫」と言い張って我慢してしまう方がいるなど、つい我慢をしてしまったり、無理をしてしまう方が多い傾向にあります。そのことから、暑いと感じていてもエアコンを使用しなかったり、暑くて服を脱ぐことを依頼したくても我慢してしまうと言ったことが起きます。
1.気温が高くても、暑さを感じにくい
2.体内の水分量が少なくなってしまう
3.無理をして、暑さを我慢してしまう
4.喉の渇きを感じにくい
熱中症の症状とはどんなものですか?

熱中症の症状は次の3段階(*1参照)に分かれています。
熱中症初期であるⅠ度では、こむら返りやあくび等一見関係のない症状のように見えまうすが、身体の中の電解質(ナトリウムやカリウム等のイオン)が崩れたことによって起こっているものです。このような症状を感じた時点で、スポーツドリンクを摂取するのがよいでしょう。
最近では塩飴等熱中症予防の製品も販売しているのでうまく利用してみるものおすすめです。
いずれにしても早い段階で対処しましょう。進行すると、熱中症は命に関わるもので甘く見てはいけせん。

熱中症の対策をしましょう

熱中症の症状について理解していただいたとろで、次に熱中症の対策についても考えていきましょう。
1.室温の調整をする
エアコンの使い方がわからないから、お金がかかってもったいないからとエアコンを使わない高齢者の方は少なくありません。家族や介護職の方が日ごろからエアコンの使い方を教えることも大切です。また体感できないだけで室温や湿度があがっていることもあるので、室内に温時計や湿度計を用意しておき、高齢者に目で確認していただき、理解してもらうことも大切です。例え室温が低くても熱中症になることはありますから、冷房を使用してもらうことの大切さを理解してもらいましょう。
意図的に換気を定時で行うのも良い対策です。
2.水分摂取を小まめに行い、塩分の摂取も適切に行う。
高齢者は水分が不足してしまう傾向にあることは先にご説明した通りですが、それを補うのは水分摂取を行うことが最大の予防です。また水やお茶だけでは体内の電解質バランスが崩れてしまうために、塩分の摂取をする必要があります。
3.外出時間を検討する
散歩等の運動習慣は大切です。そのため暑い時間帯を避け外出することや、炎天下の中長いしないことなど注意が必要です。早朝の涼しいうちに短時間ででかける等の外出時間を工夫しましょう。
4.熱中症対策につながる食物を取り入れる
水分摂取は、スポーツドリンクやOS1などの経口補水液を冷蔵庫で適度に冷やし、飲むのをおすすめします。冷やすことで、吸収効率が良くなると言われています。またナトリウム、カリウム、アリシン、ビタミンB1、ビタミンCを多く含む食品がおすすめです。これらは汗をかくことで失われるもの、夏バテの回復に役立つ栄養分です。次に具体的な品目の一部をご紹介します。
・うなぎ…ビタミンAやビタミンB1が豊富に含まれています。疲労回復に効果的で、夏バテにも有効な食品と言えます。夏の土用の丑の日にウナギを食べる風習がありますが、非常に理にかなっているのはこれらが所以でしょう。
・玉ねぎ、ニンニク、ネギ…胃腸の働きをよくするアリシンを含む食材です。代謝と消化を促進することから弱った胃腸の働きをよくしてくれるとも言われています。
・夏野菜…旬の夏野菜は、体を冷やし、体液を補う役割があります。なかでもリコピンやカリウムを含み水分量の多いトマトは非常におすすめです。
ただし、糖尿病や腎臓障害がある方など、食事・水分摂取に制限のある既往をお持ちの方はかかりつけ医に確認しましょう。
1.室温の調整をする
2.水分摂取を小まめに行い、塩分の摂取も適切に行う。
3.外出時間を検討する
4.熱中症対策につながる食べ物を取り入れる
まとめ
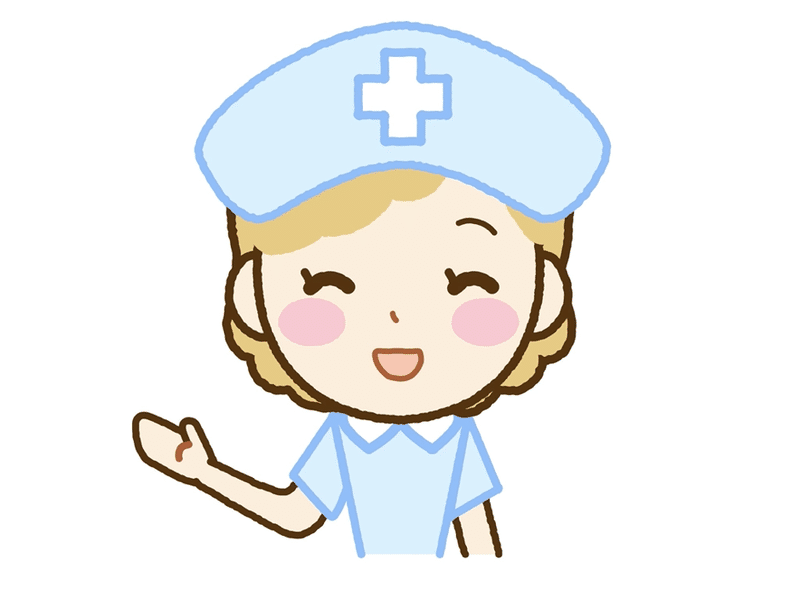
熱中症は事前の対策が大切です。
そのためにも高齢者の方がいる家族は今一度対策を考えて見ましょう。対策の一つのなかに、高齢者の身体の特徴を掴み理解をすることです。
今回の記事では一般的な高齢者に対する熱中症の対応をまとめましたが、疾患別によって、その対応は異なるものです。
かかりつけの医療機関で相談しましょう。独居の高齢者家族を持つ方は、なかなか対応がしづらい点があるかもしれません。
ご本人がお住まいの地域にある地域包括ケアセンターや介護サービスを提供する企業へご相談されることをおすすめします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

