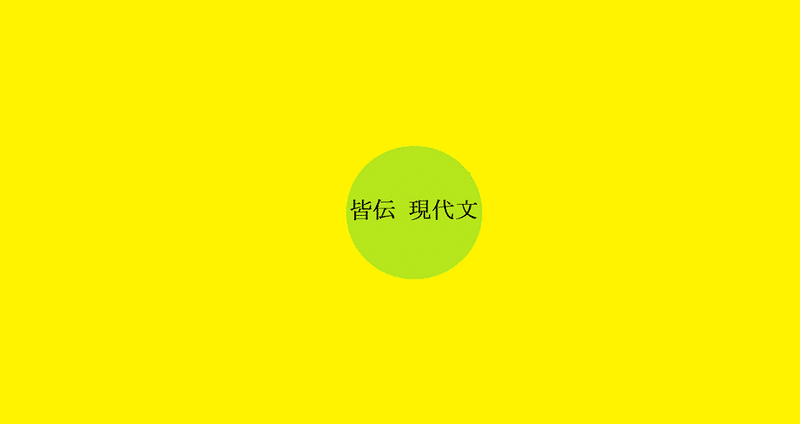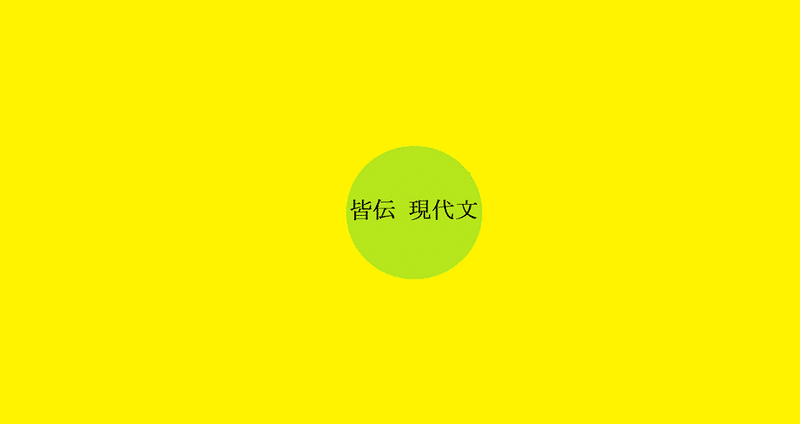皆伝 現代文 読解00
読解とは、文章を読んで意味、構造がわかることです。
文章を理解・読解できていれば「うんうん、そうだね」と同意したり、「いやー、違うんだよなあ」と不同意をしながら読むことができます。
さらに、心情としてプラス/⊕か、マイナス/⊖かのどちらか、たとえばプラス/⊕の共感やマイナス/⊖の忌避か、プラス/⊕の肯定かマイナス/⊖の否定かを感じられるということです。
例えば、
「温暖化を抑止するためにメタンの排出も減らす必要がある。従って、牛のげっぷを減らすために、げっぷの出にくい低価格